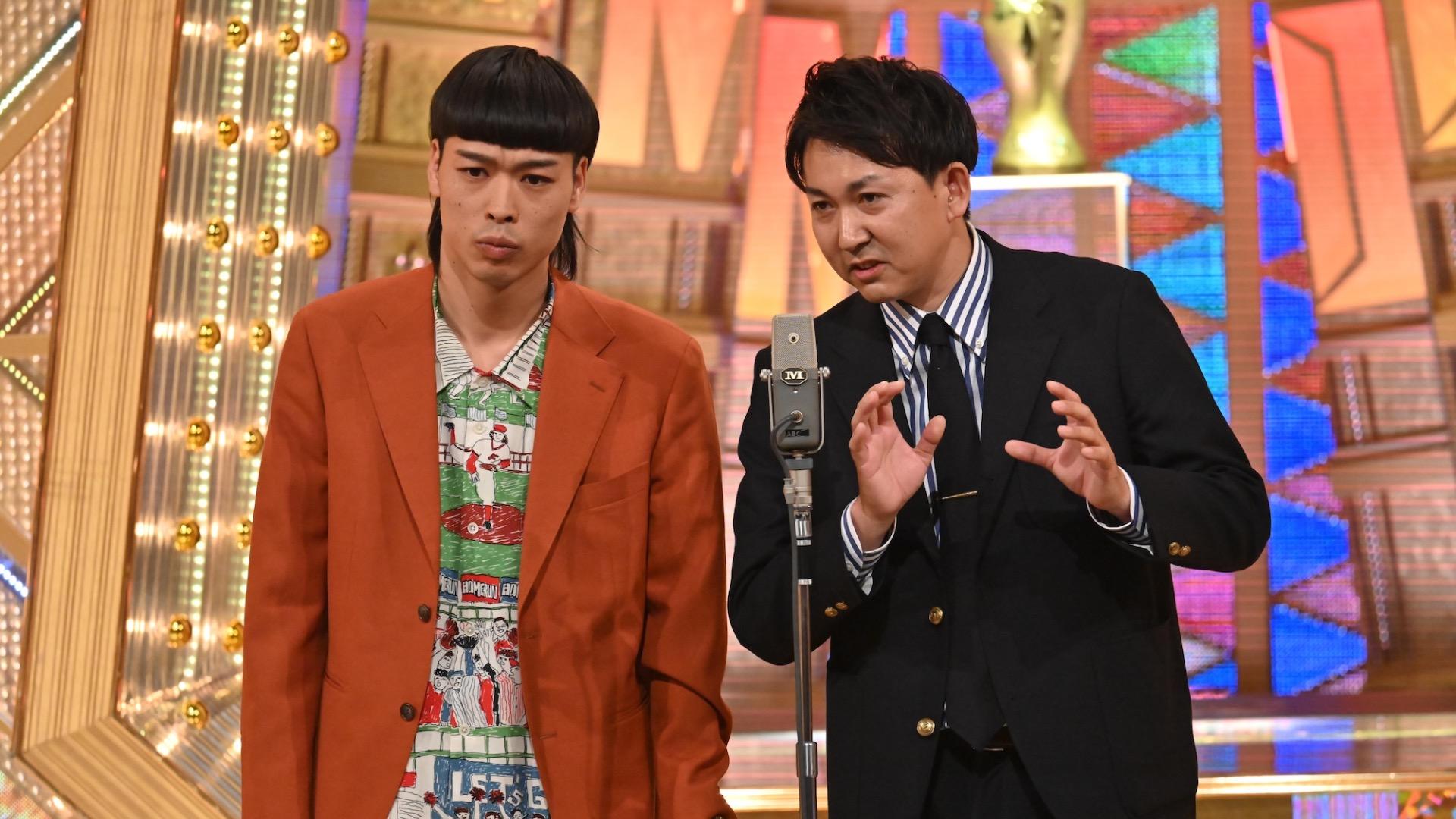クマ出没に備えるガバメントハンターについて考える

今年もクマの出没情報が各地で相次いでいる。とくに東北と北海道は、ツキノワグマとヒグマと種は違うものの、過去最高だった昨年を超えるペースだ。しかも市街地への出没が増えている傾向がある。
積極的に人を狙うクマの登場
人が山に入ってクマと出くわすのと違って、クマが人里に現れ、積極的に人を襲うという事態が続くようでは、もはや従来の「鈴を持って山に入る」といった対策は成り立たない。いかに早く、周辺の安全も見極めて駆除するかを考えないといけない。
一般には、猟銃を扱える猟友会に期待する声が高まるが、すでに高齢化と後継者難からの人数不足が強まっている。報酬が安すぎると出動拒否する猟友会が出たことも話題に上がった。
そもそも猟友会は、狩猟を楽しむ趣味の会であり、有害駆除に出動するのは、ある意味ボランティアだ。それに通常は本業を別に持つ人たちだから、緊急時にすぐ出動できるわけではないのである。
そんな彼らに過度な期待をかけつつ、過酷で責任の重い仕事を押しつけても、事態を空回りさせるだけだろう。
もっと根本的に野生動物、とくにクマと向き合う対策はとれないのか。
獣害対策の公務員ハンター
やはり駆除専門のプロのハンターが必要だろう。一つには駆除をビジネスとして請け負う認定業者があるが、業者のいない地方も少なくない。そこで少しずつ誕生しているガバメントハンターについて紹介するとともに、課題を考察しよう。
ガバメントと呼ぶのは、それが公務員だからである。主に自治体職員として、野生動物対応に向き合うハンターだ。彼らは狩猟免許を持って、多くは猟銃も扱う。仕事として害獣の駆除を行うだけでなく、野生動物の行動、生態などの知識を身につけて、地域の獣害対策全般を担う。
公務員だから身分や収入は安定している。装備や訓練、保険といった経費もカバーされる。日常的には、地域の人々に獣害予防を指導しつつ、出没情報が入れば出動する。一人で行動するのではなく、警察や猟友会の人たちとも連携して動き、ときに司令塔の役割も担う。
各地に生まれる獣害対策公務員
すでに実例はある。長野県小諸市は、野生動物の専門職としてガバメントハンターを地方上級公務員として正規雇用している。さらに狩猟免許を取得した職員によって、有害鳥獣対策実施隊を結成させた。彼らは主に罠で中小のイノシシやシカ、キツネ、タヌキ、アライグマ、アナグマ、カラスなどの被害対策を行う。
そして銃器を必要とするクマおよびイノシシなど危険性の高い大型獣には、猟友会の会員による小諸市有害鳥獣駆除班が担当する。
こうした分業体制にして効率を高め、駆除班つまり猟友会の負担を減少させた。

ヒグマの出没が頻発する北海道では、占冠村、岩見沢市、三笠市、沼田町の4市町村にガバメントハンターが置かれている。
また北海道の千歳市では、地元猟友会が選抜したハンターによるクマ防除隊が結成されている。普段は別の仕事に従事する民間人だが、クマ出没の際は、市の非常勤特別職員の立場で出動する。傷害保険なども市が負担している。
ほかにも兵庫県豊岡市はプロのハンターによる鳥獣害対策員を置いている。
異動しない部署と人が必須
こうした動きは、全国でも少しずつ広まっている。自治体職員が狩猟免許を取得して、駆除活動に取り組んでいるところは全国的に広がりつつある。またいくつかの県では、ハンターの養成のほか、射撃技術向上などに県が関わって、ハンターの負担軽減のための制度も立ち上げている。
問題は、自治体の職員には転勤があることだ。通常は数年で異動する。それでは専門性が身につかない。専門職として異動しない役職と部署を設けるべきだろう。
すでにガバメントハンターを置いている自治体の中にも、地域おこし協力隊として採用している所もある。だが獣害対策は数年で片づくものではない。永続的に取り組む体制を組まねばならない。
それに公務員相当のハンターを設ければ、現在の激化する獣害問題が即解決するわけでもない。
クマ対策には特別な技量が必要
まずハンターと一口に言っても、多くはシカやイノシシなどが対象で、銃を使わず罠による駆除も少なくない。クマに対応できるハンターには簡単になれない。
まずクマ用に必須のライフル銃は、散弾銃を所有して10年以上経たないと持てないし、すぐに扱えるハーフライフル(単弾を使う散弾銃)も、警察は規制を強めつつある。何よりクマに関する十分な知識と技量を備えないと危険だ。
加えて野生動物の行動には地域性があるので、何年もかけてその土地の動物の特徴を把握してもらわないといけない。その点からは、地域外から就職の形で赴任してガバメントハンターになる人は、一定期間、地元のベテランハンターと同行して学ぶ必要があるだろう。
欠かせぬ猟友会と警察との連携
意外と意識から欠落しがちなのが、地元の猟友会との関係である。猟友会からすると、新たなプロのハンターとは既得権益で競合しかねないうえに、役人に指示されたくはない意識があるからだ。
有害駆除を行う認定業者の制度も、上手く機能していない現実がある。なぜなら猟友会が反対しがちだからである。
だからガバメントハンターも、猟友会との人間関係が重要となる。むしろ役所の担当官として、猟友会や認定業者など関係者を巻き込み仲立ちになるべきだ。
もう一つ、警察との連携も欠かせない。人里への出没には警察官も出動するが、緊急の駆除となると、両者が情報共有するとともに野生動物に関する認識で通じ合っていないと、駆除は上手く行かない。
そうしたことから、ガバメントハンターの設置は、自治体挙げて行わないと難しい。単に若い狩猟者を役所で雇えばよいとか、動物研究者を招き入れたら何とかなるという意識では無理なのだ。
求められる長期ヴィジョン
もちろん予算の問題もある。ただ、それも自治体の覚悟次第だ。現在は森林環境譲与税が各自治体に下りてくる。それを単に林業関係へのバラマキに使うか、時間をかけてでも野生動物や自然環境の専門家を育てるのに使うかを考えてほしい。
またガバメントハンターに求められるのは、駆除だけではない。人里に害獣が出没しないようにする役割もある。クマは農作物などを求めて人里に出てくる。また登山者や山菜採りの人にも注意喚起するなどの指導が必要だ。人間側の努力・協力が欠かせない。そのための知識や交渉能力も大切だろう。
何より職務は、クマなどの害獣を駆除するだけでなく、日常的なパトロールや追跡調査を通じて、人と森の境界線を動物たちに覚えさせることが大きな役割だ。一度駆除したら片づいたということはなく、活動を持続しないと出没を押し止めることはできない。そのためにも、常勤の担当者がいるのだ。
このように見ていくと、単に自治体が新たな役職を設けて人を配置したらガバメントハンターとして機能するわけではないことがわかるだろう。
何より野生動物に関する正しい認識と、目先の被害だけでなく地域の自然環境の将来像まで目を向けたヴィジョンが必要である。