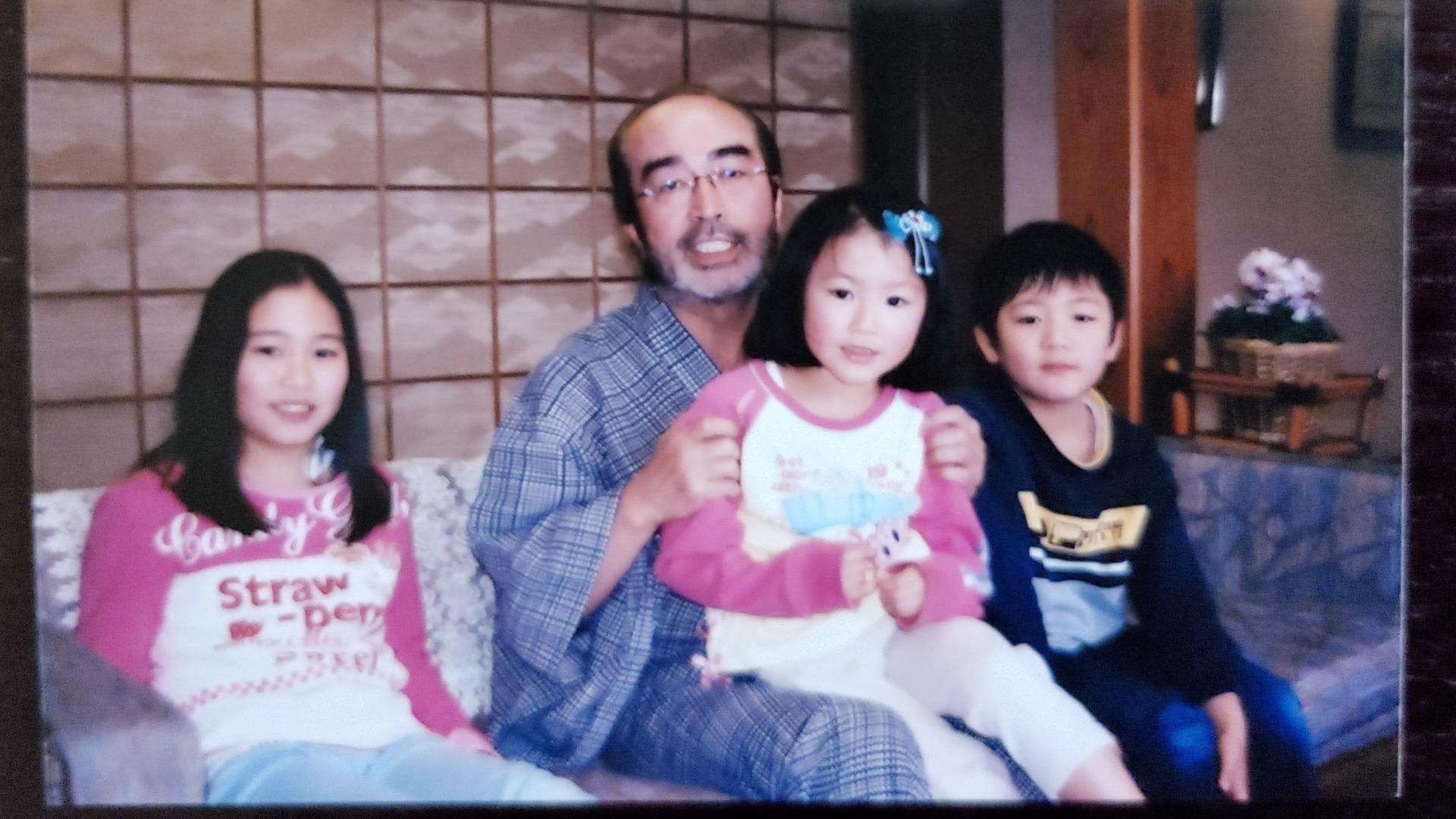「なぜ人を殺してはいけないのか?」──元少年A『絶歌』が刺激した日本の“空気”【下】

動機が見えにくい凶悪事件──それが相対的に浮上してきたのは90年代以降のことだったろうか。犯人の背景には「貧病争」が見えないものの、突然生じてしまう事件だ。その代表的なものが1997年の少年Aによる「酒鬼薔薇事件」かもしれない。そして現在も類似する事件が目立っている。
2015年、少年Aは手記『絶歌』を発表して大きな論争に発展した。その際にかの本を取り巻く日本社会の状況を描いた記事を再掲する。
初出:『論座』(朝日新聞社)2015年7月14日/一部加筆・修正
【「“サブカル”的に描かれた「僕の物語」──元少年A『絶歌』が刺激した日本の“空気”【中】」から続く】
「なぜ人を殺してはいけないのか?」
「なぜ人を殺してはいけないのか?」
1997年の神戸連続児童殺傷事件は、その後も多くの波紋を拡げた。そのひとつが、少年A逮捕から3ヶ月後のTBS『筑紫哲也のニュース23』での対論企画に出演したある高校生からの問いだった。このとき、出演していた識者たちは回答に窮したという。
それを観ていた作家の大江健三郎は、この問いに対して当時以下のように話している。
私はむしろ、この質問に問題があると思う。まともな子供なら、そういう問いかけを口にすることを恥じるものだ。なぜなら、性格の良しあしとか、頭の鋭さとかは無関係に、子供は幼いなりに固有の誇りを持っているから。そのようにいう根拠を示せといわれるなら、私は戦時の幼少年時についての記憶や、知的な障害児と健常な子供を育てた家庭での観察にたって知っていると答えたい。
人を殺さないということ自体に意味がある。どうしてと問うのは、その直観にさからう無意味な行為で、誇りのある人間のすることじゃないと子供は思っているだろう。
(朝日新聞1997年11月30日付「誇り、ユーモア、想像力 大江健三郎(21世紀への提言)」)
大江のこの回答は、子供を信頼した性善説的なものである。そこでは「まともな子供」という限定をかけ、さらに「誇り」を求めている。言い換えれば「プライドの高いまともな子供なら、そんなことはしない」というプレッシャーとして、この言葉は機能する。
しかし、それから3年後、大江の希望的観測は「誇りのない子供」によってあっさりと棄却される。
2000年5月、愛知県豊川市で高校3年生の17歳の少年が、老女を刺し殺した。元少年Aと同い年の彼は、「人を殺す経験がしてみたかった」と話した。明快すぎるがゆえに不可解なその犯行動機は、世を大きく動揺させた。
彼は、決して「人を殺してはいけない」という社会規範を認識していなかったわけではない。将来のある大人ではなく年寄りを狙い、事件後には逃走していることからもそれは明らかだ。
そこには彼なりのロジックがある。彼にとって「人を殺してはいけない」という規範は、「人を殺す経験をしたい」という欲求よりも、単にプライオリティが低かったのである。
2014年7月には佐世保の女子高校生が同級生を殺害し、2015年1月には名古屋の女子大学生が老女を殺害して逮捕された。
両者ともに、その動機として「人を殺してみたかった」と話している。名古屋大生にいたっては、2014年7月のAの誕生日に「酒鬼薔薇聖斗くん32歳の誕生日おめでとう♪(///∇///)」とツイートした模倣犯だ。豊川事件の少年同様、彼女たちも殺人欲求を抑えられなかったのである。
同時にそれは、「なぜ人を殺してはいけないのか?」という問いに対して、彼女たちが十分に納得できる回答を得ていなかったことを意味する。
「なぜ人を殺してはいけないのか?」──未成年者による不可解な凶悪事件が起こるたびに、この問いは世を漂うのである。まるで呪詛のように。
溶けなかった呪い
Aが事件を起こした当時、「なぜ人を殺してはいけないのか?」という問いに対して、明確な回答をした識者は多くなかった。きっと話しにくい“空気”だったのだろう。そんななか唯一この“空気”を打ち破っていたのは、社会学者の宮台真司だった。当時、宮台はこう書いている。
私たちが人を殺さないのは人を殺してはいけない明確な理由があるからではない。人が滅多に人を(平時に仲間を)殺さないという自明な事実に対する信頼がまずあり、その上で人を殺してはいけないという観念も抱かれるし、かかる観念に基づく殺人への否定的反応も生じる。
(宮台真司『透明な存在の不透明な悪意』p.viii/1997年・春秋社)
「人を殺してはいけない」というルールが共有されたことは、人類の歴史に一度もありません。代わりに「仲間を殺すな」と「仲間のために人を殺せ」という血讐のルールがあり続けてきました。
(宮台真司『これが答えだ!――新世紀を生きるための100問100答』p.118/1998年・飛鳥新社)
宮台のこれらの説明は、社会科学的にはごく一般的な認識枠組みである。こうしたことは、『自殺論』で知られる社学者のエミール・デュルケムが1895年に残した『社会学的方法の基準』でも、すでに指摘されている。
しかし、このような学問的な正しさはまったく支持されなかった。そこには多くのひとびとを納得させる感情的フックがなかったからだ。
それよりも必要とされたのは、「心の闇」という“サブカル”的レトリックに代表されるような、事件の要因を個人の内面ばかりに求める心理的アプローチであった。
多くの識者がその呪いを祓えなかったのは、無意識的に心理的アプローチを採用していたか(「まともな子供ならそんなことはしない」)、社会科学をまるで無視した道徳的規範を論理抜きで提示していたから(「ダメなものはダメだ」)だ。
それらはたしかに非当事者の心の安寧を導く言葉としては機能しただろう。しかし、それによって見放されていたのは、その呪詛に囚われた者たちにほかならない。
佐世保の事件も名古屋の事件も、こうした状況の果てに生じたことを、大人たちは肝に銘じたほうがいい。
「社会的な合意があれば、殺人は許される」
元少年Aが『絶歌』を出版した理由には、この呪いを祓う目的が見て取れる。前半部では、過剰に修飾をほどこした文章で事件を起こすまでを描いているのに対し、少年院退所後を描いた後半部では、打って変わって率直な心情を吐露する。
そして終盤、「なぜ人を殺してはいけないのか?」という問いに対し、Aはこう答える。
大人になった今の僕が、もし十代の少年に「どうして人を殺してはいけないのですか?」と問われたら、ただこうとしか言えない。
「どうしていけないのかは、わかりません。でも絶対に、絶対にしないでください。もしやったら、あなたが想像しているよりもずっと、あなた自身が苦しむことになるから」
(中略)
何度願ったかわからない。時間を巻き戻せたらと。まだ罪を犯す前の子供の頃の記憶が、たまらなく懐かしく愛おしい。あの頃に戻ってもう一度やり直したい。今度こそまともな人生を歩みたい。でもどんなに願っても、もう遅い。二度とそこに戻ることはできない。だからせめて、もう二度と人を傷付けたりせず、人の痛みを真っ直ぐ受けとめ、被害者や、これまでに傷付けてしまった人たちの分まで、今自分の周囲にいる人たちを大事にしながら、自分のしたことに死ぬまで目一杯、がむしゃらに「苦悩」し、それを自分の言葉で伝えることで、「なぜ人を殺してはいけないのですか?」というその問いに、僕は一生答え続けていこうと思う。
「人を殺してはいけない理由」を問う少年たちに、この苦しみを味わわせたくない。
(元少年A『絶歌』p.282-283/2015年・太田出版)
この部分は重大事件を起こしかねない未成年者に対するメッセージだが、大きな反発を呼んだのもたしかだ。それは、人を殺してならない理由を「わからない」と答えているからだ。被害者に同情を寄せる多くの人々は、2人の命を奪って自由を享受するAがその解を得ていないことに、強い憤りを覚えたのである。
しかし、この「わからない」という回答は、本音だとしたらとても正直で、嘘だとしたらとても誠実である。なぜなら「人を殺してはならない」という社会は、いまだに実現していないからだ。
常に国家は特権的に殺人を犯している。死刑と戦争がそうだ。現在の日本においては、死刑のほうが馴染み深いだろう。欧米では廃止の流れにある死刑制度は、日本ではいまだに80%を超える支持を得ている。つまりそこには、殺人を許容する多くのひとびとが「わからない」と回答するAを糾弾する、という構図がある。
もちろん、Aの起こした殺人事件と死刑や戦争は異なる。前者は国家が許さない殺人で、後者は国家が許す殺人である。言い換えれば、「正しくない(とされる)殺人」と「正しい(とされる)殺人」の差異がある。
よって、「なぜ人を殺してはいけないのか?」という問いに正面から向きあえば、「社会的な合意があれば、殺人は許される」が正解に近い回答となる。
『絶歌』出版の意義
前述した宮台だけでなく、これまでもこの問いに対する回答はさまざまなところで見られてきた。そのなかでももっともよく知られるのは、チャールズ・チャップリンの映画『殺人狂時代』(1947年)だろう。
それは、裕福な中年女性を殺して金を奪う殺人鬼の物語だった。彼は、足が不自由な妻と幼い子供を抱えていたが、銀行をクビとなり、殺人によって生計を立てていた。逮捕されて死刑台に向かう直前、彼はみずからの殺人を「事業(ビジネス)」だと言い放って、さらにこう続ける。
「ひとり殺せば悪党で、100万人だと英雄です。数が殺人を神聖にする」
この殺人鬼は、内なる明確な論理を持ち、社会に訴えたのである。
Aは、おそらくこうしたことに気づいている。もしかしたら、事件を起こしていたとき、すでに気づいていたのかもしれない。ゆえに、「わからない」と回答し、自分の境遇を切々と記したのではないか。だとしたら、それはとても誠実な対応だと捉えられる。
「僕みたいな悲惨なことになるぞ」──当事者による愚直なまでのこの回答によってこそ、「なぜ人を殺してはいけないのか?」という呪いは解けるかもしれない。『絶歌』の出版に意義があったとするならば、やはりこの点にある──。
【了】
- 関連記事
- 「酒鬼薔薇聖斗」の“人間宣言”――元少年A『絶歌』が出版される意義(2015年6月13日/『Yahoo!ニュース個人』)
- 猟奇事件報道とどう向き合うか──座間市9死体遺棄事件が向かう先(2017年10月31日/『Yahoo!ニュース個人』)
- マスコミは猟奇事件の容疑者をどう報じるか――2005年「奈良幼女誘拐殺人事件」における物語化(2016年3月31日/『Yahoo!ニュース個人』)
- SNSと民主主義が攻略された後に──ポスト・トランプ時代のゲーム再構築(2021年4月30日/『Yahoo!ニュース個人』)
- 『イカゲーム』はデスゲームを“重く”描く──韓国版『カイジ』がNetflix世界1位の大ヒットに(2021年9月30日/『Yahoo!ニュース個人』)