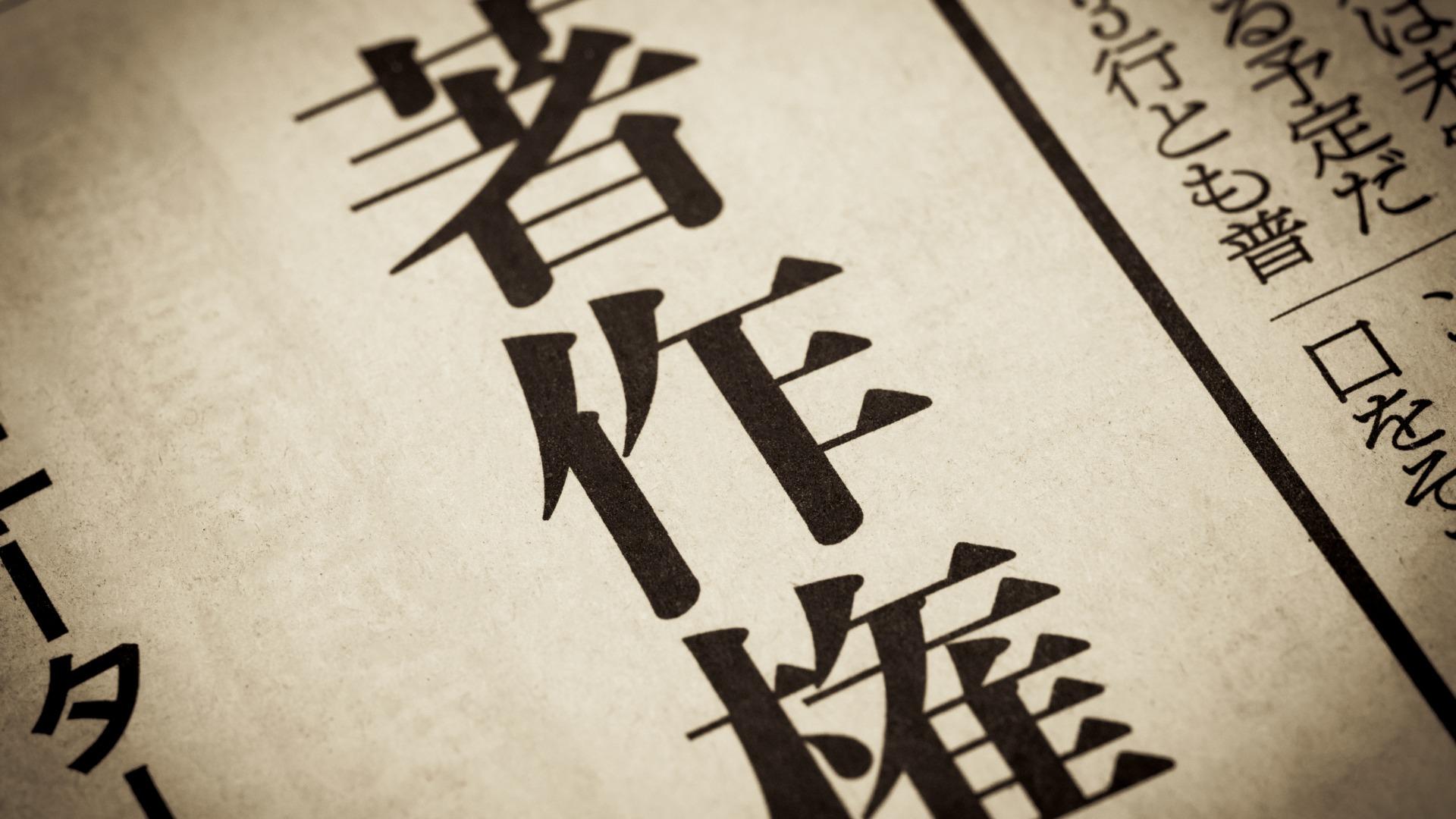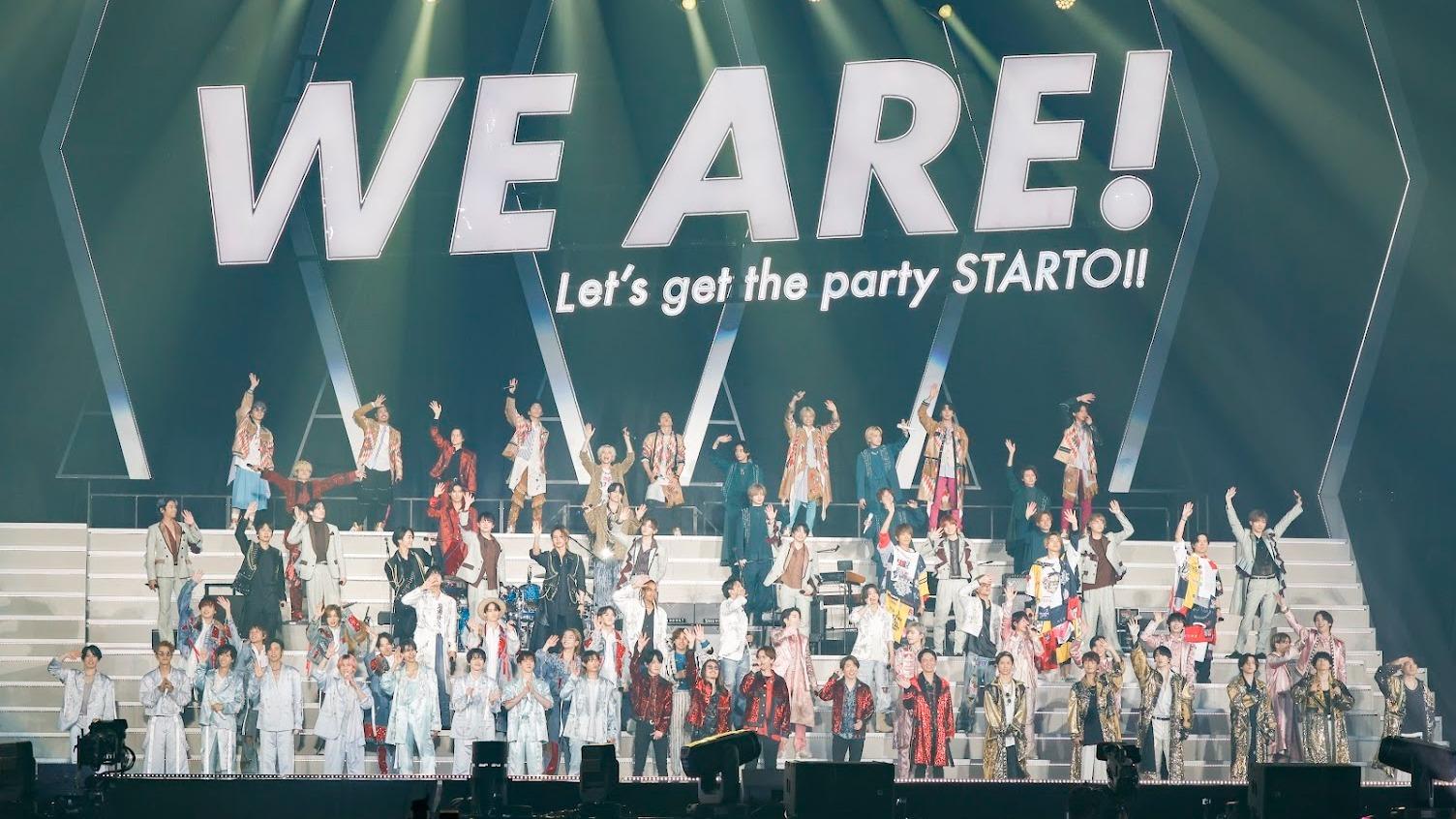【戦国こぼれ話】関ヶ原合戦前夜、会津に移った上杉景勝が越後からすべての米を持ち去った驚倒すべき事情

岐阜関ケ原古戦場記念館で、関ヶ原合戦に臨む姿勢を示した徳川家康の書状が公開されている。その関ヶ原合戦の引き金となったのが、徳川家康による上杉景勝の討伐だ。なぜ、景勝は越後から会津に移封されたのか考えてみよう。
■会津への移封
上杉景勝は、越後などを拠点とする大名だった。慶長3年(1598)1月、景勝は豊臣秀吉から会津(福島県会津若松市)への移封を申し付けられた。その史料は、次のものである(「上杉家文書」)。
今度の会津への国替えについて、その方の家中は侍は言うに及ばず、中間(ちゅうげん)・小者に至るまでの奉公人は、一人残らず召し連れること。行かない者があれば、速やかに成敗を加えること。ただし、田畠を持ち年貢を納める検地帳に登録された百姓は、一切連れて行ってはならない。
史料中の中間・小者とは、侍に従う軽輩者で、カテゴリーとしては武士身分に分類されていた。彼らを会津に連れて行くことは、これまで培ってきた土地との関係を一切絶つということになろう。
それゆえに、どうしても越後に残ると主張する者は、処罰の対象となった。逆に、百姓は土地に縛り付けて、移動を禁止することになる。百姓を残すのは、新しく入部した大名が困ってしまうからである。
会津への国替えにより、景勝は120万石の大名になった。五大老にふさわしい規模である。景勝の会津への国替えは、当然ながらほかの大名の国替えをも意味した。
同年3月、会津92万石に本拠を置く蒲生秀行は、下野宇都宮(栃木県宇都宮市)19万石へと国替えを命じられている。蒲生家で家中騒動があったので、減封のうえ宇都宮に移ったのである。
また、景勝が会津に移ったあとの越後などには、堀秀治が越前北庄(福井市)18万石から45万石に加増されたうえで移ってきた。栄転である。
■年貢米を運び去った景勝
ところが、景勝は越後から会津に移る際、年貢米をすべて運び出したという。それゆえ秀治は財政難に悩まされ、これがのちの禍根となった。
上杉氏の会津移封で貢献したのは、景勝の股肱の臣・直江兼続である。兼続は景勝に先立って、国替えの準備を取り仕切り、これに協力したのが石田三成であった。
領内には支城が構築され、城主・城代が置かれた。兼続自身も、出羽米沢城(山形県米沢市)主として6万石を与えられた。こうして会津では、着々と国づくりの整備が進められた。
京都にいた景勝は、越後を経由して3月24日に会津に到着した(「塔寺八幡宮長帳」)。景勝が赴任することにより、本格的な会津支配がはじまったといえよう。
■国替えの意味
この国替えは、意味なく実施されたわけではない。秀吉は天正18年(1590)に奥州仕置を行なったとはいえ、伊達政宗をはじめ東北の諸大名の監視を緩めるわけにはいかなかった。
秀吉は五大老の1人である景勝に、その重責を担わせたのである。同時に関東に支配権を持つ、家康の監視と牽制の意味合いが含まれていたのかもしれない。
重責を背負った景勝は、期待を胸にして会津へと向った。慶長3年(1598)8月に秀吉が亡くなると、徳川家康は景勝に再三にわたって上洛を要請した。しかし、景勝はこれを拒否。会津征討から関ヶ原合戦に至る流れを作ったのである。