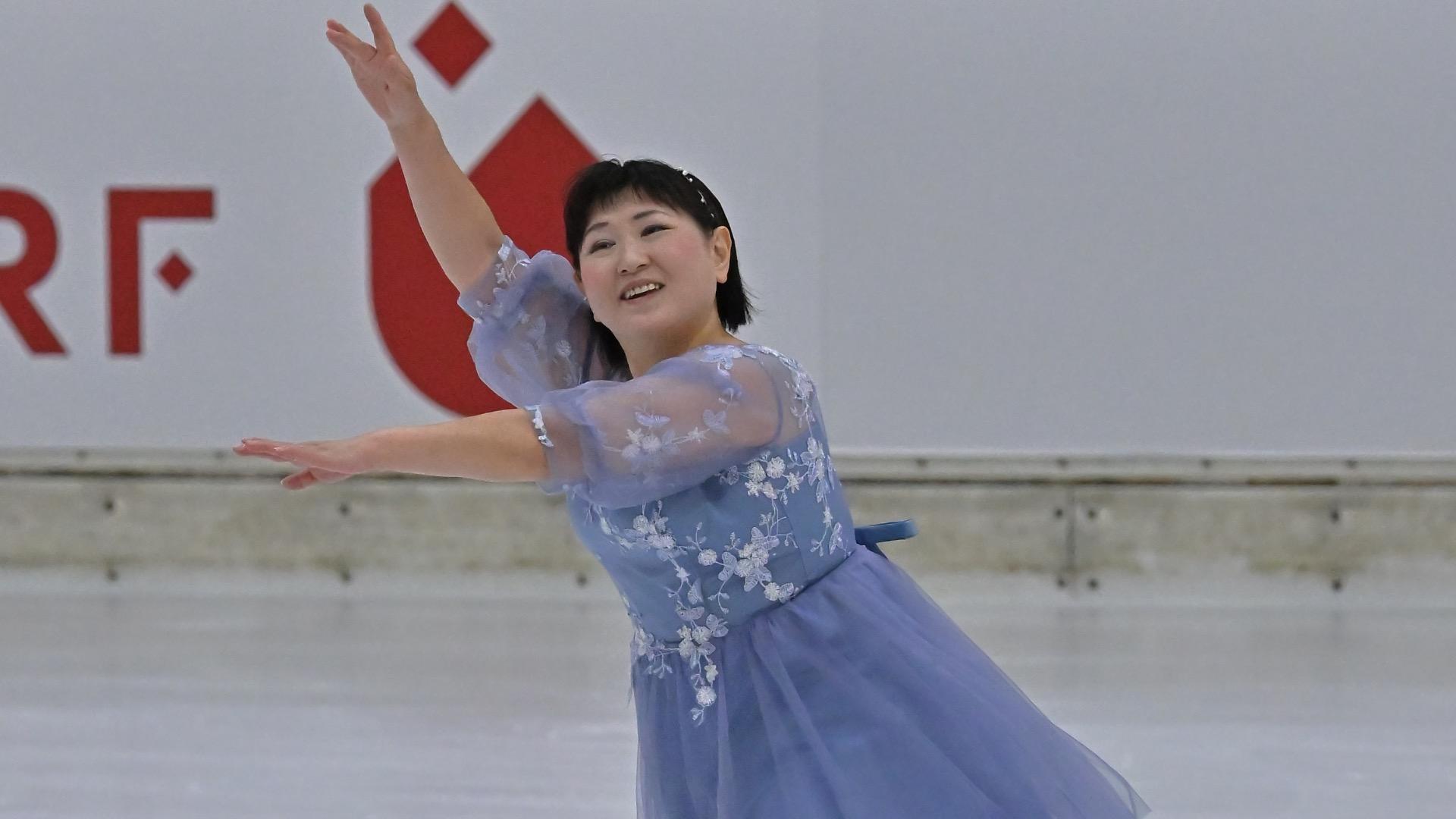原石の輝きか。すでに実力派俳優か。母親はあの人。21歳のフランス俳優が主演作で放つ魅力が鮮烈すぎる

初めて目にした俳優になぜか胸が高鳴り、その演技に他の誰とも違う才能を発見する。そして近い将来、その俳優が大きく羽ばたく姿を予感してしまう──。映画を観た時に、そのような経験をすることが、たまにある。
フランス人俳優、ポール・キルシェ。現在21歳。リセ(フランスの高校)の最終学年の時に、いきなり主役に抜擢されて映画デビューを果たした彼だが、最新主演作『Winter boy』の公開によって、日本でも一気にファンが増えるかもしれない。
『Winter boy』で演じたのは、学校の寄宿舎生活を送る17歳のリュカ。同年代のボーイフレンド的な相手もいる彼だが、父親の交通事故死を経験し、兄が暮らすパリで1週間を過ごすことで、そこで出会った年上の青年に惹かれていく。17歳が体験する現実、その切なさと苦さが入り混じった成長の物語で、俳優ポール・キルシェとリュカ役の信じがたい一体感を、映画を観た誰もが味わうことになるだろう。
『Winter boy』では、無造作に伸ばしたようなヘアスタイルがリュカのキャラクターにしっくりきていたし、どこか憂いと心の迷い、哀しみをたたえた表情が心に残るが、現在のポールは髪をばっさりカット。顔つきも映画とはまったく違う。この年代の俳優で、役と素顔をここまで変えられるとは──。こちらのそんな感想に、ポール・キルシェは、あっけらかんと笑いながら答える。
「撮影を終えたばかりの作品で、実際に髪の毛を剃るシーンを撮ったばかりなんです。だから、そのままの状態で……」
思いのほか背が高いので、身長を聞くと「うーん、測ってないけど、180cm以上はあるかな」とのこと。映画のリュカは、そんなにスラリとした雰囲気ではなく、このギャップもまた俳優の資質か。

フランス映画が好きな人なら、もしかしてポールの顔に“ある人”の面影を感じるかもしれない。母親の名はイレーヌ・ジャコブ。1990年代、『ふたりのベロニカ』『トリコロール/赤の愛』で主役を務め、日本でも人気のあった俳優だ。そして父のジェローム・キルシェも『肉体の森』などで知られる俳優。ある意味、ポールはサラブレッドである。
「子供の頃から両親に劇場へ連れて行かれていた僕は、楽屋で寝かしつけられていたりしました(笑)。当時は両親の仕事なんてまったく理解していなかったのですが、大きくなるにつれ『あなたも将来、俳優になるの?』と周囲に聞かれ、『いや、いや』なんて答えつつ、大学生になってようやく、演じる仕事は世界や周囲の人々を観察することだと知り、喜びを見出したのです。最近、弟も俳優デビューし、家族全員が同じ職業になりました。仕事の話も同業者として理解してもらえるし、悩んだ時にアドバイスを与え合ったりして、いい関係です」

“俳優一家”の現状に満足しているポール。『Winter boy』でリュカの母親を演じるのは、ジュリエット・ビノシュだが、1990年代、日本の映画ファンの間では、イレーヌ・ジャコブとビノシュが「けっこう似ている」との評判もあった。
「そこは今回のキャスティングに多少、影響を与えているかもしれません。僕も自宅で『トリコロール』3部作を観たとき、『青の愛』のジュリエットと『赤の愛』の母が似ていると感じましたから。彼女たちは特に親しい関係ではないようですが……。今回、ジュリエットは私に母性愛で接してくれ、映画の中の家族関係をうまく構築してくれました。現場での彼女の存在感は大きかったですね。クリストフ・オノレ監督は以前、『ジョルジュ・バタイユ ママン』でジュリエットに出演オファーしたものの実現せず、今回ようやく夢がかなったようです」
リュカは、パリで出会った年上男性リリオへの想いを募らせるが、そのきっかけのひとつが、リリオが描く絵だった。じつはポール自身も人一倍、美術への興味があるようで、来日して向かった場所があるという。
「東京国立近代美術館へ行ってきました。内部は歩きやすかったですし、情報の量も的確。侍のオブジェや、ヨーロッパが中世だった時代の日本の絵に感激しました。僕は美術館で絵を見るのが大好きなんです。リュカの場合は、僕ほどにはアートに詳しくなくて、リリオの作品を評するわけではないけれど、何かを強く感じたのは事実でしょう」

『Winter boy』ではラブシーンもあり、もちろん俳優という職業をしているのなら、そのチャレンジは“当然”のこと。しかし近年、こうしたシーンの演出にはインティマシー・コーディネーターが参加し、俳優たちに不安を与えないよう配慮される動きが加速している。
「フランスでもインティマシー・コーディネーターがいて、僕も以前に彼らのいる現場を経験しています。でも本作に関してはインティマシー・コーディネーターが必要ありませんでした。親密(=インティメイト)な関係性を描き、その目的でラブシーンがあるとわかりきっていたので、監督と俳優の合意のうえで進められたのです。すべての動きは監督が振付のように指導してくれました」
さらにもうひとつ。最近は「その役を当事者が演じるべき」という流れもある。この流れは一方で、演じる側にセクシュアリティを問いただすこと(=アウティング)にもつながる。ポールにとって本作はそうしたリスクも伴うわけだが、この難しい問題を突然ぶつけても、彼の答えは明晰であった。
「農家の役を演じる俳優を探す際に、農家の人を雇う必要がありますか? 俳優である以上、どんな性質、職業でもリサーチすることで、自分の栄養分として、その役を体現することが求められます。セクシュアリティの場合、役と同一の人が演じることも重要ですが、すべてそのパターンというわけにいかない。何より、本作はセクシュアリティが重要なテーマではないので……」

やや深刻なトピックになったので、『Winter boy』でカラオケを歌うシーンに話を移すと、「じつは高校、大学とバンドを組んでいて、ボーカル担当だったので歌は大好き!」と目を輝かせる。
劇中ではなかなかの美声を聴かせてくれるので、俳優だけでなくミュージシャンの仕事にも意欲的なのかも。ジョニー・デップやキアヌ・リーブスもバンド活動をライフワークにしているし……と話を向けると、「いやいや、あくまで僕はアマチュア。今は本格的にやってないです(笑)」と謙虚な表情に変わる。
『Winter boy』は、サン・セバスティアン国際映画祭でポール・キルシェに最優秀男優賞をもたらした。同映画祭では史上最年少の快挙であった。
「この映画は主人公が回想する構成ですが、その回想の目的が、より良い自分になろうとすること。思春期の彼は自分のエネルギーや家族への感情、死などを理解できないし、基本的に悲しい物語なのに、あちこちに美しい瞬間があります。演じたのは20歳の時ですが、自分の少し前の時期を振り返って、分析や発見する作業によって、僕自身の足跡が映像にやきつけられました」
演じる役と素顔が異なるのが俳優。同時に、役と本人がひとつになるのも俳優。『Winter boy』は、その両面が実現されたことで、後に大きく飛躍するであろうポール・キルシェにとって、語り継がれる鮮烈な一作となるはずだ。

『Winter boy』
12/8(金)よりシネスイッチ銀座、新宿武蔵野館ほか全国順次公開
(c) 2022 L.F.P・Les Films Pelléas・France 2 Cinéma・Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma