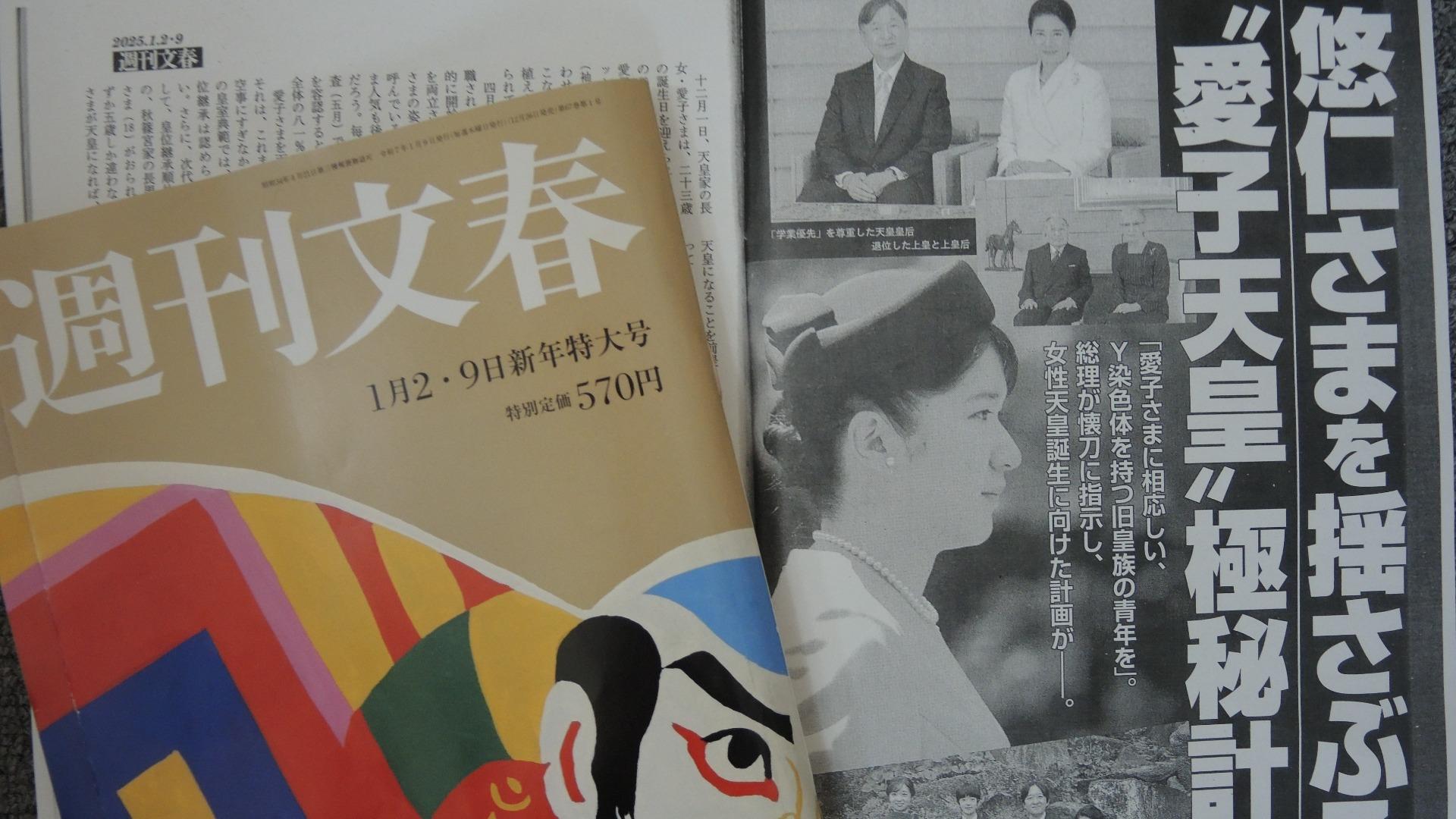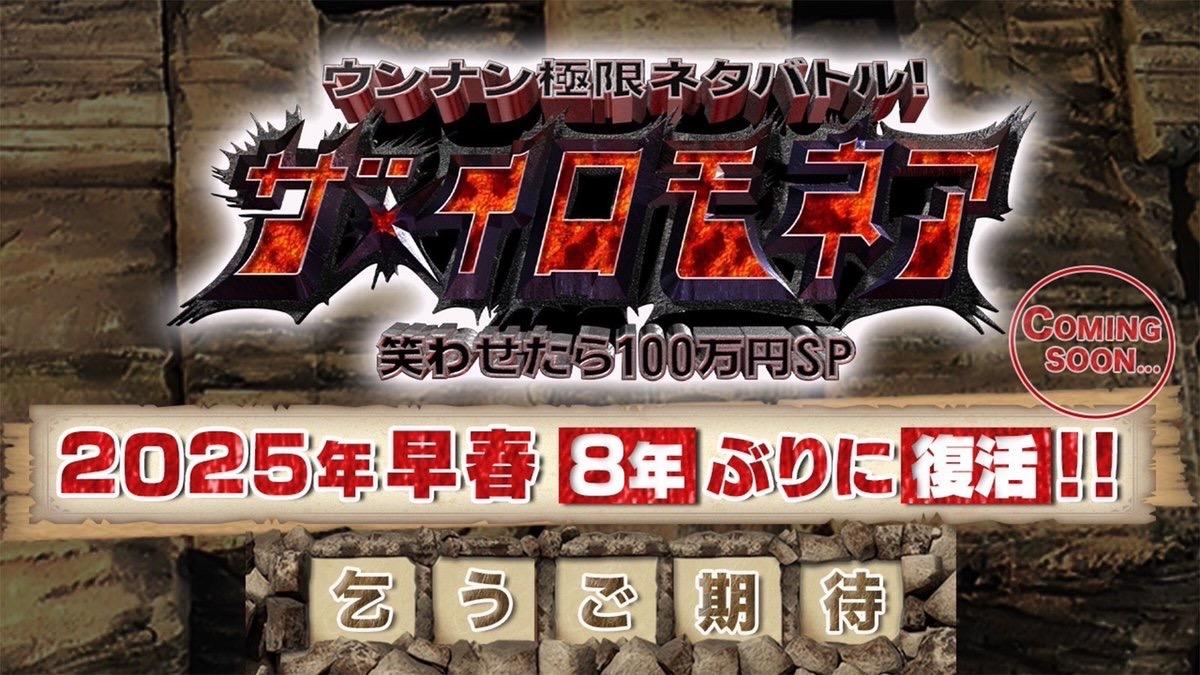下水管の破裂が散発しかねない理由を、財政的に突き詰めてみたら

下水道は、生活に欠かせないライフラインの1つである。ただ、下水管が破裂して一時的に使用できなくなって困るといった事故が時折起きたりする。2024年1月の能登半島地震でも、被災地で下水管の復旧に長い時間を要しており、上水道が復旧しても下水道が復旧できないのでトイレが使えないなどの事態も起きた。
6月17日、日本の下水道事業に関して、新たな調査結果が発表された。そこでは、下水管の破裂が今後散発しかねない理由を、財政的に明らかにしたのである。
調査結果を示したのは、同日開催された財政制度等審議会(財務大臣の諮問機関)の財政投融資分科会で公表された資料「下水道事業者の資金繰りの研究」(財務省理財局・財務総合政策研究所)である。
この調査では、日本の地方自治体の下で運営されている下水道事業者の財務状況を初めて分析し、その実態を解明した。
財政投融資制度には、国が地方自治体に融資をする仕組みがある。その融資を所管するのが財務省理財局で、財政融資資金(財政投融資特別会計財政融資資金勘定)から地方自治体にお金を貸している。中でも、地方自治体が運営する公営企業(会計)にも融資しており、公営企業(会計)の中に下水道事業がある。
財務省理財局は、お金の貸し手として、地方自治体が運営する下水道事業のモニタリングをしており、前掲の調査はその一環で行われた。
この調査結果によると、下水道事業者のうち、企業会計(発生主義 ・複式簿記会計)を採用している団体(地方公営企業法適用団体)となっている878団体を分析したところ、次のような実態が判明した。それは、今後の下水道事業の行方に示唆を与えるものといってよい。
その実態とは、財務省理財局が保有する行政データに基づいて資金繰り能力に着目すると、下水道事業者878団体のうち731団体(約83%)<注>が、なんと
この記事は有料です。
慶大教授・土居ゼミ「税・社会保障の今さら聞けない基礎知識」のバックナンバーをお申し込みください。
慶大教授・土居ゼミ「税・社会保障の今さら聞けない基礎知識」のバックナンバー 2024年6月
税込550円(記事2本)
2024年6月号の有料記事一覧
※すでに購入済みの方はログインしてください。