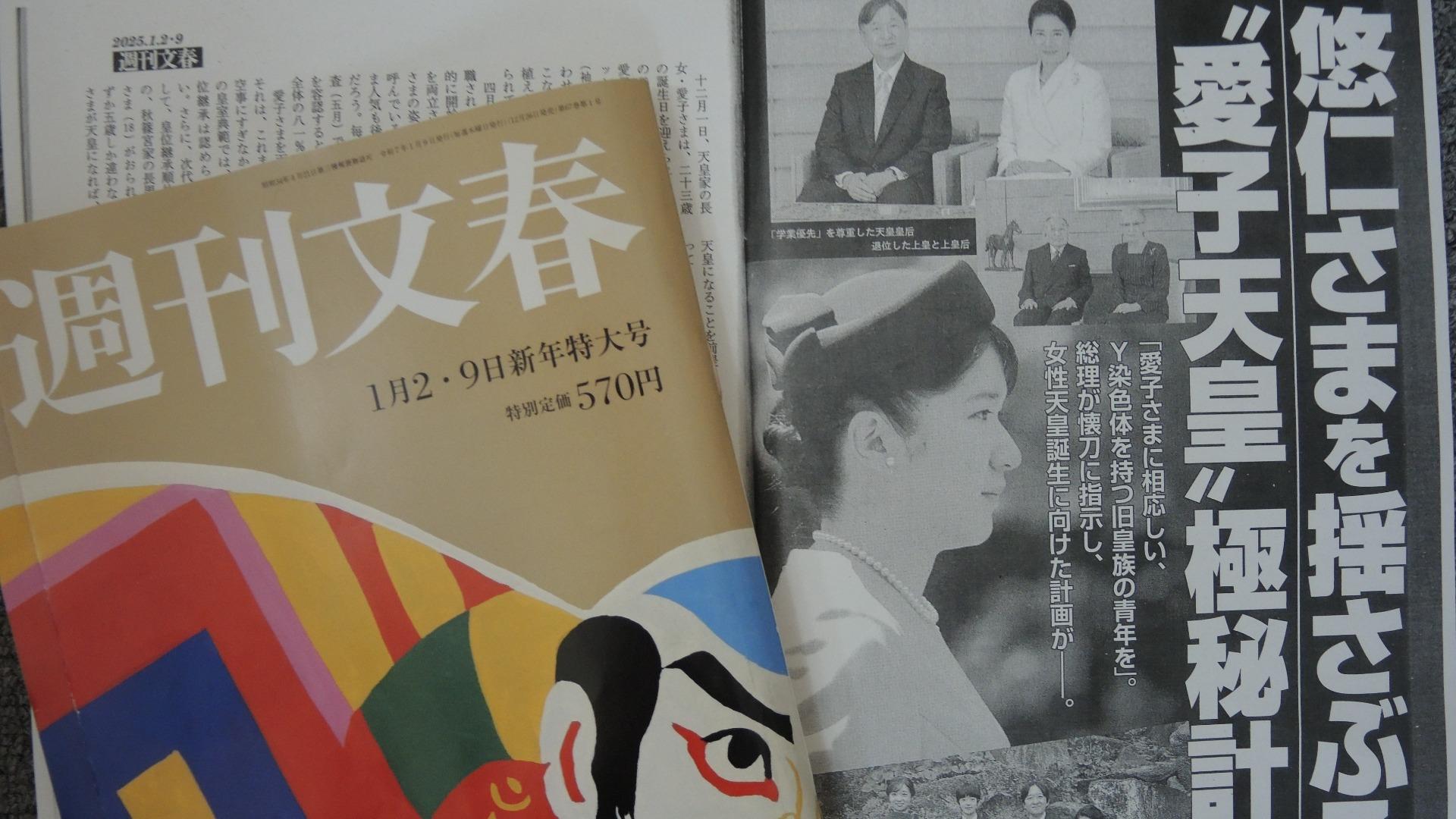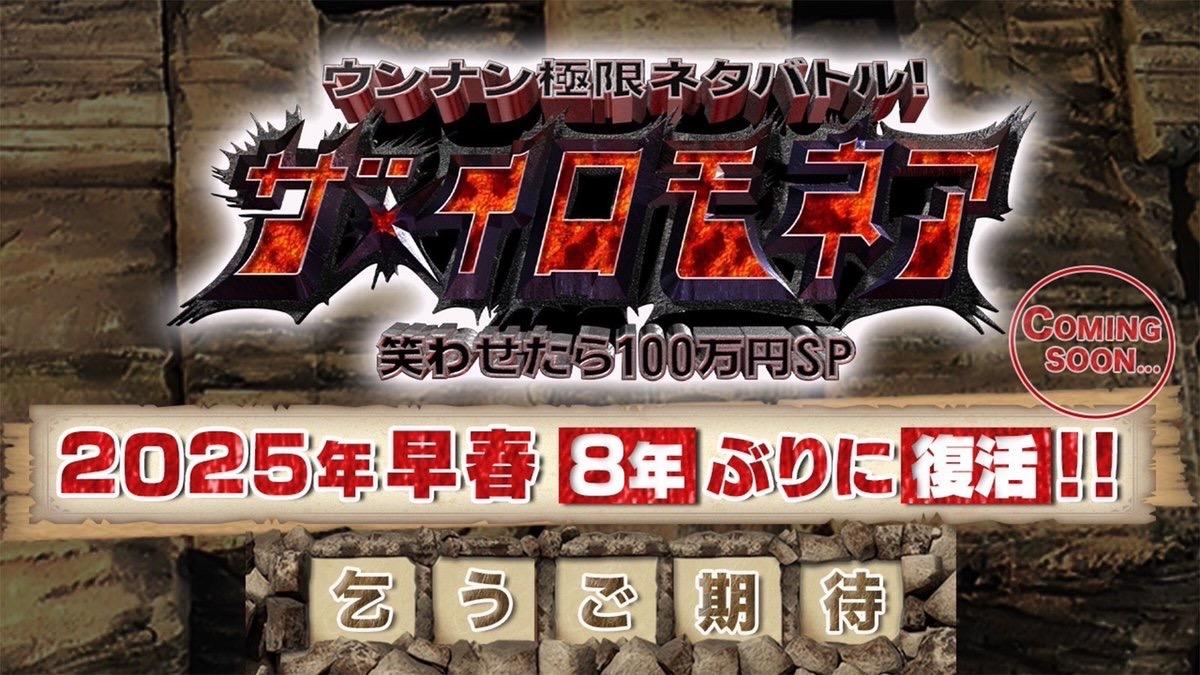「骨太方針2024」で、財政健全化目標はどう位置付けられたか

6月21日に、「経済財政運営と改革の基本方針2024」(骨太方針2024)が閣議決定された。
今年の骨太方針での注目点の1つは、財政健全化目標に関する記述である。
これまでの骨太方針では、2025年度の基礎的財政収支(PB)の黒字化が掲げられてきた。骨太方針は閣議決定されるものだから、そこで明記されることは内閣において極めて重い意味を持つ。
2021年6月に閣議決定された「骨太方針2021」では、次のように明記されていた。
2025年度の国・地方を合わせたPB黒字化と、債務残高対GDP比の安定的な引下げを目指す財政健全化目標を設定する
出典:「経済財政運営と改革の基本方針2021」(骨太方針2021)
しかし、2021年10月に岸田文雄内閣が発足して以降、2022年6月の「骨太方針2022」と、2023年6月の「骨太方針2023」では、「2025年度の基礎的財政収支黒字化」という文言がなくなった。
代わって、
財政健全化の「旗」を下ろさず、これまでの財政健全化目標に取り組む。
出典:「経済財政運営と改革の基本方針2022」(骨太方針2022)
という表現が、2年連続で用いられた。「これまでの財政健全化目標」の中には、前述の通り、2025年度の基礎的財政収支黒字化が含まれることは自明とはいえ、明記はされていなかった。
では、冒頭で触れた「骨太方針2024」では、財政健全化目標についての文言はどうなったのか。
財政健全化の「旗」を下ろさず、これまでの目標に取り組むとともに、今後の金利のある世界において、国際金融市場の動向にも留意しつつ、将来の経済・財政・社会保障の持続可能性確保へとつながるようその基調を確かなものとしていく。そのため、2025年度の国・地方を合わせたPB黒字化を目指すとともに、計画期間を通じ、その取組の進捗・成果を後戻りさせることなく、債務残高対GDP比の安定的な引下げを目指し、経済再生と財政健全化を両立させる歩みを更に前進させる。
出典:「経済財政運営と改革の基本方針2024」(骨太方針2024)
これをどう解釈すればよいだろうか。それは、「2025年度の国・地方を合わせたPB黒字化
この記事は有料です。
慶大教授・土居ゼミ「税・社会保障の今さら聞けない基礎知識」のバックナンバーをお申し込みください。
慶大教授・土居ゼミ「税・社会保障の今さら聞けない基礎知識」のバックナンバー 2024年6月
税込550円(記事2本)
2024年6月号の有料記事一覧
※すでに購入済みの方はログインしてください。