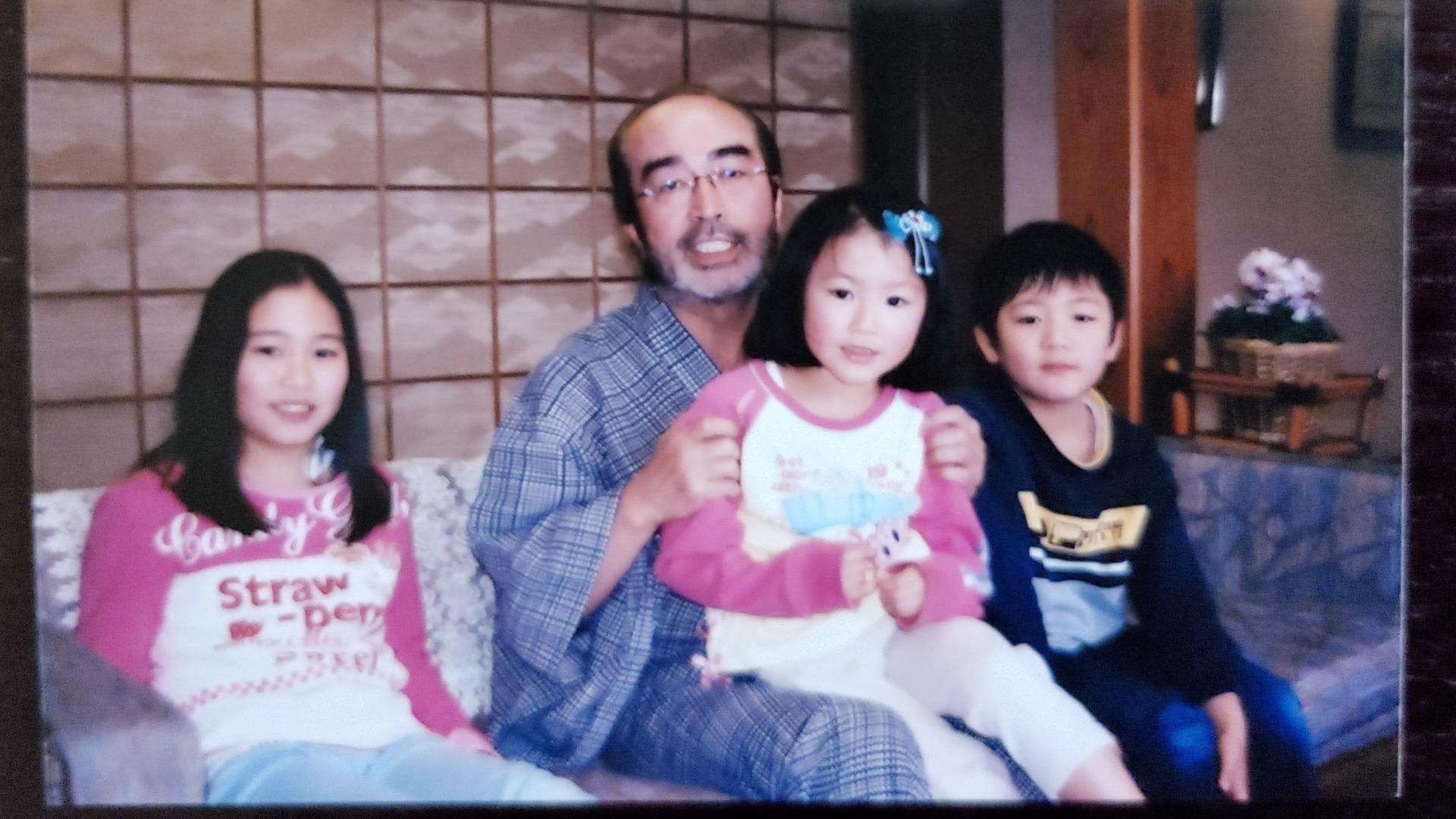総合経済対策39兆円というバラマキで、円安もインフレも加速し、家計は破綻する!

■経済対策をすればするほどインフレが進む
岸田文雄首相は、28日、「総合経済対策」を発表した。それによる財政支出の規模は、財政投融資をあわせた総額がおよそ39兆円。経済対策の裏付けとなる補正予算案の一般会計歳出は29兆1000億円で、この中に“家計に対する支援策”が盛り込まれている。
すでに行われているガソリン補助金の継続、電気料金やガス料金の支援などが支援策の柱とされ、これらによって、標準的な家庭で来年1月から9月までの総額で一世帯あたり4万5000円(一月5000円)程度の負担が軽減されるという。会見で首相は、「(これにより)消費者物価を1.2%以上引き下げる」「生活を支えていることを実感してもらうため全力を尽くす」と、力説した。
しかし、これは単なるバラマキであり、その財源はほぼ国債である。つまり、借金でインフレ対策をするのだから、インフレはさらに進むことになる。それなのに、「消費者物価を1.2%以上引き下げる」とは、どういうことなのだろうか?
■財政を拡大し続ければインフレは進む
国債を発行して、それで得たおカネをバラまくことは、誰にでもできる。この国では、事実上、日銀がいくらでも国債を引き受けてくれるからだ。これは、市場経済を無視した「財政ファイナンス」だが、それを咎める人間は、いまやほとんどいなくなった。
国債を中央銀行に引き受けさせるということは、おカネをいくらでも刷り続けるということだから、マネーストックは膨張し続ける。つまり、おカネが市場に溢れ、インフレは進む。
コロナ禍により、政府は財政を拡大し続けた。2020年度、2021年度に補正予算を含めてそれぞれ175兆円、142兆円という巨額の財政支出が行われた。そしてまた今回、巨額の補正予算が組まれた。
この度を越えた「放漫財政」をやめない限り、インフレは止まりようがない。このままインフレが進めば、一月5000円程度の支援額など、すぐに吹き飛んでしまうだろう。
■世界の中央銀行と真逆のことをやっている日銀
政府による「総合経済対策」の発表と合わせるように、日銀はもはや“異次元”以上となった、異常な金融緩和の続行を決めた。金額に制限をつけず国債を買い入れる「指し値オペ」も続行される。つまり、金利は徹底して抑制されるので、日米の金利差によって拡大する円安は止まらない。
金融政策の常道では、インフレ抑制のためには金利を上げることになっている。いま、FRBをはじめ各国の中央銀行は、どこも金融を引き締めて金利を上げている。しかし、日銀は世界で唯一、その真逆のことをやっているのだから、インフレもまた止まりようがない。
その結果、現在、円は世界でただ一つ、利息がつかないおカネになった。円はもはやおカネとは言えない。
日銀は2022年度の物価上昇率見通しも発表した。それは、2.9%。はたして、こんなものですむだろうか? 来年となれば、これ以上のインフレとなるのは間違いない。
中央銀行は政府の財布ではない。本来なら、政府の放漫財政を止めなければならない。なぜ、財源は国債という「放漫財政」を誰一人として止めようとしないのだろうか。
■「特例法」という例外で際限なく国債発行
そもそも、国債発行は財政法で禁じられている。日銀が国債を引き受けることも禁じられている。しかし、日本では、「特例法」という例外をその都度つくりあげ、財政規律は完全に無視されてきた。
現在にいたる国債乱発のきっかけは、1966年1月19日までさかのぼることができる。
この日、「昭和四十年度における財政処理の特別措置に関する法律」が公布施行され、1965年度限りの臨時特別措置として、租税及び印紙収入の減少見込額2590億円の範囲内で「建設国債」が発行された。これが、戦後初の国債発行である。この最初の国債発行は単年度だけとされたにもかかわらず、以後毎年発行されるようになり、ついには財政赤字を埋めるための「赤字国債」になってしまった。
1966年の最初の国債発行当時、日本銀行理事の吉野俊彦は、「国債発行は、禁断の木の実になる恐れがある。満州事変以降の苦い経験を忘れてしまったのか」と、強く反対した。国会でも反対の声が上がった。しかし、1度限りということで許されてしまったのである。
■なぜ国債発行に歯止めがなくなったのか?
国債発行額は、1965年度にはわずか2000億円だった。しかし、1975年度からは、オイルショックによる経済停滞を乗り切るという理由で大量発行が始まった。国債は借金だから、いずれ返さなければないが、このときは10年後の1985年度から償還を開始すると決められた。
ところが、いざ1985年度になると、政府は「借換債」というものをつくり出し、償還を先送りしてしまったのである。これは、借金のための借金だから、俗にいう自転車操業である。
このときもまた、財政特例法に「借り換え発行はしない」と明記されていたにもかかわらず、無視された。以来、日本の財政には歯止めがなくなってしまったと言っていい。
本来、財政支出は、税の範囲内で行うものだ。足りない部分は、ほかの支出を削るなどしてやりくりしなければならない。それをしないで安易に借金ばかりを続けている日本政府は、まさに借金の“病人”“中毒患者”である。
■財政赤字を維持するための「定理」がある
すでに日本の財政は、「ドーマーの定理」をはるかに逸脱している。ドーマーの定理とは、1940年代にE.D.ドーマーによって提唱された財政赤字の維持可能性に関するセオリーで、財政が赤字でも維持を可能にするには、対GDP比でみた政府債務残高を膨張させずに、一定の割合以下で推移させることが必要だというものだ。
そのためには、まず「プライマリーバランス」(基礎的財政収支)を均衡させねばならない。それができていれば、名目GDP成長率が政府債務の名目利子率を上回ることにより、財政赤字の維持は可能だというのだ。
政府債務の名目利子率と名目GDP成長率が等しい場合は、プライマリーバランスがゼロであれば、政府債務の名目GDP比は膨張しない。毎年の政府の支出は毎年の税収で賄われるので、赤字になるのは過去の債務の金利負担分だけとなる。この負担分が名目GDP成長率と同じなわけだから、政府債務の名目GDP比は上昇しないのだ。
■プライマリーバランス無視の先にあるもの
以上がドーマーの定理だが、この条件が満たされれば、政府債務の名目GDP比が100%であろうと300%であろうと、理論的には破綻しない。
ということは、まずはプライマリーバランスの均衡化を達成し、次にこれを少しでも黒字化する。あるいは、名目利子率を上回る名目GDP成長率を達成する。
その努力が、国家としては絶対に必要だ。
しかし、現在の日本政府は、プライマリーバランスをさんざん先送りした挙句、ついに無視するようになってしまった。
もう手遅れに近いが、この先になにがあるかは言うまでもない。ハイパーインフレによる国民生活の崩壊だ。国の財政破綻はなくとも、国民の家計は必ず破綻する。
ハイパーインフレはいつ起こるかわからない。しかし、いまの日本のインフレは、まだ欧米諸国に比べて低いとはいえ、その入り口にいるのは確かである。なぜなら、基本的な対策すらなされていないからだ。
■思い出される財政改革「ネバダ・レポート」
これまで、何度となく財政危機が叫ばれ、その処方箋も提案された。しかし、アベノミクス以降、ほぼ誰もそんな提案をしなくなった。
たとえば、2002年2月14日の衆議院予算委員会では、当時、議員や関係者にかなり出回っていた通称「ネバダ・レポート」が取り上げられ、議論があった。
第154回 衆議院予算委員会(第10号2002年2月14日)
(参照)国会会議録検索システム:https://kokkai.ndl.go.jp/#/
「ネバダ・レポート」が示した改革案は、まとめると次の通りである。
①公務員の総数及び給料の30%カット。ボーナスはすべてカット。
②公務員の退職金は100%すべてカット。
③年金は一律30%カット。
④国債の利払いは5~10年間停止。
⑤消費税を15%引き上げて20%へ。
⑥課税最低限を年収100万円まで引き下げ。
⑦資産税を導入し、不動産に対しては公示価格の5%を課税。債券・社債については5~15%の課税。株式は取得金額の1%を課税。
⑧預金は一律、ペイオフを実施するとともに、第2段階として預金額を30~40%カット。
■「最後の審判の日」は必ずやってくる
いまや、これくらいのことをやっても、日本の国家財政は持たないかもしれない。しかし、公務員のリストラと給料カットもしないで、増税に等しい国債発行でバラマキをやろうという政府は、国民にとっては“敵”でしかない。
英国でトラス首相が退陣せざるを得なくなったのは、安易な国債発行に頼るインフレ対策を発表したからだ。これで国債金利は上がり、年金資金は破綻しそうなった。“市場の反乱”にあったのである。
このまま行けば、日本もいつか“市場の反乱”にあうのは間違いない。その日(「ドゥームズデイ」=「最後の審判の日」)は、必ずやってくる。