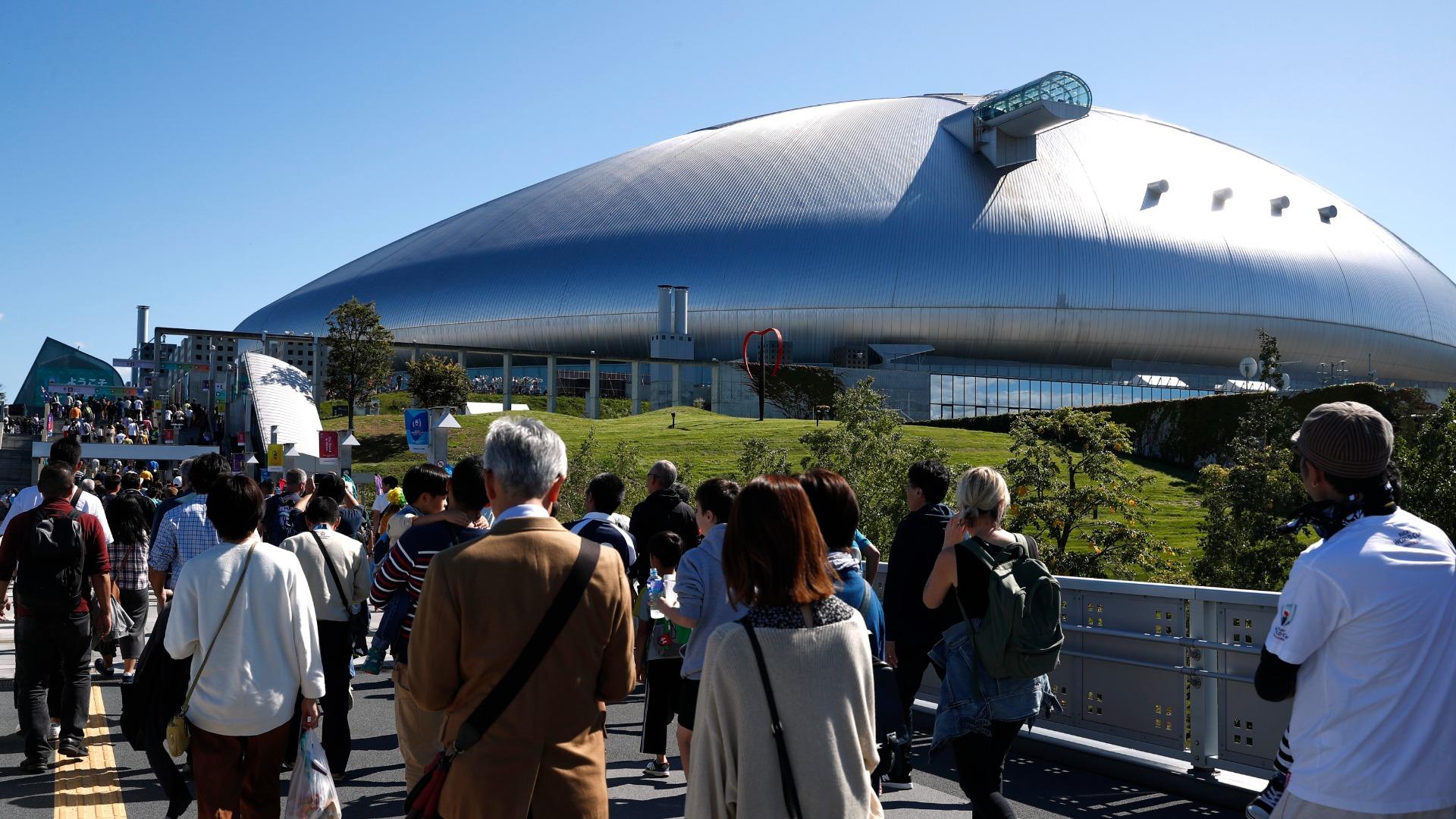今川氏真は今川氏を滅亡に追い込んだ愚将だったのか

大河ドラマ「どうする家康」では、今川氏真の動きが注目されている。氏真は愚将と評価され、今川氏を滅亡に追い込んだ張本人であると言われてきた。今回は、その点について考えてみよう。
今川氏真は、「海道一の弓取り」と称された義元の子である。永禄3年(1560)5月、義元は桶狭間の戦いで織田信長に敗れ、討ち取られた。
かつて義元は和歌などの文芸にうつつを抜かし、公家文化に傾倒するなど、武将にあるまじき軟弱な武将と評価されてきた。それは、周防の大内氏(学問)、将軍足利義政(茶道)も同じである。
実は、氏真も父と同じような評価を受けていた。松平定信は、氏真が歌道に執心するあまり、滅亡してしまったと指摘した(『閑なるあまり』)。氏真は、公家化した軟弱な武将と言いたかったのだろう。
氏真は譜代の家臣を重用せず、佞人を登用したとされ、国を滅ぼした無能な大名との評価も与えられた(『甲陽軍鑑』)。また、氏真は父の義元が桶狭間で信長に討たれたにもかかわらず、復讐すらしなかったと辛辣に批判された(『徳川実紀』)。
氏真の代になって今川家は滅亡したのだから、有能な武将だったとは言えないかもしれない。しかし、氏真が歌道や蹴鞠に熱心だったから、無能だったというのは短絡的である。
当時、武田氏、北条氏が関東、東海地方で大勢力を誇っており、信長と同盟を結んだ徳川家康も勢いを増していた。義元にはカリスマ性があったが、氏真は実績が乏しかったので、父の戦死は大きな痛手だった。
今川氏が同盟を結んでいた武田氏、北条氏も、氏真の力量に疑問を持ったに違いない。そうした政治的な状況の中、氏真は十分に家臣団をまとめきれず、外交にも失敗したというのが現実だったと考えられる。
父の死後、氏真は北条、武田、徳川の諸氏を相手にして、よく家を保ったといえるかもしれない。同盟を結んでいた武田氏、北条氏が手のひらを返したように氏真を裏切ったのは、予想外だったことだろう。
実質的に今川氏が滅亡(大名としての地位を失った)したのは、永禄12年(1569)のことである。氏真はその後も各地を流浪しながら長生きし、慶長19年(1614)に亡くなった。