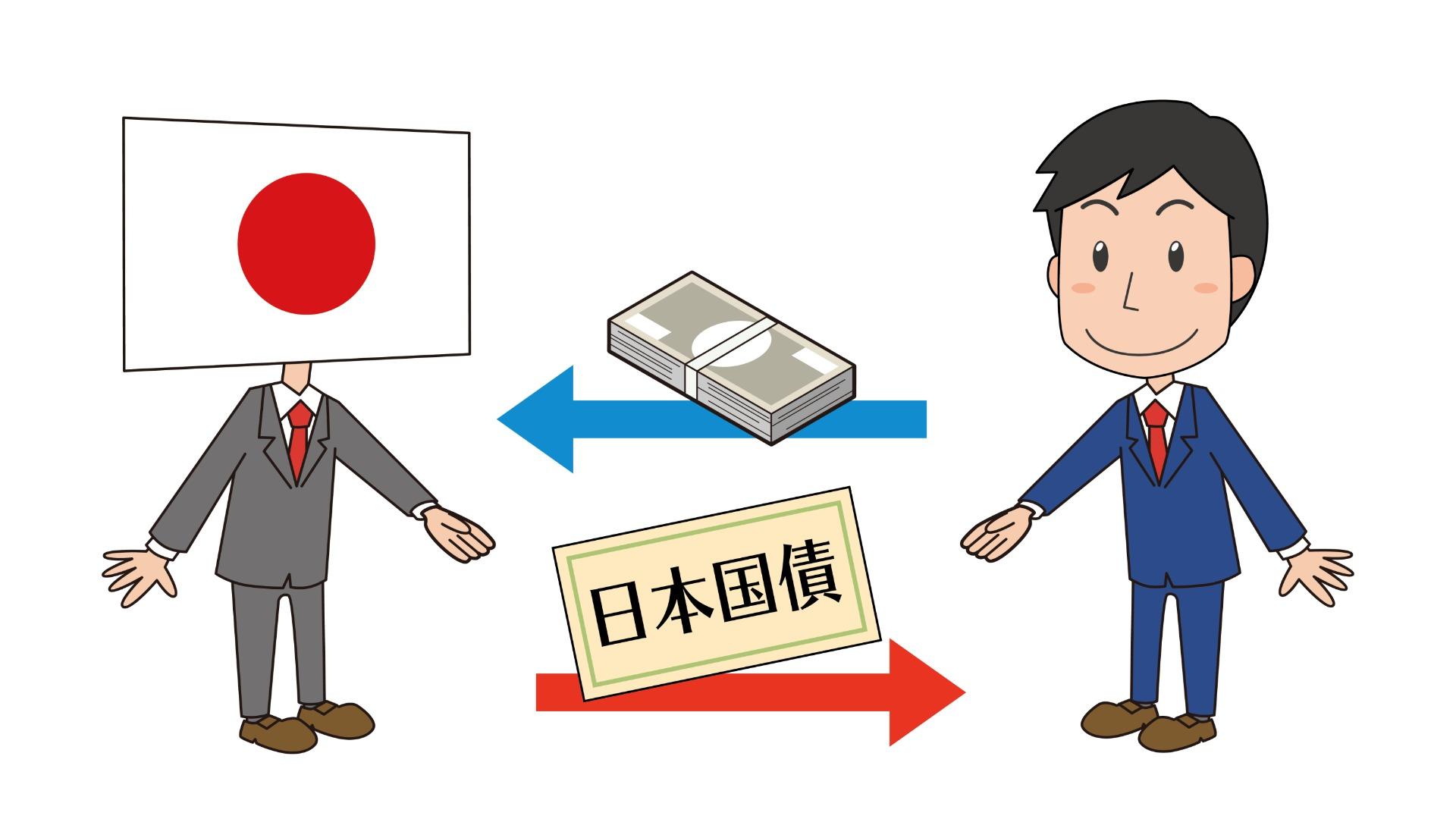ハリー王子とメーガン妃、アメリカでの人気が急落。過剰なメディア露出が裏目に出た?

2021年3月、オプラ・ウィンフリーによるメーガン妃とハリー王子の独占インタビューが放映された時、メーガン妃の母国アメリカでは、彼らに対する同情が強く寄せられた。イギリス王室の誰かが生まれてこようとしているメーガン妃とハリー王子の赤ちゃんの肌の色について憶測したとか、メーガン妃が精神を患っているのに治療を受けさせてもらえなかったなどという暴露話をアメリカ人は信じ、青ざめたものだ。その直後にはマイケル・ムーア、セリーナ・ウィリアムズ、ジェイダ・ピンケット=スミスなど多くのセレブがメーガン妃とハリー王子を応援し、アメリカへの移住を歓迎するメッセージをソーシャルメディアに投稿している。
メーガン妃とハリー王子によるイギリス王室の実態についての告発はその後も止まらず、昨年末にはNetflixで6話構成のドキュメンタリーシリーズ「ハリー&メーガン」が配信され、先月はハリー王子の回顧録「Spare」が発売されてベストセラーとなった。だが、それらのおかげで彼らへの共感が強まるかと思いきや、現実は逆だったようだ。

「Newsweek」が今週発表した調査結果によれば、2月19日の段階で、メーガン妃を「好き」と答えたアメリカ人は27%、「嫌い」と答えたアメリカ人は44%。昨年12月、今年1月と時間を減るごとに「嫌い」が増えている。「ハリー&メーガン」が配信開始になる前の12月に比べると、40ポイントもマイナスだ。ハリー王子を「好き」なアメリカ人は32%、「嫌い」なアメリカ人は42%。彼もまた前回の調査より10ポイントもマイナスとなった。
一方で、ウィリアム王子、キャサリン妃、チャールズ国王、カミラ王妃のアメリカにおける好感度はアップしている。2月19日段階で、ウィリアム王子を「好き」と答えた人は、なんと42%。「嫌い」は19%だ。キャサリン妃は、「好き」が44%、「嫌い」が12%。チャールズ国王の場合は、「好き」が29%、「嫌い」が18%、カミラ王妃は「好き」と「嫌い」がいずれも23%だった。
これらの人々は、「Spare」の中で、ハリー王子が悪口を散々浴びせた相手。彼らが自分にどんな酷いことをしたのか具体的に書き、それは世界の多くの人に読まれたのに、むしろ彼らの人気が上がったとあれば、ハリー王子はおそらく悔しくてたまらないに違いない。逆に、被害者であるはずの自分たちへの支持は落ちるばかり。ほんの少し前までは自分たちを大歓迎してくれたアメリカで、そんなことが起きているのである。
これは明らかに、ハリー王子とメーガン妃に対するアメリカ人の信頼が崩れてきたことの表れだろう。ウィンフリーによるインタビューが放映された直後、イギリス人ジャーナリストのピアース・モーガンはメーガン妃の発言を「何も信じない」と言ってレギュラー番組を降板させられ、人種差別者とまで呼ばれている。しかし、時間が経つごとに、彼の指摘することがまっとうであることを、人は気づいていった。たとえば、「実は結婚式の3日前にこっそりと結婚していた」ということはそのひとつ。よく考えれば考えるほど、そんなことが本当にありえるのかと疑問が濃くなっていったが、「ハリー&メーガン」では完全にスルーされている。全部で6時間もあるシリーズで、彼らの言う“本物”の結婚式について述べる時間がなかったとは、とても思えない。
皮肉にも、彼らがメディアに露出して発言すればするほど、アメリカ人は彼らを見抜いていったということ。最近放映された「South Park」最新回のパロディが大好評を得たのも、そんなアメリカ人の気持ちをばっちりととらえていたからだと言える。

このアニメの中で、ハリー王子とメーガン妃をモデルにしているのが明白なフィクションの“カナダの王子とその妻”は、「プライバシーをくれ」と言いつつ、わざと目立つことをして人の注目を集めようとする。そんな夫妻にうんざりした登場人物らは、「もうその人たちの話は聞きたくない」と言うが、そう思ってはいても避けられないほど、彼らはうるさい。それを「どんぴしゃだ」と、今やアメリカ人は思っているのである。
好感度という重要なものが失われつつある今、ハリー王子とメーガン妃は自分たちのブランドを次にどう持っていくのか。Netflixとは、「ハリー&メーガン」のほかにもコンテンツを提供していくということで、1億ドル(約135億円)の契約を結んでいる。「Spare」を出版したペンギン・ランダムハウスとハリー王子の契約は、4冊。つまりこの後にも3冊の執筆が期待されているということだ。さらに、メーガン妃も回顧録を執筆中だという報道もある。それらの新たなコンテンツの内容や、その宣伝のためにまたメディアに露出すれば、再度「South Park」のネタにされかねない。そんな不名誉はなんとしても避けたいところだろう。生き残りのためには、「イギリス王室にいじめられた被害者」のアプローチとは違う新たな戦略が必要とされているようだ。