脳死臓器移植400例目。法改正を見据えた議論を
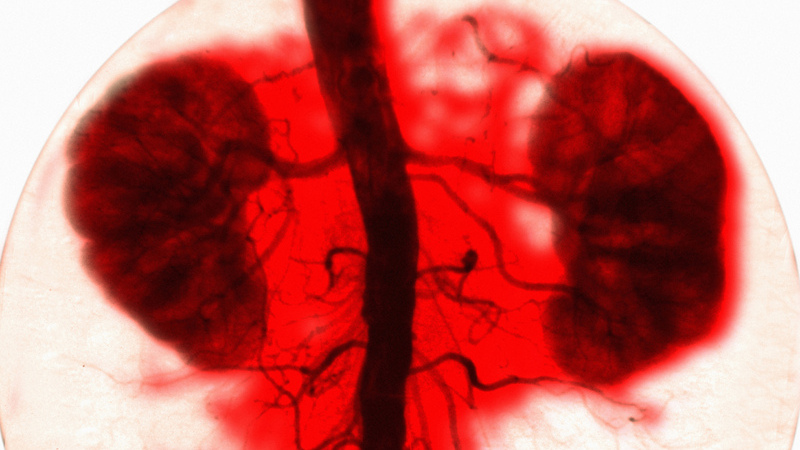
兵庫県内の病院に蘇生後脳症で入院していた30代男性が脳死と判定され、順調に行けば臓器移植法施行後400例目となる脳死移植が行われる見通しである。
400例を超えたことは喜ばしいが、残念ながらまだまだ臓器提供数は足りていない。日本は次の法改正を見据えた議論を始めるべきときに来ている。
2010年の法改正で脳死移植は増加
上記の400例目の脳死臓器移植を報道する記事では次のように書かれている。
同法〔臓器移植法〕は1997年10月に施行され、2010年9月に100例を超えた。同年7月の法改正で本人の事前の意思表示がなくても家族の承諾で提供可能となり、以降は提供数が大幅に増加。現在は年間50例程度のペースで脳死移植が実施されている。
たしかに2010年の法改正以前と比べれば、脳死体からの臓器移植は多くなったと言える。しかし、死体と生体からの臓器提供数を全体として眺めた場合、現状は決して手放しで賞賛できるものではない。
(なお、正確には、臓器移植法は2009年法改正、2010年改正法施行であるが、便宜的に以下でも「2010年法改正」と記す)
死体からの臓器移植は増えているのか
2010年の法改正によって、家族の承諾で脳死下での臓器提供ができるようになった。それにより、これまで年間10件程度だった脳死からの臓器提供は、5倍程度増えた。
しかし、その影で、以前から家族承諾のみで可能であった心停止後の献腎移植は減っている。そのため、トータルには死体からの提供数は減っている(「臓器移植ファクトブック2015」2頁図2参照)。
心停止後の死体からは、腎臓や眼球の移植は可能だが、脳死の場合とは異なり心臓や肝臓などの移植はできない。その結果、脳死体からでなければできない心臓や肝臓の移植数は増えたが、腎臓移植は改正前よりも減ってしまった(同、2頁図3参照)。
腎臓について言えば、現在、日本臓器移植ネットワークに腎移植を希望して登録している人は約12,400名である。一方、心停止および脳死を含めた死体からの腎臓提供数は年間130件程度だ。すると、単純計算すると、死後の臓器提供を受けるには約100年待たないといけないことになる。
もちろんそんなに待てる人はいないので、多くの人は親族から片方の腎臓のもらい受ける生体腎移植を行っている。生体腎移植は現在では年間1400件以上行われている。
しかし、本当は生体臓器移植は望ましくない。ドナー(臓器提供者)となる家族への身体的・心理的な負担や、ドナーになれる家族のいない患者にとって不公平であるなどの問題があるからだ。したがって、なるべくなら死体からの臓器移植の方が望ましい。
また、海外に渡航して移植を受ける人もいる。これはとくにドナーの少ない小児において深刻な問題で、2億円から3億円のお金を募金で集めて米国などに心臓移植を受けに行く子どもたちが後を絶たない(「臓器移植ファクトブック2015」21頁図12参照)。
しかし、米国でも移植用の心臓が余っているわけではなく、日本人の子どもが心臓移植を受ける影では、移植を待って死んでいる米国人の子どもが毎年50名から100名程度いるという現実がある(同、22頁図13参照)。
2010年の法改正の背景には、臓器移植の一国内での「自給自足」を謳った国際移植学会によるイスタンブール宣言(2008)があった。しかし、法改正後5年を経て、提供数が十分に増えていないことは明らかだ。次の法改正を見据えた議論を始める必要がある。
次の臓器移植法改正に向けて
来年は臓器移植法ができて20周年になる。これを機会にぜひ次の法改正に向けた国民的議論をすべきだと思われる。議論すべき一つの点として、オプトアウト制度が挙げられる。
現在の日本の臓器移植法では、本人あるいは家族が承諾しなければ、死体からの臓器提供はなされない。これはオプトイン制度と呼ばれる。
一方、ヨーロッパ諸国を始め、国によっては「拒否しない限りは臓器提供の意思があるとみなす」というオプトアウト制度を取っているところがある。こちらの方が一般的には臓器提供数が増えることが知られている。この制度の導入の是非を真剣に議論すべきである。
たとえば、サンスティーンらのナッジの一例として紹介されたこともありよく知られている例だが、オプトイン制度を取っているドイツでは臓器提供の有効同意率は12%程度に留まるのに対して、オプトアウト制度を取っている隣国のオーストリアでは有効同意率はほぼ100%である。また、昨年12月にオプトアウト制度に変更したウェールズでは、臓器提供数が3倍近くになっている。
もちろん、これだけではなく、なぜ臓器提供数が思ったようには増えていないのかについて、十分に議論を尽くす必要がある。また、キメラ動物からの異種移植などの技術的可能性も議論すべきであろう。
移植医療は「命のリレー」とも呼ばれるが、現在はバトンが足りずに多くの命が失われている状況である。我々に何ができるかをよく議論すべきであろう。(了)










