音楽用語「アーバン」禁止の衝撃! アリアナ・グランデら所属レーベルがBLM運動に共振した新方針とは?

青天の霹靂に、米英音楽業界が激震した
思わず自分の目を疑って、BBCニュースを二度見してしまった。6月8日のことだ。「音楽用語としての『アーバン(Urban)』を、当社では今後一切使用しません」との宣言を、当代屈指の有力レコード・レーベル「リパブリック(Republic)」が公式SNSで発表したのだ。アリアナ・グランデやドレイクを擁する、つまりアメリカの「いま」の音楽シーンを明らかにリードする、ユニヴァーサル・ミュージック傘下のレーベルによる突然の宣言だったから、文字通り、米英の音楽業界は「激震」した。「ブラック・ライヴズ・マター(Black Lives Matter=以下BLM)運動の波は、ここまで来たのか!」と。

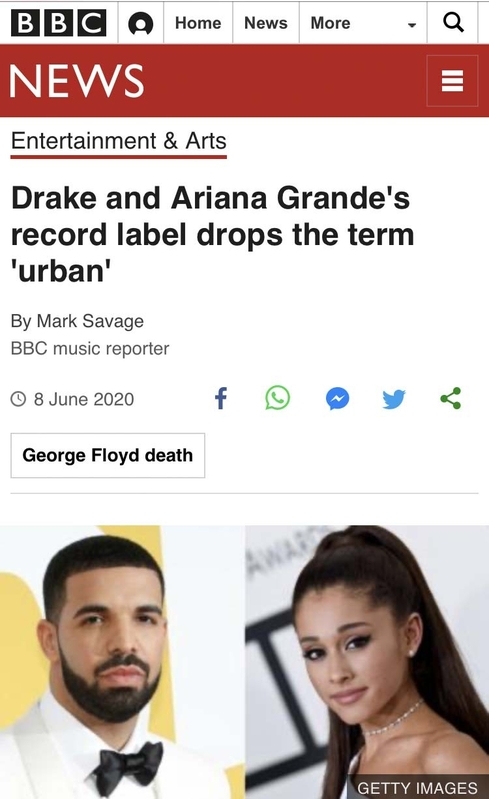
「禁止」のどこが「びっくり」だったのか?
この「アーバン」なる言葉、音楽用語としては、日本ではあまり馴染みがない人もいるかもしれない。しかし英語圏においては、かなり以前から当たり前に親しまれていたものだ。平たく言うと「黒人が作った今日的なポップ音楽の、ほとんどすべて」を包括する言葉がこれだった。
だから、こんな例を想像してみてほしい。「今日から音楽用語としての『Kポップ禁止』!」とか突然言われても、みんな困る。びっくりする。そんな感じの「超大型版」がこの「リパブリック宣言」だった、と考えていただければ、遠くはない。
しかも、もしかしたら「アーバン」なる音楽用語に関連する曲やアルバム、つまり黒人音楽に起源を持つポップ音楽によって「当代屈指の」恩恵をこうむっているレーベルこそがリパブリックだった、かもしれないのだ。上記2名以外にも、同社には、ニッキー・ミナージュとザ・ウィークエンドとポスト・マローンがいて、テイラー・スウィフトもいまはいる!のだ。桁外れのメガスターが揃い踏みしていて、そのうちの大半が(肌さえ黒ければ)「アーバン」と分類されるような音楽に、濃厚な影響を受けているのだから。
そんなレーベルの宣言だから、すでに業界に波紋は広がりつつある。まずは、あのグラミー賞を主催するレコーディング・アカデミーが、リパブリックに追随して「アーバンやめます」との発表を10日におこなった。

同賞には「アーバン」を冠する賞がいくつもあった。その名称を、ほぼ全部変更するのだという。たとえば「最優秀アーバン・コンテンポラリー・アルバム賞」は「最優秀プログレッシブR&Bアルバム」とする。「最優秀ラテン・ロック、アーバン、オルタナティヴ・アルバム賞」は「最優秀ラテン・ロック、オルタナティヴ・アルバム賞」と「アーバン」だけをそこから抜く……というわけで今後「アーバン」が、業界のいろんなところから急速に消えていくことは、まず間違いない。音楽業界が劇的に変化していく、その糸口となるような「事件」がこれだった――と、のちの音楽史家は言うのかもしれない。
アーバンはなんで「ダメ」になったのか?
では「どんな呼称が」今後は浮上してくるのか?――というとこれは、まったく難しくない。たんに「ヒップホップ」「ラップ・ソング」「R&B」と、それそのものが指向している音楽性を指せばいいだけだ。アーバンとは「これら全部」を無理にたばねようとしていて、それゆえに問題視された、のだから。
逆に言うと、ヒップホップやラップ、R&Bといった、黒人社会や人々から生み出されてきた、現代のポップ音楽を語る上で欠かすことができない(そう「まったく」できない!)要素、素晴らしい貢献の「具体性」を、意味のぼんやりした用語のなかに溶かし込み、希釈してしまう……という意味において、ここのところ非難されていたのが「アーバン」だった。
という点について、日本の人はピンとこないかもしれない。音楽ジャンル用語としての「アーバン」があまり定着しなかったからだ(その理由は後述)。それどころか、こんなふうに思う人もいるかもしれない。
英語の Urban とは「都会的な」という意味があるから、いいじゃないか? なんで怒る人がいるの? それこそ、いまリヴァイヴァル中の日本の「シティ・ポップ」みたいでお洒落なのに……とか。
まあお洒落かどうかはおいといて、問題はそんなところにはない。こんな例を想像してみてほしい。たとえば「白人が作ったポップ音楽はすべて『カントリー』と呼ばれる」ことに決まっていたとしたら?――
業界紙も、音楽賞も「白人が作ったんだから『カントリー』でいいでしょう」と、なにもかも全部ひとまとめにしていたら……きっとみんな、怒るはずだ。「俺はロックをやってるんだ」とか、「フォークでなにが悪い」とか、「白人がラップやっちゃいけないのか」とか。そして、みんなが声を揃えてこう言うはずだ。「まとめるなよ」と! 「人種で、肌の色で、ひとまとめにするんじゃないよ!」と……。
つまり、それが「いま」起こりつつあることなのだ。「アーバン」を廃止しようとする、原動力となっている精神性なのだ。
だからこれは、アフリカン・アメリカンが新たに獲得した「勝利の地平」へと、確実につながっていくものだと僕は考える。上記のたとえ話のごとく、とみにここ最近、当事者である黒人アーティストたちから「評判が悪かった」呼称がアーバンだったからだ。BLMの大嵐が音楽業界をも吹き荒れている現在、起こるべくして起きた「肯定的な前進の一歩」こそが、この「アーバン禁止」だったわけだ(まあ突然なので、びっくりさせられたが)。
とはいえ、「ではなぜ」アーバンなる呼称が黒人のポップ音楽の総称となったのか? じつはそこにこそ、無数のアーティストの、音楽業界人の「肯定的な」日々の行為の積み重ねも反映されていた。最初から「悪い意味で用いられていた」わけではない。ここの点を解説しよう。
「アーバン」はどこから生まれたのか?
黒人が作るポップ音楽と「アーバン」が結びつけられたのは、70年代中盤。当時人気のラジオDJだった、フランキー・クロッカーが「アーバン・コンテンポラリー(Urban Contemporary)」なるフレーズを考案したのが最初だ。ニューヨークで活躍する黒人DJの彼は、音楽的アイデア豊かな、一種の名物男だった。彼の選曲は、ソウルもファンクも一緒くたにして、分け隔てなくエアプレイしていく、というもので、ときにドリス・デイなんかもミックスされた。なにかと折衷的なこのスタイルについて彼が自称したのが「アーバン・コンテンポラリー」だった。現代の都会、メトロポリスの住人は、こんな音楽を聴くべきなんじゃないの?といった、ひとつの提案をおこなう際の呼称だったわけだ。
ときあたかも、ディスコ・ブームの黎明期だった。洗練された「都会の夜遊び」が輝きを放つ時代の入り口だった。ゆえにこの新語の語感はとても耳触りがよく、クロッカーの選曲の洒脱ともども、「新しく」感じられた。たとえば70年代前半あたりまでのファンク「ばかり」を連続して聴き続けるのってしんどいよね、汗臭くてつらいかも――なんて感じているような層に受けたのだが、この数が少なくなかった。つまり、当たった。
まさにこんなテイストが「アーバン」イメージの総集編だった、のかもしれない。
アメリカにおける音楽ジャンル用語のかなり多くが、その発祥をラジオ局の選曲(の方針)に求めることができる。日本とは違って、ちょっとした街ならば選択に困るほどのラジオ局があるのが「アメリカの普通」なので、特徴を打ち出していかないと埋没してしまうからだ。ゆえにこの「アーバン・コンテンポラリー」も、多くのステーションが模倣した。そしてこの「ラジオ局の選曲方針」が、徐々に「黒人が作った現在進行形のポップ音楽」全体を表するジャンル用語、概念として定着していく。そして(カントリー&ウェスタンが「カントリー」になり、ロックンロールが「ロック」となったように)「アーバン」と省略されてしまうまで、あまり時間はかからなかった。
つまり最初は「とてもイケている」呼称だったわけだ。事実今回のリパブリックのコメントにも「アーバンの最初の定義には、否定的な意味はありませんでした」として、一定の歴史的評価を与えている。問題は「やがてアーバンの定義と含意が変化して、音楽業界のいろんな分野にいる黒人を、大雑把にまとめてしまう役割を果たすようになりました」というところにあったわけだ。
でもなぜに「アーバン」だったのか?
クロッカーが「アーバン」なる語を選んだ理由、単純にそれは、彼がニューヨークを基盤としていたからだろう。また彼に追随した各地のステーションも、都会の局が多かった。なぜならば「黒人音楽を好む層は都市部に多く住む」とされるテーゼが、まだ一般的に生きている時代だったからだ。黒人やヒスパニック、あるいはアジア人などの移民系の有色人種は都会に住んで労働者となる――とされた時代があった。そんな印象からも「アーバン=黒人音楽」という図式は、わかりやすくもあった。
ちょうどそれは、きわめて「白人向け」とされている音楽が、「田舎」という意味もある「カントリー(Country)」の名を冠していることと、好対照を成してもいた。だからそれぞれがそれぞれに「わかりやすい」先入観の道具とも、なっていた。
だが現実的には、たとえばニューヨークにかぎらず、全米の主要都市の多くは90年代以降の急速な「ジェントリフィケーション」による開発の果てに、正気では考えられないほどの住居費がかかる、新興成金の牙城となっていった。だからかつて、映画『タクシードライバー』(76年)にあったような、荒れ果てたインナー・シティの軋轢が叩きつけられていた音楽ジャンルがファンク(の一部分)だったとしたら、ディスコという「かりそめの社交界もどき」を経由して、光輝くトランプ・タワー(とミニ・トランプ軍団)が各地の街をお買い上げになるまでのあいだ、水先案内人となっていた概念が「アーバン」だったのかもしれない。そしていま、その歴史的役割が「完全に終了した」ということなのだろう。
「人種音楽」なんて呼ばれていた時代もあった
ちなみに音楽業界において、黒人音楽を「総称する」用語というのは、なにもアーバンが最初じゃない。時代ごとに変遷してきた。最初の例は、なんと「レイス(Race)音楽」というものだった。つまり「人種音楽」なんて呼ばれていたわけだ。ブルースもゴスペルも、全部ひとまとめにして。これが20年代から40年代いっぱいまでの話だった。歴然たる人種隔離政策があったアメリカにおいては、この呼称は妥当なものと考えられていた。
これを「変えた」のは〈ビルボード〉だった。のちに名音楽プロデューサーとなるジェリー・ワクスラー(当時はジャーナリストだった)のサジェスチョンによって、49年、黒人音楽レコードの人気チャートを「リズム&ブルース(R&B)」と記するようになった。これは「作っている黒人側」が使用している呼称とほぼ同じものだった。同欄は時代に合わせて変遷した。一時の休止を経て、69年より「ソウル」チャートになり、82年には「ブラック」チャートになり、そして90年に再び「R&B」に戻り、そこにヒップポップが並ぶ形の名称で、今日まで続いている。
日本には、「アーバン」のかわりに「ブラコン」があった
日本において、略称「ブラコン」なるものが一般的だった時代をご存じだろうか? 「ブラック・コンテンポラリー(Black Contemporary)」の略なのだが、これが日本では「現代的な黒人ポップ」の総称として、70年代末から90年代初頭まで、きわめて支配的だった。そもそもは〈キャッシュボックス〉が一瞬だけ(78年から82年まで)R&Bを指す際のキャッチフレーズ的にバナーで使用した呼称だったのだが、これが何故か日本で受けた。この「受けかた」には、ある種アメリカにおける「アーバン」の増殖と近いものがあった、のかもしれない。たとえば、これぞ「ブラコン」のイメージだった曲というと、僕の場合、こんなのが思い浮かぶ。
たとえばこの「ブラコン」周辺から、あまたの「日本にしかない」ジャンル用語も派生していった。たとえば「ソフト&メロウ」「アーバン・メロウ」とかいったものが、ディスコやFM放送などを経由しては、広がっていった。まるでそれは「日本人が言うAOR」の大誤解の上の流行とも似ていた。
こちらもラジオ局の特徴を指す用語だった「AOR(Album Oriented Rock =シングル・ヒットではなく、ロック・アルバムの収録曲をかけるステーションという意味)」が、なぜか日本でのみ「アダルト・オリエンテッド・ロック(=大人向けのロック)」と勝手な誤訳をされてしまう。よほどそれが気に入ったのか、間違いだとわかったあとも、そのままに定着してしまって今日に至るのだが――アメリカにおける、頑迷なる「アーバン」支配と、どこか一脈通じはしないだろうか?
というか、アメリカにおける「アダルト・コンテンポラリー」音楽のうち、まさに当時の「アーバン」の影響を適度に受けた白人が作ったポップこそ、日本人の言う「AOR」の王道だった、のかもしれない。そしてこれら双方をネタ元とするような精神性こそが「シティ・ポップ」の根本だった、のかも……というところから、意外にも(?)日本人にとって遠くはなかった名称「アーバン」は、しかしこれから「消えていく」ことになる。
ところで、日本では百年一日のごとく、レコード店などで「ブラック・ミュージック」もしくは「ブラック」との区分けがあることが多い。しかし僕は、少なくとも90年代以降、アメリカにおいて、そんなものを見た憶えが一度もない。「いま現在、流行っている」音楽であれば、全部「ポップ(Pop)」とするのが、アメリカでは普通だ。だからロックもヒップホップもR&Bも、「いまのもの」は全部そこに入る。マイケル・ジャクソンが「黒人音楽のキング」ではなく「ポップのキング」と呼ばれたように。
「やっている人の肌の色で」区別する必要など、あるわけがないからだ。人種隔離政策じゃあるまいし――と、いつも日本のレコード店で僕は思う。あまりにもレイシズム的であり、世界の先進国の現在と比較して、遅れすぎているのではないか、と。ほかの点は置いといて、こと「レイス」の問題にかんしては。
だからこそ逆に、ここでまた思いっきり「周回おくれ」となった日本の人は、いまからでも遅くない。気分も新たに、「未来の音楽の道筋」などを想像しながら、レコード店や自宅レコード棚の区分を刷新してみてはどうだろうか?
あくまでも「音楽ジャンル」で切ることが、いつどんな場合も、最重要なのだ。音楽性で、趣味や思想で「いかなる肌の色だろうと」連帯できることの証明としての旗印こそが、我々が心寄せるポップ音楽の本質にほかならない。それゆえに、いつの時代も、きちんとした定義の言葉で、相応の敬意を表されて然るべきなのだから。










