日本古来のクジラ食文化:守れないのは、シーシェパードではなかったのか!?

縄文時代から継承してきているクジラの食文化
クジラの食文化は縄文時代から日本で受け継がれ、祝事などではクジラが大きいことから「商売繁盛しますように」と縁起のものとして祀ってきた珍しい食材でもある。
消えていく文化、栄える文化がある中で、クジラの食文化においては、自ら衰退させてきた食文化ではなく、1970年代から栄えた反捕鯨活動による人命に関わる嫌がらせや政治的な外圧の双方によって衰退の道を余儀なくされてきた食文化としても顕著である。
今、存続の危機に立たされている。なぜだろうか。
江藤拓農林水産大臣の会見「海外から評価されている」は本当か?
日本は昨年6月にIWCから脱退し、江藤拓農林水産大臣は、商業捕鯨が再開されて1年経過した今年の6月30日の記者会見で、「海外からはおおむね冷静な反応を得ている。わが国の対応が非常に評価されているということではないか」と述べているが、実態は、クジラ業を営む民間の企業が苦しめられている。
国際条約の権利放棄、新たな代替え条約なし、捕獲頭数の減少、消えていく補助金
IWC脱退の声明を出した際、捕獲頭数の増加や、公海で捕鯨を行えるようにする新たな条約の案などが打ち出されると思われた。そして、海外メディアは前のめりで批判した。
しかし、日本側には準備がなかった。「感情的にIWCを脱退したのではなく、数年前からの計画性あるものだ」と主張した。しかし、捕鯨国による新たな条約作りはおろか、捕獲数の計算方法も決めていないままの脱退だった。
「トリックと脅しに負けない交渉」の課題
今年2月に参議院[国際経済・外交]に関する調査会に招集された元IWC代表代理の小松正之氏は、同じ官僚の経験を持つ立場から答弁をした。(2月12日付:https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php)
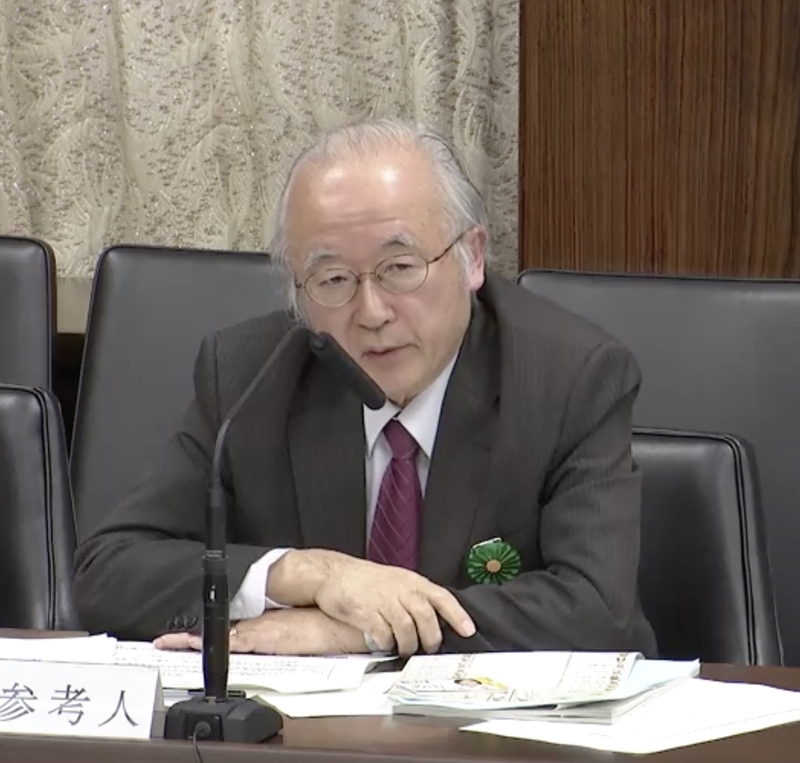
今回の商業捕鯨再開を巡る対策において「水産庁職員が用意したプレゼンをそのまま国会議員の先生が鵜呑みにして反映され、国益を失っている」と指摘する。
小松氏は水産庁の中で「相手泣かせの交渉人」として、日本に優位な結果をもたらす人物で有名であった。小松氏は今回の取材で「国家公務員とは難しいことをするのが責務と矜持であると考えるが、実態は国益の対策よりも自分たちの仕事を増やさないことが念頭にある。場当たり主義が反映されることが多く体質改善が難しいのが現状だ。海外との交渉において脅しに負けない国際法の知識と交渉力の強化が省内の課題」だと見解を示した。
先日、アメリカのトランプ大統領が「日本は脅せばいい」と発言していたことがボルトン前米大統領補佐官によって暴露されたことにも通じるが、こうしたトリックと脅しの外交手段は、今に始まったことではない。あらゆる貿易や交渉、捕鯨においても日本は交渉で譲歩し続けてきた経緯と今がある。

「商業捕鯨と呼ぶのは誤りである」
現在の状況を商業捕鯨と呼ぶのは誤りである、と、小松正之氏は、この呼称に強い憤りを感じている。
世界で一番資源が多い南極海での権利を放棄し、自分が担当していた調査捕鯨時代には1300頭を捕獲していたのに比べ、今回の商業捕鯨再開ではその約15%の195頭としたのは明らかなる自滅削減であり、狭い200海里内で今後、少しずつ捕獲を増やす程度では、自立する「商業」は困難だとみている。
「商業」といえども、水産庁が許可を出した頭数までしか捕獲できないからだ。
「需要がない」以前に・・
しばしば取り上げられるのは「需要がない」ということだが、そもそも「目にして食べる機会が圧倒的にない」「値段が他の肉に比べて高い」。
実際、国内に流通しているタンパク源を比較すると、牛肉に比べて鯨肉は、おおよそ1000対4、豚肉に比べて鯨肉は2400対4(トン)となっており、「需要がない」と語る以前に、「供給」がほとんどされていないのが現状だ。飲食店のメニューの中で「選択肢にない」のである。
これまでは、クジラの食文化の衰退は環境テロリストとも呼ばれる人命に危機を及ぼす反捕鯨活動家の脅しとトリック仕掛けの政治的圧力であったが、今は反捕鯨による小規模なデモがあるものの、昔に比べたら比較にならないほど激減し手段も穏やかになってきた。
2017年には、シーシェパードは、南氷洋への攻撃を止めている。今の状況を動物愛護団体のせいにできるのか。今、残された課題は、大きく2つあった課題のうち、政治的な部分ではないだろうか。
国際法の権利とチャンス
ICRW条約の下にできたIWC国際捕鯨委員会であるため、IWCにおいて他国が多数決で反対しようが、ICRWの条約の元、強制力はなく南氷洋での捕獲の権利は存在していた。
小松氏は、現在、一般社団法人生態系総合研究所の代表理事に赴任している見地から、「今は科学が重要な時代、国際社会からデータの信用を得るためにも、公海において日本の負担だけで調査をするのではなく、他国を巻き込んで公的なウィルスからクジラまでの海洋環境の関係を調べる鯨類調査を行うべきである」と見解を示した。

外交上の対策でいえば、数々のチャンスが過去にもあった。
1つとして大きいのはICJ国際司法裁判で日本がオーストラリアに敗訴した時だった。当時、小和田恆氏(皇后・雅子さまの父上)は、国際司法裁判所判事であった。裁判の敗訴という結果について勝手な解釈を日本国内でしていないで、国際司法裁判所ICJで日本は訴訟を起こすことが出来たと記者会見で述べている。(https://www.youtube.com/watch?v=nqM3IV99RIk&t=1134s)
水産庁はこれまで「費用対効果がない」として国際裁判を避けてきた。しかし、これまで費やしてきた巨額な税金と廃業に追い込まれたクジラ店がどれだけあったかを直視していないのではないだろうか。
日本は科学調査の結果が認められず、長年くすぶる思いを強いられてきた。この不毛な状況から脱するためには、オーストラリアを相手取って訴訟を起こせば、IWCが条約違反を犯していることや、生態系を崩しかねないほどクジラの資源が南氷洋に豊富にあることを世界に示せる絶好のチャンスであった。
江藤拓農林水産大臣の日本の商業捕鯨は「海外から評価されている」の実態は、
「日本の商業捕鯨では採算がとれない、いずれ衰退しなくなっていく」という反捕鯨国の安心感の裏返し
に思える。
奇しくも、日本の外交力を表しているかのごとく、日本経済の成長と捕鯨の供給量は比例しているのである。
今、先人たちにより受け継がれてきたクジラの食文化は国力とともに衰退と存続の危機に立たされているのが現状ではないか。
<参考>
日本記者クラブ会見:
小和田恆氏(元国際司法裁判所判事、皇后・雅子さまの父上)
(https://www.youtube.com/watch?v=nqM3IV99RIk&t=1134s)
参議院[国際経済・外交に関する調査会にて]:
小松正之氏の捕鯨について説明は、2月12日にカレンダーで選択、
[国際経済・外交に関する調査会にて]をクリック。
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php










