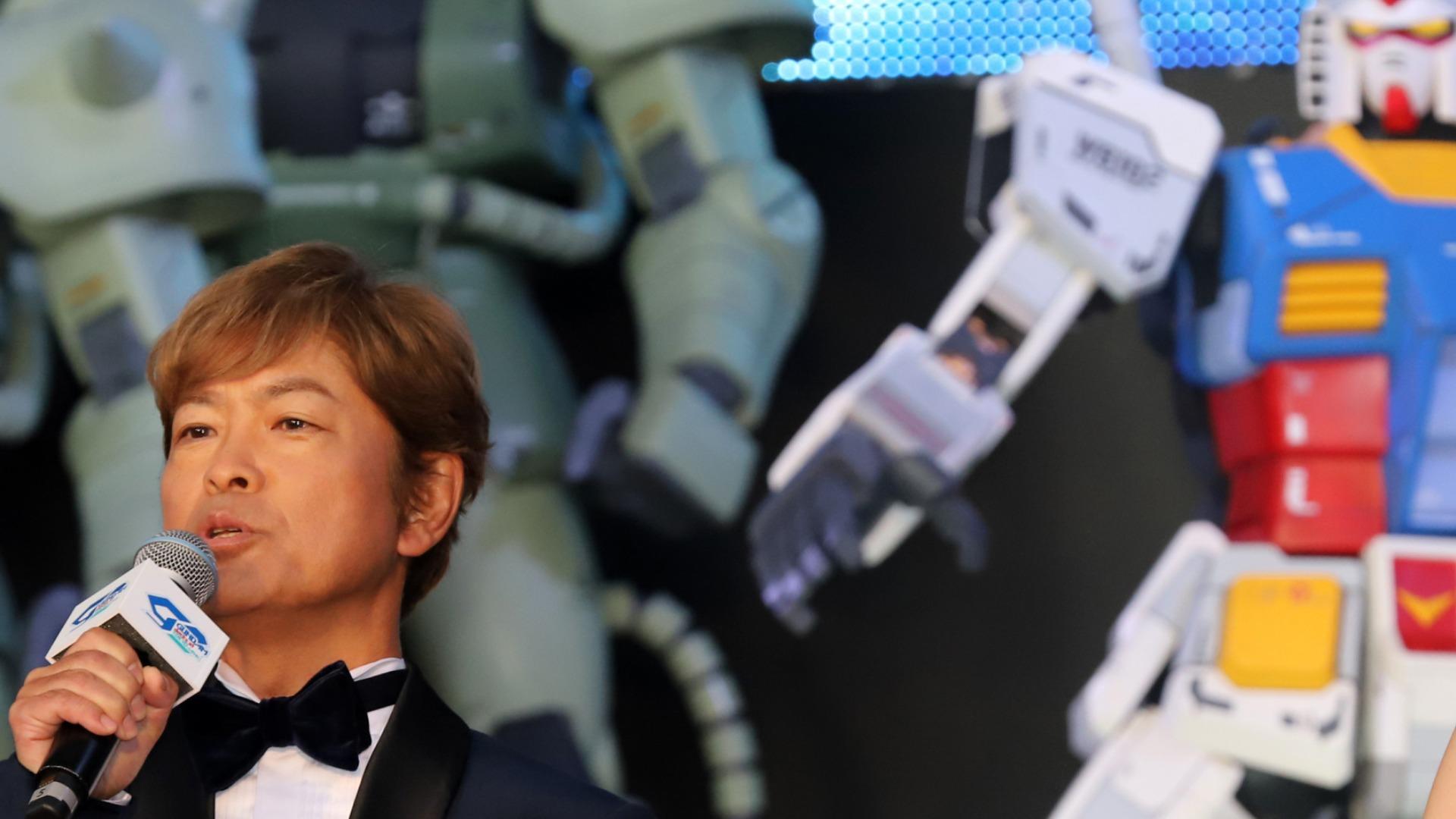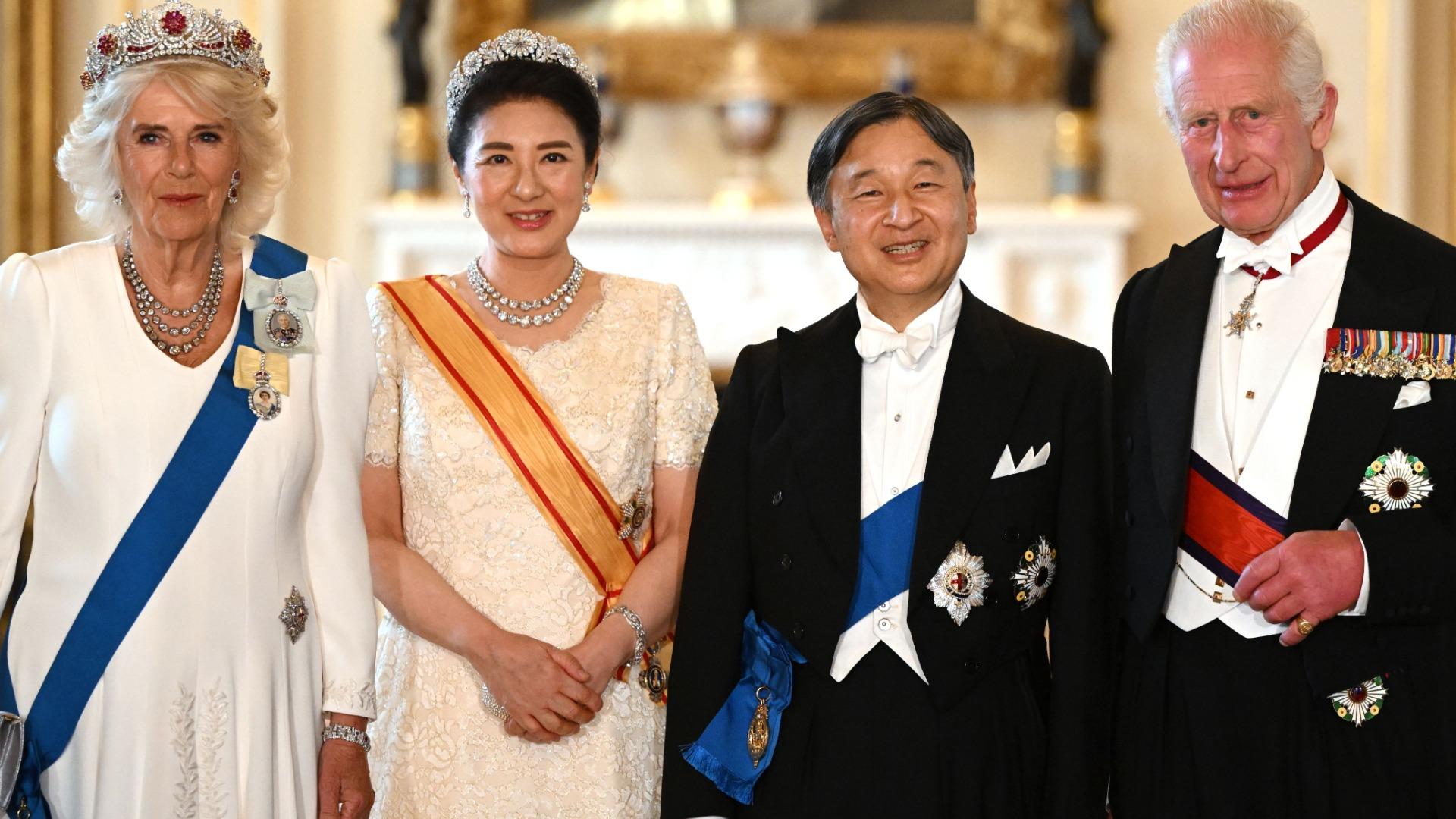【戦国こぼれ話】毛利元就が陶晴賢軍を撃滅した「厳島の戦い」は、なぜ成功したのだろうか?

5月21日、文化審議会は、厳島神社(広島県廿日市市)の門前町を文部科学相に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定するよう答申した。今回は、厳島神社も関係した「厳島の戦い」を取り上げることにしよう。
■厳島の戦いの背景
厳島の戦いとは、天文24年(1555)10月に安芸国厳島で毛利元就軍が陶晴賢軍を打ち破った戦いだ。
天文20年(1551)、晴賢は中国西部から北九州を支配領域とする大内義隆に叛旗を翻し、長門大寧寺(山口県長門市)で討伐した。義隆は寺社保護や文芸に熱中しており、奢侈が目立ったという。これに家臣団が大きく反発し、反乱の大きな原因となったといわれている。
義隆の討伐に成功した晴賢は、豊後の大友義鎮の弟・晴英(義長)に大内家の家督を継承させ、自らは実権を掌握した。そして、晴英の「晴」字を拝領し、名をこれまでの隆房から晴賢と改めたのである。
当初、元就は、晴賢に恭順の意を示した。そして、これを機会として安芸、備後に勢力を伸張したのである。元就にとって、大内氏の滅亡は好都合であった。同時に、元就が侵攻を試みたのが、海運で栄えた厳島だった。やがて、厳島をめぐって、元就と晴賢の間に確執が生じることになる。
天文23年(1554)、晴賢は石見国津和野の吉見正頼を討伐するため、元就に参陣するよう命じた。しかし、元就はこの申し出を拒否した。このことを契機として、両者の武力衝突は避けられなくなった。そして、決戦場となったのが厳島なのである。
■戦いの開始
天文24年(1555)9月、陶氏との戦いを控えた元就は、小早川隆景に書状を送り、来島村上氏の援軍がいつになるのかを問うた。そして、隆景に草津に急行するように伝え、「小早川衆の6・70艘、川内警固衆の5・60艘の船だけででも決戦に臨みたい」と述べた。いかに名将の元就とはいえ、焦りを隠せなかったのだ。
結局、元就の苦悩は、杞憂に終わった。能島・来島の村上水軍が2・300艘の船を率いて、元就の応援に馳せ参じた。元就の命を受けた乃美宗勝が来島で行った説得工作は、成功したのである。能島・来島の村上水軍の援軍が来たことで、劣勢を挽回できる芽が生じたが、元就が晴賢を打ち破るには、正攻法では勝ち目がなかった。
能島・来島の村上水軍が毛利氏に味方したのは、陶氏にとって大誤算だった。村上水軍が毛利氏に与したのには、大きな理由があった。晴賢は大内氏を滅したあと、村上水軍の瀬戸内海における諸特権を奪っていた。村上水軍が毛利氏の申し出に応じたのは、むしろ当たり前のことだったといえよう。
ただし、最新の研究によると、来島村上氏が応援に来たのは間違いないが、能島村上氏が毛利方に馳せ参じたという確かな史料がないということが指摘されている。今後の検討課題である。
■毛利氏の厳島上陸
9月30日、元就の本隊は厳島の包ヶ浦に上陸し、陶軍の本陣の背後の山頂から攻めようとした。隆景は別動隊を率いて正面の鳥居から攻め込み、二手に分かれて陶軍を挟み撃ちにした。厳島は周囲約29キロメートルの小島で、山々が海岸線に迫る狭隘の地である。陶方の軍勢は、本陣のある狭い平野部分に押し込まれるという危うい事態になった。
毛利氏が厳島に攻め込んだのは、夜間だった。非常に風が強く、船が大きく揺れたため、兵卒は船酔いに苦しめられたという。当初、隆景の別動隊は、晴賢が陣を敷く大元浦に上陸しようとしたが、厳しい警固のために取りやめた。
そこで、乃美氏は作戦を見直し、多数の敵船が停留する鳥居付近へ思い切って上陸することを献言した。鳥居付近には陶方の軍船がひしめいていたが、敵味方の判別は夜の闇で困難だった。
乃美氏は陶氏の状況をつぶさに観察して、あたかも筑前国から応援に馳せ参じた宗像氏らを装い、敵中に堂々と紛れ込んだ。そして、敵の意表を突き、鳥居前に軍船を近づけると、そのまま上陸して攻撃のチャンスをうかがった。
10月1日早朝、毛利軍は突撃を合図する太鼓の音と同時に、背後の山頂から一斉に鬨の声を上げて陶軍を攻撃した。激しい暴風雨で、毛利方の攻撃を予想しなかった陶軍は激しく動揺した。
■晴賢の敗北と最期
狭い場所が災いして、2万という大軍の陶軍は身動きが取れなかった。陶軍は背後からの毛利軍の奇襲作戦に対応していると、小早川軍が岡の下から攻め込んできた。陶軍は挟み撃ちに遭って大混乱に陥ると、たちまち総崩れとなって、兵卒が続々と逃げ出したのである。
海上でも、毛利方の村上水軍は陶方の船の碇綱を切り、火矢を放つと、敵船に乗り移って白兵戦に臨んだ。陶方の水軍は船に火を掛けられ沈められるか、乗っ取られるかの散々な敗北を喫した。晴賢は毛利方を攻撃すべく、全軍に引き返すよう命じたが、すでに時遅しだった。
逃亡した陶軍は海岸線に殺到し、船で逃げようとしたが、陶方の水軍は逃亡したあとだった。毛利軍に応戦する者もいたが、すべて討ち取られた。
晴賢は逃亡したが、大江浦で自害した。享年35。