【解説】こども政策のスタートへ!#こども家庭庁 何が良くなる?略称 #こども庁?#子どもの権利

こども家庭庁設置法、こども基本法が、参議院本会議で可決成立しました。
こども財源があいまい、幼保一元化ができてない、教育は文科省所管のまま、様々な批判も多いこども家庭庁ですが、いったい何が良くなるのでしょうか?
私は、これまで子どもの貧困対策、教育政策の専門家として、こども家庭庁に関する議論の経過をウォッチしてきました。
財源も人員も保障されないこども家庭庁に、当初は疑念を持っていました。
しかし、「子ども国会」とも言える今国会(第208国会)において岸田内閣と与野党国会議員との質疑を通じて、こども家庭庁への期待も大きくなっています。
子どもの権利の国内法である、こども基本法が同時成立したことにより、こども家庭庁もその機能を発揮しやすくなったともとらえています。
なおこども家庭庁、こども基本法ともに、年齢規定はなく「心身の発達の過程にある者」と定義されています。
18歳以上の若者も、こども政策の対象となることは、多くの方に知っていただきたいことです。
1.本題の前に、こども家庭庁の略称は「こども庁」にしませんか?
―略称が「こ家庁(コカチョウ)」で、こどもまんなか?
こども家庭庁で何がよくなるのか?
本題の前に、ひとつ提案させてください。
こども家庭庁の略称ですが「こども庁」にしませんか?
こども家庭庁の生みの親ともいえる自民党ChildrenFirst勉強会を主催してこられた、自見英子議員、山田太郎議員も、Youtube発信で「こども庁」の略称を使用しておられます。
子どもたちへの思いのこもった発信です。
※提唱者が語る!こども家庭庁(こども庁)はなぜ必要か?【自見はなこと山田太郎のこどものみかた01】 #こども庁 #こども家庭庁
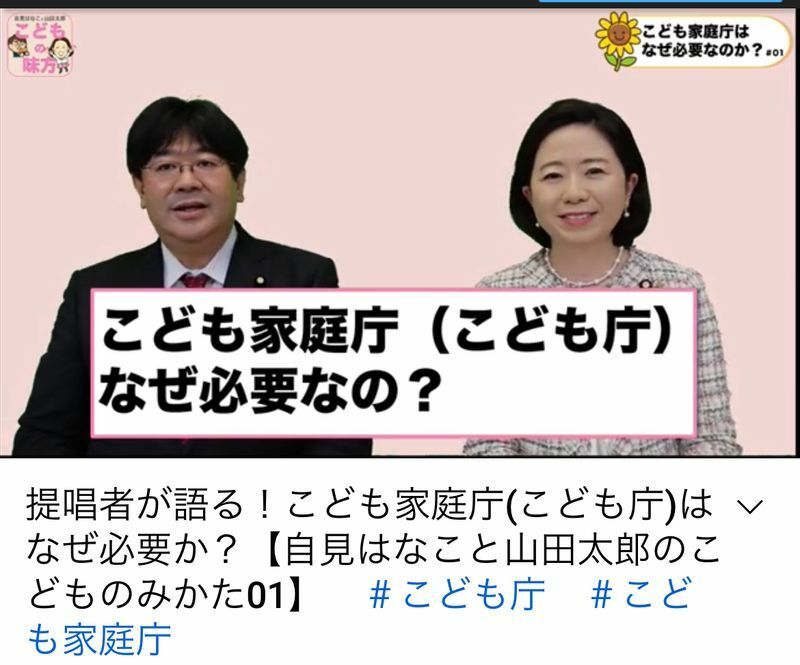
実はこのまま放置すると、霞が関ルールでは「こ家庁」(コカチョウ)にされてしまうのでと心配しています。
(科学技術庁は「科技庁/カギチョウ」、国土交通省は「国交省/コッコウショウ」などの例もあります。)
しかし、こども家庭庁は、岸田総理、野田聖子少子化担当大臣も強調するとおり、「こどもまんなか」の省庁です。
略称も、子どもにわかりやすく「こども庁」と、大人たちが気を付けていく思いやりが、わが国において「こどもまんなか」を実現するために大事だと思いませんか?
2.こども家庭庁で何がよくなるのか?
―子どもの権利がこども家庭庁の魂(機関哲学)
―こどもの目線、こどもの幸せ
―「だれひとり取り残さない」、「切れ目のない支援」
セーブザチルドレンが作成した「こども家庭庁」の特設サイトでは、こども家庭庁の意義が次のように説明されています。
子どもに関する取り組みを日本の社会の中心において、子どもの目線で、子どもの権利を大切にして、すべての子どもがその命を守られ、自分らしく健やかに安心して成長することができるように、政府は「こども家庭庁」という新しい国の組織を作るための法律案を2022年2月に国会に提出しました。その法案が6月に可決(賛成)され、こども家庭庁ができることが決まりました。具体的な役割について、この後も様々な話し合いが持たれた後、こども家庭庁は2023年4月1日にスタートする予定です。
こども家庭庁は、子どもの権利を大切にし実現していくための省庁です。
子どもの権利がこども家庭庁の魂(専門用語でいうと機関哲学)ということもできるでしょう。
素晴らしいことに、こども家庭庁(設置準備室)は「こども向け資料」を準備しています。
こども家庭庁への期待が大きいのは「組織は人なり」という言葉のとおり、子どもの権利を基盤とし、こども政策の実現に全力を注ぐ官僚が、そこにいるからです。
「こども向け資料」もあたりまえのように、子どもたちのために発信する官僚集団なのです。
こども家庭庁と連携する他省の官僚も、いまこそ子ども若者のための政策・予算・制度を充実させたいと強い意気込みを持って、予算や政策の充実に取り組んでいます。
こども家庭庁「こども向け資料」ではこども政策で大事にすることとして、以下の6つの方針が書かれています。
(1)こどもや子育てをしている人の目線に立った政策を作ること
(2)すべてのこどもが心も身体も健康に育ち、幸せになること
(3)だれひとり取り残さないこと
(4)政府の仕組みや組織、こどもの年齢によって、こどもや家庭への支援がとぎれないようにすること
(5)こどもや家庭が自分から動かなくても、必要な支援が届くようにすること
(6)こどものデータを集め、それをしっかり政策にいかすこと
こどもの目線、こどもの幸せを実現すること
「だれひとり取り残さない」、「切れ目のない支援」を実現していくこと
大きくまとめると、こども家庭庁でそうしたことが実現されていくことになります、
何よりも、こども家庭庁設置法が子どもの権利を位置づけられていることが重要です。
ここから、こどもの権利を基盤とした、こども政策がわが国でどんどん実現されていくのです。
3.具体的にどのような政策が実現されるのか?
―子どもの意見表明・参画により進化しつづけるこども政策に
こども家庭庁で実現が期待されている政策はいくつもあります。
・子どもの意見表明を国・地方自治体や学校・園など子どもに関わる場で実現していく仕組みの推進
・性犯罪者から子どもを守る日本版DBSの実現
・児童養護施設や里親世帯で暮らしている社会的養護の子どもたちの意見
・子どもたちへのプッシュ型支援・アウトリーチ型支援
・子どもの意見表明、子どもの参画
・いじめ対策
・不登校の子どもたちの「学ぶ権利」の保障
・子ども若者のための居場所を増やす
・働いていない保護者の子どもでもニーズに応じて保育を受けられる保育のユニバーサル化
・児童手当・児童扶養手当の拡充
これらの意見は、昨年末に閣議決定された「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」に際し、子どもたちからの意見としても寄せられたものです。
こども家庭庁は、設置法第3条にあるとおり「その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本」とする省庁です。
こども基本法でも、子どもの意見表明と尊重、参画を位置づけており、こども家庭庁は全省庁の先頭にたって、それを実現していく省庁となります。
子どもの意見表明・参画により進化しつづけるこども政策になっていくことが期待されます。
4.財源!財源!財源!
―こども選挙=参議院選挙が行方を決める!
こども政策を充実させていくためには、やはり財源です。
私も衆議院内閣委員会参考人として強調しましたし、こども家庭庁に関する質疑の多くは、財源の確保、こども予算の確保に集中しました。
日本の子ども家族給付は、先進国最低水準です。
こんなことで少子化は止まりませんし、「子育て罰」とすら称される親子に冷たい日本を変えることもできません。
いま、子どもが幸せな日本、子どもを社会で宝物としていつくしむ日本に進化しなければなりません。
そのためには、こども選挙=参議院選挙が行方を決める!
真に子どもたちのために貢献する国会議員を選ぶことが、こどもまんなかのこども政策の基盤になります。
私もこどもまんなかの候補者については、昨年の衆議院議員選挙に続き、参議院選挙についても与野党ともに注目の候補者を分析し公表する予定です。
子どもを大切にする日本になってほしいみなさんは、ぜひ「こどもまんなか」の候補者に投票しましょう!
こどもまんなかの日本にむけて、国会も行政(こども家庭庁)も本気を出していかねばなりません!










