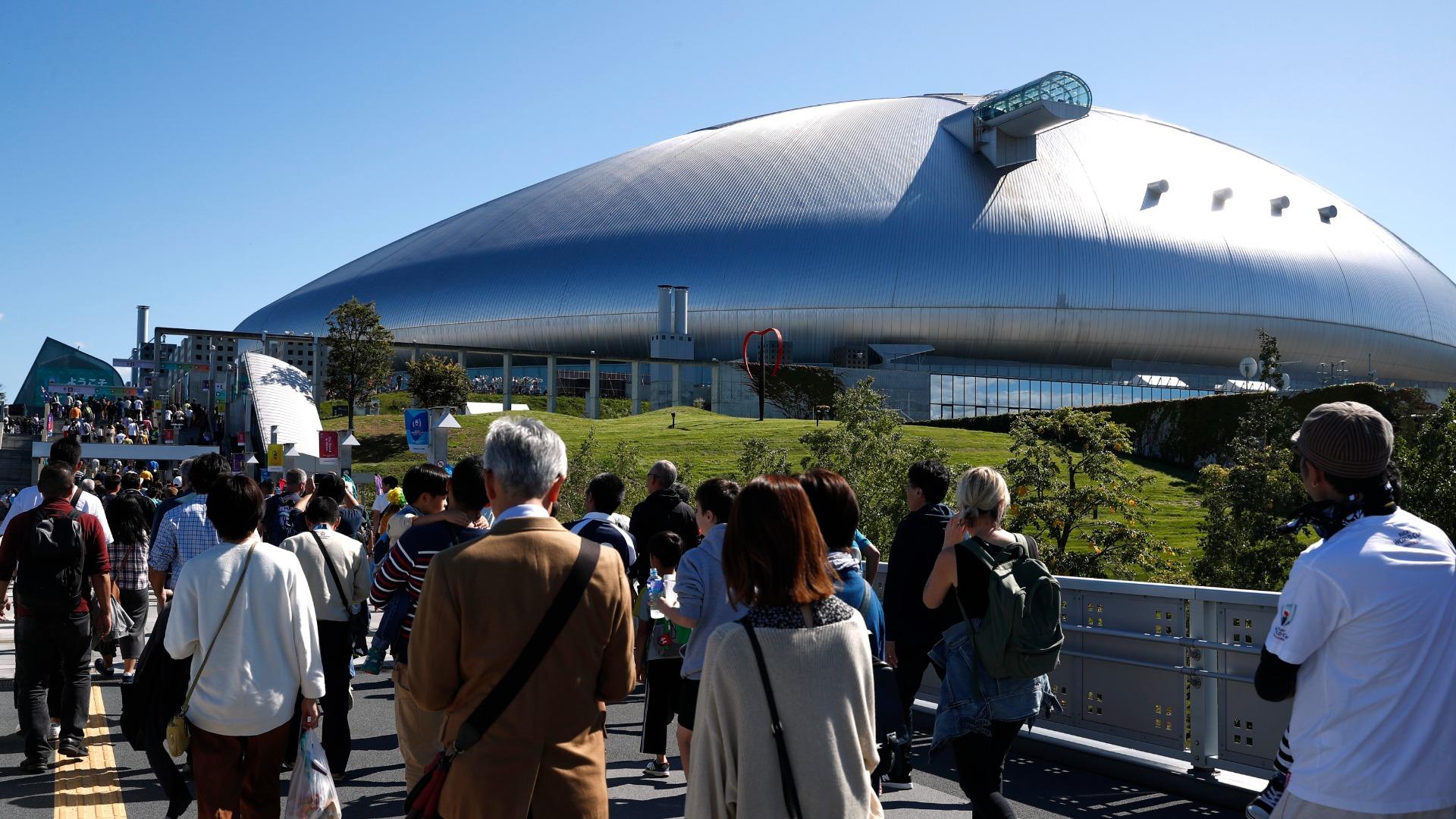家康は宗教弾圧の一環として、三河一向一揆と戦ったのか

大河ドラマ「どうする家康」では、三河一向一揆の場面が描かれていた。今回は、家康が宗教弾圧の一環として、三河一向一揆と戦ったのか考えることにしよう。
そもそも一向宗とは、親鸞が開祖となった仏教の宗派の一つで、教義は阿彌陀仏の本願他力の回向によって往生すると説くものだった。親鸞が没したあと、一向宗は本願寺派など10派に分かれた。一向宗は、のちに浄土真宗と称されるようになった。
一向一揆が見られるようになったのは、1460年代のことである。一向一揆が盛んになったのは、中興の祖である本願寺第8世の蓮如(1415~99)の頃だった。蓮如は精力的に布教活動を行い、教団の規模を拡大させていった。
一向一揆は、別に門徒(信者)だけが加担したのではない。農民、名主、地侍等々の広範な勢力が結集し、守護や大名の支配に抵抗した。特に、畿内、東海、北陸方面で一揆は勃発し、加賀守護の富樫氏は滅亡に追い込まれたほどだった。
それゆえ、各地の守護や大名は、一向宗の動きを警戒していたのである。それは、家康も同じだった。永禄6年(1563)に三河一向一揆が勃発した。家康が対策に忙殺されたのは、ドラマのとおりである。
三河一向一揆が勃発した理由は、①不入特権侵害説(家康が一向宗寺院が保持していた不入の特権を侵害したこと)、②流通市場介入説(家康が一向宗寺院が保持していた水運、商業などの特権を侵害したこと)という説がある。
この一揆では、もちろん一向宗寺院が拠点となり、家康に兵を挙げたのだが、問題はそれだけではなかった。一揆勢の蜂起のどさくさに紛れて、家康の家臣だけでなく、吉良義昭、荒川義広といった三河の国衆も家康に反旗を翻したのである。
最初は一向宗の権益が問題だったが、便乗するかのように家康の敵対する勢力までもが与同したのだ。もはや、一向一揆という枠を超えていたのである。むろん、家康は彼らを徹底的に弾圧せねば、生き残ることができなかったといえよう。
一揆の鎮圧後、家康は一向宗の布教を禁じたが、それは宗教弾圧とは言えない。家康は一向宗と諸勢力が再び連携し、歯向ってくることを恐れたのだ。天正8年(1580)になると、大坂本願寺が織田信長に降参し、一向宗の威勢が衰えた。
その3年後、家康は一向宗の布教を許したが、その理由は彼らが挙兵しないことを確信したからだろう。家康が本気で一向宗を弾圧しようと考えたらならば、皆殺しにするなど徹底した方策で臨んだはずである。