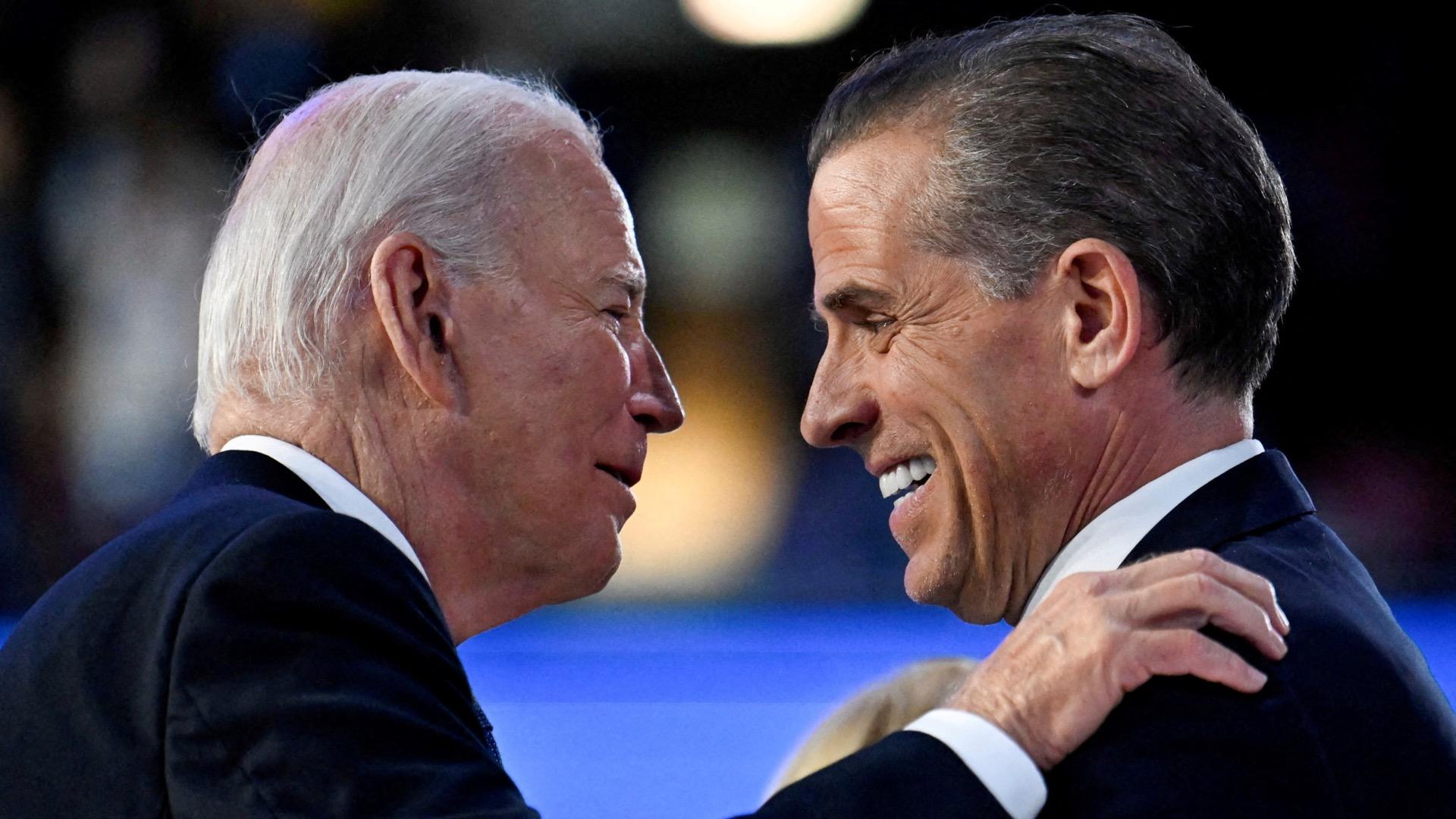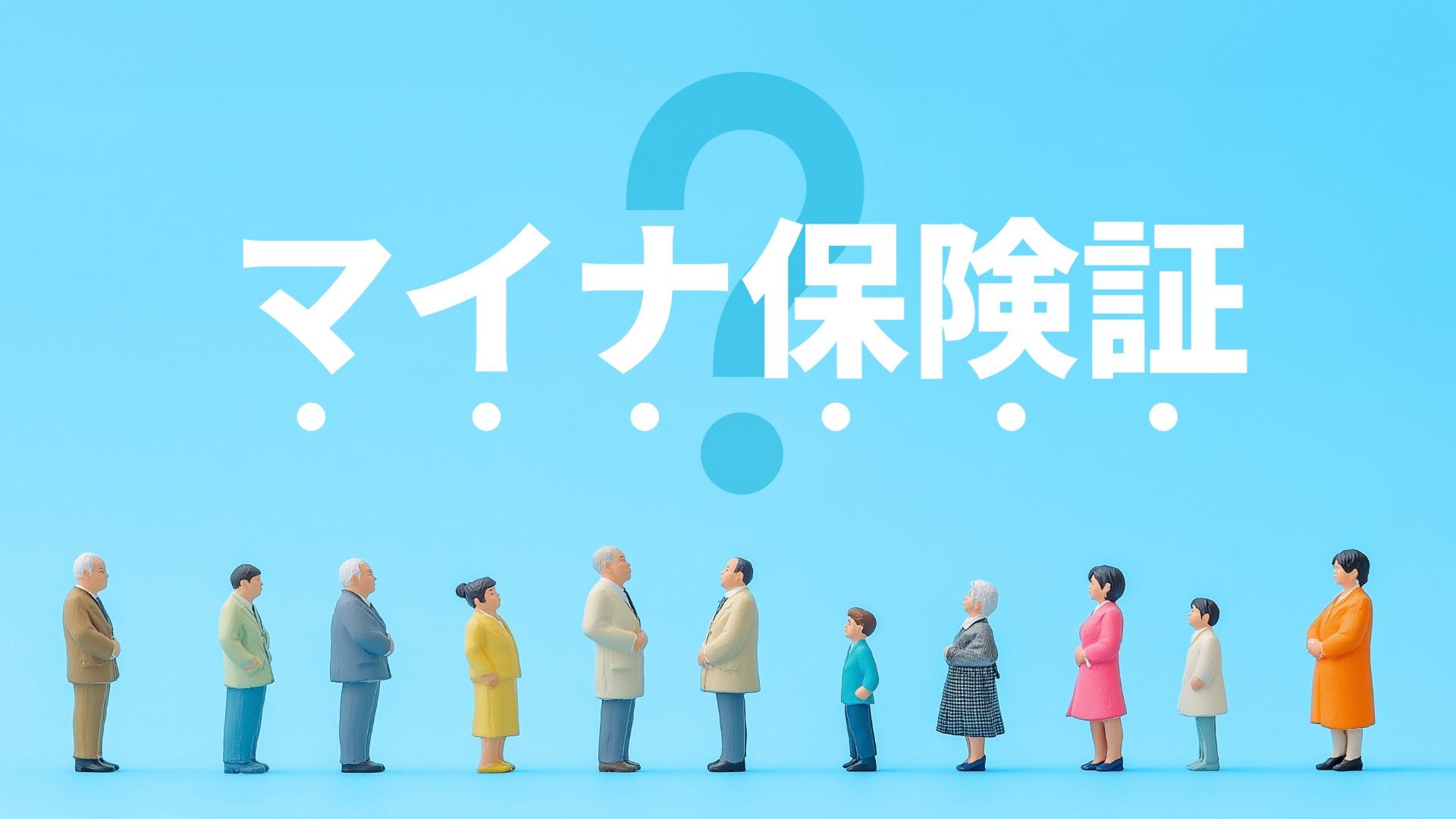幼児教育講師がおすすめする「子どもの記憶力」が育つ方法11選!

幼児教育講師のTERUです。
日々の子育て本当にお疲れ様です!
今日は『子どもの記憶力を育てる11の方法』というテーマについてお話しします。
【なぜ記憶力が重要なのか?】
皆さんは、これからの時代に必要な力って何だと思いますか?
もちろん様々ありますが、これからの変化の早い時代ではクリエイティブな発想が重要だと言われることが多くなってきています。
AIはまだ新しい価値を生み出すことはできないですし、新しい枠組みをデザインすることはできないといわれています。
なので、今後の時代を生き抜いていくためには新しい価値のあるアイディアをどんどん生み出すクリエイティブな発想が重要だということです。
ではそのクリエイティブな発想はどこから生まれてくるでしょうか。
それは、過去の知識からです。
人間は新しいことを生み出すために、過去の知識を総動員し、組み合わせたり変化させたりして今までと違うものを生み出します。
つまり、過去の知識がすっからかんであれば、クリエイティブな発想も生まれづらいのです。
そんなロジックから、私はこれからの時代でも物事を記憶できる力は重要であり、クリエイティブな発想を持って活躍できる人になるために、記憶力を大切にしてほしいと思っています。
【記憶力を鍛えるオススメトレーニングや遊び】
それでは具体的な方法をご紹介していきます。
①いないいないばぁ

定番も定番の遊びですが、やっぱりいないいないばぁってすごいんです!
大体ですが、生後2ヶ月くらいから開始してあげてください。
「いないいない」のときに、指の隙間から赤ちゃんの顔を見て赤ちゃんがお母さんの顔を見ていることを確かめてから、「ばぁ」と大げさに言い、赤ちゃんと目があったら一緒に笑ってあげましょう。
いないいないばぁはワーキングメモリーといって、一時記憶をつかさどる重要な能力を育てるトレーニングになります。
赤ちゃんは人の顔を一番認識しやすいので、物でやるよりもお母さんやお父さんの顔でやることが大切です。
②絵本
絵本は実は記憶力のトレーニングにもなります。
もちろん記憶だけではなくあらゆる良い効果が期待できますから、生後早いうちから触れていってほしいなと思う取り組みの1つです。
色んな本を幅広く読み聞かせてあげるのも良いですが、子どもが読んでとせがむ絵本を何度も繰り返し読んであげることで、子どもが次のページに何が書いてあるか。そのページではどんな言葉が出てくるか。などを覚えてるようになります。
よく「同じ絵本ばかりせがむのですが、どうやったら他の絵本に興味を持ってくれますか?」と質問を受けますが、
「その子にとってその本には何か大きな意味があり、そして記憶力向上のチャンスでもあるので、気が済むまで何度も同じ絵本を読んであげてください」
とお伝えさせていただいています。
③お散歩しながら会話

これも生後2ヶ月くらいから意識してほしいのですが、まずお散歩をするときに赤ちゃんを前向きに向かせてたて抱っこをします。
赤ちゃんが色んなものを見やすくするためです。
そしてお散歩をしながら、目につくものを指差しながら「あれはお花だよ」「あれは車だよ」と子どもに教えていってあげましょう。
物を目で記憶して、耳から聞いた言葉と一致させていく記憶の練習になります。
このときに私は、幼児言葉でなく正しい言葉を教えてあげることをオススメしています。
「あれはブーブーだよ」→「あれは車だよ」
ただ、これは賛否両論あるので皆さんの価値観で教えてあげれば大丈夫です。
歩けるようになってからも同じです。
一緒にお散歩しながら子どもが興味を持ったものなど名前を教えていくのも良いですし、お散歩しながら会話をするだけでもOKです。
④歌の掛け流し
生後6ヶ月くらいからは童謡や子どもの歌などをかけ流しがオススメです。
記憶には目からの記憶と耳からの記憶がありますが、子どもの耳記憶は凄まじいものがあります。
これは右脳が優位な幼少期特有の現象ですが、この耳記憶が得意な時期にたくさんの歌を耳から聞いて自然に覚えることで、耳記憶の回路を太くすることができます。
聞くだけではなく、親が歌ってあげたり、歌える歌が出てきたら一緒に歌っていくのも良いですね。
ちなみに1日30分〜1時間くらいでも十分効果があると私は考えているので、ご家庭の状況に合わせて取り入れてみてください。
⑤顔覚え
これは生後6ヶ月くらいからオススメのトレーニングです。
鏡に向かってお母さんと赤ちゃんが座ります。
そしてお母さんは、お母さん自身の目や赤ちゃんの目を指差しながら「これは目ですよ」と教えてあげます。
他のパーツも同様に行い繰り返していくと、そのうち自分で自分の顔のパーツを指させるようになっていきます。
そうなったら今度は「目はどこかな?」と聞き、赤ちゃん自身に自分の顔のパーツを指差しをさせていきましょう。
まずは自分の身近なものから記憶をしていくのが赤ちゃんがスムーズに記憶力を伸ばしていく良い方法です。
⑥どっち遊び
これも生後6ヶ月くらいから始められる遊びです。
やり方はシンプルで、お母さんは両手の手のひらを子どもに見せ、どちらかにおもちゃなどを置きます。
それを赤ちゃんがちゃんと見たのを確認したら、両手を閉じて赤ちゃんにどっちに入っているのかを指差しさせます。
シンプルですが、短期記憶の良いトレーニングになるので、繰り返して楽しく遊んであげてくださいね。
⑦おもちゃの場所覚え

生後10ヶ月くらいになるとおもちゃ遊びに好みが出てきます。
気に入ったよく遊びたがるおもちゃが出てきたら、遊び終わったときにその気に入ったおもちゃを子どもに見せ「ここに置いておくからね!」と言いながらしまいます。
そうすると、次の日に遊ぶときにその場所を覚えていて、そこからおもちゃを出すようになります。
最初いきなりはできませんが、繰り返していくと1日をまたいでもちゃんと覚えておける記憶力につながっていきます。
⑧道覚え
1歳くらいになってお母さんと一緒に歩いてお散歩できるようになったら、道を覚える練習をしていきましょう。
まずはいつも通る道があれば、その道にあるお店や建物、目印になりそうなものを「あれは〇〇だね」と教えてあげます。
それらを覚えられたら次は「あの角を曲がると何があるかな?」と子どもに聞き、「パン屋さん」などと答えられたら褒めてあげてください。
最終的に子どもがお母さんの前を歩いていつもの道を歩いていけるようになっていくと、いつも何となくお母さんの後をついていっていたときと比べて自分の記憶を元に道を進んでいくので、記憶力がグングン上がっていきます。
⑨神経衰弱

やはり神経衰弱は幼児からできる記憶力のトレーニングとして効果的です。
1歳くらいから、まずは少ない枚数でやってみましょう。
カードもいきなりトランプではなく、子どもが目を引くような絵が大きいシンプルなものの方が認知しやすくて良いと思います。
最初は4枚から始め、できるようになったら徐々に枚数を増やしていってみてくださいね。
⑩たくさん歩かせ、たくさん寝る
記憶力を育てるには何かに取り組んでいくことも大事ですが、それ以上に記憶ができる強い脳を育てることが重要です。
そのためには、皆さん分かっていることだとは思いますが『たくさん歩くこととたくさん寝る』ことが効果的です。
これは記憶力を育てるために限らずで、たくさん歩いて前頭前野をはじめとした脳に刺激を与え、睡眠を通じて脳のメンテナンスをしっかりと行う。
それが脳を育てるのには一番です!
昼間にたくさん歩いたり遊んだりすれば、疲れて夜はぐっすり寝れるようになっていきますから、良い循環も生まれやすいと思います。
⑪好きなものをとことん深堀していく
子どもが1〜2歳くらいになると、自分の好きなものがはっきりしてきます。
記憶力を伸ばすには、この好きなものを掘り下げて色んな知識と触れていくということが超効果的です。
虫が好きであれば、虫に関する図鑑や虫を題材にした絵本、そして実体験を通じてたくさんの虫の知識に触れていき、好きを掘り下げていく。
子どもは好きなことに最も能力を発揮しますから、そこから記憶の回路が作られていくのだと思います。
いかがでしたでしょうか?
特別なトレーニングではなかったと思いますが、幼児教育というのは当たり前のことをできる限りでやってあげることが大切なのです。
今回ご紹介したもの中から特に大切にしたいなと感じたものがあれば、まずは1つ取り入れてみたり、すでに実践しているものはさらに意識をしていただけたら嬉しいです。
皆さんの子育てを応援しています!
オススメの関連記事はこちら
動画でより深く学びたい方はこちら