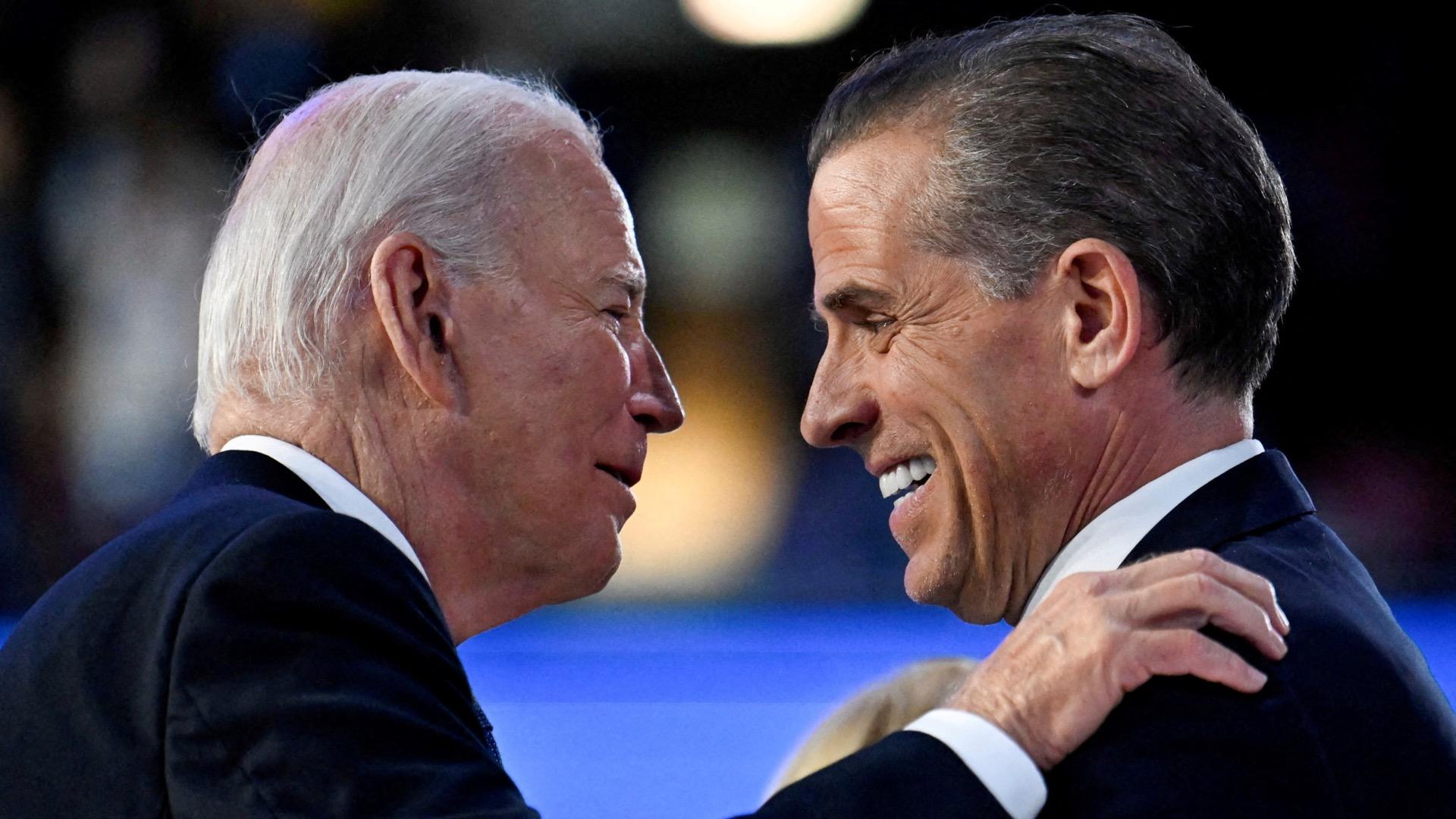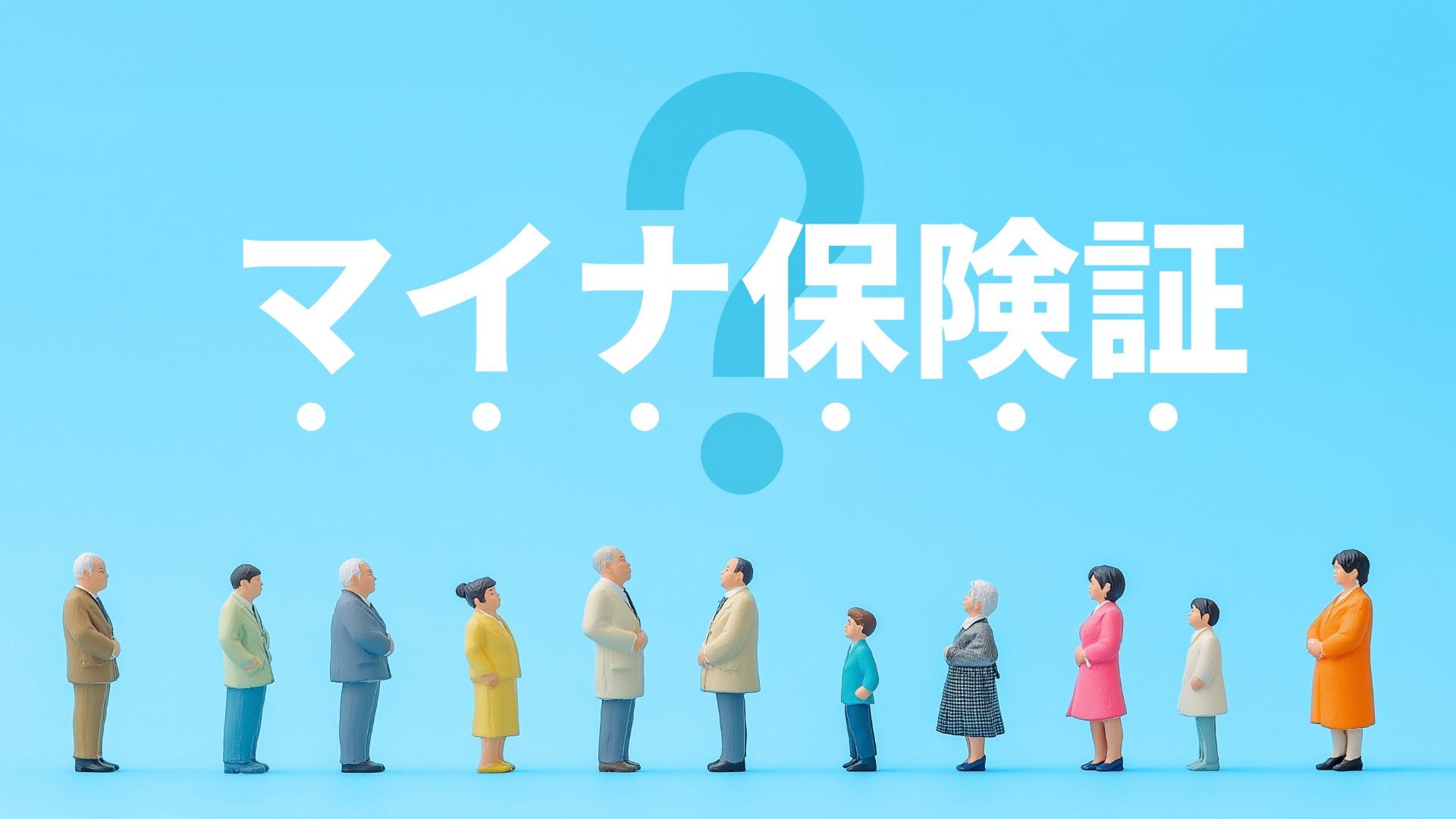【育脳】「天才は幼少期にハマり体験をしている!」の陰で親がしている2つのことを幼児教育講師が紹介!

幼児教育講師のTERUです。
日々の子育て本当にお疲れ様です!
今日は『子どもの脳の発達のために親ができること』というテーマについてお話しします。
子どもの脳を健やかに、そして強く育んであげたいと願う方が、この2つをまずは意識してみると良いですよ!と私が考えるものをご紹介させていただきたいと思います。
ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。
【①『何の役にも立たないこと』を大切にする】

子どもは日々『親から見て意味がないと思うようなこと』になぜだか一生懸命になりますよね。
とにかく虫を集めたり、電車の路線や駅名などを覚えまくっていたり、恐竜にハマりすぎて大人顔負けの知識を披露したり、ポケモンの名前を挙げさせたら誰にも負けない自負があったり・・・
「そんなことより勉強してよ!」と思うことがあるのではないかと思います。
ですが、子どもの強い脳を育んでいくには、その『何の役にも立たないこと』がカギであることが多々あります。
大人から見て価値のないことだとしても、興味を持ったものを主体的に覚えていくのは素晴らしい能力です。
子どもはそういった好きなものをただ覚えているのではなく、ちゃんとその物事を分類して、整理して、記憶するという手順を追って脳内に記憶しています。
これは紛れもなく学習の基本です。
なので、この一見何の役にも立たないことをできる限り尊重してあげ、
・「よく覚えたね!」と褒めてあげる
・「お母さんに教えてよ!」と親も一緒に興味を持ってあげる
このようなことをしてあげることで、子どもはさらに『分類→整理→記憶』を繰り返し、こうして作られた脳内ネットワークはいずれ勉強や社会人になった時の仕事に必ずつながっていきます。
そしてさらに、このように子どもが興味を持ったことを受け入れてあげ、認めたり、褒めてあげることで『ドーパミンサイクル』というものを作ることができます。
人間は誰かに認められたり、それまでできなかったことができるようになったり、何か達成感を感じたときに、喜びや快感に関係する神経伝達物質である「ドーパミン」が脳内で出ます。
ドーパミンが出れば出るほど、私たち人間は物事に対する意欲が高まって、何事にも積極的に取り組みやすくなっていくのです。
そのために必要なのが、
幼少期に自分が興味を持ったことへのチャレンジを尊重してもらえ、そして認められたり褒められる経験
なのです。
そんなシンプルな過程の繰り返しが、ドーパミンを出す脳の回路作りに繋がっていくのです。
『天才は幼少期にハマり体験をしている』とよく言いますが、これを親目線に言い換えると『天才を育てた親は幼少期の子どもの興味を大切にしてあげた』と言えると思います。
もちろん天才に育てないといけない!なんていうつもりはありませんし、そもそも天才って何?という疑問もあるので、天才という言葉に深い意味はないのですが、天才ではなくても、子どもの興味を尊重してあげることは大事ですよね!
②小さな変化を作り出す

ドーパミンを生み出す脳の回路を作っていくために『興味の尊重』と対になってキーワードになるのが『変化』です。
子どもの脳にドーパミンが多く溢れるのは「はじめての経験」をした時だといわれます。
「はじめての経験」にはドキドキ・ワクワクという感情が起こりますが、それがドーパミンを出すためには大切だということですね。
これは1つ目の話とも通ずるものがありますが、まずは子どもの興味を持ったことをできるだけ尊重してあげることで、子どもはどんどん「はじめて!」の経験することができます。
ですが、その「はじめて!」もいつか「当たり前」に変わっていきますし、その都度毎回「はじめて!」の経験させてあげようとするのは親もしんどいですよね。
そこで僕は、何かを始めた後で一定期間経ったら『少しの変化』を演出してあげることをおすすめしています。
例えば、子どもが新しいパズルと出会ったとします。
子どもが慣れてきた・上達してきたタイミングで『少しの変化』を考えてみましょう!
・「よし、今日はパズルを左手だけでやってみよう!」
・「今日は机の上からパズルのパーツを落としたら最初からね!」
・「お父さんと競争ね!」
・「ママと協力して交互にやって、◯分以内にこのパズルをクリアしてみようよ!」
など、どんな変化でも良いです。
子どもが「それ面白そう!」とワクワクするような変化を考えて、上手に作り出してあげることが、ドーパミンが出やすい強い脳を育てていくポイントです。
この変化は時折で良いですからね!
『できる時にちょっとの工夫!』これがとてもバランスの良い関わり方だと思います。
ちなみにもう少し深く話すと、幼児前期(0〜3歳)くらいの子どもは、心の安定のために『同じであること』も大事だといわれます。
このバランスはすごく難しいのですが、生活リズムや家の中のものの配置など、そういった子どもの基本を支えるものは同じであることを大事にしていき、その上で遊びなどの楽しい要素の中でいろんな変化を経験していくのが最適なバランスになりやすいのではないかと思います。
いかがでしたでしょうか?
できる限りできる範囲で子どもの興味を尊重してみていただけると嬉しいです。
皆さんの子育てを応援しています!
オススメの関連記事はこちら
動画でより深く学びたい方はこちら