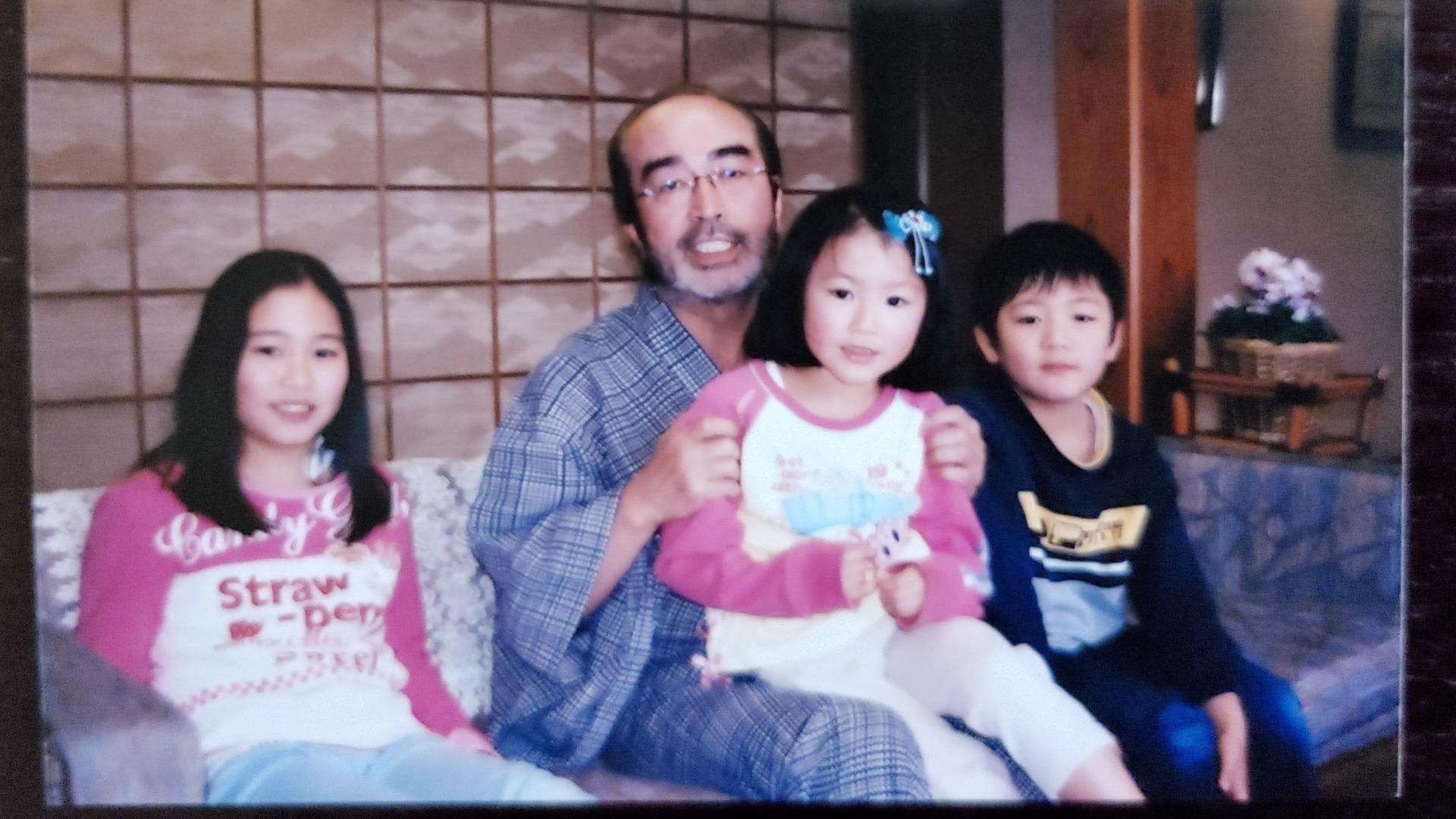21年越しの夢を叶えたチーム・タイワンとファンの「アイデンティティ」【プレミア12】

遠かった日本の背中
2年後に迫ったWBC連覇に向けての試金石とも考えられていた今年の「世界野球」プレミア12は、台湾の歴史的勝利で幕を閉じた。日本、韓国と並ぶ「アジアのビッグ3」と言われながらも、実際は国際大会へのプロ参入後は、まれに韓国相手に「金星」をあげることはあっても、日本の壁には常に跳ね返されてきた。
これまでの台湾野球のピークは、オリンピックにまだプロが参入していないバルセロナ大会にさかのぼる。郭李建夫(のち阪神)をエースに、黄忠義、羅国璋ら、のち台湾プロリーグ入りするトップ選手たちがプロ予備軍の集まる日本を抑えて「アマチュアの雄」・キューバに次ぐ銀メダルに輝いた1992年は、「職棒3年」であった。当時プロリーグCPBL発足3年目を迎え、国中が野球熱に沸いていた。ナイター帰りにまだ日本統治下の昭和時代を思わせる古い街並みを歩いていると、ブラウン管テレビから代表チーム「中華隊」の活躍を報じるニュースが流れていた。
国際大会への「プロ解禁」後、国際大会で1度だけ金メダルをとったことはあるが、その2006年のアジア大会は、オールトッププロの台湾が、プロ中心の韓国、そして社会人選抜の日本を下して頂点に立ったものだった。

野球の「世界大会」に本格的にプロが参入したのは、2004年のアテネオリンピックと言っていいだろう。2002年シドニー大会でオールプロの韓国の前に敗れた反省から、この大会に際して日本は「ミスタープロ野球」を監督に据え、「挙国一致」体制でオールプロによる「長嶋ジャパン」を結成した。長嶋本人は病に倒れ、チームを率いて聖地へ行くことは叶わなかったが、前年2003年に行われた、この大会の予選にあたるアジア選手権では指揮を執った。札幌ドームで行われたこの大会こそが、アジアの「ビッグ3」がプロ主体で臨んだ最初の大会である。この大会は、予想通り日本が優勝し、2枚ある五輪切符の1枚を手にした。そして、もう1枚をもぎ取ったのが、延長戦で韓国を破った台湾だった。この頃はまだ、日本と韓国、台湾の差は誰の目にも明らかだった。この3年後の第1回WBCではイチローから「向こう30年は手が出せない」発言があったが、韓国に火をつけたその発言も、当時の実力差からむべなるかなと思えるものだった。1990年代、台湾には日本のプロチームが何度か遠征に来ていたが、それらは二軍チームだった。

オリンピック本番では、台湾は日本相手に延長戦まで戦ったが、結局は10回にサヨナラ負けを喫している。台湾野球にとってはプロ発足以来追ってきた日本の背中が初めて見えた瞬間だったが、点差以上にその背中は遠くに見えた。
プロ主体の国際大会WBCが始まったのは2006年のことだ。しかし、ここでも台湾は、「アジア代表」として主役を演じることになる日本、韓国の引き立て役となる。2009年の第2回大会においても、アジアの両雄が熾烈な優勝争いを繰り広げる中、台湾は第1次ラウンドで姿を消すことになったばかりか、前年のペキンオリンピックに続いて、本来格下である「敵国」である中国に敗退し、参加国が拡大される第3回大会に際して予選を戦わねばならなくなった。
それでも、その予選を勝ち上がって臨んだ2013年の第3回大会では、「アジアナンバー2」の韓国を抑えて初めて第1次ラウンドを突破。東京での第2次ラウンド1回戦では、9回2アウトまでリードを保ち、侍ジャパンを追いつめた。この時、土壇場から同点打を放ち、延長10回の逆転劇を導いたのが、他ならぬ今大会の監督を務める井端弘和だった。
結局、台湾はこの試合には負けたのだが、国民は侍ジャパン相手の「大健闘」を称えた。ナンバー4の中国に2度までも負けるというどん底からナンバーワンの侍ジャパンを追いつめるところまでいけば「よくやった」というところだった。まだまだ日本の背中は遠い存在だった。
しかし、それもつかの間。台湾野球は再び暗黒期に戻ってしまう。2017年の第4回、昨年の第5回WBCはともに第1次ラウンド最下位で予選からの出場を余儀なくされた。また2018年のアジア大会では、トッププロを揃えた韓国に金メダルをさらわれたのはともかく、メンバーの半数をプロで占めながら台湾はオールアマチュアの日本に銀メダルまでも奪われてしまった。

アジア大会は昨年にも開催された。ホスト国の中国が日本相手に勝利を収めるなど、アジア野球の新時代を感じさせたこの大会では、台湾も決勝に進むなど数年来の国際大会での不振を払拭したかに見えた。2対0という接戦の中、結局は例年のように、金メダルは韓国がさらっていったが、このオールスター軍団を前に先発投手として力投したのが、今回決勝で侍ジャパンの前に立ちはだかった林昱珉(リン・ユーミン)だった。夜明けは確実に近づいていた。
新時代を感じさせる快進撃
今大会の第1次ラウンドは名古屋での日豪戦を除いて台湾で行われた。とくに昨年開場した台湾ドームは連日、「チーム・タイワン」を応援するファンが押しかけ、その声援を受けたメンバーたちはライバルの韓国を下すなど快進撃を続け、東京行きの切符を手にした。東京行きが決まったその瞬間から、日本行きの航空券の価格が急騰し、東京ドームでの台湾戦のチケットが飛ぶように売れていった。そして、台湾から東京への「民族大移動」が起こった。

「青天白日満地紅旗」の下に
東京ドームが台湾ファンにとりわけ好評だったのは、彼らの「国旗」を堂々と掲げることができたことだ。
「台湾」という「国」の国際社会での立ち位置は非常に微妙である。かつて中国大陸を統治していた「中華民国」政府が、日本の敗戦後、その支配下にあった台湾を接収し、その後、現在中国大陸を収めている共産党政権との内戦に敗れ、その統治範囲が台湾島とその周辺に縮小してしまったのだ。その結果、国際社会はその安定のために「一つの中国」の原則の下、「中華民国」か「中華人民共和国」のどちらかしか「国家」として認めないという建前で台湾と向き合っている。日本もそれに従い、この「国」を「台湾」という地域名で呼び、スポーツ界は、「チャイニーズ・タイペイ」という呼称でこの「国」の参加を認めている。そのような事情から、国際スポーツの場では「中華民国」の「国旗」で青天白日満地紅旗が掲げられることもないし、「中華民国国歌」が流されることもない。今大会でも台湾戦の試合前に流れていたのは台湾、公式にはチャイニーズ・タイペイの五輪委員会の歌だった。
それでも、東京ドームではスタンドのファンが「国旗」を持ち込むことが許された。台湾戦のスタンドではいたるところで青天白日満地紅旗が振られていた。

しかし、「中華民国」と中華人民共和国の「分裂」状態はもう70年以上続いている。九州と同じくらいの面積の島の住民の多くは「台湾人」というアイデンティティを形成している。そのことは、決勝戦で勝敗を半ば決める3ランを放ったチームの主将、陳傑憲(チェン・ジェシェン)が、三塁ベースを回る際、手で胸を大きくアピールしたことにあらわれている。通常、このポーズを取るとき、選手が手で示したその胸には国名が大きく縫い込まれている。しかし、彼が示したその胸にはなにも記されてはいなかった。「チーム・タイワン」のユニフォームには左上に「チャイニーズ・タイペイ」を示す「CT」の組み合わせ文字がプリントされているだけである。
複雑な国際事情中、陳が強烈なアイデンティティを示した瞬間だった。それが、「台湾」なのか「中華民国」なのかそれさえも聞くことが憚られる国内事情の中、「チーム・タイワン」は「世界一」の栄冠を手にし、トロフィーを持ち帰った。
このフィーバーはしばらく続くだろう。打倒侍ジャパンを目指す様々な国、チームが台頭してくる面白味がこのプレミア12という国際大会の醍醐味であることを示してくれた「チーム・タイワン」に拍手を送りたい。

(写真は筆者撮影)