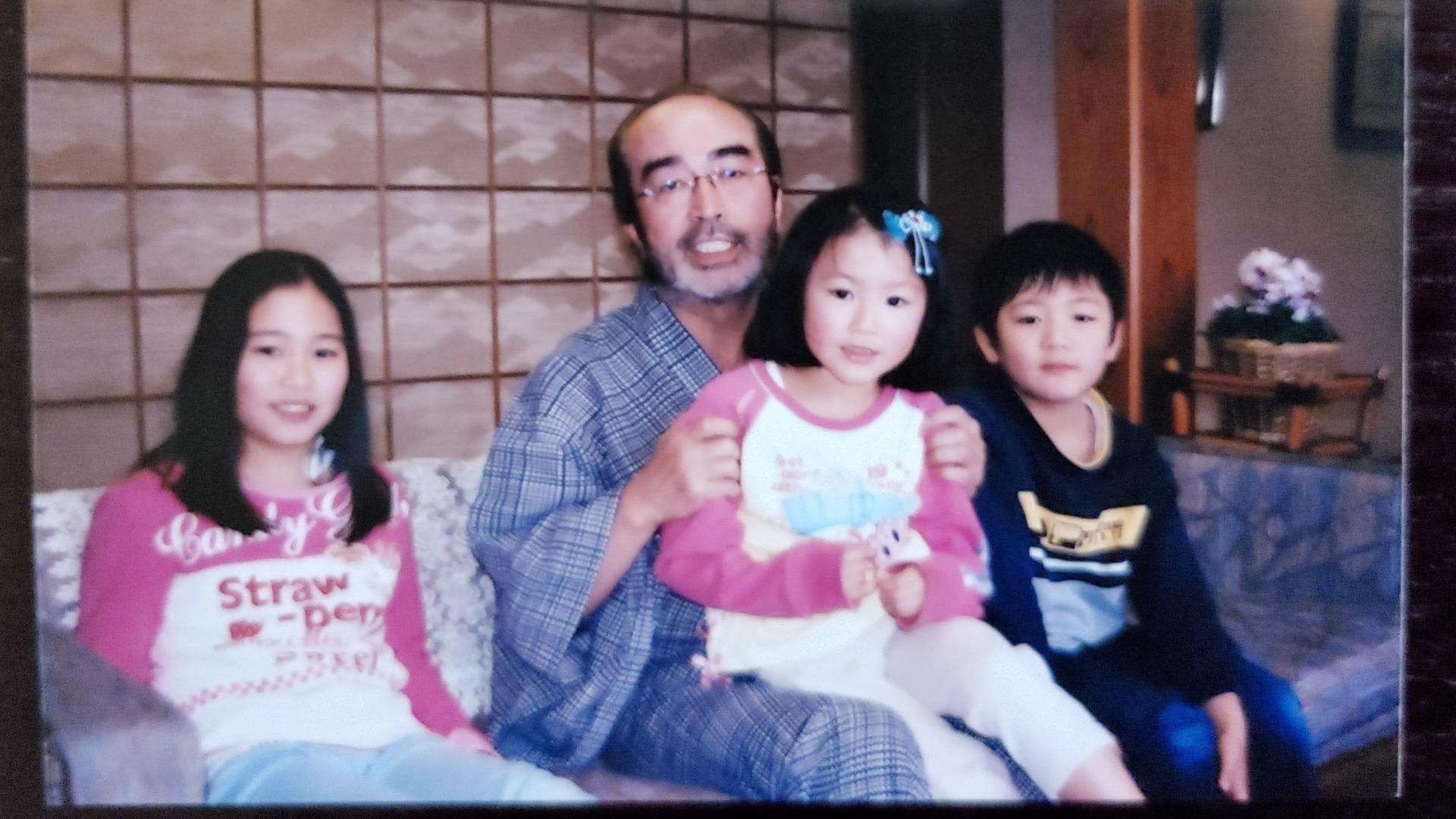久住昌之インタビュー!「こういうのでいいんだよ」で語る『孤独のグルメ』論

『孤独のグルメ』の原作者の久住昌之さんの町歩き&自伝的エッセイ『東京都三多摩原人』が集英社より文庫化された。
生まれ育った三多摩地区を歩き、食べ、また歩くなか、少年期の記憶を蘇らせる軽快なエッセイである。
この記事では、本のバックボーンを語っていただきながら、最後に今年で66歳になった心境について、話を聞いてみた。
ファストフードとカップ麺、そしてレトルトカレー。日本の食文化の発展を間近に見てきた
東京都三鷹市で生まれ、現在に至るまで住み続けている久住さん。『東京都三多摩原人』(集英社文庫)は、そんな久住さんが「知ってるようでよく知らなかった」三多摩地区を歩いて、歩いて、探求した軌跡が綴られている(ちなみに三多摩地区とは、東京都の23区と島嶼部を除く市町村部分のことである)。
「1958年、つまり昭和33年に生まれて、東京の三鷹市で少年期を過ごした人はみんなそうだと思うんだけど、当時の東京はいろんなものが過渡期を迎えた時期でした。小学校の校舎は木造から鉄筋の建物に移り変わる時期で、僕は木の廊下にワックスを塗って、四つん這いで雑巾がけをした最後の世代。
『ドラえもん』に出てくる空き地の土管もそのままリアルにあって、にわか雨が降れば土管で雨宿りしたし、基地も作ったし、落とし穴も掘ったりして遊びました」
大阪で万国博覧会が開かれたのが、久住さんが小学校の6年生のとき。その会場に、日本初のファストフード店のケンタッキーフライドチキンが登場した。
連合赤軍事件で、あさま山荘を包囲する機動隊員の非常食としてカップヌードルが脚光を浴びたのが、中学1年生のとき。もう、そのころには昭和レトロの琺瑯看板のボンカレーの広告も町のいたるところに掲げられていた。
「要するに、日本人の食のバリエーションが圧倒的に広がった時期でもあるんです。その延長線上に『孤独のグルメ』があるのかもしれない。
今、インバウンドでたくさんの外国人が日本に来て、ラーメンだの寿司だのを食べて「OISHII!」って言ってるけど、今の日本のグルメブームの歴史って、自分が生まれ育った時期とピッタリ並行しているんだなって感じます」

新しい発見のある町なら、
いつまでも歩けちゃうんだよね
『東京都三多摩原人』を読むと、久住さんがかなりの健脚の持ち主だということがよくわかる。
歩いた距離は1回の取材で十数キロに及ぶコースもある。普段からそんなに歩いているのだろうか?
「そうですね、僕の母親もけっこう、歩く人だったんですよ。だから、遺伝の要素もあるかもしれない。特に歩くのが『好き』というのではなくて、『苦ではない』という程度です。
だから、山登りみたいなのは好きじゃない。キツいのは嫌い。でもどこまで歩いても、単調な自動車道だと飽きてしまうんです。緑があって川が流れて海があれば、いつまでも歩けちゃうんですね。でも、知らない街歩きは、それはそれでわくわくしますが」
ついこの間も、福岡の春日市という初めて訪れる街に行ったそうだが、思いがけない経験をしたという。
「実はその日、雨が降ったりやんだりで、傘をさしたり閉じたりの歩きだったんですよ。ところが途中、公園があって、そこのトイレに入って出てきてふと振り返ったら、見たこともない大きな虹の二重アーチが見えたんです。虹が本当に7色に分離していて。
感動って、どこから飛んでくるかわからない。そこに、町歩きの楽しさがあるんだと思います」
「いつも御馳走を食べたがるのは、みっともない」というおばあちゃんの教え
もちろん、久住さんは歩いた先での食事にも『孤独のグルメ』の井之頭五郎ばりにこだわりを見せる(原作者なのだから当たり前なのだが)。
例えば、田無駅前の480円の「正しい昔ラーメン」を食べて、「こういうのでいじゃん」とうなる描写がある。このひとこと、実に的を射ている言葉に聞こえるのだが、その真髄について、もう少し説明してもらおう。
「『こういうのでいいんだよ』っていう表現は、ある人から『上から目線じゃないか』って言われたことがあるんだけど、そうじゃないんです。だってそれは、自分の心のなかの声なんだから。
要するに、食材は何を使っているとか、権威ある団体から評価されているとか、そういう情報はどうでもいい。そういうことぬきに、今、食べている自分がおいしく感じてるっていうのがかけがえないことだと思うんです」
『東京都三多摩原人』には、そうした価値観に影響を与えた人物として、母方のおばあさんの話が出てくる。
「おばあさんはこう言っていました。
『いつも御馳走を食べたがるのは、みっともないこと。でもね、おいしいものの味は、知っておかなきゃダメ。そうしないとマズいものの味がわからないから』って。
当時は意味がわからなかったけど、ずいぶん時間がたって、おばあちゃんが亡くなってから、わかるような気がしてきました」
ちなみに久住さんのおばあさんは、彼が高校生時代、わざと裾をほどいたベルボトムのジーンズを履いたり、ボサボサの長髪にしたりすることを「時代時代に流行っちゅうもんがあって、それはアタシらのときも同じ」と言って、決して咎めなかったという。
「でもね、おばあちゃんはこう厳しく言ってました。
『だけど、ズボンの裾を引き摺って歩いて、公衆便所に行ったりして、家に上がるようなのは、誰だって嫌でしょ、されたら』って。
そのとき、長髪の僕は本当にそうだと思いました」

「老い」というのは、引力に屈するということなんだ
1958年、つまり昭和33年に生まれた久住さんは、2024年に66歳になった。
そんな久住さんに最後に「老い」との付きあい方について、聞いてみた。
「最近になって、わかってきたのは、『老い』というのは引力に屈していくありさまだってこと。
引力というのは、生命を土のなかに還そうとする力ね。
若いころは元気だから、その力に負けまいと必死に抵抗します。だけど、ある程度、年をとってくると、引力に負けてきて、いろんなところが垂れてくる。
でも、それは自然なことで、あらがいようのないことなんだよね。
そう考えると、生きている人はみんな、土に還る途中の段階にあるんだから、その途中をできるだけ楽しむのがいいと思う」
ちなみに「最後の晩餐で何を食べたいですか?」と聞かれるたび、久住さんは「くたばる間際なんて、ものを食べるどころじゃないはずだからわからない」と答えているという。
これも、「こういうのでいいんだよ」と同じく、腑に落ちる言葉のような気がするのである。

※この記事は、かっこよく年を重ねたい人におくるWEBマガジン「キネヅカ」に公開された記事を加筆・修正したものです。是非、そちらの全長版もお楽しみください。

『東京都三多摩原人』(集英社文庫)の購入サイトはこちら。