【「麒麟がくる」コラム】明智光秀が担当した京都馬揃え。織田信長は軍事力で正親町天皇を脅そうとしたのか
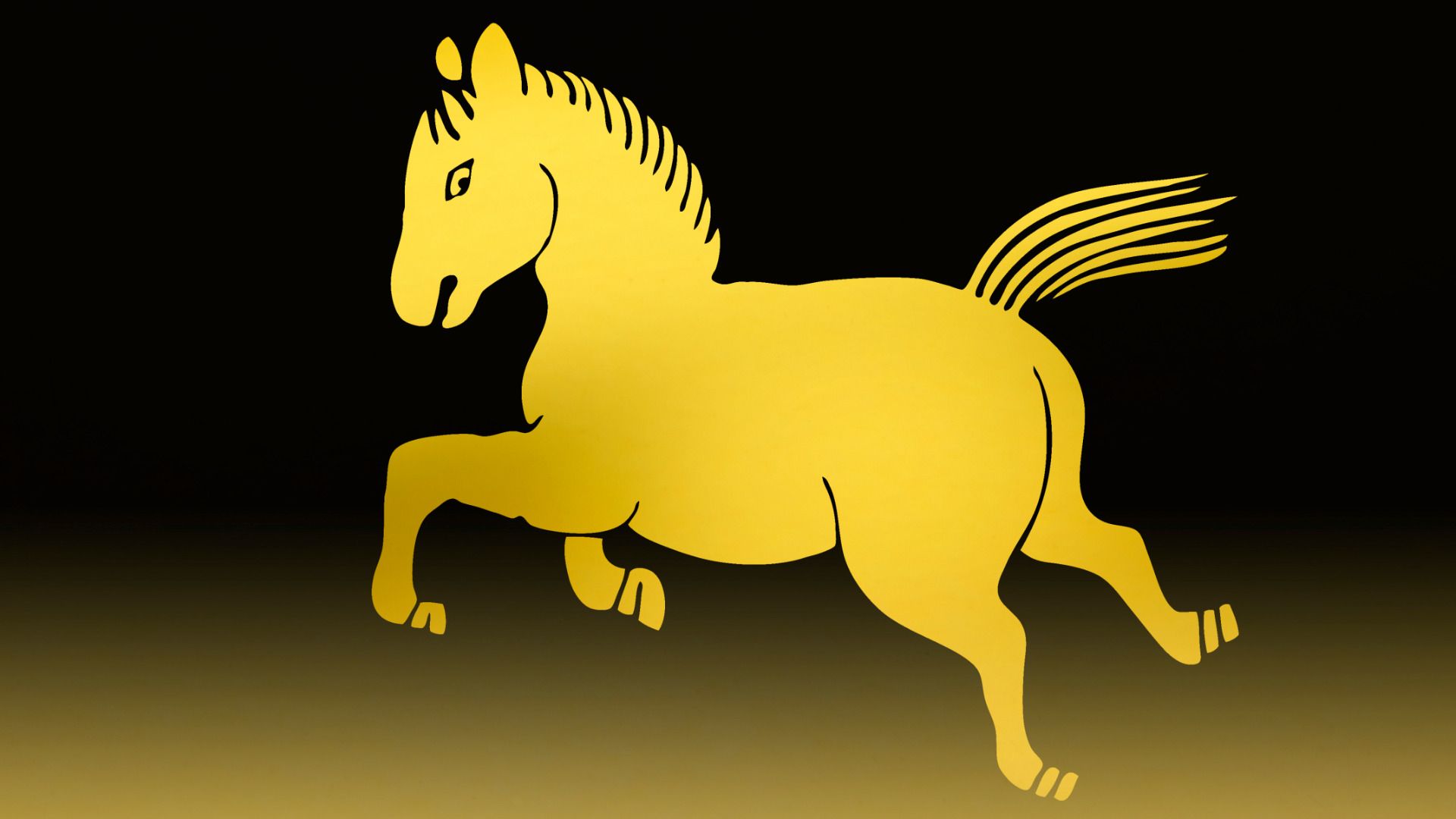
■完全にスルーの京都馬揃え
大河ドラマでは、完全にスルーされた京都馬揃え。一説によると、信長は正親町天皇に自らの軍団の威勢を見せつけ、軍事力を誇示しようとしたという。本当に信長は、そのような目的で馬揃えを行ったのだろうか。
■馬揃えとは
天正8年(1580)7月、織田信長は宿敵の本願寺と講和を結び、11年もの長きにわたった抗争は、ようやく終止符を打った。信長にとって、本願寺を降伏させることは大きな悲願だった。
こうした祝意の意味もあったのか、翌天正9年(1581)1月15日、信長は馬廻衆を安土城(滋賀県近江八幡市)に招き園遊会を催そうと考えた。しかし、当日は雨ということもあり、左義長に振り替えられた(『信長公記』)。
同年1月15日、信長は左義長を催すため、安土城に馬廻衆を招いた。左義長とは小正月に行われる火祭りのことで、地方によって「どんど」「どんど焼き」「さいと焼き」「さんくろう焼き」などと称されている。
民間では竹を立て、門松・注連縄・書き初めなどを焼き、その火で餅を焼いて食べて無病息災を祈った。宮中では1月15・18日に清涼殿南庭に青竹を立て、扇・短冊などを結びつけて焼いた。
信長が主催した左義長では、爆竹が派手に鳴らされるなどし、見物人が大いに盛り上がったと伝わる。信長自身が豪華な衣装を身にまとって登場するなどし、織田家の一門がほぼ勢揃いした。
なかでも騎馬行列は多くの見物人の目を引き、注目を集めたといわれている。これこそが、馬揃えだ。正親町天皇は安土城下で催された左義長と馬揃えの噂を耳にして、ぜひ見学したいと熱望した。そこで、京都においても、信長が主催して馬揃えが行われることになったのだ。
■明智光秀に命じられた馬揃えの準備
天正9年(1581)1月23日、信長は明智光秀に京都における馬揃えの準備を命令した(『信長公記』)。馬揃えの準備のことは、信長の書状によって光秀に準備が命じられたことがわかる(『士林証文』所収文書)。
この信長の書状によると、先の15日に催された左義長に関しても、光秀が担当者であったことが判明する。信長は重要な行事を光秀に任せたのだから、かなり信頼していたと考えられる。
馬揃えとは信長軍団の軍事パレードのようなもので、それは大規模なものだった。参加者の人数の多さもさることながら、良い馬を準備する努力も惜しまなかった。
徳川家康は、信長に鹿毛の駿馬を1頭贈ったほどだ。馬揃えを開催する当日には、禁裏の東門付近に正親町天皇のための行宮(あんぐう。仮の御所)が設営されるなどし、準備は万端整った。
■挙行された馬揃え
天正9年(1581)2月28日、信長は正親町天皇を招き、禁裏(京都御所)の東門外で壮大な馬揃えを行った(『御湯殿上日記』など)。
会場の広さについては諸説あるが、長さ(南北)は約436メートル~872メートル、幅(東西)は109メートル~163メートルという広大なものだった。
馬揃えに参加した武将は約700名といわれ、騎馬武者の衣装も豪華壮麗だった。見物人は約20万人も集まったというので、世間の注目は大きかった。
朝廷との関係を考えるうえでは、公家衆が参加したことに注目すべきだろう。この壮大かつ葬礼な馬揃えを見物すれば、見学した誰もが信長の威勢を感じずにはいられなかったはずだ。
■馬揃えの目的
信長が馬揃えを行った目的は、いかなる点にあったのか。『信長公記』には、「天下(=畿内)において馬揃えを執り行い、聖王への御叡覧に備える」と記されている。
信長の本当の目的は、天下(=畿内)が治まりつつある状況下で、正親町天皇と誠仁親王に馬揃えを叡覧に供することだった。馬揃えも朝廷に対する奉仕の一環である。
信長は馬揃えを挙行したことにより、朝廷への奉仕を行ったという強い達成感を感じたに違いない。同時に信長軍団の威勢の顕示と士気高揚を広く知らしめ、信長が畿内近国を制覇したことを天下に示したのだ。
■喜んだ正親町天皇
その結果、「このようにおもしろい遊興を正親町天皇がご覧になり、喜びもひとしおで綸言を賜った」と書かれているので(『信長公記』)、正親町が大喜びだったのは疑う余地がない。
最近の研究によって、別の馬揃えが行われた理由が示されている。その理由は、誠仁親王の生母・新大典侍が天正8年(1580)12月29日に亡くなったからだった。
朝廷はそうした沈滞ムードを破るべく信長に馬揃えの開催を要望した。そうした理由から、信長は生母を亡くして落ち込む誠仁を励まそうとしたという。信長の優しい心遣いだった。
つまり、信長が馬揃えを挙行したのは、朝廷に対する圧迫でも嫌がらせではなく、そもそもは正親町天皇が要望したものだった。そして、大いに喜んだのだ。あるいは、信長が朝廷の沈滞ムードを破るために協力したものであって、決して正親町天皇を脅す気はなかったのである。










