「昼夜を問わず、家庭ごと支援」 県教委とNPOのタッグで全公立小・中・高校に訪問支援員を派遣・佐賀

登校は雨の日だけ
中学2年のA君が学校に来るのは、雨の日だけだった。
雨の日は建設関連で働く父親の仕事がない。そのときだけ、父が車で送ってきた。月に1~2回だった。スクールカウンセラーにも一度会ったきりで、それ以降、学校からの働きかけを受け入れずにいた。
伊東毅さんは、A君が学校に来る機会をみはからって会い、また、兄弟の入学式で学校に来た父親をつかまえて、訪問の同意を得た。
家はゴミ屋敷状態で、膝までゴミで埋まっていた。ネコが5~6匹飼われており、階段にはフンが放置してあった。
A君はそれをまたいで自分の部屋に入った。伊東さんの手前で気まずそうにするそぶりもなく、伊東さんは「これが日常なんだな」と感じた。
いつも靴下だけが真新しいのはなぜだろうと思っていたが、家を訪問して理由がわかった。A君は靴下を脱ぎ捨てると、そのままゴミ箱に入れた。
まずは父親から
母親が家を出て以来、生計を立てることで精いっぱいの父親は家を片づける気力も失っていた。伊東さんは同僚の応援を得て父親の家事や経済的な負担を減らすことから支援を始めた。
伊東さんは、昼夜逆転しているA君を週1回ペースで訪問し続けている。
A君はまだ学校には関心を示さないが、将来「父のそばで働きたい」と語り出すなど、だんだん伊東さんに心を開き始めている。しゃべり方にもエネルギーが出てきて、資格や免許も欲しいと言い出した。
伊東さんは、そんなA君の思いに寄り添いつつ、まずは勉強や進路について一度先生に相談してみないかとA君に水を向け始めている。

相談室に「登校」
高校1年のBさんは、学校にまったく来られなかった。多子家庭で、母親の関心が自分には向いていない。さみしさを表現できない分、腹痛やめまいなどの身体症状が表れていた。
江崎優子さんはBさんを訪問し、1週間に一度、学校の相談室で面談する約束をとりつけた。スクールカウンセラーとは一度会ったものの、男性で話しづらいということもあってか、面談は継続しなかった。しかしBさんは、江崎さんとの約束は守り、相談室に「登校」してくる。
徐々に気持ちを出せるようになり、進級したいという希望が見えたので、江崎さんは担任の力を借りてBさんと学習面でのやりとりを始めた。
その後、江崎さんはBさんの承諾を得て、母親にBさんの気持ちとがんばっている相談室での姿を共有した。ほどなく母親の対応に変化が生まれ、Bさんは徐々に教室に足を運べるようになった。

佐賀県教委の挑戦
伊東毅さん、江崎優子さんは、佐賀県が今年度に始めた「訪問支援による学校復帰サポート事業」という不登校対策事業の主任コーディネーターとコーディネーターだ。
佐賀県教育委員会は、今年度から県内すべての公立小中高校を対象に、訪問支援員を派遣するという思い切った事業を始めた。
「昼夜を問わず訪問し、家庭ごと支援する」のが目的だ。
不登校対策は、すべての都道府県で実施されているが、全国に4704か所ある教育支援センター(適応指導教室)に登録して通室を促すだけの自治体もあり、ここまで徹底した対策をとっている自治体は、他に聞かない。
なぜ佐賀県でそれが可能となったのか、県教委の担当者・宮崎耕一氏(佐賀県教育庁学校教育課参事)、伊東さん、江崎さん(ともに所属はNPOスチューデント・サポート・フェイス)の3人に聞いた。
不登校等の長期欠席児童・生徒は27万人
現在、不登校等による長期欠席児童・生徒は、小学校で63,089人、中学131,844人、高校79,207人。全児童・生徒数に占める割合は、それぞれ1.0、3.8、2.4%(文科省「平成27年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」2016(平成28)年10月速報値)。
2008年度以降は減少傾向にあったものが、2013年度以降ふたたび増加傾向にある。
わずか1~3%と見るか、27万人と見るかで、受け取り方は変わってくるだろう。
「学校に行かなくても立派な大人になれる」という意見もあるだろうし、学校には行ってなくてもフリースクール等で大事な学びを得ている子どもたちもいるだろう(学校外の機関等で相談・指導等を受け、指導要録上出席扱いとした児童生徒数は18,696人。同上による)。インターネットを活用して、非常に質の高い勉強をしている子もいるかもしれない。
受け止めきれるのかという不安
同時に、27万人の大多数が家庭・学校・友人関係等で困難を抱え、十分な知識・学力や社会性を得られずに苦しんでいるだろうと想像しても、おかしくはない。
この子たちが十分な力を蓄えられないまま大人になったとき、今よりもさらに少子高齢化の進んだ日本社会が、その人たちを受け止めきれるのかという不安は、多くの人が共通して抱いているものではないか。
増加に転じた危機感が後押し
――すべての公立小中高校を対象に訪問支援員を派遣するというのは、相当思い切った事業ではないかと思いますが、実施に至った経緯は?
(宮崎)本県の不登校児童生徒数は、平成19年度に一つのピークを迎え、それを受けてさまざまな対策を打ちました。学校にも大変ご尽力いただき、平成25年度くらいまでは中学は減少、小学校も減少傾向にありました。
しかし、平成25年度を境に再び増加に転じ、全国平均を上回ってしまいました。これはなんとかしなければいけないと、この事業に至ったわけです。
本県の場合、指導の結果、学校復帰を果たした児童生徒の割合が少ないんです。子どもたちの状況が深刻化・重篤化していることが予想されました。
これまでも私たちなりに手は打ってきたんですが、今回の増加を受けて、さらに本格的に「しっかりやらなければならない」ということで、全県、小中高すべてを対象に実施することになりました。
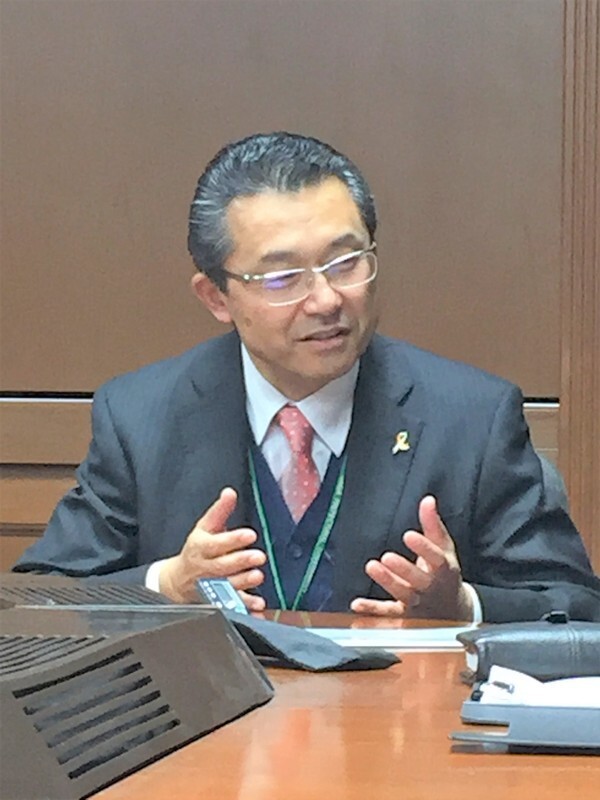
佐賀県にこのNPOがあったからできた
――今回の事業は、NHK番組「プロフェッショナル」にも取り上げられた谷口仁史さんが代表を務めるNPOスチューデント・サポート・フェイス(以下SSF)に委託していますね。
(宮崎)SSFには、今回の事業の原型になった高校の事業もお願いしていました。そのときには、支援してもらった生徒への効果ももちろんですが、もう一つ、その支援のあり方を見て、高校教員の考え方が変わってきたという効果がありました。
高校は、中学までと違って義務教育ではないので、生徒への距離感も中学までよりも遠い。ともすると、学校に来ないことも含めて、生徒の自主性・主体性に任せるという雰囲気もあったのですが、訪問支援員の方たちの熱心な姿を見て、教員たちが生徒の困りごとをより親身に受け止めるようになりました。
さまざまなことをやってきましたが、今、特に課題だと考えている家庭への支援については、手が届いていなかったというのが正直なところなんです。やはり学校として家庭に入っていく、支援をすることには限界がありました。
また、家からなかなか出られない子どもは昼夜逆転している場合がありますが、私たち行政職員だとどうしても、何時から何時までという勤務時間に縛られてしまいます。
昼夜にかかわらず、家庭に関わるという点で、この事業は民間の力を借りなければならないだろうと思ってきました。
そこで、協働する民間団体として頭に浮かんだのが、これまで訪問支援の実績を積み上げてこられたSSFでした。逆に言えば、この事業は佐賀県にSSFがあったからできたと言っても過言ではありません。全県規模で、事業が目指す体制をとれるのはSSFしかありません。
私もSSFとこれまで関わってきた経験から「大丈夫です」と自信をもって言い切ることができました。SSFとのつながりがなかったら、課題のあることがわかっていても、この事業はできなかったでしょう。

学校現場に受け入れられるための仕掛けと工夫
――すべての公立小中高校を対象に、しかもNPOへの委託で、というのはかなり異例と思います。教育現場などからの異論はありませんでしたか。
(宮崎)たしかに丁寧に進めていく必要がありました。
一つには、学校現場に理解をしてもらうために、事業実施前に、私たち教育委員会が県内20の市町の校長会すべてを回って、事業説明をしました。
――そのときの反応は?
(宮崎)基本的には「ありがたい」と。
毎年、不登校児童生徒の多い学校を訪問してヒアリングしながら県の施策に反映させてきていますが、最近は本当に「子どもたちを見るだけでは限界で、それ以上に家庭を支援しなければいけない」という声が多いんです。それはもう、訪問したすべての学校から言われるほどです。
ただ、どこまでやればいいのかという物理的な悩みがあるのと、もう一つは、仕方のないんでしょうが、やはり学校の先生には家庭支援の十分なスキルとノウハウがない。その自覚があるからでしょう、「学校の中にそんなに踏み込んでもらっちゃ困る」という声はありませんでした。
もう一つの工夫は、今回の事業をSSFに対する単なる委託ではなく、県教委との協働事業としたことです。県内に3つある教育事務所に江崎さんたちの座席をつくって、そこを拠点にコーディネーターとして働いてもらっています。江崎さんたちは「県の教育事務所から来た人」ということになるわけです。
そして、江崎さんたちには県内すべての学校を訪問してもらっています。学校からすると、いくらか立ち入った話を学外の人にすることになりますから、やはり信頼関係の構築が重要だろうと。

最初はなかなか難しかったが…
――江崎さんは、学校を訪問してみてどうでしたか?
(江崎)正直言うと、最初は「NPOに何ができるの?」という不安の声もあり、理解を得るのはなかなか難しかったですね。ただ、徐々に理解を得られるようになったと思います。
(宮崎)そうでしたか…。私たちには伝わってこないご苦労もおかけしているんですね。たしかに校長会で事業説明をする際、声としては返ってこなかったけど、ウェルカムな方もいる一方で、本当に大丈夫なのかと心配げに話を聞いておられる方もいて…、すべての校長先生の意識をそろえることはなかなか難しいところです。
(江崎)私が不慣れなこともあって最初は事業説明だけで終わってしまってたんですけど、慣れてくると、不登校の子の現状を聞いた上で「こんなふうにできたらいいですね」ってお話できるようになり、「じゃあお願いしてみようかな」と言ってくださる校長先生もいらっしゃって、徐々にスムーズになってきました。

半年で200件、課題も見えてきた
――実質的に去年の8月スタートで、約半年間で200件の相談があったそうですね。この数字をどう受け止めていますか。「まだまだ」なのか「ここまでできたなあ」なのか。
(宮崎)私は、まだまだだと思っています。本県の不登校児童生徒は、小学校で213人、中学校で754人、高校で274人の合計1,241人います(平成27年度文科省調査)。この2倍に増えてもおかしくはありません。
事業のスキームとしては、家から出ることのできない、ひきこもりがちの児童生徒を対象とすることになっていますが、適応指導教室に通えているけどときどきとか、パキッと分けて考えることはできない。困っている子どもたちにはできるかぎり対応していきたい。
(伊東)親の同意をもらわないと関われない仕組みになっているところが大きいかなと感じますね。学校からは訪問候補者として挙がってきているケースでも、同意がとれないために訪問できない家庭がけっこうある。
――同意はどうやってとっているんですか?
(宮崎)基本的には学校が保護者の意向を確認し、同意をいただいています。
ただ、学校に対してさまざまな思いを抱いていらっしゃる保護者もいることから、場合によっては第三者からの声かけが効果的なこともあると思います。たとえばスクールソーシャルワーカーなどから「こういう支援を受けてみませんか」と声かけしてもらうなどの工夫はできるかもしれません。
学校でケース会議を開いてもらって、別の側面からのアプローチを検討していただくようなお願いをしないといけないのかもしれませんね。

学校に来てくれただけで十分と感じる子どもは数多くいた
――現場と制度設計者のこうしたやりとりが、始まったばかりの事業の運用を一つひとつ改善させていくんでしょうね。
ところで宮崎さんはずいぶんご熱心に見えますが、小学校の先生として、不登校の子を担当されたご経験などがあるんですか。
(宮崎)教務主任や教頭をやっていたときにはおりましたけど、私自身がクラス担任をしていたときに不登校の子がいたことはないですね。
ただ、経済的な理由で学校に来られないというケースはありました。ご両親がその日の生活をするのが精いっぱいで、子どもたちにまで手が回らない。生活面のサポートがおろそかになって、子どもが学校に出てこなくなる。そうした例は数多く見てきました。朝起こしに行って、学校に連れてくるということもやった。まずは学校に来てくれただけで十分と感じる子どもは数多くいました。
そうした家庭を見てくると、子どもたちをどうにかしてあげないといけない、とやはり思いますよね。
「本当にもう無理」ってなってしまう場合も…
以前に比べると、離婚家庭も増えました。家庭環境が大きく変わると、子ども本人に自覚がなくても、心のどこかに不安があって、家庭から離れられなくなったりする。家庭の不和もそうですが、そういう深層心理が影響して、不登校になってしまったりする。
学校サイドの人間がこう言うと怒られるかもしれませんが、やはり家庭の要因は大きい。外で大変なことがあって心身ともに疲れて帰っても、家で充電できるといい。でも、充電すべき家庭で充電できないという状況が、最近特に多いように感じます。
そうならざるをえない状況というご家庭もあるし、もうちょっとお父さんお母さん頑張ってよと思う場合もあります。子どもたちからすれば、不安定な中で、精いっぱいがんばって学校に来ているのに、学校で何かあって「本当にもう無理」ってなってしまう場合もあるんじゃないか。
そう考えると、せっかく教育委員会にいるんだから、この場所でできる限りのことはしないといけないと思うんですよね。

子どもたちは見ている
――とはいえ、なかなか目に見える効果を出しにくい事業でしょう。
(宮崎)今関わってもらっているのは大変なケースが多いので、一朝一夕で効果が出るものはないのは事実です。
ただ、学校に行ったときにお話させてもらうのは、目に見える成果が出にくいかもしれないが、前年度のA君と今年度のA君は必ず違うはずだと。
不登校の定義の30日は超えてしまったけど、昨年は60日だったのが今年は40日だったとか。あるいは、学校に来ても午前に帰っていたのが、午後までいられる日が増えたとか。何がしかの成長があるはずで、それを励みにしてほしいと伝えています。そういうことを数値として出していき、関係者のご理解を得ていきたいですね。
今日の明日で効果が表れなくても、伊東さん江崎さんたちが対応してくれた200人の子どもたちが、少しずつでも必ず前向きになっていってくれるものと信じています。
何よりも、不登校にまでは至らずに今をふんばっている子どもたちも、万が一そうなってしまったときに大人たちがその子たちにどう接するかを見ているはずです。
大人たちが誰一人見捨てない気概を示すことは、不登校になった子どもたちはもちろん、そうでない子どもたちにも大切なメッセージを送ることではないかと思っています。











