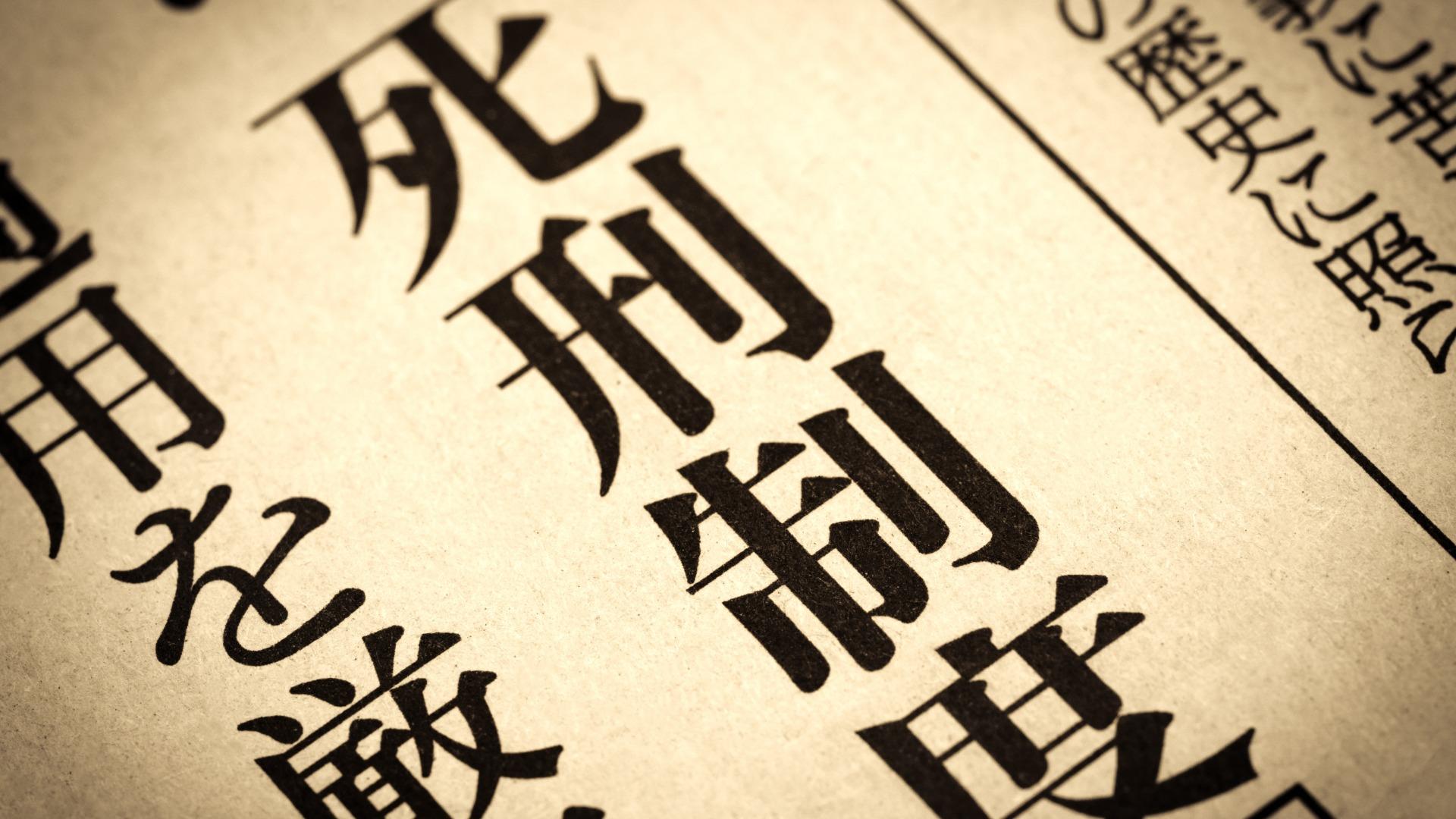熱中症を防ぐために「暑さ指数」を知ってほしい

今年も、5月のうちから熱中症で救急搬送される方が散見されます。山梨で運動会の練習後に多数の児童が救急搬送されたというニュースもありました。改めて、熱中症をどのように予防していくかを共有したいと思います。
熱中症って何!?
救急医学会では、熱中症診療ガイドラインを作成しています。以前は熱けいれん、熱失神、熱疲労、熱射病という分類の下、こうした症状があったら熱中症かなという判断をしていましたが、このガイドラインでは診断しやすさを上げるため、暑熱環境にいる、あるいはいた後に全身症状を起こしたもので、他の原因疾患を除外したものは熱中症と診断しましょうとしています。平たくいうと、「暑い環境にいた後、何らかの症状が出て、それが他の病気によるものじゃなかったら熱中症と考えましょう」ということです。
熱中症の症状は?
熱中症の症状はけいれんや失神、意識障害や高体温だけではありません。めまいや立ちくらみ、大量発汗、口渇、筋肉痛やこむら返り、頭痛、嘔吐、倦怠感、せん妄、小脳失調(真っ直ぐ歩けない)などの様々な症状を呈するので、意識障害や高体温がないという理由で過小評価するのは避けたいところです。
小学校低学年は特に、自身の症状をうまく伝えられないこともあります。「しんどい」、「疲れた」、「のどが渇いた」などの、熱中症が疑われる情報発信があれば、積極的に熱中症を疑う必要があります。
何で熱中症になるの?
人間は熱を産生して、全身に運び、皮膚表面から放散するというプロセスで体温を維持しています。熱を産生し過ぎたり(運動、風呂、暑熱環境)、循環が維持できなかったり(脱水、心機能低下)、放散されなかったり(発汗能低下、高温多湿環境)で、熱が体にこもると熱中症となります。
特に高齢者は脱水になりやすく、発汗しにくくなるので、必ずしも運動をしなくても熱中症になり得ます。炎天下で運動して脱水になると熱中症になりやすくなるのは言わずもがなです。
どうやったら熱中症にならなくて済むの?
熱中症予防の方法は、高温多湿環境を避けることです。救急外来でいつも実感しているのですが、高齢者の熱中症の多くが、冷房を使用しておりません。冷房を使ってください。今年は電気代が高くなる見込みで、冷房の使用控えから熱中症が増えないか懸念しております。自宅からの救急搬送も多いので、気をつけていただければと思います。
もう一つの予防策が水分摂取です。この時、水分と一緒に塩分を取るのが大事です。特に運動時は汗で塩分の喪失もありますので「水分+塩分」の摂取が求められます。経口補水液や梅干しがおすすめです。
暑さ指数と上手に向き合おう
運動時は特に熱中症のハイリスクとなります。だいぶ「暑さ指数」が浸透してきたように思いますが、改めて共有しておきます。
暑さ指数は1954年に米国で提案された指標で、「湿球黒球温度(WBGT:Wet Bulb Globe Temperature)」を指します。湿度、日射、輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、気温を加味した数値です。環境省の熱中症予防サイトで詳しく説明されています。同じ気温でも、湿度によって快適さに違いがあるでしょうし、熱中症リスクは変わりますから、対策のためには有効な指標となります(詳細はこちらの記事を参照)。
およそ日本の湿度と気温を考慮し、次の表が用いられています。

気温30度を超える環境では、積極的な休息が推奨されています。また、気温35度以上では運動の中止を考えるべきとしています。冒頭の山梨の件では同県内で気温30度を超えるところが確認されており、危険な環境であったことが示唆されます。
実は、環境省と文部科学省から、学校における熱中症対策を進めるべく、「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」が発行されており、気象庁が出す熱中症警戒アラートも参考に対策するように促されています。これを受けて、近年各教育委員会でガイドライン作成に取り組まれています。重要なのは、どうなったら運動の中止をするのかという線引きを明らかにしつつ、各家庭で共有すること、そして各家庭でも熱中症の危険性に敏感になっておくことだと考えます。暑さ指数を確認しないままに運動し、死亡に至ってしまった例も報告されています。これは学校での運動に限らず、職場においても重要ですし、趣味のウォーキングやジョギングなどの運動でも同様です。
Yahoo!JAPANでは熱中症の注意喚起をすべく、全国の熱中症情報を出してくれています。こうした情報も参考に、熱中症を避けつつ、安全な運動環境、就労環境の調整に取り組んでいただければと思います。