シリア化学兵器(塩素ガス)使用疑惑事件と米英仏の攻撃をめぐる“謎”

米国は期せずしてシリア撤退の「足固め」を行い、バッシャール・アサド政権は「独裁」の汚名を隠蔽する好機を得た――米英仏が14日にシリアに対して行った攻撃の「成果」は、穿った見方をすると、こう総括できるかもしれない。
米国務省が誇示した戦果
攻撃は、7日にダマスカス郊外県東グータ地方のドゥーマー市で発生した塩素ガス使用疑惑事件への制裁措置として敢行された。
米国防省やUSEUCOM(米欧州軍)によると、米軍は、紅海、アラビア湾、地中海に展開していた艦艇からトマホーク巡航ミサイル57発を、また戦略爆撃機からJASSM空対地ミサイル19発を化学兵器関連施設に向けて発射した。英仏軍も戦闘機および艦艇からミサイル20発を打ち込んだ。
105発ものミサイルにより、ダマスカス県バルザ区にある「化学兵器研究施設」(ただし、シリア政府側によると、この施設は抗ガン剤などの研究開発を目的とする「製薬化学研究所」)、ヒムス市近郊の化学兵器貯蔵施設、同じくヒムス市近郊の機器貯蔵施設および司令所の3カ所で、「数年分の研究開発データや特殊機器、化学兵器の原料となる物質」を破壊するなどの戦果があがった――米英仏政府は、こう主張して作戦成功を誇示した。

ロシアとアサド政権による反論
だが、ロシアとアサド政権の主張は違った。シリア軍武装部隊総司令部は、ミサイルのほとんどを防空兵器によって撃破し、バルザ区の研究所内にある施設1棟が破壊されただけと反論した。
ロシア軍の発表はより詳細だった。セルゲイ・ルドスコイ参謀本部機動総局長は14日の記者会見で、シリア軍がS-200などの防空システムを駆使して、ミサイル71発を破壊したと発表した。標的についても、ダマスカス国際空港、ドゥマイル航空基地、ブライ(マルジュ・ルハイル)航空基地、ジャルマーナー市の施設(以上ダマスカス郊外県)、シャイーラート航空基地、ヒムス航空基地(以上ヒムス県)、マッザ航空基地、バルザ区の施設(以上ダマスカス県)が狙われたが、被弾したのは、マッザ航空基地(4発被弾)、ヒムス航空基地(3発被弾)、バルザ区の施設(ジャルマーナー市の施設と合わせて23発被弾)だけだったと主張した。

情報の「ねじれ」はシリア内戦では常で、真偽の確認は難しい。だが、筆者が攻撃直後にダマスカス郊外県在住の知人に連絡したところ、弾道や爆音は聞こえたが、警戒警報は発令されず、シリア軍がミサイルを撃破するのが確認できたと言う。
事態悪化を回避しようとする攻撃
今回の攻撃は、化学兵器使用に象徴されるアサド政権の非道を黙認しないとの意志によって正当化された。だが、それによって政権の動きを封じることなどできるはずもなかった。理由は簡単だ。攻撃があらゆる意味でヴィジョンを欠き、事態悪化を回避しようとするものだったからだ。
この事実は、ロシアやアサド政権のプロパガンダではなく、米英仏政府の言動などから明らかだ。ジェームズ・マティス米国防長官は作戦実施直後の記者会見で、攻撃が「現時点で1回限り」と述べ、軍事バランスを変化させるような大規模且つ中長期の介入は想定していないことを確認した。ジョセフ・ダンフォード米軍統合参謀本部議長も「ロシア軍の巻き添えが出ないよう攻撃目標を精査した」と述べた。米国防総省にいたっては「二次被害を回避するため、化学兵器は破壊しなかった」と言い切った。

メディアでも、UAEの衛星テレビ局アラビーヤが15日、複数の米政府高官の話として、ロシアだけでなく、イランの拠点も標的から外されたと伝えた。『ウォール・ストリート・ジャーナル』誌も、米主導の有志連合が占領するタンフ国境通行所(ヒムス県)一帯で活動する反体制派が、空爆に乗じてアサド政権を攻撃した場合、有志連合の支援は打ち切られる旨、事前(そして事後)通告されていたと報じた。
事態悪化を避ける慎重な攻撃であれば、アサド政権に化学兵器の再使用を断念させることも、ロシアにシリア支援策を再考させることもできるはずない。にもかかわらず、攻撃が敢行されたことは“謎”としか言いようがない。
塩素ガス使用疑惑事件をめぐる“謎”
“謎”というと、攻撃の効果もさることながら、発端となった7日の塩素ガス使用疑惑事件も不可解だ。備忘のため、事件をめぐる幾つかの“謎”に言及しておきたい。
最初の“謎”は、塩素ガスが実際に使用されたのか、使用された場合、それは誰によるのかという問いにかかわる。
米英仏がアサド政権を実行犯と断じているのは言うまでもない。米政府高官は14日、被害者に瞳孔の収縮や中枢神経系の障害といった症状が見られたとしたうえで、塩素ガスだけでなく、サリンが使用された可能性もあると報道関係者に説明した。また攻撃は樽爆弾によるもので、事件発生時にヘリコプターが旋回、このことがシリア軍の関与を裏付けていると指摘した。このブリーフィングに先だって、NBCも12日、複数の米政府高官の話として、現地の病院で入手した被害者の血液や尿のサンプルから塩素ガスや種類不明の神経剤を示す陽性反応が出たと伝えていた。
だが、すでにさまざまな場で指摘されている通り、圧倒的優位に立つシリア軍が、欧米諸国の非難に曝される危険を冒してまで化学兵器を敢えて使用するメリットはどこにあったのか? また12日までに完全制圧されたドゥーマー市で、米英仏はどのようにサンプルを採取し、診断結果を得たのか? 同日までにドゥーマー市からトルコが実質占領するジャラーブルス市(アレッポ県)方面退去したイスラーム軍の戦闘員や家族のなかに被害者がいたのか?

ダナ・ホワイト国防総省報道官の14日の発言を引用すると、答えはこうだ――「いろいろな情報があるが、それについて今は話したくない」。
これに対し、ロシアとアサド政権は、事件が英国の支援を受けたホワイト・ヘルメットによる捏造で、塩素ガスを含む化学兵器はそもそも使用されていないか、シリア軍を貶めようとする反体制派が使ったと反論した。
ロシア国防省のイゴール・コナシェンコフ報道官は13日、事件現場の撮影に参加した複数の人物をつきとめたとしたうえで、彼らが「身元を隠さず実名で」(とは言っても氏名などは公表されていない)こう証言したと発表した――「現場から病院に搬送された人たちには、有毒ガスで負傷した症状はなかった…。だが、負傷者への応急処置をしていると、何者かが病院に進入した。何人かはカメラを持っており、パニック状態を作り出そうとして叫び出し、そこにいた人たちに水をかけ、現場にいた全員が有毒ガスで負傷していると主張した」。
こうした主張をプロパガンダだと一蹴して、無知と思考停止に陥ることは簡単ではある。だが「フェイク・ニュースの常習犯」であるはずのロシアやアサド政権の反体制派自作自演説に説得力を与え、謎と疑念を深めているのは、透明性を欠く米英仏の態度なのだ。
OPCWを黙殺しようとする米英仏
もう一つの“謎”は、化学兵器禁止機関(OPCW)が現地調査を行うにもかかわらず、米英仏がシリアでの化学兵器の使用実態の調査と責任追及を目的とした独立国際調査機関(UNIMI)の設置に固執していることだ。米国は9日、国連安保理にUNIMI設置を定めた決議案を提出、10日にロシアの拒否権発動で否決されると、15日には英仏とともに、UNIMI設置と、人道支援、和平協議再開をセットにした新たな決議案を提出した(なお、この決議案もロシアの反対で否決される見込み)。
UNIMIは、昨年末に任期を終了した国連OPCW合同査察機構(JIM)の後身として位置づけられる機関だ。このJIMは、ドナルド・トランプ米政権による最初のミサイル攻撃のきっかけとなった昨年4月のハーン・シャイフーン市(イドリブ県)でのサリン使用疑惑事件について、現地調査を行わないまま、欧米諸国の主張に沿ったかたちで使用の有無と実行犯を断定した。このことがロシアとアサド政権の反発を招き、JIMはロシアが任期延長を求める国連安保理決議案に2度にわたって拒否権を発動することで廃止に追い込まれていた。
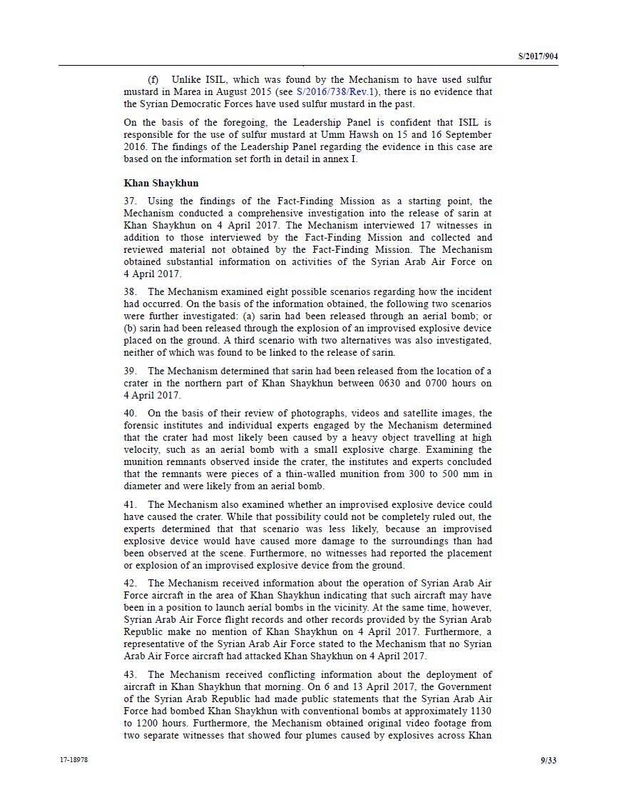
シリア政府の支配下に復帰したドゥーマー市でOPCWが調査を行えば、証拠の隠滅や捏造に巻き込まれる――そう警戒するのは当然と言えば当然だ。だが、OPCWの存在を黙殺する米英仏の姿勢は、化学兵器の廃絶や拡散防止に向けた国際的な枠組みをないがしろにした行為であり、調査で自らに不利な真実が暴かれることを嫌っていると勘ぐられても仕方がない。
事実、アサド政権と一貫して共闘態勢を敷くヒズブッラーのハサン・ナスルッラー書記長は15日のテレビ演説で、「米英仏のシリア攻撃はOPCWが真実を明かす前に実行された」と批判した。
攻撃は何をもたらすのか?
そして第3の“謎”――今回の攻撃にいかなる効果があるのか、である。その答えは、トランプ政権が攻撃そのものを目的化せざるを得ない政策を打ってきたことを踏まえることで導出される。
トランプ政権にとって、シリアに対する昨年のミサイル攻撃は、アサド政権による化学兵器使用を「レッド・ライン」としつつも軍事介入に踏み切れなかったバラク・オバマ前米政権との違いを示すこと、あるいは核・ミサイル開発を進める北朝鮮を牽制することが真の狙いだったと解釈されることが多い。その是非はともかく、こうした認識が定着しているなか、トランプ政権がもし今回の攻撃を見送っていたら、これまで強く非難してきたオバマ前政権と同じとみなされ、北朝鮮を再び増長させていたかもしれない。
有言実行の男だと誇示すること、おそらくそれが攻撃の主目的であり、その限りにおいて、シリアで具体的な戦果が得られるか否か、さらには攻撃の根拠が妥当か否かは大きな問題ではないのだ。
だが、シリアを軽んじる姿勢は、トランプ政権のシリア政策において実は首尾一貫したものだ。トランプ大統領が攻撃の2週間前の3月29日、中西部オハイオ州リッチフィールドでの演説で、「米国はシリアからすぐに出て行くだろう」と述べたことは記憶に新しい。また、イスラーム国との戦いに注力するという基本方針のもと、アル=カーイダ系組織に「ハイジャック」されて久しいシリアの反体制派への支援を打ち切っており、ロシアとともに共同議長国であるはずのジュネーブでの和平協議でも積極的役割を果たしていない。トランプ政権は、イスラーム国が事実上壊滅したはずのシリアで、西クルディスタン移行期民政局(ロジャヴァ)の「テロとの戦い」を支援するとして、基地を維持し、部隊を駐留させているに過ぎない。
米軍の早期撤退は、シリア国内に権力の真空を作り出し、イスラーム国の復権をもたらしかねないと懸念する国防総省や軍の説得によって撤回されたようだ。だが、トランプ大統領がシリアから手を引きたいと考えていることは事実だ。
今回の米英仏の攻撃に対して、多くのシリア人は、その政治的立場にかかわらず、異を唱え、反感を改めて強めている。米国の庇護を受けるロジャヴァでさえ支持を表明せず、その支配下で暮らす人々は沈黙を続けている(あるいは沈黙を余儀なくされている)。米国への同調が侵略の是認を意味するからだ。シリアで米国の攻撃に期待を寄せたのは、アル=カーイダの系譜を汲むシャーム解放委員会ぐらいだ。
シリア国外でも状況はほぼ同じだ。アラブ連盟首脳会議が15日、サウジアラビアのダーランで開幕したが、基調演説を行ったサルマーン・ビン・アブドゥルアズィーズ国王は、自らに反米感情の矛先が向くのを避けるためか、攻撃について言及しなかった。シリアに比較的近い立場のイラク、アルジェリア、エジプトは外務省や大統領府を通じて、予め異議を唱えた。
アサド政権は非道だ。だが、その事実を差し置いても、米英仏の攻撃を是認する雰囲気はシリアにはほとんどない。「独裁」と「侵略」という不義が錯綜するこうした状況は、アサド政権が米英仏の覇権主義への抵抗者を自負し、自らの非道を包み隠す余地を与えてしまう。一方、トランプ政権にとって、シリア人からいくら嫌われても、それは撤退の機運を高めるだけで、損した気分にはならないだろう。
こうした奇妙な利害の一致ゆえに、米英仏の攻撃は、SNSの炎上のように現状に何の変化ももたらさないまま、一過性のものとして終わったと言えるかも知れない。










