海王星の常識が覆った!最新の大発見3選
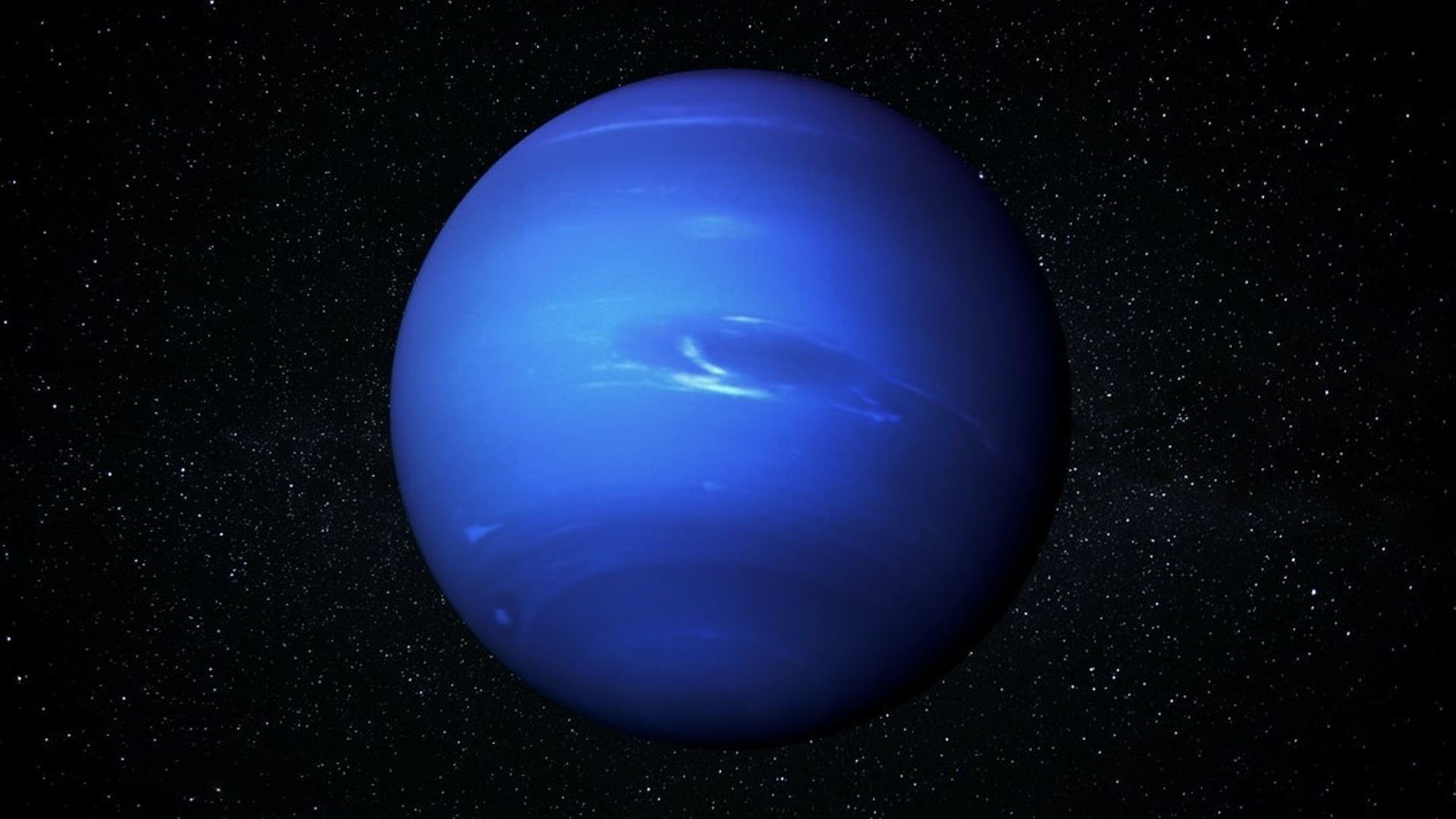
どうも!宇宙ヤバイch中の人のキャベチです。
今回は「海王星にまつわる最新の大発見3選」というテーマで動画をお送りしていきます。
太陽系の惑星の中で最も外側に位置し、地球から約45億km離れた海王星は、観測が難しく謎が多く残されている星です。
探査機「ボイジャー2号」がこれまでで海王星の接近に成功した唯一の探査機となります。
そんな海王星でも、火星や木星など他の惑星と比べると頻度は高くないものの、最新の発見が発表されています。
今回は海王星にまつわる最新の発見を3つまとめて紹介したいと思います。
●海王星表面での奇妙な現象

海王星の表面の構造で有名なのが、黒い渦のように見える「暗斑」です。
暗斑の正体は、地球ほどの大きさで風速は時速2,000kmに達する嵐で、1989年にボイジャー2号に発見されました。
実はこの暗斑は、出現と消滅を繰り返していることが知られています。
1994年にハッブル宇宙望遠鏡が撮影した画像ではボイジャー2号が捉えた大暗斑は消え、代わりに別の暗斑が北半球に現れたものの、しばらくするとまた消滅しました。
中緯度で形成された後数年かけて赤道付近まで移動して消えていく現象は海王星の暗斑に共通するそうで、このことから赤道付近の領域を「キルゾーン」と呼ぶこともあります。

2018年には北半球で新たに「NDS-2018」と命名された、直径11000kmの暗斑が発見されましたが、その動きも科学者たちは、赤道付近で消えるという予測の元観察していました。
NDS-2018は2020年1月に再観測された際には赤道付近に位置していて、実際に直径7400にまで収縮していたため、その後予想通り消滅していくと考えられていました。
ですが2020年の8月にさらに再観測を行った結果、なんとNDS-2018は再び北半球に戻っていたそうです!
これは暗斑観測史上初めて見られた現象です。

さらに不思議なことに、進路を反転させたと推測されている2020年1月には、NDS-2018の近くに「ダークスポットJr.」と名付けられた、直径6,275kmほどの比較的小さな暗斑が出現していました。
そんなダークスポットJr.は2020年8月時点ではすでにその姿をとらえることができなかったので、わずか数カ月で消滅したと考えられています。
ダークスポットJr.がどのように誕生したか決定的な証拠はありませんが、NDS-2018の一部が分裂した結果ダークスポットJr.が誕生し、その分裂の影響でNDS-2018の赤道に向かう運動が食い止められたと推測されています。
シミュレーションによって、ダークスポット・ジュニアは、NDS-2018の移動を止めるのに十分な力を持っていた可能性があることはすでにわかっているようです。
今後NDS-2018からどのようにダークスポットJrが切り離されたのか、そもそもこの二つの暗斑に関連性はあるのか、という研究が進められていくと考えられます。
●海王星の大気大循環
2020年10月、東京大学などの研究チームは、これまで知られていなかった海王星大気の大規模な循環を新たに発見したと発表しました。
海王星大気の大循環が判明する手掛かりとなったのは、海王星大気に存在する「シアン化水素」というガスです。
これまでも海王星大気のシアン化水素が存在することは知られていましたが、その生成メカニズムは不明でした。
というのも、海王星大気においてシアン化水素が存在する成層圏と、より高度が低い層である対流圏に挟まれた「対流圏界面」の温度は-200度と非常に低いためです。
これほど低温の対流圏界面ではシアン化水素を含むあらゆるガスが気体から液体に変化してしまうため、シアン化水素が海王星内部から上昇してくる可能性は低く、その生成メカニズムが謎として残されていました。

そんな中、地上にある大型望遠鏡「アルマ望遠鏡」の観測により、今回新たに大気中のシアン化水素の「分布」を明らかにすることに成功しました。
表示中の画像にも表現されていますが、海王星大気のシアン化水素の濃度は赤道付近で最も高く、南緯60度付近の領域で最も低いことが明らかになっています。

シアン化水素の分布とその生成メカニズムの謎に対する新たな説明として、研究チームは海王星の南緯60度付近で上昇し、赤道や南極で下降する、「大気の大循環」が起きている可能性が高いという理論を提唱しました。
南緯60度付近で成層圏上部に上昇してきた窒素分子は、赤道や南極の方向へ水平移動する過程で起こる化学反応により、シアン化水素に変化すると言います。
このように成層圏上部でシアン化水素が生成されるのであれば、その下部の対流圏界面が非常に低温であっても問題ないですし、シアン化水素が南緯60度付近で低濃度で、赤道や南極でより高濃度であることも説明ができます。
今回の研究成果から、地上からの観測と分析だけで、海王星で起きている現象を新たに解明できる可能性が示されたんですね!
●海王星内部にある「灼熱の氷」と磁場
海王星の内部では、水分子が高い温度と圧力によって押しつぶされて「超イオン氷」という物質を生成していることが明らかになりました。
超イオン氷は特異な性質によって、海王星の磁場にも影響を与えています。
超イオン氷は一体どのような物質なのでしょうか?
海王星や天王星に存在する超イオン氷は、光との相互作用が原因で透明ではなく黒い見た目をしている特殊な氷です。
私たちが普段生活している環境では、H2Oは液体の水と固体の氷、気体の蒸気の3つの状態になることができます。
超イオン氷は、この3つのどれにも属さない特殊な環境でのみ存在するH2Oの状態です。
超イオン氷が生成する環境は、圧力100万気圧~400万気圧、温度は3,000度近くという、極限の環境です。
氷とは言っても、とんでもなく熱い氷であることが分かります。

シカゴ大学の研究チームは、H2Oに極度の熱と圧力を加え、海王星の内部の状況を再現するための実験を行いました。
すると、酸素イオン(O2-)が格子状にきれいに並んで固定され、水素イオン(H+)は酸素イオンの隙間を自由に飛び回るようになります。
この状態が超イオン氷と呼ばれるH2Oの新たに発見された状態です。

超イオン氷には、電気を通す性質があります。
電気を通す性質がある超イオン氷が海王星内部に存在することで、海王星の磁場に影響を与えます。
地球の磁場は自転軸からそれほど傾いていないのに対し、海王星や天王星の磁場は大きく傾いています。
この2つの惑星の磁場が自転軸からずれている原因として惑星内部の超イオン氷が影響していると考えられています。

地球の磁場は、地球内部の鉄やニッケルを多く含んだ液体状の核が自転や熱対流によって回転することで電流が生じているとされています。
これはあくまで地球の磁場を説明する1つの説に過ぎませんが、地球の自転が核付近の電導性流体の運動方向に影響を与えていると考えられるため、磁場の向きと自転軸がある程度一致していることを説明できるのです。
このようなメカニズムはダイナモ効果と呼ばれ、天体内部の大規模な流動によって大規模な磁場が生成されることを説明しています。
このメカニズムは超イオン氷が磁場を発生させる理由も説明できます。

超イオン氷は「氷」と名付けられているものの、温度と圧力によっては液体のようにふるまうことも可能です。
海王星や天王星の場合、電気を通す性質がある超イオン氷が惑星内部で対流することで磁場を形成している可能性があります。
海王星や天王星の内部にはイオン性を帯びた液体部分があるとされています。
この液体部分に超イオン氷が存在し、対流することで惑星の自転軸とは異なる方向に磁場を作り出している可能性があるのです。
超イオン氷の発見は、海王星や天王星にある極端に傾いた磁場の謎を解明する手掛かりを与えてくれました。
海王星は探査が難しい謎多き天体ですが、意外にも新たな発見がもたらされ続けています。
今後も海王星の研究が続き、いずれは木星探査機ジュノーのように、海王星の探査に特化した探査機が現地に送られることに期待したいですね。
https://hubblesite.org/contents/news-releases/2020/news-2020-59
https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z0310_00023.html
https://phys.org/news/2021-10-scientists-strange-black-superionic-ice.html
https://phys.org/news/2021-10-evidence-superionic-ice-insights-unusual.html
https://phys.org/news/2021-03-strange-planets-neptune-uranus-mysterious.html










