半世紀以上も続くレジェンド番組『笑点』が今でも根強い人気を保っている理由とは?
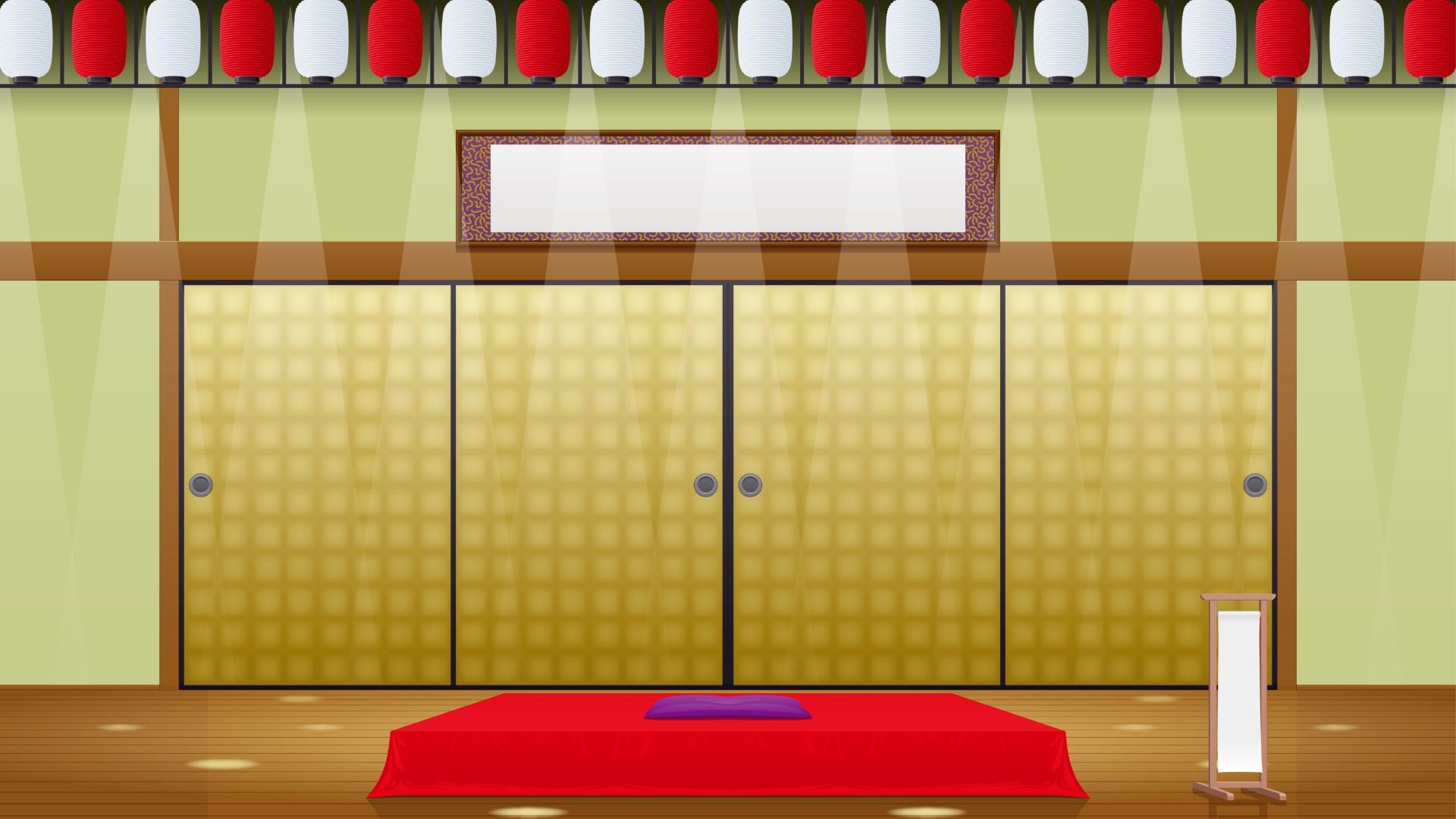
テレビの世界では視聴率が取れない番組はすぐに打ち切られてしまう。特に、スポンサーからの広告収入に頼っている民放ではそれが顕著である。どんなに面白い番組であっても、数字が悪ければ長続きはしない。テレビ番組が長く続いているというのは、ただそれだけで価値のあることなのだ。
全国ネットの民放番組の中で、最も長い歴史があるのは1962年に始まった『キューピー3分クッキング』(日本テレビ)である。実は、これに続く歴代2位に入っているのが『笑点』(日本テレビ)だ。1966年に始まった『笑点』は、現在56年目に突入している恐るべき長寿番組だ。ほとんどの日本人が物心ついた頃からずっと放送されているのだから、その歴史には並々ならぬ重みがある。
しかも、特筆すべきは、『笑点』は現役の人気バラエティ番組だということだ。ここ数年は世帯視聴率でも個人視聴率でもバラエティ番組のトップ集団に位置している。ニュース番組などと違って、流行り廃りの移り変わりの激しいバラエティの世界で、50年以上も同じスタイルの番組が人気を維持しているのだから、驚くほかはない。なぜ『笑点』はこれほど長年にわたって多くの人に愛されてきたのだろうか。
「大いなるマンネリ」を確立した
その理由を一言で言うなら、「大いなるマンネリ」を確立したからだ。「マンネリ」という言葉は悪い意味で使われることが多いが、この場合は悪く言っているわけではない。番組を長く保つための「型」を作ったことが成功の秘訣だったということだ。
『笑点』という番組を長年見ていると「今に逆らわず、今に流されない」という哲学のようなものを感じることがある。いわば、常に新しいものを取り入れながらも、大事なところは昔からずっと変えていない、というふうに見えるのだ。
たとえば、『笑点』は意外とそのときの流行をいち早く取り入れたりしている。特番では旬の俳優やアイドルが出演して、レギュラーメンバーの落語家と一緒に大喜利に参加したりする。演芸コーナーに出てくる芸人も、少し前まではベテランの寄席芸人が多かったが、最近ではほかのバラエティ番組にも出ているような漫才やコントをやる若手芸人も増えてきた。また、普段やっている大喜利のお題にも、最先端の風俗流行が取り入れられることが多く、その時代ごとの空気をしっかり意識していることがうかがえる。
一方、番組の全体的なフォーマットに関しては保守的なところもある。寄席形式の舞台で、カラフルな着物を着た落語家が座布団の枚数を競い合う大喜利は、番組開始当初からある人気コーナーだ。前半に奇術、曲芸、漫才などを演じる芸人が出てくる演芸コーナーがあり、後半に大喜利コーナーがある、という形も長年変わっていない。
番組の演出に関しても、頑なに同じ形を保っている。出演者が話したことをなぞるようなテロップは一切使われず、説明テロップすらほとんど入らない。観客を入れて公開収録をしているものの、笑っている観客の顔が途中に挟まれることもない。これは、作り手に「寄席に行っている気分で番組を楽しんでほしい」という意図があるからだ。寄席の空間自体を再現するためには、いかにもテレビ番組っぽいテロップやカットは不要なのだ。
キャラが立っている大喜利の魅力
『笑点』の「大いなるマンネリ」の核となっているのは、やはり大喜利コーナーである。時代ごとにメンバーは少しずつ変わっているが、基本的なフォーマットは全く変わっていない。面白い解答をした人に座布団を与えるというシステムは、前身番組である『金曜夜席』で始まり、この番組でも取り入れられた。座っている座布団の高さでそれぞれの成績が一目瞭然になるというのは、いかにもテレビ向きの画期的な演出である。
大喜利コーナーでは、毒のあるネタやきつい下ネタはほとんど出てこない。どの世代の人が見ても安心して楽しめる笑いというのが理想とされている。そして、『笑点』の大喜利のもう1つの特徴は、メンバーの「キャラ」が立っているということだ。レギュラーメンバーはそれぞれが個性的なキャラを備えていて、それを生かした解答をしていく。解答者同士が相手をネタにしてみせるのも、それぞれのキャラがあるからこそ面白い。
ただ、これらのキャラは初めから存在していたものではない。もともと落語というのは1人で高座に上がる芸能であり、バラエティ番組に出ている「ひな壇芸人」のように、目立つためのキャラを立てる必要はなかったからだ。
彼らのキャラはあくまでも、大喜利のやり取りの中で自然発生的に生まれているものだ。ある解答者が別の誰かのことをイジってみせると、相手も負けじと言い返してきたりする。この言い合いがエスカレートしていくうちに、それぞれのキャラが作られ、次第に定着していく。それぞれのキャラが固まっているので、毎回お題が変わっても解答の方向性はあまり変わらない。だから、いつ見ても同じように楽しむことができる。
『笑点』は年配層向けの番組だと思われることが多いが、実は子供に愛されている番組でもある。番組で提供されている笑いの健全さとわかりやすさがその人気の秘密だろう。ここ数年は長年愛されてきたレギュラーメンバーが次々に入れ替わる過渡期にあるが、『笑点』がいまだに多くの視聴者に愛されているのは、半世紀以上も貫いている「大いなるマンネリ」の美学があるからなのだ。










