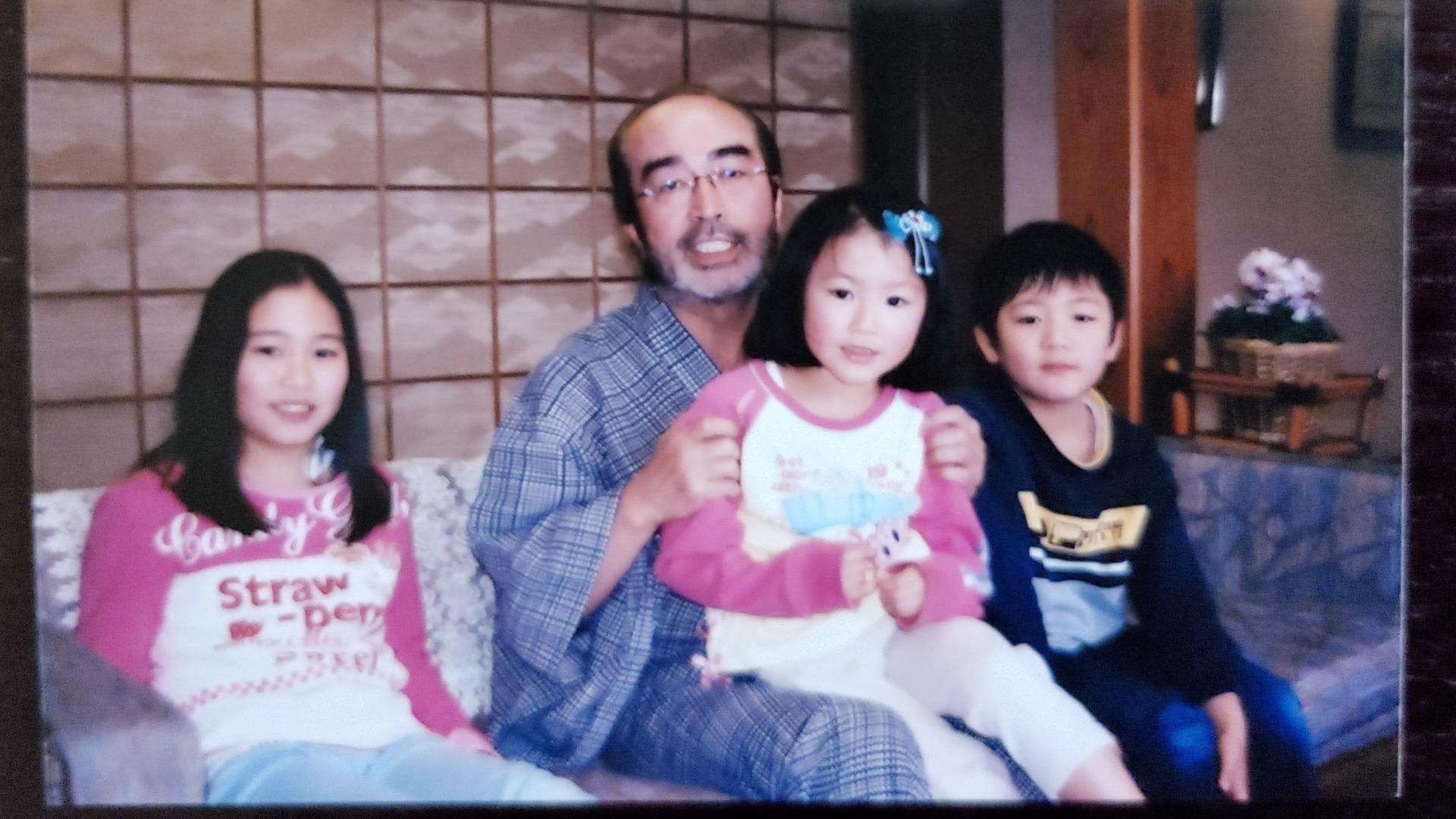「R−1ぐらんぷり」は売れっ子を生み出さない ピン芸人としての野田クリスタルの限界

「R−1ぐらんぷり」で優勝しても売れっ子タレントにはなれない
ひとり芸のコンテスト「R−1ぐらんぷり」の2020年の優勝者はマヂカルラブリー野田クリスタルだった。
放送されたのが3月8日日曜。それから一週間経つが、あまり野田クリスタルをテレビで見かけない。私が確認できたのは、翌日のいくつかのワイドショーと、一週間後15日の松本人志たちの「ワイドナショー」くらいだった(ほかにも出てるはずだが、目立ってはいない)。
「M−1グランプリ」と違い「R−1ぐらんぷり」に優勝したからといって、売れっ子タレントになれるとは限らない。というか、滅多に売れっ子タレントは生まれない。
野田クリスタルも、以前よりは露出は増えるだろうが、この優勝だけで売れっ子芸人になるのはむずかしいだろう。
「R−1ぐらんぷり」優勝者をさかのぼって並べてみると、去年は霜降り明星の粗品で、それから順に濱田祐太郎、アキラ100%、ハリウッドザコシショウ、じゅんいちダビッドソン、やまもとまさみ、三浦マイルド、COWCOW多田、佐久間一行、あべこうじとなる。これで10年。
いまでもドラマやコマーシャルで見かける人もいるが、そもそも誰だっけと顔がおもいだせない芸人もいる。この10人の芸風と顔をしっかり記憶してる人は、かなりのお笑いマニアだといっていいだろう。
「R−1ぐらんぷり」で優勝しても売れないというところに、ピン芸人のむずかしさがある。
決勝出場者のコメントは司会の蛍原徹が笑いにつなげることを放棄させていた
2020年の決勝に残ったのは3人だった。マヂカルラブリー野田クリスタルと大谷健太、すゑひろがりず南條である。
3人の決勝パフォーマンスが終わり、採点を待つあいだに司会の蛍原徹(雨上がり決死隊)がそれぞれにいまの心境を聞いた。
このときの反応がいろんなことを象徴している。
まず大谷健太が「放し飼いに近い猫が、2週間ぐらいいなくなってるくらいです」と言った。蛍原は「おれでは無理だー」とそのコメントを拾えないと宣言した。笑いにつなげられないと司会者に放棄させてしまったのだ。(粗品が「誰でも無理ですよ」と言って蛍原―粗品ラインで何とか笑いを作ろうとはしていた)
続いてすゑひろがりず南條が「心の臓が、ばくり、ばくりよ」と言って鼓をぽぽん、と叩いた。申し訳ないが、おもしろくも何ともない。(発表前の心境を聞かれて、心臓がどきどきしてますでは、言い方がおもしろかろうと何だろうと、内容があたりまえすぎる)。ただこれは司会の粗品が間合いよく「やかましいわ」とちゃんと拾ったので何とか笑いのもとにはなっていた。
最後に野田クリスタルが変顔をして「勝ちてーえ」と叫んで、これはもう誰も反応しなかった。からんだら、一緒につまらない人に見えてしまうので、もう誰もさわらなかった、というふうに見える。
審査員の陣内智則が「いまCM中ですよね」と声をかけてきて蛍原が「違います、生放送中です」と答えた事態であった(あまりの惨状におもわず審査員席から救い手を差し伸べた、ということだったのだろう)。
3人ともおもしろいことを言おうとした。でも笑いにつながらなかった。
それだけのことであり、それがすべてである。
「R−1ぐらんぷり」のファイナリストだからということで、テレビで使われることはないだろう。そうおもわせるシーンだった。
このあたりが、ピン芸人のむずかしいところだ。
コンビだと相方がクセを知りつくしているので、突拍子もないことを言っても、何とか笑いに持っていくことができるが、ピン芸人の場合、司会者やそのとき一緒にいる芸人との呼吸が合わないと、「ただ駄洒落を言ってまわりを引かせてしまうおじさん」と同じ立場にされてしまう。そして今年の決勝に残った3人は3人ともそのタイプに見えてしまった。
テレビでは、ただおもしろいことを言うだけでは、お笑いにはつながらない。他人の助けが必要である。
初対面だろうと、呼吸の調整が必要だ。
それはたとえば、質問されて、すぐに大きくボケずに、質問をリピートするなり何なりでいったん受けて、これから変なこと言いたいんだけど、というタメと空気を醸し出してから言う、というようなことである(たとえばの方法である)。溜めれば、たぶん、何とかしてくれる可能性が高まる。最悪の事態は避けられる。
それもやっていなかった。
余裕がなかったのだろうが、あまりテレビ向きの芸人ではないのはたしかである。
「R−1ぐらんぷり」の「R」の意味
もともとR−1のRは落語を意味している。
本来は、落語形式の漫談をイメージして始められたらしい。
たしかに落語は一人芸である。
ただ落語は、基本、2人以上が会話しているように展開する。演者が客に向かって直接話しかけているわけではない。ある種の演劇に近いところがあり、それがライブで聞いていても緊張を緩める役割をになっている。
1人で喋るピン芸人はそれとは違う。
ずっと客へ直接、話しかけている。
いわゆる漫談家と呼ばれる人たちである。
寄席には落語家と漫談家が交互に出てきたりするが、両者の醸し出す雰囲気はずいぶんと違っている。
漫談家は常に客に直接話しかけているからだろうか、いかにも「芸人さん」という気配に満ちている。現場でたたき上げたという雰囲気を全身から醸し出していて、タレントさんとはほど遠い気配がする。おそらく直接、客に向かって話しかけ、その反応をもろに浴び続けるからだろう。落語家さんたちとも違う匂いがする。
私個人の印象としては、ピン芸人は面白い人が多いが、基本、暗い。
明るい気配で登場して、それだけで明るくする、ということをしない(そういうタイプでおもいつくのは曲独楽の三増紋之助くらいである)。
だいたい暗い感じで始めて、でもステージはしっかり受ける。そういう印象を持つ。
何十年も同じ芸を続ける寄席の「ピン芸人」の凄み
寄席に出てくる一人芸の芸人さんといえば、たとえばこういう人たち。
ぺぺ桜井。アサダ二世。林家ぺー。立花家橘之助。のだゆき。新山真理。国分健二。ぴろき。マグナム小林。ねづっち。
それほどテレビで見かける芸人ではない。
ときどき『笑点』の演芸コーナーで見ることもあるが、あまりテレビ向きの芸をやっていない。寄席という空間でこそ光る人たちである。爛(ただ)れたようなおもしろさが魅力である。
この人たちの芸は、言ってみれば「丸い」のだ。
丸めてある。尖っていない。
「R−1ぐらんぷり」に出てくる芸人たちの芸が尖っているのと対称的である。丸めてある。
もちろん客に突き刺さる部分がないと笑いは起こらないから、尖ってるところは尖っているのだが、それを目立たないようにしている。
毎日毎日、同じ芸で二十年、三十年と客前でやっていると尖った部分さえも丸みを帯びてくるのだろう。
すべて予定されていたとおりに芸が展開し、予定されていたように客が笑い、予定されていたとおりに淡淡と終える。ものすごい芸だ。
最初みたときは楽しく、何度か見てるといつも同じだなとおもい、10年15年と見続けていると何十年も同じギャグを同じトーンで話して必ず受けているところには凄みを感じるようになってしまう。ときに不気味な怪物のように見えてくる。そういう存在である。
私が抱くピン芸人というのは、そういう芸を見せる人たちだ。
笑いを取りにいかないこともある「R−1」での芸
「R−1ぐらんぷり」を見ていると、「おもしろい芸を見せる」ということと「しっかり笑いを取る」ということが別々に行われているようにおもえる。
「M−1グランプリ」ではあまり起こらない現象である。M−1では笑いの数を競っている。漫才芸の評価は、その芸人そのものがおもしろいという評価と直結している。
ところが、R−1では、芸人ではなく、ときに「芸」そのものが評価されることがある。
M−1が身体に響いた順にランキングしていくのと違い、R−1では頭で判断しているようなところがある。
無観客公演だったのに「かえってやりやすかった」という言葉がいろんなことを象徴しているとおもう。松本人志も、毎年、無観客でもいいのではないか、とも言っていた。
「R−1ぐらんぷり」の芸はときに身体性より、頭でひねって考えた芸が評価される傾向がある。今年はそうだったとおもう。「ななまがり森下の乳首芸」が逆に評価基準を決めてしまったようなところがあった。
かつては身体性の高いアキラ100%やハリウッドザコシショウが優勝したこともある。その基準は毎年揺れ動いてるようにおもう。身体性の高い芸で優勝した人は、その後、テレビでの露出が増える。ややM−1寄りの芸だからだ。
「R−1ぐらんぷり」はテレビ用の芸人を選ばない。
テレビでは、一人だけで喋り続けて受ける、ということがあまり必要とされないからだ。どちらかというと寄席小屋に合うような芸人が優勝する。
その対比がおもしろい。
みんなも気づき初めているが、M−1の優勝者とR−1の優勝者は横並びで評価するものではない。別の世界でのトップである。
ただ、今年の優勝者・マヂカルラブリー野田クリスタルの「つまらないゲームを作る能力」というのは過去にないおもしろさだとおもった。この部分での活躍があるかもしれない。少し期待したい。