「お世話になった人」になる 新たな支援のカタチを創造する若者たちの挑戦 NPO法人PIECES
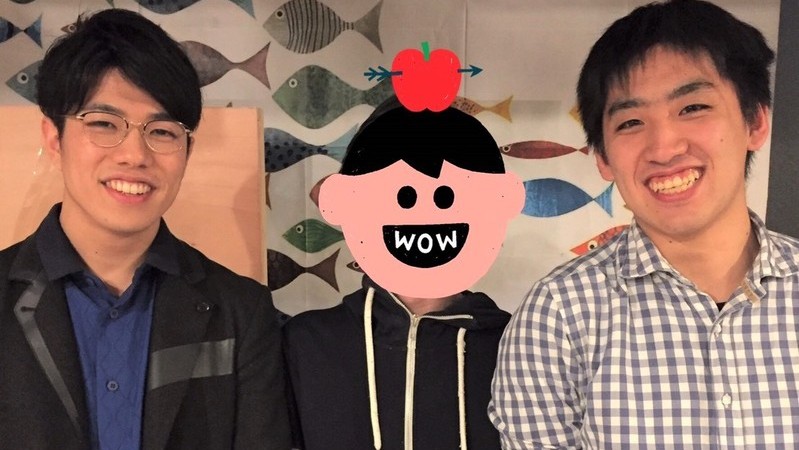
「ちょっとした弟のような感じ」
大学3年生の北山雄大は、高校3年生のヒロト(仮名)のことを弟のように感じている。
「ちょっとした弟のような感じ。ヒロトはどう思ってるかわかんないですけど(笑)」。
ヒロトもまんざらではないようだ。就職か進学かで迷いに迷っていた昨年秋を支えてくれたのは雄大だった。
「(振り返ると)助かった〜って思います。自分一人の力じゃここまでいけなかったなって。自分一人だったら、就職か大学かずっと悩んでたと思います。雄大さんの助けがあったからこそ、ちゃんとした道を見つけられて、将来も明るい未来が見えるようになったなって」。
「昔は、一人で悩んじゃうことがよくあって、相談しないで全部自分一人で解決しようとしてたんですけど、今は相談できる人もいるし、悩んだらすぐ相談できるので、なんかこう、そこが変わりました」
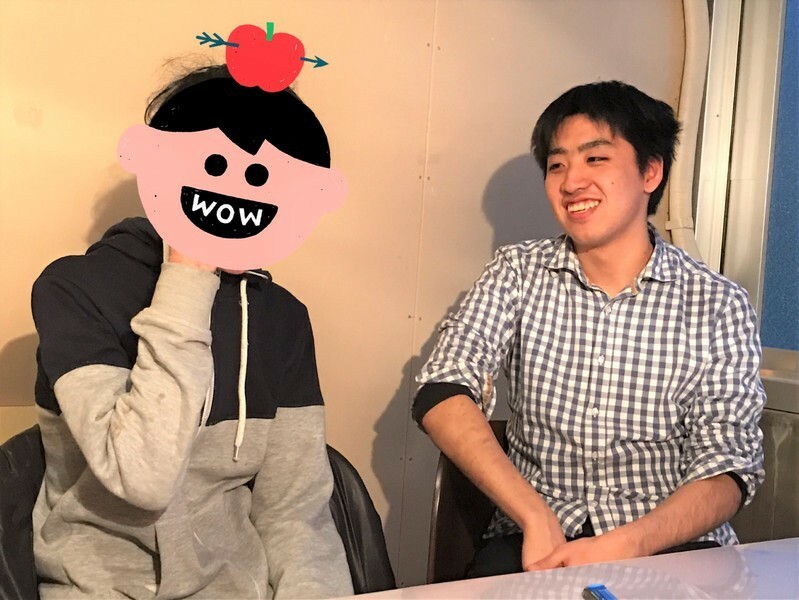
「壁打ちの壁」になる
ヒロトの父親は優しいが「自分がやりたいようにやればいい」と言うばかりで、具体的な相談にはあまりのってくれなかった。学校の先生は知識も経験もあるのだが、ポンと結論を出してくるところがあって、その結論は正しいのだろうが、納得感がなく、物足りない。友だちとは、ゲームの話ばかりだ。雄大は、その誰とも違った。
雄大がやったのは、ヒロトの「壁打ちの壁」になること。ヒロトが就職か進学かで一番悩んでいた1ヶ月の間「ヒロトが安心できる、ヒロトが本当に進みたいと思えるような道を選べたら」と思いながら、多いときは週3で会って、企業や進学先の情報を提供し、言葉を交わし、ヒロトの気持ちが熟していくのを支えた。
「ヒロトが自分一人でやろうと思えばできただろうけど、未知の世界であるし、誰か力を貸してくれる人をヒロトは求めているような気がして、一緒に力を合わせれば、ヒロト自身もわからないヒロトの本音を見つけられるんじゃないか、と…」と雄大。
結局ヒロトは、企業3社を受けた後、進路を進学に切り替えて職業訓練校に合格。現在は、学費を貯めるためにコンビニのアルバイトに精を出している。

支援者ベースの友だち、友だちのような支援者
雄大がヒロトに出会ったのは、NPO法人PIECESの研修の一環でだった。
PIECESは「コミュニティ・ユースワーカー(CYW)」の育成を行うNPO法人で、雄大はその研修1期生だった。
ユースワーカーとは、若者(Youth)向けのソーシャルワーカーのこと。欧米では一般的だが、日本ではほとんど知られていない。
PIECESは、その育成プログラムの開発と普及を通じて、日本の若者支援に新しい領域を切り開くことを目指す。
その領域を、中心メンバーの一人・荒井佑介は「家族でもなく、支援者でもなく、友だちでもない関係性をもてる人づくり」だと表現する。
家族にはなれない。しかし、支援者のように役割や職業で相談に乗るのとも違う。困ったときに相談できる友人に近いが、相談されてから考えるというのではない。本人のことを日常的に考えて、支援者目線も大切にする。
「支援者がベースにある友だち、友だちのような支援者」「家族、兄、姉、いとこの姉とか、親戚の類になるようなあたり」と荒井は言う。

「この子、お母さん的な人の関わりが足りないな」ってなったときに
良質な支援者とはそういうものだと言うこともできるが、荒井はその領域を画定し、コミュニティ・ユースワーカーとして「新設」したい。
「コミュニティ」という欧米にはない言葉を頭につけたのは、地域住民がそれぞれにコミュニティ・ユースワーカーの役割を果たし、共同で子ども・若者を育成していく地域のありようを思い描いているためだ。
そのイメージを荒井はこう語る。「家族という箱が担ってきた機能を分解して、お母さんの機能、お父さんの機能を、家族だけでなく第三者でも補っていこうという発想。機能を補うことができれば、形にこだわらなくて済む。地域の人を開拓し、どこにどんな人がいるのか、それを子どもたちにつなげることを繰り返しながら、地域の人をネットワークでつないで『この子、お母さん的な人の関わりが足りないな』ってなったときに、あの人こういう関わりできるよとか、この場に行けば出会えるよっていうネットワークを構築していきたい」。
雄大は、そうしたビジョンを掲げて発足したPIECESが最初に迎え入れた研修生の一人だった。

「もっと新しいところ、もっと自分を変化させられる場所」を求めて
雄大は、なぜPIECESの研修生に応募したのか。
雄大は広島県出身。親類の交流が盛んで、年の離れた甥っ子姪っ子の面倒をよく見ていた。
子どもと関わることが好きで、何かしたいと思っていたが、東京の大学に出てきた最初の1年は何もせずに過ごしてしまい、そのことを後悔していた。そこで大学2年のとき、あるNPOの中高生支援のボランティアに関わった。
悪くはなかったが、物足りなかった。子どもたちが来て、おしゃべりをし、イベントの企画などをする。楽しかったが、その場かぎりの付き合いとも感じていた。子どもが来なければ何もすることはないし、子どもの様子で気にかかることがあっても「追う」ことはできない。自分が必要と感じたことを追求する「自由」はなかった。
一年が経過し、その場で何ができて、何ができないかが見えてしまったとき、雄大は「もっと新しいところ、もっと自分を変化させられる場所」を求めるようになった。そこで見つけたのがPIECESの研修生募集のサイトで、研修の一環のフィールドワーク先で出会ったのがヒロトだった。

「家計が苦しい中、自分だけ勉強していていいのか」
ヒロトとの関わりの中で、雄大は「新しい世界を見た」気がしている。
ヒロトは父子家庭で、母親はヒロトが小さいころに離婚して出て行った。父親は居酒屋、警察官、警備員、建設と仕事を転々とし、今は食品工場で落ち着いている。勉強は苦手で、小学校5~6年くらいから、ついていけなくなった。
ゲームが好きで、プログラミングの仕事に就きたいと思っていたヒロトは、地域の遊び場で出会ったおばさんの紹介で無料塾に通い、工業高校に入学する。しかし、高校3年から不登校気味になった。
就職か進学かというヒロトの悩みには、さまざまな要素が絡まりあっていた。プログラマーとして就職するためにより高い技能を身につけたいという希望と欲求、「家計が苦しい中で自分だけ勉強していていいのか」という罪悪感、進学する場合にも大学なのか専門学校なのか、両者の場合の資金繰り、奨学金利用の是非…。
反面教師としての兄の存在が、話をさらに複雑にしてもいた。
ヒロトから見ると、兄は勝手だ。家族のことを考えずに金を遣い、身勝手にふるまう兄だった。一度家を出て寿司屋で働いたが、それも上司が厳しすぎるとか言って辞めてしまった。「家に戻ってきて、親から金奪ったりして、自分のことしか考えないで、家族のこと考えないで、自分がよければいいと思って、そのせいでお金がなくなっていって、家計が破綻していった」とヒロト。
兄のおかげで苦労させられてきたことを考えると、自分も夢を見ていいような気もするし、逆に自分の夢のせいで父親に苦労をかけたのでは、兄と同じではないかという気持ちもあったようだ。

「ヒロトの存在がかっこいい」
雄大にとっては、これらすべてが新しかった。
雄大の父親は地元の名士で、雄大に経済的に苦労した経験はない。父親や母親の意見が強く、進路ややりたいことなど親の勧めに従うことが多かった。そのため雄大には、自分の人生を苦労しながらも自分で選び取ってきた実感が乏しい。だからだろう、雄大は3つ年下のヒロトに「かっこいい」という表現を使う。
「僕は学生で、知らないこともいっぱいあって…。一生懸命考えて、もがいて、ただがむしゃらに走っているヒロトの存在がかっこいいなって。彼の存在は大きいなって思います」。
雄大は、自分の人生と向き合うヒロトとの関わりを通じて、雄大自身の人生と向き合っているのだろう。

ロールペーパーの細い芯にどんどん紙が巻き取られていくように
自立とは、自己決定するプロセスとその結果を引き受ける中で得た体験や感情が自分の中に蓄積された結果として、自分の中の「芯」が太くなった状態を指す。
決定に至る過程で感じた喜怒哀楽や、想定外の結果までをも引き受けざるを得なかった苦い経験、逆に思わぬ喜びに満ちた経験、そうしたものが、ロールペーパーの細い芯にどんどん紙が巻き取られていくように十分に太くなったとき、簡単に折れることなく、自己を引き受けられる自己が形成される。それが自立だ。
逆に、安心して自己決定できず、家族や周囲の顔色をうかがい、事情に配慮しながら、それを自己決定の基準とせざるを得なかった者には、いかにそれが外形上「自分の選択」に見え、またそう思い、あるいはそう思い込まされていたとしても、ロールペーパーに紙は巻き取られず、芯は太くならない。
それは学歴とは関係ないし、経済的に稼げているかどうかとも本質的な関係はない。雄大は、ヒロトが安心して自己決定の悩みを生きられるように「壁打ちの壁」になった。そして、それを通じて、自己決定することがどういうことなのかを学んだ。雄大が「新しい世界を見た」と言うのは、あながち大げさではない。

「ヒロト以上にヒロトのことを考えないといけない」
荒井は、その2人のプロセスを見守り、そして促してきた。
「ヒロト以上にヒロトのことを考えないといけないよ」
雄大は、荒井にそう言われたことが忘れられない。
父親が強かった雄大には、ともすると自分で答えを出せない弱さがあった。それが、ヒロトとの関わりにも出てしまう。ヒロトの言葉を額面通りに受け取って、それに直接答えることで、自分の価値判断を回避する。
荒井が雄大に求めたのは「これがあなたのためなんだよ」と、ヒロトに答えを提示せよということではない。そんなパターナリズムではなく、ヒロトが望みつつヒロトに思いつかない選択肢を雄大なりに考え(疑問と仮説)、ヒロトに提示し(言語化)、その反応を見て(対話)、また考えを進める(より深まった疑問と仮説)という、雄大自身の「自分で考えるサイクル」を駆動させろというアドバイスだった。

「関わる大人がいかにナチュラルでいるかが大事」
荒井は言う。「雄大は、自分の意見を表に出すことが怖い、と一期生たちのふりかえりの場で話したことがあります。そこを自覚して、そこと戦ったのが彼の半年かなと思います。子どもたちと関わることを通して、ヒロトと関わる中で、自分を見つめて、自分の人生を振り返って、自分を苦しめていた価値観を外そうともがいていた。雄大は、自分との戦いがすごくあったと思いますよ」
他者と関わり、支援するというのは、自分を問うことだ。
荒井が研修を通じて伝えようとしているのは、テクニカルな支援スキルではない。個々の支援スキルが植え付けられる土壌になるような支援者の態度、心構えだ。荒井はそれを「自然体」と表現する。
「これからもヒロトと関わる中で、雄大は自分を苦しめている価値観と戦っていきながら、どんどん自然体になるんじゃないかなと。関わる大人がいかにナチュラルでいるかが大事だと思うんですが、彼はそこに向かっているんだろうなって感じます」
雄大がヒロトと関わる中で「自分で考えるサイクル」を回し続けていければ、ヒロトの芯が太くなると同時に、雄大自身の芯も太くなっていく。
十分に太くなったとき、そこに表れる態度は、自分なりの考えを口にでき、わからないことは素直にどうしてと聞ける、「自然体」の雄大だろう。
その鷹揚で、どこか背中のあたりがゆったりとしたナチュラルな態度は、自分の中に太い芯を感じていなければ生まれない。「人と関わる中で学ぶ、成長する」というのは、そのようなことだ。荒井は、半年間の研修で、そのことをおぼろげながらでもつかみとってもらいたいと願う。

それにしても、「ちょっとした弟のような感覚」(雄大)で子どもたちと付き合うような濃密な関係性は、対応できるケースが限られすぎていて、普遍的な支援モデルの構築にはつながらないのではないか。また「ヒロトのやりたいことってなんだろうっていうのを、3ヶ月間ひたすら考えた」(雄大)というような関わり方は、「甘やかしすぎ」なのではないか。荒井に聞いた。
「人生で一番お世話になった人」
(荒井)「甘やかしすぎ」というのは、よく言われますね。ただ、私自身が「そこまでやるか」っていう関わり方をしてきましたが、深く関わっただけの変化が本人にも起こります。なかなか本音を言わなかった子どもが、虐待のあったときの話を泣きながらしてくれて、それがその子にとっての転機になるとか。
そして、たくさんの無駄話もしながら、たくさんの時間を共有して、深いところにも触れる体験を共有すると、親友を超えた存在になれることがあります。それは支援の最終形かなと思います。
そうなると、あんまり会わなくても「あのときあの人にすっごいお世話になったんだから私がんばる」っていう気持ちに本人がなってくれる。恥ずかしながら「人生で一番お世話になった人です」って紹介されることがあって、そういう人が人生で一人でもいれば、人って幸せなんじゃないか、どんなに大変なことがあっても力強く生きていける種になるんじゃないのかなと思うんです。
今がんばれている人たちって、みんな誰かしらそういう人がいるんじゃないでしょうか。
でも世の中には、そういう人が身近なところにいない子どもたちがいる。その子たちにとってのそういう存在になりたいと思うんですよね。
もちろん本人の力を奪うような支援になっちゃったら元も子もないんで、そうならないようには一番気をつけていますし、みんなに押し付けるつもりもないんで、そこまで踏み込みたい人が踏み込めばいい。
ただ、私自身、小さいころ親から「どうせできない」と言われてきて、それに対する反発もあるんですよね。社会に対しても、ここまでしかできないって、本当にそうか、それでいいのか、もっと深い関わりが求められてるし、必要なんじゃないかって。

普遍的な支援モデルの構築は不可能ではない
(荒井)普遍的な支援モデルの構築に関しては、今、社会的起業家などを育成・輩出するNPO法人ETICなどの取組が注目され、広まってきていますが、あれのコミュニティ・ユースワーカー版を作れればといったイメージですかね。
地域のふつうの人だけど、子どもたちと、家族でもなく、支援者でもなく、友達でもない関係性を日常的につくっていくような人の採用・育成・輩出をパッケージでできるようなモデルづくりです。
今、研修は2期目に入っていますが、これ自体が私たちにとっては「どういう資質があればコミュニティ・ユースワーカーとしてうまくいくのか」という問いに対する素材集めという面を持っていて、メンバーの中には東京大学大学院でそうした評価指標づくりを専門に勉強している者もいるので、いずれ形にしていきたい。
そして、そのパッケージを地域の人たちにノウハウ提供して、地域の人たち自身がコミュニティ・ユースワーカーを採用・育成・輩出できるようにしていければと思っています。そうできれば、私たち自身は指標の洗練化とノウハウ提供に特化していくことになるかもしれません。
すでに都内の複数の区で、実験的に社会資源のデータベース化を進めています。料理が得意で食事を提供してくれる人、週一で自宅の一室を使わせてくれる人などを書き出していくと、私たちが知り合った人たちだけでも結構すごい数になります。
こうした協力者の中から、コミュニティ・ユースワーカーが生まれたり、またコミュニティ・ユースワーカーがこうした社会資源を活用できるようになれば、一人のワーカーが多数のケースを丸抱えしなくても、子どもたちを支えられる地域づくりが可能になるのではないか。そんな仮説をもちながら進めています。
まだまだ試行錯誤の段階だし、行政や自治会など住民組織との協力もこれからですが、普遍的な支援モデルの構築は決して不可能ではない、と感じています。

「お世話になった人」になる
荒井にとって、コミュニティ・ユースワーカーのゴールは「お世話になった人」になること。どんな家庭に生まれた子にも、たまたま学校でうまくいかなくなった子にも、「お世話になった人」が地域に複数いて、そこで励まされた思い出をもって生きていける社会――そんな社会は、きっと多くの子どもたちにとって生きやすく、楽しみのある社会になるだろう。
2月16日、PIECESは、寄り添っている子ども一人ひとりに合わせた支援を行うため、子どもたちの「やってみたい」を形にするための一つ一つの活動に関してクラウドファンディングを開始した。
詳細はこちら。

(注)本文中の敬称は略しました。また、筆者はNPO法人PIECESのアドバイザー(無給)を務めています。










