映画作家はコロナの現実をどう自作に込めたのか。石井裕也監督が明かす苦悩と、その先の希望

2020年の夏、映画監督は苦悩していたーー。
世の中全体が、出口の見えないトンネルの中を進んでいるような雰囲気で、他人と触れ合い、話すことにも躊躇し、気づけば精神が疲弊しきっている。そのような状況下で、作品で何かを表現するプロフェッショナルは、どこにモチベーションを見つければいいのか。
「こんなに大変な状況になって、自分が生きる意味もあやふやになっている。だからこそ、逆に大切なものが見えてくるのではないか。そういう物語が作り出せると思ったのです」
『舟を編む』『映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ』などで知られる石井裕也監督は、その苦悩を作品にぶつけることにした。
2020年を描くならコロナと切り離せない
『茜色に焼かれる』は、そうして産み落とされただけあって、コロナ禍での虚しさと苦しさ、その先の希望も見据え、映画を観るわれわれの心を、有無を言わせずざわめかせる。交通事故で夫を失くし、中学生の息子を一人で育て、施設に入所する義父の面倒もみる主人公。2020年の6月に物語を思いつき、8月に撮影を始めるという急ピッチの展開にとって、社会全体を暗く覆う新型コロナウイルスの要素を取り入れるのは「必然」だったようだ。
「映画を撮るなら、その時点の世相や社会状況が必ず紐づいてくると思うんです。だから、いま作るなら、“コロナ以前”の物語か、“コロナの最中”の物語か、あるいはまったく関係ないSFになってしまうでしょう。2020年に撮るなら、こうなってしまった……という感じです」
劇中では、主演の尾野真千子が多くのシーンでマスクを着けて演技をしている。他の登場人物も同様だし、近い距離での会話では、両者の間にアクリル板が置かれていたりする。いたるところにコロナ禍の日常が盛り込まれているのだ。

コロナ禍の社会になってから、一時、リモートを駆使した映像作品が急増し、話題になったりもした。しかしこれまで公開されてきた映画や、放映されたドラマで「現在」の風景をここまではっきり収めた作品は少ない。大きな規模で公開される映画では、この『茜色に焼かれる』が初めてと言ってもいい。
マスク姿の演技で、どこまで感情が伝わるのか
そもそも映画やドラマで、マスク姿の俳優の演技を観たいのか? そんなシンプルな疑問もある。
「今回は物語にとってもコロナは重要であり、自然に付随すると確信できました。ただ、マスクに関しては、撮影する前に、俳優が顔の半分を隠して芝居になるのか、あるいはドラマや映画として成立するのか、その懸念はありましたね。マスクなしの方が俳優の表情をわかりやすく伝えられますから、監督としてはありがたいわけです。でも、この物語はコロナの前提で書いていますから、マスクを外していい場面では、その根拠が示されなければならない。
実際に撮ってみると、顔が半分隠れていることで別の効果が表れました。本音がどこにあるかわからない主人公のキャラクターが際立ったのです。マスクの下で、彼女がどういう表情で、どんな感情なのか、目の前の相手はもちろん、映画の観客も想像することになります。映画って、当然のように“見せる”ことにこだわりますが、同時に“見えない”ことも扱うのだと改めて認識しました」
実際にマスクを着けているシーンが多いことで、撮影の際にメリットもあったという。現在、コロナ禍での撮影現場では、キャストが本番ギリギリまでマスクを着けているのが常識だ。
「リハーサル、テストの段階では、マスクに、さらにフェースシールドを着けたりして、本番ではそれを外して、カットがかかったらまた装着。それこそ不自然で、今回の現場ではマスクでテストをして、そのまま本番に入れたことは良かったです。もちろんスタッフや出演者の数を制限し、防疫対策もガイドラインにしっかり従うという苦労はありましたが」
高齢者ドライバー問題も突きつけた理由は?
そして、この『茜色に焼かれる』でもうひとつ心をざわめかせるのが、2019年、東池袋で起こった自動車暴走死傷事故とのリンクである。状況は別物だが、明らかに重なる要素が描かれているのだ。こちらも「今」を映し出しているようで、石井監督の強い思いを感じてしまう。
「高齢のドライバーがアクセルとブレーキを踏み間違える事故は多発しており、池袋のケースに特化したわけではありません。僕が問題視したのは、理不尽に命が奪われることです。これに関しては、僕も家族、とくに子供をもつ身として訴えたい気持ちが強くなっています。理不尽という意味でコロナの状況とも似ていますし、そういった思いが作品に結びついたのではないでしょうか。
3.11の後の原発の汚染水処理とか、とにかく片付いていない問題が多すぎて、しかもその事実を誰もがわかっている。でも、そこで立ち止まってもいられないので、問題を先送りにしている状況があると思うんです。僕自身も数年前までは、何かの問題に対して正々堂々と対決していく意思があったのですが、最近は無力感もあって、何かまったく違うやり方が必要なんじゃないかと、悩ましい日々ではありますね……」
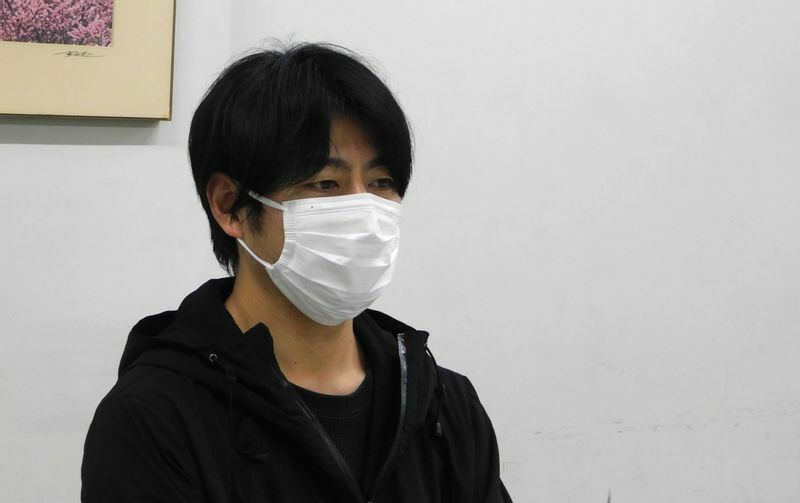
5年後、10年後も色褪せない物語に
あまりに多くの問題が噴出している現在の社会に対して、映画作家として複雑な心境を吐露する石井監督だが、では『茜色に焼かれる』はバリバリの社会派作品なのか? 決してそのような印象ではない。どちらかといえば、母と息子のドラマとしてストレートに胸に迫ってくる。監督が心から描きたかった物語が、根底に貫かれているからだろう。
「僕の母は37歳で亡くなりまして、去年、ちょうど僕もその年齢になったこともあり、作品で母親に向き合おうという気持ちになりました。母への愛や、母と子の強い関係性や希望が、コロナによって皮肉にも色濃く見やすくなったのではないかと思います。そして、コロナ以前からの人の心の荒(すさ)み、脆さが、コロナによって暴かれた部分もあるわけで、だからこの物語は5年後でも、10年後でも、色褪せないという確信があるのです」
現在の状況と、描きたい物語。その両者を融合させるという、映画作家にとって、もしかしたら最も望むことを石井裕也監督はやりとげたのかもしれない。
尾野真千子の主人公は劇中で、「まぁ、がんばりましょう」と何度も繰り返す。
「よく言えば、どんなに辛くてもがんばろうという希望の言葉ですが、悪く言えば、怒りを押し殺して、この感情に慣れるしかないという、今の日本の、あるいは日本人の態度だという思いも込められています」
シンプルに前向きになるようで、諦めにも聞こえるこの言葉は、コロナ禍の現在に響くと皮肉な意味でも受け取れるが、5年後、10年後に聞いたら、また別の意味を帯びている。そう信じたくなってしまう。

『茜色に焼かれる』
5月21日(金)、TOHOシネマズ日比谷ほかロードショー
配給:フィルムランド、朝日新聞社、スターサンズ
(C) 2021「茜色に焼かれる」フィルムパートナーズ










