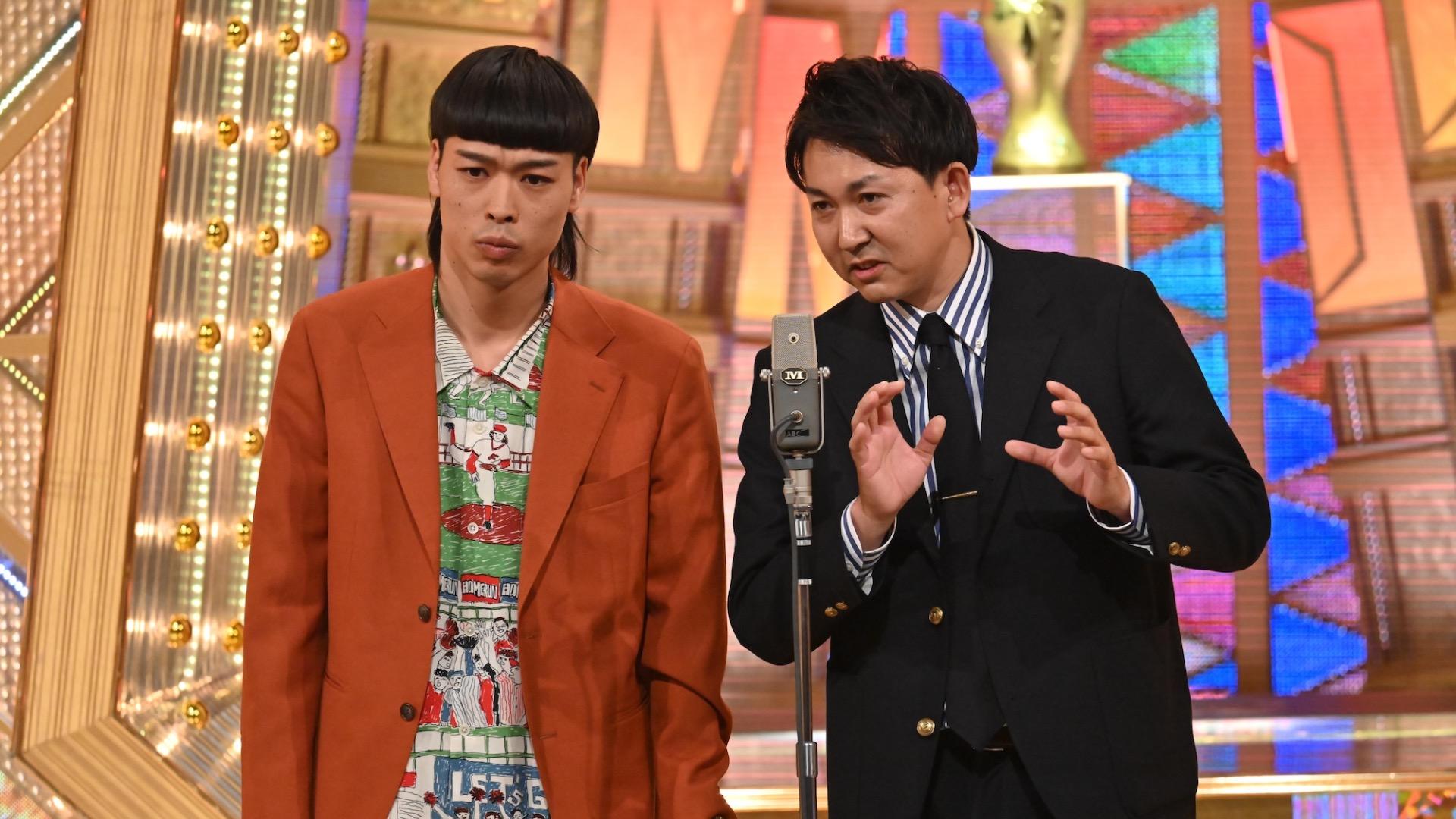ゾウやイルカにも実験!動物に鏡を見せたら自分だとわかるのか?

鏡に映った自分の姿を見て、「これは私だ」と認識できるのは、人間の特別な能力だと思っていませんか。しかし、実は人間の赤ちゃんは、生後すぐには鏡の中の自分を認識できません。自己認識ができるようになるのは、1歳半~2歳頃だと言われています。
つまり、鏡に映った自分を認識できるかどうかは、その個体の認知能力の発達度合いを測る重要な指標となるのです。そこで、多くの研究者たちが、動物の自己認識能力を調べるために、鏡を使った実験を行ってきました。
その実験の対象となった動物たちの種類は、実に様々です。ネコやイヌなどの身近なペットから、高い知能を持つとされるサルや鳥など、あらゆる動物が実験に参加してきました。中には、ゾウやイルカまで含まれているのですから驚きです。
この記事では、さまざまな動物を対象とした鏡の実験についてサイエンスライターの筆者がわかりやすく解説します。ゾウやイルカなど特殊な実験の場面についてもご紹介しておりますので、ぜひダイナミックな実験のようすを想像しながら読んでみてくださいね。
参考:Sociality and self-awareness in animals
動物が鏡に映る自分を認識しているか確認するには?

動物が自分自身を認識しているかどうかを調べるために、科学者たちは「鏡自己認識(Mirror Self-Recognition:MSR)テスト」と呼ばれる実験を行いました。その手順は以下の通りです。
- 動物が十分に鏡に慣れるまで、鏡との接触の機会を与える
- 動物を軽く麻酔をかけて眠らせ、目立たない位置(額や耳の後ろなど)に、においのないマーカーで印をつける
- 動物が目覚めたら、再び鏡の前に置く
- 動物が鏡を見て、自分のからだについた印に気づくかどうか観察する
最後に鏡でマーカーを見た動物が、その部分を触ったり、においを嗅いだりすれば、自己認識があると判定されます。
この一連の手順は、多様な動物に対して行われてきました。しかし、ゾウやイルカのような大型の動物となると、実験にも特別な工夫が必要です。
ゾウの場合、まず大きな鏡を用意することから始まります。通常の鏡では、ゾウの体全体を映すことができないためです。実験では、大型トラックの横に鏡を設置し、ゾウが自分の姿を十分に見られるようにします。
一方、イルカは泳ぎ回ってしまうため水中に鏡を置くだけでは鏡に映る映像を認識しない恐れがありました。そこで、イルカ用のプールの壁面に大きな鏡を設置し、イルカが泳ぎながら自分の姿を見られるようにしました。
このように、動物の種類によって実験方法を工夫することで、多様な動物の自己認識能力を調べることができたのです。
社会的動物の多くは鏡の自分に気づくもイヌはNG

MSRテストの結果、チンパンジーやボノボ、オランウータンなどの大型類人猿、イルカ、アジアゾウ、そしてヨウムなどの一部の鳥類が、鏡に映った自分の姿を認識できることがわかりました。これらの動物は、いずれも複雑な社会生活を送る種であることが特徴です。
一方で、イヌやネコ、ウマといったヒトになじみの深い動物は、鏡の前で自分の反応を見せるものの、自己を認識している証拠は得られませんでした。
特に興味深いのは、イヌの結果です。イヌはオオカミから進化した動物で、群れを形成して狩りをするなど社会性の高い動物として知られています。しかし、鏡の前では自分の姿を認識できないのです。
なぜイヌは鏡の中の自分を認識できないのでしょうか?その理由として、イヌが視覚よりも嗅覚に頼って世界を認識していることが挙げられます。イヌにとって、鏡に映る映像よりも、そこから得られる匂いの情報の方が重要なのかもしれません。
これらの結果から、自己認識能力の有無は、単に社会性の高さだけでは決まらないことがわかります。むしろ、視覚情報をもとに自己と他者を区別する能力が、鏡の中の自分を認識するカギとなるようです。
鏡を使った自己の認識には、社会性と視覚認識の両方が必要であることが浮き彫りになりました。多様な動物の認知能力を測るためには嗅覚などを活用した新しい自己認識テストの開発も望まれます。
動物の自己認識が明かす「心の進化」の謎

動物の自己認識を理解することは、動物とのより良い付き合い方を考える上でも大切な意味を持ちます。自分を認識し、感情を持つ動物には、もっと思いやりのある接し方が必要だと気づかせてくれるでしょう。
また、私たち人間を含めた動物の「心の進化」を探る上でも、重要な役割を果たしています。今回紹介した研究では概ね群れをつくって生活する動物が、自己認識の力が高い傾向にありました。自分を認識できるようになることは、他の個体の気持ちや考えを理解する力(心の理論)を身につける第一歩と考えられています。つまり、鏡の中の自分がわかる動物は、仲間の感情や意図をより深く理解できるようになる可能性が高いのです。
自己認識は、思いやりの心や社会性の土台につながる重要な能力です。自己認識の能力がどのように進化してきたのかを知ることは、ヒトを含む動物の心の進化の謎を解く鍵にもなります。これからの研究の進展に、大いに期待が持てそうですね。