関ヶ原合戦後、徳川家康が東軍諸将を大幅に加増し、厚遇した当たり前の理由
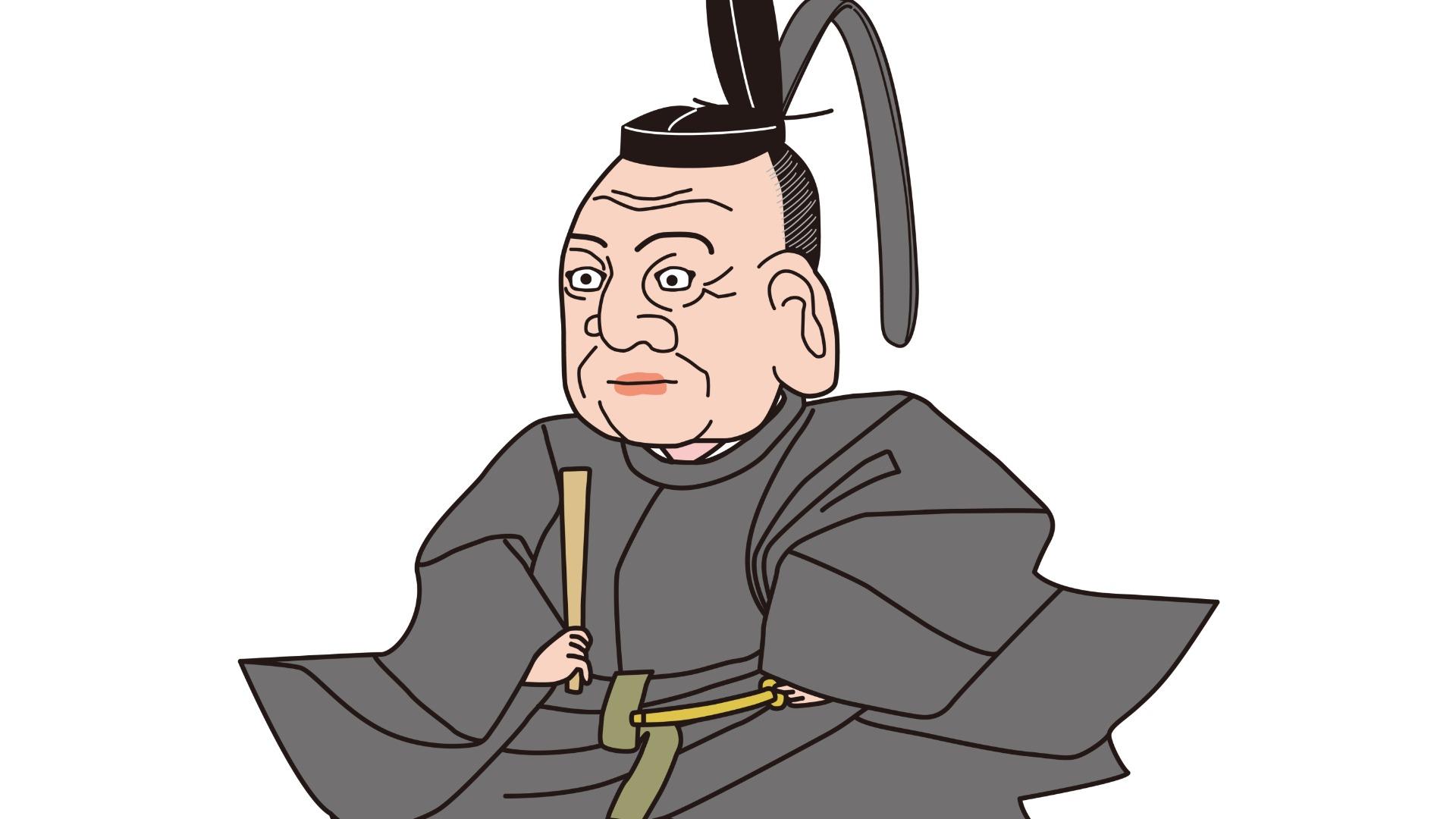
大河ドラマ「どうする家康」では、関ヶ原合戦後の模様が描かれていた。戦後、家康は東軍諸将への領知配分を行い、中には大幅に加増された大名も存在した。なぜ、家康は味方となった東軍諸将を大幅に加増し、厚遇したのか考えてみよう。
慶長5年(1600)9月の関ヶ原合戦後、勝者と敗者の差は非常に大きなものがあった。東軍で多大な加増(30万石以上)をなされた大名を順に列挙すると、次のようになろう。
①結城秀康 10.1万石(下総・結城) → 56.9万石(越前・福井)
②松平忠吉 10万石(武蔵・忍)→ 52万石(尾張・清洲)
③蒲生秀行 18万石(下野・宇都宮)→ 60万石(陸奥・会津)
④池田輝政 15.2万石(三河・吉田) → 52万石(播磨・姫路)
⑤前田利長 83.5万石(加賀・金沢) → 119.5万石(同左)
⑥加藤清正 19.5万石(肥後・熊本) → 51.5万石(同左)
⑦黒田長政 18万石(豊前・中津) → 52.3万石(筑前・福岡)
参考までに補足すると、関ヶ原本戦でも大活躍した福島正則は、20万石(尾張・清洲)から49万8千石(安芸・広島)へと、29万8千石も加増された。
同時に重要なことは、家康配下の数千石レベルの家臣についても、1万石以上の大名に多くが取り立てられたことである。家康家臣の多くは江戸周辺の関東地域に配置され、防備体制を築いた。
外様大名や徳川家の一族譜代そして家臣に加増した所領は、西軍から没収した所領、あるいは豊臣家の蔵入地(直轄領)から分け与えられた。
一方で、負けた西軍諸将は、改易や減封などの厳しい処分が科された。慶長8年(1603)には江戸幕府が成立するが、その磐石な体制はここに築かれたのである。
ところで、東軍諸将に対する領知配分は、家康が発給する領知宛行状ではなく、口頭で行われたという。あえて口頭で行われたのは、家康が秀頼の主宰する豊臣政権の存在を憚ったからだった。
しかし、実際には家康が領知宛行を行ったのだから、その威勢は諸大名に浸透したはずである。そもそも三成らが家康に兵を挙げたのは、家康が無断で知行を与えていたからだった。
家康が東軍諸将や家臣を厚遇したのは、当然ながら軍功に報いるためである。同時に、家康が与党として、彼らを引き込むことを意図していたのは疑いない。
家康は謀反人である三成らを討伐し、自らの与党を形成することに成功した。武家社会で棟梁になるには、配下の者の軍功に報い、知行を与えることは当然のことだったのだ。
主要参考文献
渡邊大門『関ヶ原合戦全史 1582-1615』(草思社、2021年)










