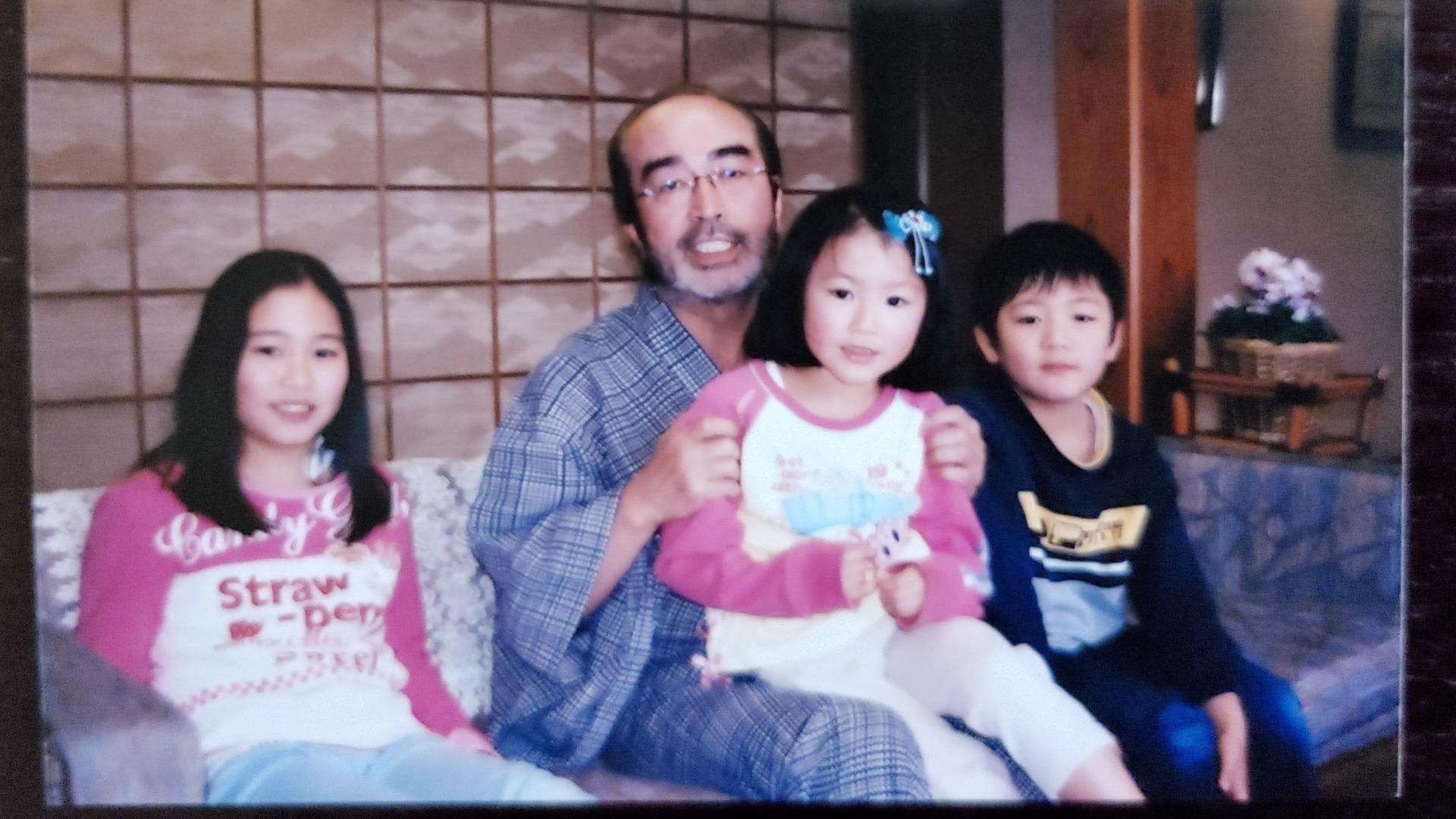阪神タイガースのリリーフ左腕三人衆とブルペンの「超変革」
■リリーフ左腕3人は「超変革」なのか!?
プロ野球が開幕し、明日からふた回り目に入る。ここまで阪神タイガースは15試合を戦い、8勝6敗1分けで終えている。
現在、タイガースのブルペンは右投手4人、左投手3人だ。リリーフの左は1人ないし2人というチームが多い中、3人はなかなかない。左投手不足に悩むチームから見ると、なんとも羨ましいのではないかと思うのだが…。これも「超変革」の一端か。
金村曉投手コーチに訊くと「ウチの左は3人ともワンポイントじゃないからね。左打者だけじゃなく右打者にもいけるから、イニングを任せられる。特に左が多いからいいというようなことはない」と答え、矢野燿大 作戦兼バッテリーコーチも「いいピッチャーから入れていったら、力関係で左が3人になっただけ。左が3人おるから使いやすいとか戦いやすいとかはない」と話す。
実際、極端に相手打者の右左にこだわった起用もしていない。展開、状況、また投手の状態や疲労度などを考慮した登板になっている。むしろ、その起用法こそが「超変革」と言えるのかもしれない。
それでは奮闘している“左腕三人衆”に注目してみよう。
■フォームを「超変革」した榎田大樹投手
春季キャンプで金本知憲監督から「MVP」に挙げられた榎田大樹投手。春季キャンプには並々ならぬ思いで臨んでいた。というのも、前年の秋季キャンプ中に右太もも裏を痛めてリタイアしていたのだ。「だからまさか沖縄キャンプに行けると思ってなかったんで、選ばれてビックリした」。そこで「マイナスからのスタートだし、とにかく動けるというところ、パフォーマンスに影響ないというところをアピールしようと思った」という。
それに加え、嬉しいことがあった。臨時でコーチに来た下柳剛氏との出会いだ。これまで左投手出身のコーチがいなかったため、「フォームを一から指導してもらったことないんです」と話す榎田投手に、下柳コーチはこれまで見てきて気づいたことを教示した。
最も注意をうけたのは“頭”だ。「頭が突っ込んで、ボールを覗き込んでいると言われました。(投球時に)出ていく時も、頭から出ていたんです」。
そのフォームの欠陥に気づかず投げていた昨年は「強く投げようとするとボールがスライドしていたんで、ゲームで抑えてもどこか気持ち悪かった。それに結果を気にし過ぎて腕の振りが弱くなって、腕振っているつもりが置きにいっていた」と振り返る。
フォームを修正するに当たり、プレートの踏み方も変えた。これまで軸足である左足の外側をプレートに掛けるようにしていたのを、プレート側面に添えるだけにした。スタート位置を修正したこともあって、頭が突っ込まなくなったという。「キャッチボールからしっかり軸で立つ意識でやっています」と話す。
「今はしっかり腕振って自分のイメージ通り投げられています。こうなったらこうというのが、一致しているんです」と、腕の振りとボールの軌道がピッタリと合っているそうだ。
榎田投手は試合後、VTRを見ない。「後ろからの映像は意味ないんで。それよりも自分の感覚の方が大事なんです」。気になるチェックポイントは、センター位置のカメラから撮った映像では確認できないからだ。何より「正しいフォーム」がわかった今、そのズレは自分自身の感覚が最も明解な答えとなる。
9日のカープ戦で3連打を浴びて3失点を喫した時、香田勲男投手コーチは「たまたまやられたけど、彼のお陰でこれまで救われてきた。信頼は変わらないし、これからもやってくれる」と言い切った。その言葉通り、翌日は2イニングスをパーフェクトに抑え、「リベンジという意味ではよかった。これを続けていければ…」と榎田投手は胸を張った。
「榎田はすごい。どんな場面でも応えてくれる。初回からでもいけるし、終盤にもいける。ショートはもちろん、ロングもできる。本当にタフで使い勝手がいい」。金村コーチも大絶賛するように、チームにとって不可欠な存在だ。
■赤丸急上昇の人気、高宮和也投手
早い回から準備する榎田投手とは違い、ほぼ中盤以降からの出番となる高宮和也投手と高橋聡文投手。
「去年は四回からブルペンに行っていたけど、今年は五回から。今年は『どんな展開でも作らなあかん』というのはないから、コンディショニングを整えやすいし、体も楽」という高宮投手。「経験もそこそこ積んだし、狙ったところに放れるようになってきた」とコントロールの精度が上がったことに自信を見せている。
「スライダーを狙われることが多くなっていたけど、まっすぐやスライダーだけに頼らず、シュートやカーブもしっかり使えるようになったんで、狙い球が絞られにくくなったと思う」と、“上積み”もある。
春季キャンプでは思わぬ注目を集めた。金本監督考案のリレーで激走し、走り終えた後のヘロヘロな姿が笑いを誘い、ファンの間でも「生まれたての仔馬みたいで可愛い〜」と話題になったのだ。「あぁ、あれね(笑)。ちょいちょい聞きますね」と、本人もまんざらでもないようだ。しかし「いや、野球で結果出して、もっと応援してもらえるように頑張ります」と、“本業”で魅了してのファン増加を誓っている。
■新加入の高橋聡文投手
FAで獲得した高橋投手はセットアッパーとして黄金時代の中日ドラゴンズを支え、虎打線を散々苦しめてきた。高橋投手の特徴を訊くと、金村コーチは即答した。「ハートが強い!それに尽きるね」。
「こう言っちゃなんだけど、ブルペンでは全く見栄えしない(笑)。それがゲームにいくと、グッとギアが上がる。ブルペンではの〜んびりしてギリギリまでスイッチ切っといて、行くぞって時にピピっとスイッチを入れる。オンオフが本当にうまい」。
これは長年かけて培ったものだが、「経験なんだけど、金田や歳内はそういうところ勉強しないとね」と金村コーチは若手投手に要求する。「緊張感が長過ぎると相当、疲労がたまる。それが1年間となるとね」と、オンとオフの切り替えの大切さを説く。
「人それぞれの上げ方があると思う。高宮なんて、とにかくよく喋っている。『マジ、無理〜!マジ、無理〜!』とかブルペンで弱音吐いているくせに、いざマウンドに行ったら相手を飲んでしまう。ネガティブからポジティブへの切り替えがすごい!福原も含め、高宮、高橋のそういうところ、参考にしてほしいね」。
高橋投手自身も「投手王国」と言われたドラゴンズで、名立たる先輩たちから学んできたという。「(落合)英二さんや岩瀬(仁紀)さんを見てきて、それを見習ってきました。ドラゴンズではブルペンで先輩たちがすごくよく喋っていて、和ましてくれるんですよ。そういう上の人たちのスイッチの入れ方とか、見てきました」と話す。「それまで喋ってて、(マウンドに)行く寸前にガラッと変わるんです。ブルペン全体がピリッとなる」。その口ぶりからドラゴンズの黄金時代を築いた強力投手陣のすごさが伝わってくるが、FAでタテジマに袖を通した今、その経験を若虎たちに示してくれている。
スイッチの入れ方だけではない。肩を作る早さも、若虎たちが見習うべきことだろう。「行けと言われれば、投球練習は何球ででも行けますよ」と笑顔を見せる。キャッチボールさえ済ませていれば、いつ登板を告げられても数球で仕上げられるという。「マウンドでも5球投げられるしね。『できている』『できていない』も気持ち。気持ちの整理が大事なんです。いつでも行けますよ!」と頼もしい。金村コーチが讃える「ハートの強さ」というのが頷ける。
「あの声援が味方になるのは心強い」。8日、公式戦で甲子園初登板した時、感激の面持ちだった高橋投手。ここまでの働きを「最低限」とし、「毎回抑えるのは無理だけど、しちゃいけないことだけはしないように、調子を維持していきたい」と、虎党の大声援に応えていくつもりだ。
■金村暁コーチによるブルペンでの「超変革」
左腕3人はもちろん、マルコス・マテオ投手、福原忍投手、安藤優也投手、歳内宏明投手の4人を加えた投手陣が存分に働けるよう、ブルペンを預かる金村コーチも密かに「超変革」を行っている。
「疲れをためないように、偏った使い方にならないように考えている」と、展開をみながら「完全ノースローデー」を作るなどしているのだ。「一回作ってドン(試合での登板)」というのが理想。何回も何回も作らなくていいようにね」と語り、展開を見ながら“無駄な”ピッチングは避けるようにしている。「展開によってはうまくいかない日もあるけど」。バタバタした日もあったそうだが、それでもここまでうまく機能している。
また「空きすぎてもよくないので、3日を限度として3日投げてなかったらピッチング入れとうか、とか」と投げ過ぎず、空き過ぎずということを常に考えている。
登板直前の投球練習も極力、球数を減らすようにしている。「球数少なくというのは、キャンプから意識づけをしてきた。10球、多くても15球で作ってくれと言ってある」。
指導者1年目の金村コーチだが、解説者4年の経験が生きているという。北海道日本ハムファイターズのテレビ中継の解説者時代、ファイターズ投手陣の取材を綿密に行っていた。その中のよかった部分を今、タイガースのブルペンで実践しているのだ。また、「香田さんもこっち(ブルペン)の動きをちゃんと見て考えてくれているから、やりやすい」と、ベンチからの一方的な指示だけではなく、ブルペンに主体性を持たせてくれている。つまりベンチとブルペンの連携がスムーズに行われているということだ。
「でも結果がすべての世界。結果が伴ってこそ、『うまくいった』と言える。1年間、いいパフォーマンスを出すために、もっともっとブルペンでも工夫していきたいね」と金村コーチ。
それぞれの持ち場で見られる「超変革」。“中継ぎ左腕三人衆”もそれぞれが自分自身の「超変革」を目指して、腕を振るっていくだろう。