諸大名は徳川家康を支持した。豊臣秀頼に突き付けられた厳しい現実
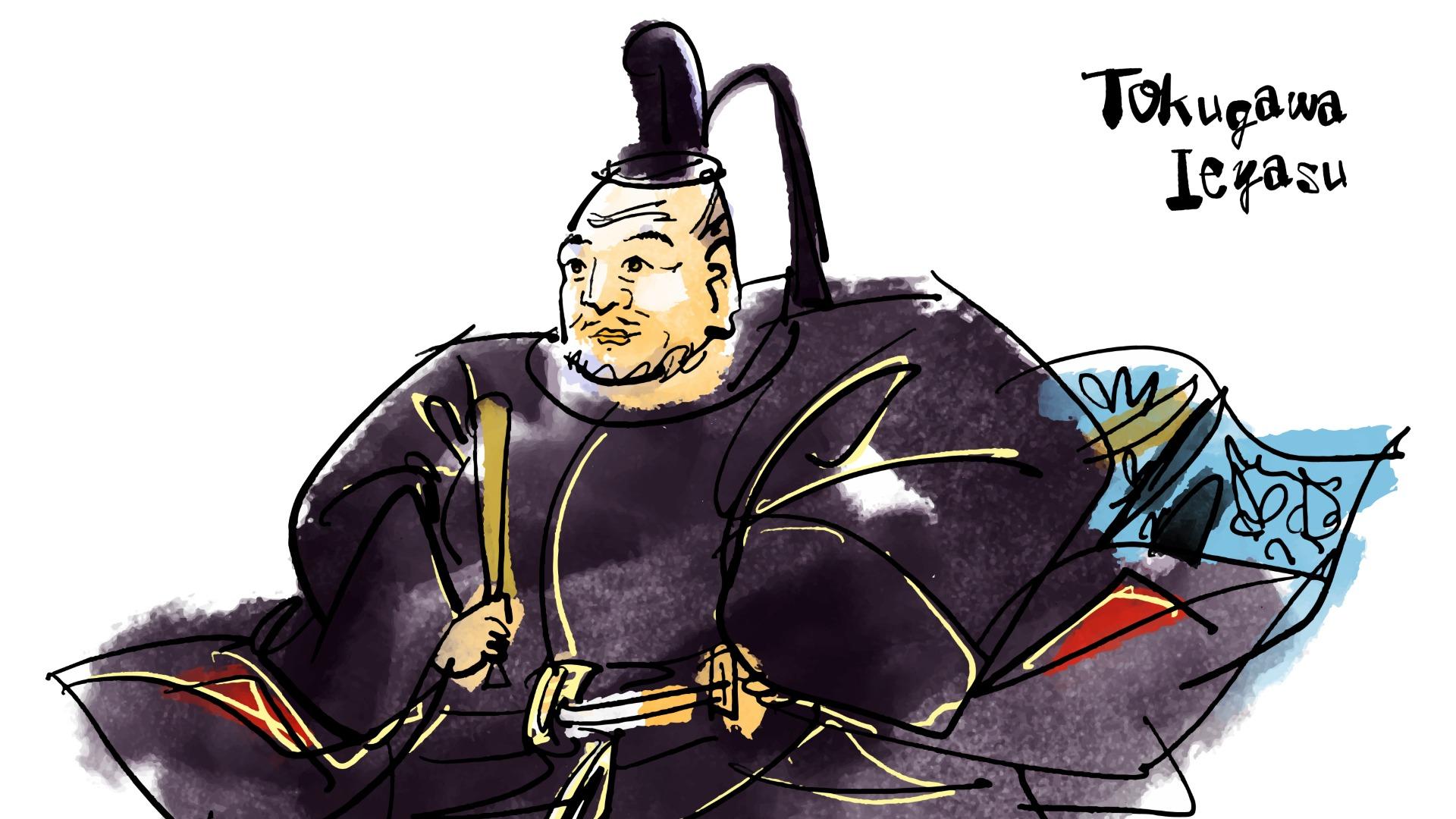
大河ドラマ「どうする家康」では、徳川家康の威勢が際立って描かれていた。家康が征夷大将軍に就任すると、諸大名はこぞって支持した。豊臣秀頼には厳しい現実が突き付けられたが、その辺りについて触れることにしよう。
慶長8年(1603)2月、家康は征夷大将軍に任じられ、武家の棟梁として君臨した。同時に、江戸幕府が成立したので、各地の大名は家康に従ったのである。
一連の事実は、豊臣方に大きな衝撃を与えたに違いない。やがて、家康の優位な立場は徐々に鮮明となった。それは、家康に対する諸大名の姿勢から理解される。もう少し具体的な事例を取り上げておこう。
家康の征夷大将軍任官以前、諸大名は歳首(年頭)を祝うため、まず大坂城(大阪市中央区)の秀頼のもとに伺候し、次に伏見城(京都市伏見区)の家康を訪問した。
訪問する順番は幼少の秀頼が先で、家康が後だったので、諸大名は家康よりも豊臣公儀を尊重していた事実を読み取ることができる。つまり、関ヶ原合戦後においても、まだ豊臣政権は諸大名から重要視されていたのだ。
諸大名だけでなく、家康も歳首を祝うため、真っ先に秀頼のもとへ伺候するという現実があった。家康が秀頼のもとを最初に訪れたのは、臣下の礼を取っていたことを意味する。家康は関ヶ原合戦で勝利したが、形式的には秀頼の下に位置していたので、豊臣公儀の存在意義は大きかったといえる。
慶長8年(1603)2月に家康が征夷大将軍に就任して以降も、いまだに諸大名は歳首を祝うため、相変わらず秀頼のもとへ真っ先に駆け付けるという現実があった。
家康が征夷将軍職に就任した時点では、諸大名が優先して家康のもとへ伺候することは意識されていなかった。むろん、急に彼らの意識が変わるとは考えられず、諸大名はごく自然な形で、まず秀頼のもとへ訪問したと考えられる。
家康が征夷大将軍になっても、豊臣政権の威光は、尊重されたままだったのである。むしろ重要なことは、家康自身が征夷大将軍に任官されて以降、秀頼のもとに伺候することがなくなった事実である。
家康は征夷大将軍に就任したことで、徳川公儀を確立し、豊臣公儀に対抗しうる新たな権威を獲得した。家康は徳川公儀を確立したので、豊臣公儀の主宰者たる秀頼への伺候は不要と考えたのである。
やがて、諸大名も雰囲気を察したのか、秀頼への伺候を徐々に取りやめることになった。家康への遠慮である。家康の威光は徐々に諸大名へ浸透し、家康の子・秀忠が2年後の慶長10年(1605)に征夷大将軍に任官し、将軍職が徳川家で世襲されたことによって決定的になった。
こうして秀頼、そして豊臣政権の威光は徐々に失われていった。とはいえ、秀頼は単なる一大名ではなく、天下人そして関白だった亡き父・秀吉の子として、辛うじて権威を保っていた。そうでなければ、家康が豊臣家を滅ぼそうとはしなかったはずである。
主要参考文献
渡邊大門『誤解だらけの徳川家康』(幻冬舎新書、2022年)










