運用開始が近づく「電子処方箋」 私たちへの影響は? 導入の課題は?
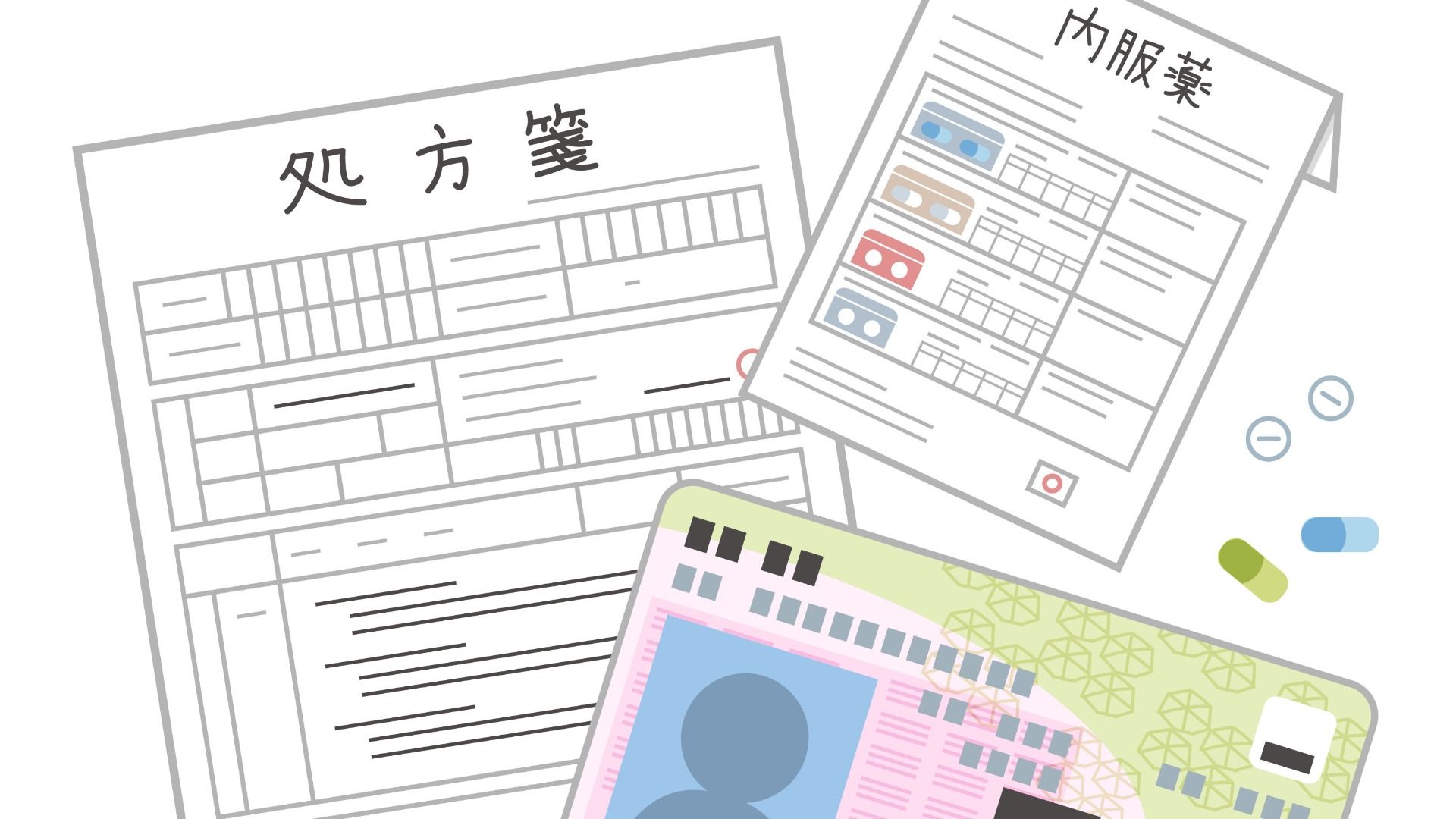
2か月後の2023年1月から、ついに「電子処方箋」の運用が始まります。電子処方箋とは、現在紙で運用している処方箋を電子化したものです。私たちにどのような影響があるでしょうか?
複数の医療機関を受診する高齢者が多い
外来で「この薬が欲しい」と言われることがありますが、お薬手帳を見てみると、他のクリニックから同じ薬効の薬が処方されていることがよくあります。
重複がないかどうかは調剤薬局で検薬してもらえますが、カタカナばかりの薬品名なので、「何の薬なのか」を分かっていない患者さんも多いです。
院外処方箋の場合、今までは紙の処方箋を発行していましたが、これが完全に電子化する方向に進んでいます(図1)。当初は必ず導入しなければならない仕組みではありませんが、政府としてはこれを積極的に進めていく方針にしています。

医療機関や調剤薬局は本来、患者さんの病気、アレルギー、検査結果、薬剤服用歴などの多くの医療情報を集約したファイルにアクセスできることが望ましいのですが、日本ではこれが長らく進んでいませんでした。
バルト三国のエストニアで包括的システムが導入されたのは14年前の2008年です(2)。いかに日本が後れをとっているか、おわかりでしょう。
電子処方箋のメリット
①重複投薬等の防止
複数の病院をかけもち受診している高齢患者さんが多いため、電子処方箋の仕組みが始まれば、重複投薬チェックや併用薬チェックが可能になります(図2, 3)。


また、医療機関と調剤薬局とのコミュニケーションが円滑になることが期待されます。現在は「疑義照会」というFAXのやりとりが主ですが、もう少し密な連携がとれないだろうかといつも感じています。
②処方箋紛失の防止
外来予約票や領収書など、病院を受診するとたくさんの紙が渡されます。時に、「処方箋をなくした」と相談してくる患者さんもいます。電子化されることで、紛失が防止できます。
③コンピュータの入力業務の省力化
薬局の窓口でコンピュータに処方情報を入力する業務が省力化され、誤入力が防止できます。入力時間が減ることで、患者さんへの薬剤指導にもう少し時間を割けるかもしれませんね。
④オンライン診療の普及につながる
処方箋が電子化されることで、紙の処方箋を患者さんが持ち運びする必要がなくなります。オンライン診療が普及すれば、診察から服薬指導までオンラインで完結する時代がやってくるかもしれません。
電子処方箋の課題
①認知度の低さ
日経メディカルオンラインの医師会員へのアンケートによると、電子処方箋の運用が2023年1月から始まることを知っているかどうかを聞いたところ、「知らない」と回答した医師が7割を超えたとされています(3)。
実は、私自身も電子処方箋という言葉は知っていたのですが、制度概要については最近まであまり知りませんでした。
この制度に関して、医師と薬剤師はHPKIカードというオンライン資格証の発行が必要になります。医師の場合、2022年9月末時点で、発行は3万枚に到達していないため、34万人いる医師のほとんどがこの存在を知らないということです。
導入まで2か月を切っているので、もう少し広く通知すべきと思います。
②マイナンバーカードの普及
電子処方箋は、マイナンバーカードを健康保険証として活用するオンライン資格確認のシステムを基盤とします。現時点では紙ベースの健康保険証でも対応できるように検討されていますが、マイナンバーカードの普及をさらに進めないといけません。
③システムの脆弱性
別の医療機関を狙ったものは珍しいと思いますが、大阪の病院で先日サイバー攻撃がありました。支払基金・国保中央会に電子処方箋管理サービスが立ちあげられるので、将来的なシステムトラブルは1つのリスクと考えられます。
④費用
国策でもあるため、医療機関や医療従事者に過度な負担がかからないようにお願いしたいところです。医師と薬剤師はHPKIカードが必要になりますが、実は発行費用がかかります。補助金が出るとはいえ、費用が高いがゆえに導入がうまくいかないというのは避けたいところです。
まとめ
電子カルテは多くの医療機関で普及しましたが、医療機関ごとにスムーズなデータのやりとりはできません。
紹介状を印刷して渡してスキャナーで取り込んだり、データをCD-Rに焼いてもらったり、デジタルなのかアナログなのかよく分からない状況です。
電子処方箋は、今後諸外国のように医療情報を中央でデジタル化するという取り組みの基盤になるのではないかと期待されます。
(参考)
(1) 厚生労働省. 電子処方箋の概要等(URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html)
(2) 総務省. 情報連携による効率的・効果的な地域医療の提供 (URL:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/nc233210.html)
(3) 医師8782人に聞いた「電子処方箋」への対応電子処方箋の1月開始、医師の7割が「知らない」(URL:https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/series/1000research/202211/577081.html)(医療従事者向けの要登録ウェブサイト)










