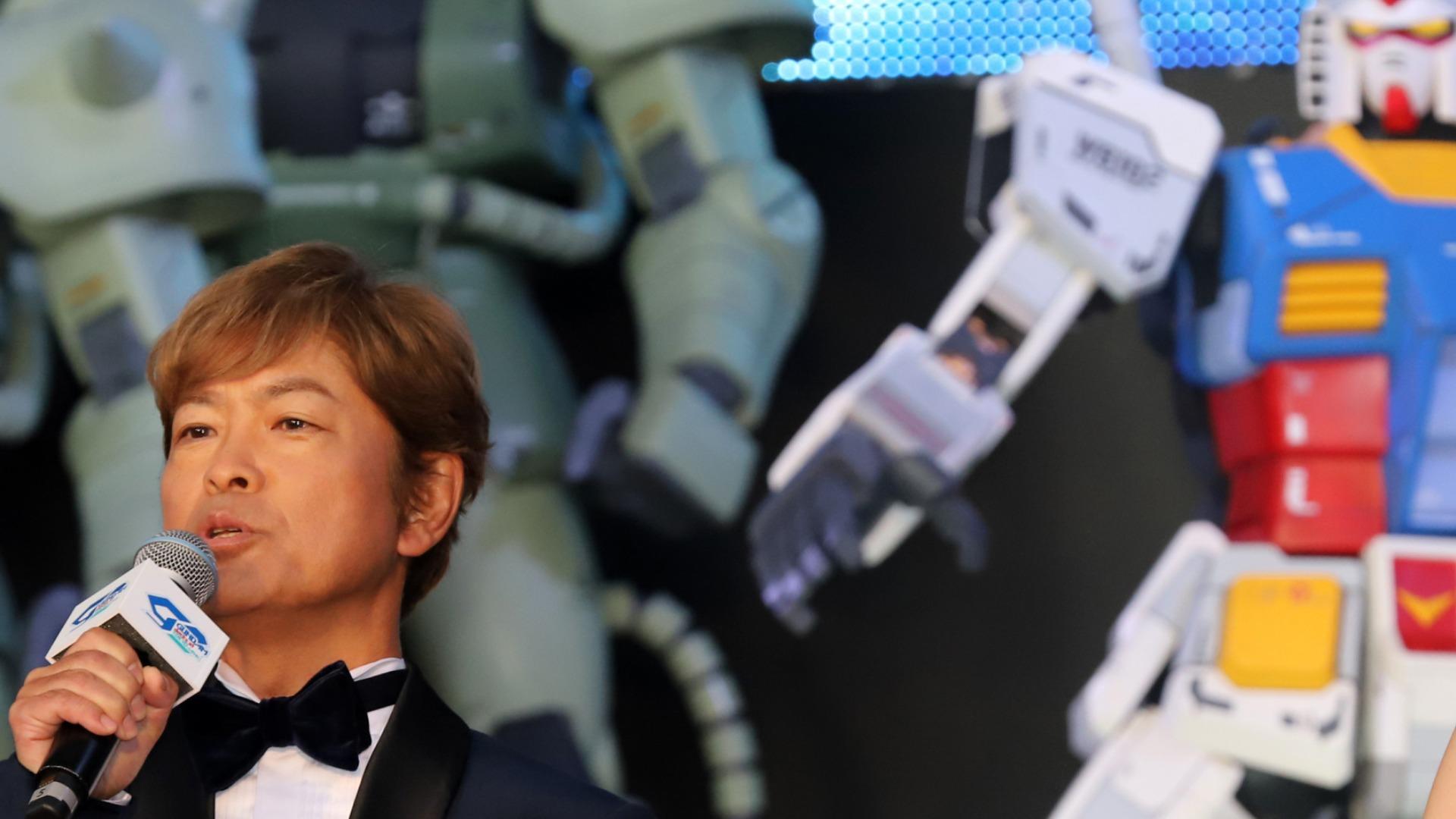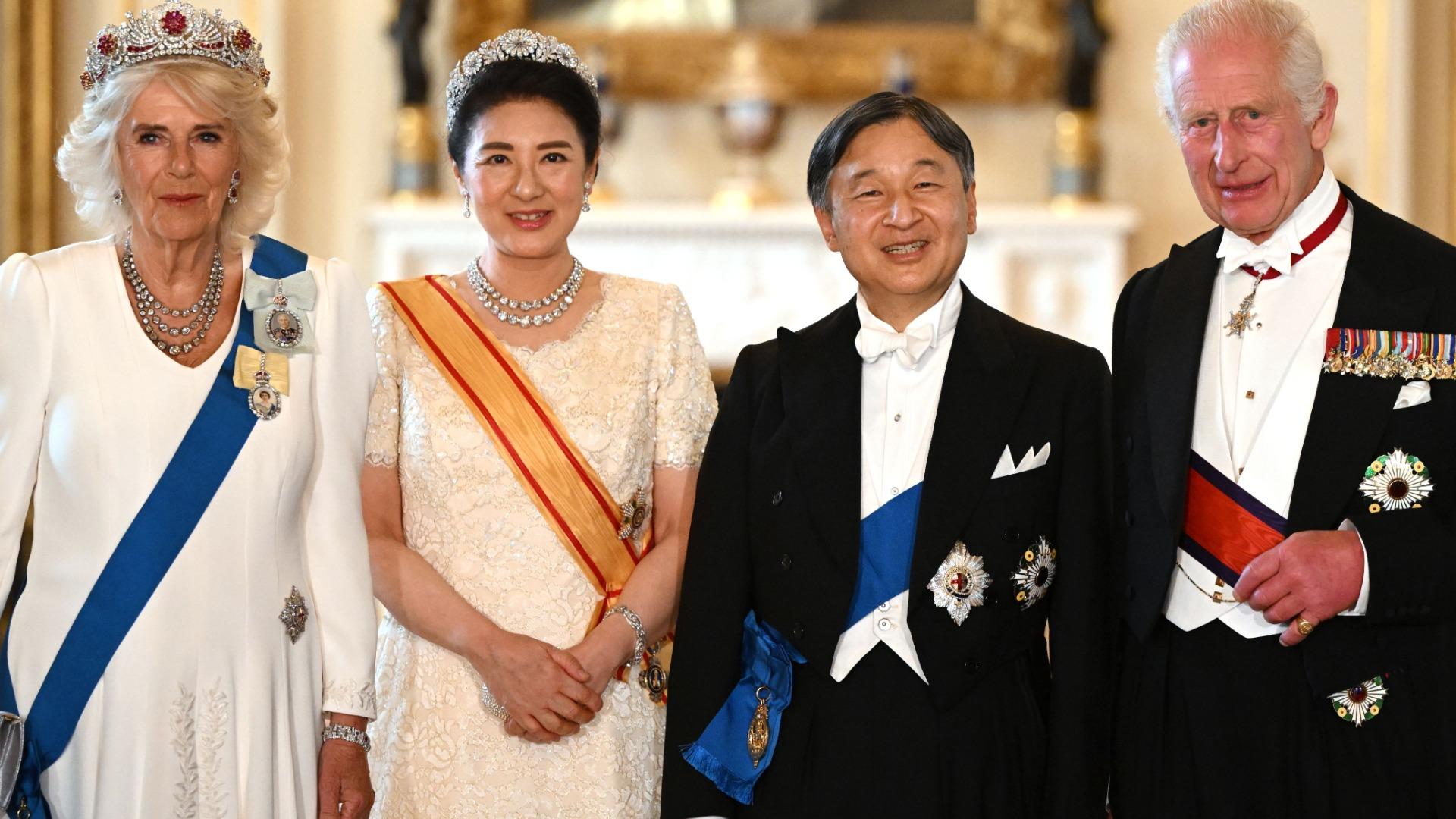寒い冬から暖かい3月へ 春を告げるため福井県若狭から奈良県東大寺へ「お水送り」

北海道では、発達した低気圧によって暴風雪となり、冬真っ盛りですが、東日本から西日本では気温が上昇し、春の兆しが感じられるようになりました。
奈良・東大寺のお水取りと若狭井
春を告げるとされる奈良・東大寺のお水取りは、1260年以上一度も休むことなく続く伝統行事で、3月12日深夜(13日の午前2時)に、若狭井(わかさい)という井戸から観音さまにお供えする「お香水(おこうずい)」を汲み上げる儀式が行われます。お水取りに続き、大たいまつを持った練行衆が内陣をかけまわる達陀(だったん)という妙法があります。
東大寺の若狭井は、その名のとおり、若狭の国(現在の福井県西部)と関係があります。
東大寺でお水取りが行われる10日前、3月2日に福井県西部の神宮寺では、お水送りの行事が行われます。
それは、日本海神宮寺にある井戸から汲んだ水を、東大寺に送る行事です(写真1)。

神宮寺の井戸の水は、遠敷川(おにゅうがわ)の鵜の瀬(うのせ)までたいまつ行列でおごそかに運ばれ、若狭小浜の「鵜の瀬」から送られ、10日かかって東大寺二月堂の「若狭井」に届(とど)くとされています(写真2)。

大陸文化が天然の良港である若狭の国・小浜から奈良へと伝えられた足跡が、この伝統行事の中に残されているともいえます。
火祭り
平成17年の神事の時には福井県で勤務していましたが、このとき、お水送りの神事を見学し、冷たい雨のふるなか、たいまつ行列に参加しましたが、勇壮な火祭りでした。
火祭りで有名な若狭の神宮寺、京都の鞍馬寺、奈良の東大寺、和歌山の熊野那智大社の4つの火祭のお寺が南北一直線にならびます。日本人は古くから東西を意識していたことが多いと言われていますので、ひょっとしたら、南北を意識していた人々、遠くまででかけてきた渡来人が起源になっているのかもしれません。
寒かった冬から暖かい3月へ
平成30年(2018 年)の冬は、全国的に気温が低くなりました。これは、日本付近に強い寒気の流れ込むことが多かったため全国的に冬の気温が低く、特に西日本は32年ぶりの寒い冬となりました(図1)。

1ヶ月予報によると、3月は全国的に気温が高く、特に、北海道のオホーツク海側と東海地方では、気温が高くなる確率が特に高くなっています(図2)。寒かった冬はようやく終わり、暖かい3月になりそうです。
その中で、若狭の国から奈良へお水が送られ、奈良に春を告げる東大寺のお水取りが行われます。

なお、冬型の気圧配置がしばしば強まったため、降雪量は西日本の日本海側ではかなり多く、東日本の日本海側は多くなりました。福井県を中心とした記録的な大雪が大きなニュースとなりましたが、今年の大雪は福井県北部の越前の国です。お水送りが行われる南部の若狭の国は平年より少ない降雪でした。
タイトル画像、写真1、写真2の出典:著者撮影。
図1、図2の出典:気象庁ホームページ。