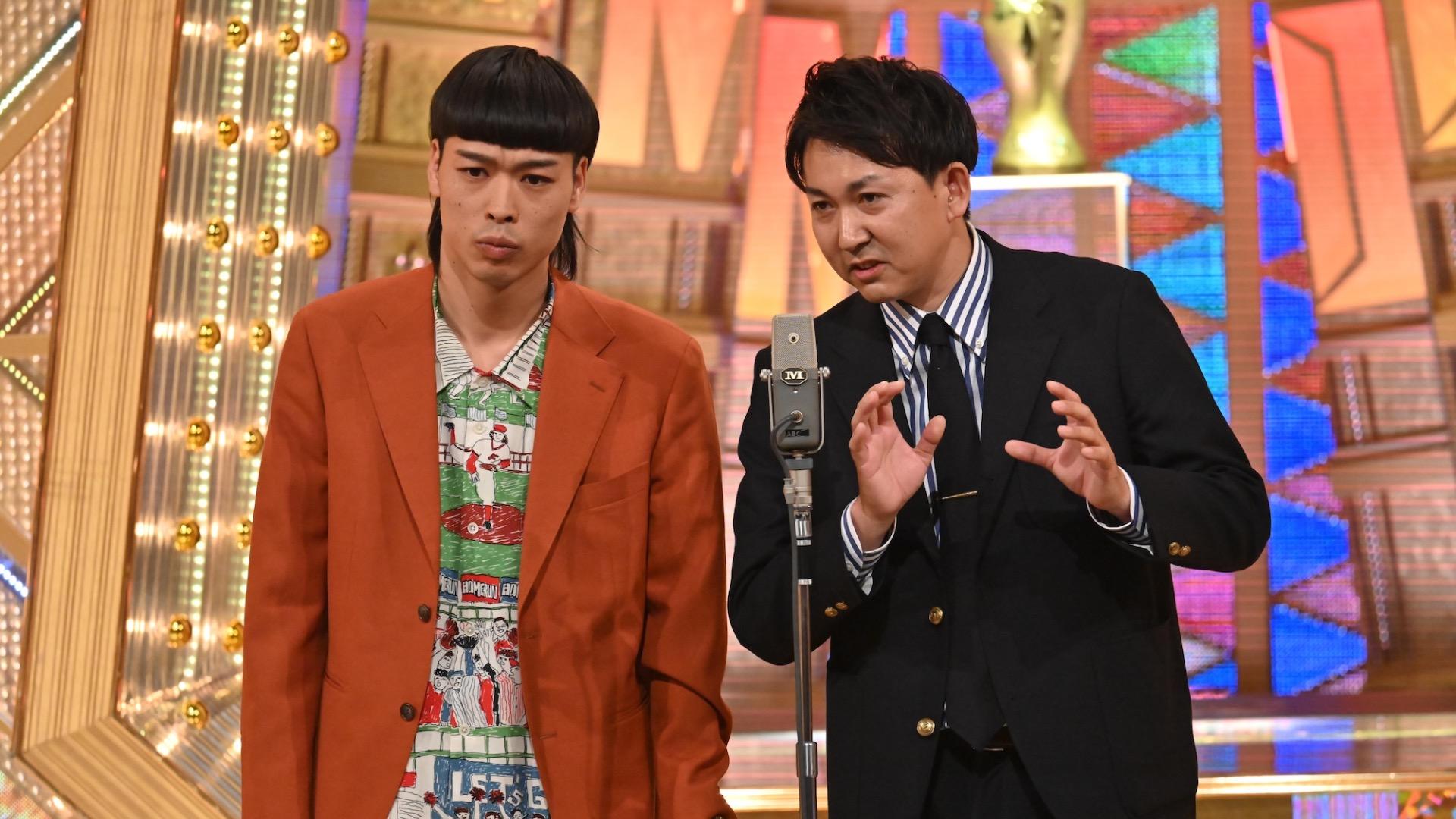ロシアのウクライナ侵攻から考える---「台湾有事」に備える情報・コミュニケーション戦略

ロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始し、世界が騒然となる中、25日午後、プーチン大統領は習近平国家主席と電話で会談した。「アメリカとNATO(北大西洋条約機構)は長きにわたってロシアの安全上の合理的な懸念を無視し、何度も約束に背いて東への軍事配備を続けた」と述べたプーチン大統領に対し、習主席は「冷戦思考を捨て、持続可能なヨーロッパの安全保障の枠組みを形成すべきだ」と応じ、ロシアの立場に理解を示したという。
2人は北京オリンピックの開幕式に先駆けて行った首脳会談でも、NATOの東方拡大とウクライナのNATO加盟、アメリカ主導の中国包囲網に反対することで一致し、共同声明を発表した。さらに、プーチン大統領は年間100億立方メートルの天然ガスを極東から中国に供給することを約束した。
ロシアは中国にとって世界で3番目のガス調達先であり、ロシアの申し出はエネルギーの供給を安定させたい中国にとって願ってもないことだ。しかし、この時期のロシアによる唐突なウクライナへの侵攻は、習主席を大いに悩ませているのではないか。
習主席にとって、今年は北京オリンピックを華々しく開催した後、秋以降の党大会で中国共産党総書記として3期目を確実にしなければならない年だが、中国国内は経済格差の拡大、急速に進行する少子高齢化、不動産会社のデフォルト(債務不履行)連発、ゼロコロナ政策などによって成長が鈍化し、食糧やエネルギーの供給も不安定になっている。西側諸国との部分的な関係改善も視野に入れていたところに、ロシアとの協調も示さなければならない。
ロシアのウクライナ侵攻に刺激された中国が台湾への圧力を強めるとの見方も出ているが、習近平政権にとって武力行使のコストとリスクは大きく、共産党の支配体制に悪影響を与えることは必至だ。相互の攻撃と制裁によってロシアにもウクライナにも甚大な被害が生じていることを見れば、習政権のそうした感触は一層強まったのではないか。
東京外国語大学の小笠原欣幸教授は『Voice』3月号(PHP研究所)で、中国にとって武力行使のハードルは高く、中国政府は国際的なイメージと影響力を毀損することも恐れており、「中国の台湾侵攻を抑止することは十分に可能」と述べる。アメリカから経済制裁を受けている中国は、台湾から半導体やIT部品を調達せざるを得ないという事情も抱えている。
さらに、小笠原教授は「有事が発生したらどうするか」ではなく「いかに発生させないか」に議論を集中させなければならないとも述べている。私も現時点において最も重要なのは、有事を発生させないための議論であり、そのために日本政府は情報戦略に平時の何倍もの資金と人を投入すべきだと考える。
先にも述べたように、中国政府は国内に多くの社会矛盾を抱え、不安定要素に対応する必要に迫られており、そうした中で、プロパガンダを強化している。プロパガンダとは、特定の思想によって個人や集団に影響を与え、その行動を意図した方向へ仕向けようとする宣伝活動である。習近平が中華民族の団結と台湾統一を強調し、「中国の夢」を国民に抱かせようとするのも、国民の不満が高まっているからこそ、夢を見させようとする側面がある。
中国政府は異論や批判に圧力を加える統治を進め、監視の体制を強化してきたが、そこにかけられるコストにも限界がある。また、インターネット上で人々が繋がるようになった時代に、毛沢東時代のような国民全体を洗脳するかのような宣伝工作は通用しない。今月、徐州市豊県で首を鎖で繋がれ監禁されていた女性が人身売買の被害に遭い、8人の子供を産んでいたことが明らかになったが、17日に発表された微信(ウィーチャット)のこの事件に関する閲覧数は39億7000万人に上ったという。家庭内暴力や性的暴行は昨今中国で深刻化しており、豊県の女性の問題を自分の身に降りかかり得た問題として捉えた人も少なくなかったのだろう。ロシアのウクライナへの軍事侵攻についても、中国の多くの人たちがSNSで反対の声を上げており、声明を出す学者たちもいる。
しかし、情報統制下で官製メディアを信じ込む人たちは一定数存在するし、「小粉紅」(ピンクちゃん)と言われるような若い愛国的ネットユーザーたちなど共産党・政府側に立つ人たち、あるいは、既得権益を手放したくない社会階層など、プロパガンダを内心疑っていても表向きは賛同する人たちもいる。
中国政府は国際政治への対応と軍事体制を増強しつつ、同時にナショナリズムを煽る傾向を強めており、偽情報が大量に溢れていても放置したり、意図的な世論誘導を行ったりしている。国際情勢が緊迫すれば、より巧妙で悪意ある情報操作が行われる可能性も否定できない。もちろん、日本でも同様の問題は見られるが、民主主義国家では、特定の権力機関が言論統制を行うことは法律的に許されず、メディアや市民社会も一定の役割を果たしている。
中国やロシアのような権威主義体制の国が情報技術を駆使して行う情報戦・世論戦に、民主主義国家はなんとしても打ち勝つ必要がある。悪意ある情報の流布に影響を受けないよう、偽情報を特定するためのファクトチェックに力を入れ、タイミングを見ながら抗議を行うなり、修正を依頼するなりすべきであろう。冷静かつ迅速に情報を分析し、自国民が誤情報や偽情報に煽られることのないように、注意喚起を行うことも重要だ。中国が力を増す中で、「台湾有事」へのリスクが高まっていることは確かであり、どのような状況にも対応できるよう、国防や安全保障に関するハードの側面で備えることも重要だが、中国の武力行使を絶対に許さないためにも、情報とコミュニケーションに関する戦略を一層強化すべきであろう。