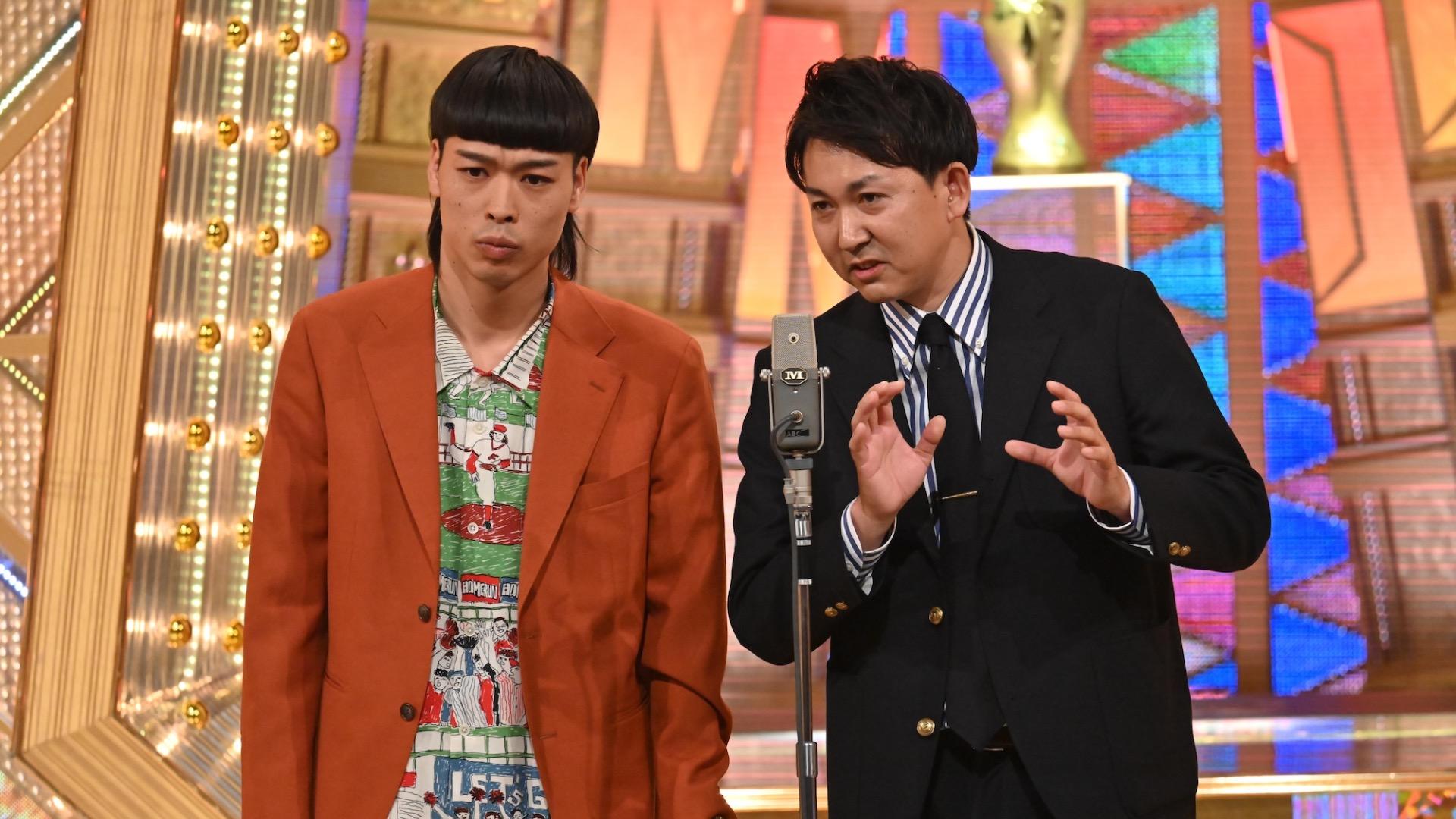『ワンダーウーマン1984』フェイクをばらまくポピュリスト批判をヒーロー映画でやることに感じる難しさ

DC映画『ワンダーウーマン』(2017年)の続編『ワンダーウーマン1984』が2020年11月18日に公開された。延期を重ねてではあったものの、コロナ禍以降数少ない洋画大作の公開ということで期待が高まっていたが、はたしてどうだったか。
■あらすじ
第一次大戦を舞台にした前作から時代が下って1984年アメリカ。文化人類学者・考古学者としてスミソニアン博物館で働くダイアナ(ワンダーウーマン)の同僚として冴えない風貌の宝石学・地質学などの専門家バーバラが現れる。
着任早々、バーバラはFBIからの依頼で違法取引の温床だった宝石店から押収された歴史的な遺物と思しきものを鑑定することに。そこに現れたのはTVで石油採掘事業についての投資を大々的に募っている実業家マックス。彼は実は宝石店襲撃を依頼した(がワンダーウーマンによって阻止された)人間であり、そのねらいはどんな願いもひとりひとつだけ
ダイアナや同僚のバーバラはそうとは知らずにそれぞれ願っていた。ダイアナは「彼(スティーブ・トレバー)にもう一度会いたい」と、バーバラは「ダイアナになりたい」と。願いの効果でパーティでダイアナが出会った男に成り代わってトレバーが1984年に現れ、バーバラはつねに衆目を集めるようになり、絶大な身体能力を手に入れていた。
バーバラに接近した石油男マックスは遺物を盗むと「私はお前になりたい」と願い、彼に触れて願いを語った者の願いを叶え――その代償としてその人間の大切なものを奪っていく存在になる。
ダイアナの願いの代償はワンダーウーマンとしての能力の弱体化であり、バーバラの代償はホームレスにもフレンドリーに接する彼女の優しい心だった。ダイアナとトレバーはマックスを追うが、男は次々と人びとの願いを叶えて政治を混乱に陥れ、代償として権力を着実に増大させていた――。
■フェイクをばらまくポピュリスト批判をヒーロー映画でやることに感じる矛盾
石油詐欺男マックスは誰が見てもわかるレベルでトランプを意識して造形されており、彼が人びとの願いを「叶えてやる!」と言って吸い上げていくことで世界の分断が加速していく。そしてそれに真実を司るヘスティアの紐を持つダイアナが立ち向かう。この構図の含意は明白だ。ハリウッド・リベラル的なフェイクニュース批判、できもしないことをぶち上げては支持率を上げるポピュリスト批判である。
お手軽に願いが叶うと思うな、フェイクに依拠して気持ちよくなるのではなく、みじめであっても真実(truth)に向き合え、と。
しかしDCがそれをやる/言うのか、ということがモヤモヤする。
そもそも観客はワンダーウーマンが活躍する姿が見たい、ふだん見られないもの、体験できないことを観たくて映画を観に行く。
そこで「うまい話に騙されるな」「口当たりのいいこと言うやつを疑え」と言われても、それはそう間違っていないだろうけれども、この映画のメッセージ自体に適用されて「こんな映画はきれいごとで真実ではない」と捉えられたら元の木阿弥では? と思ってしまう。
その昔、『新世紀エヴァンゲリオン』の旧劇場版で庵野秀明監督が観客に向けて「現実に帰れ」というメッセージを発したことを思い出してしまった。フィクションで「現実を直視しろ」「耽溺するな」と訴えることには、そもそもの難しさと居心地の悪さ、矛盾した感じがつきまとう。
ゴダールはかつて「写真が真実なら、映画は1秒間に24回真実だ」と『アルファヴィル』の中で言わせたが、フィルム時代なら「物語はフィクションであっても、映画の画面に映っていることは撮影時にそこで実際起きていたこと(真実)」という主張にも説得力はあったけれど(アンドレ・バザンの映画理論もこういう前提に立っていた)、今や「実写作品」と言ってもどこまでがCGなのかわからない映画という媒体で「真実」を訴えてもよけいに「お前が言うな」感を抱いてしまう。
■feel special論法が通じる人間だけならそもそも分断は起きない
『WW84』では安易な一発逆転願望、お手軽に願いが叶うということ、真実(人の死のような変えられない現実)を覆すことの虚偽性は否定され、ありのままの自分に向き合って日々を過ごすことは肯定される。
そういうfeel special論法(TWICEの「feel special」で歌われているような、JYP代表パク・ジニョン[J.Y.Park]がよく言う「人にはそれぞれ多様な自分らしさがあってそれを伸ばして輝かせよう」という語り)は、基本的に言っていることは正しいと思う。
しかし、この論法が通じる人間と通じない人間がいて、通じない人間は他人のことも尊重せずに差別する。通じない人間に「フェイクだから、その願いは取り下げて消してくれ」と言ったところで無意味である。それがゆえに分断は起きているのではなかったのか。
それに、ダイアナの場合は願いを捨てれば人並み外れた能力が戻ってきたわけだが、もともと恵まれていなかった人間は願って手に入れたものを安易に取り下げるはずがない(実際「ダイアナになりたい」と願ったバーバラの抵抗はきわめて激しいものだった)。
……と、ごちゃごちゃ書いたものの、80年代映画的な明るさに満ちた前半部分、カイロでのカーアクション、そしてダイアナの喜びと悲哀に満ちたロマンスとしてはすばらしかった。
死んだはずの人間が生前の姿そのままで現れて再び恋する。物語の魅力はそういうありえないことを描ける点にある。「真実に向き合うことが、待ち望んでいた関係を終わらせてしまうというジレンマを描いたフィクション」として秀逸な作品だった。