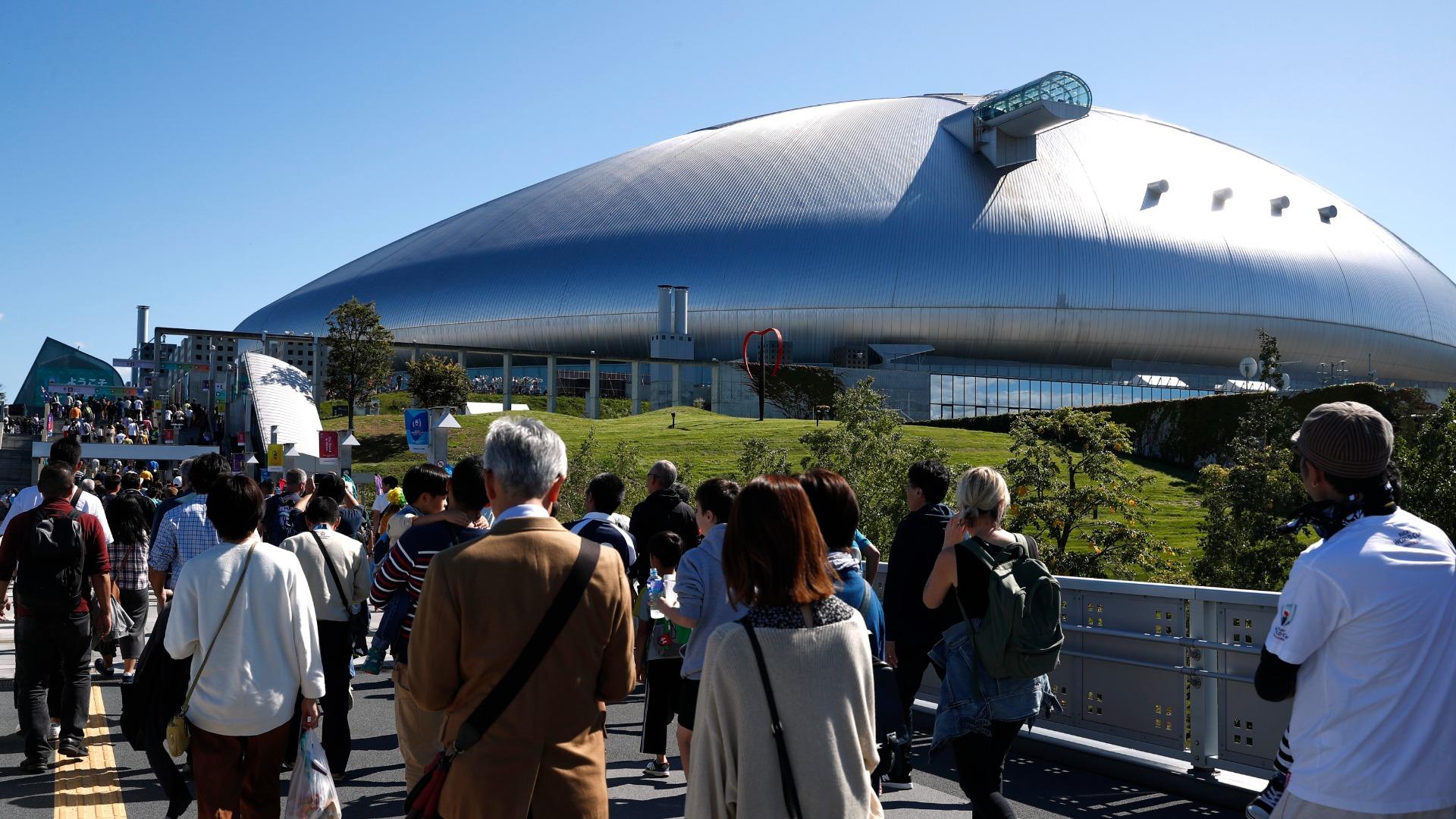【深読み「鎌倉殿の13人」】源義経の追討に舵を切った、頼朝の真意を考える

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の第19回では、源頼朝と義経との確執が描かれていた。頼朝は義経の所領を没収し、伯父・行家の追討の命を下したが、その点を詳しく掘り下げてみよう。
■源義経の伊予守任官
元暦2年(1185)6月13日、源頼朝は弟の義経の所領(平家から没収した24ヵ所の所領)をすべて取り上げた。これにより、両者の関係が破綻したとみるのが普通である。しかし、その約2ヵ月後、頼朝は奇妙な行動に出た。
同年8月16日、朝廷は平家追討の恩賞として、志田義竜を伊豆守、大内惟義を相模守、足利義兼を上総介、加々美遠光を信濃守、安田義資を越後守に任官した。それだけではない。すでに検非違使だった義経も、伊予守に任官されたのである。
しかし、すでに義経の所領を没収した時点で、両者の関係が破綻したと考えるならば、いささか理解に苦しむ行動である。なぜ、頼朝は義経の伊予守任官を認めたのだろうか。
■伊予守任官の背景
義経が伊予守に任官した背景については、さまざまな見解があった。まだ、6月の時点で、頼朝は義経の追討を決定しておらず、逡巡した挙句、伊予守の任官を認めたという説がある。いかに敵対したとはいえ、兄弟の情愛が残っていたということになろう。
もう一つは、朝廷との関係である。義経が平家追討で大きな軍功を挙げたのは、誰の目にも明らかだった。おまけに、義経は後白河法皇の信任が厚く、その功を否定することもできなかったので、頼朝は政治的な配慮から伊予守の任官を認めたというのである。
そして、近年になると、頼朝は義経が一ノ谷の戦い後に無断で任官したことを怒っていなかったとしたうえで、平家追討後に義経が鎌倉に来た時点では、まだ両者の関係は決定的に破綻していなかったという。
関係が破綻する原因になったのは、義経が伊予守に任官したにもかかわらず、検非違使として京都に残り、鎌倉に来なかったからだったという。これが頼朝への敵対行動とみなされたのである。義経は、頼朝の配慮がわからなかったということになろう。
いずれの説もユニークなものであるが、私としては二つ目の説がわかりやすいように思う。頼朝は義経との関係が破綻したものの、後白河の仲介により、伊予守任官を認めたのではないか。
頼朝は朝廷との関係を重視していたのだから、容易に断りにくかったに違いない。そのうえで、義経が自らに従うことを期待した。
しかし、これが裏目に出たのか、義経は決して頼朝に従順にはならなかった。義経にすれば、このままではいずれにしても、頼朝と対立することになると考えていた。あるいは、すでに頼朝から追討される立場にあった行家から、「ともに戦おう」と誘われたのかもしれない。
伊予守任官以後、義経は考えをめぐらせた挙句、ついに行動に出た。
■頼朝追討の院宣
元暦2年(1185)10月18日、後白河は義経に対して、頼朝追討の院宣を与えた。それ以前、義経は伯父の行家と盛んに連絡を取っていたという。義経は、頼朝による伊予守任官の真意を測りかねた可能性がある。
同年10月11日、義経は後白河に対して、伯父行家が頼朝と戦うことを思い止まらせようとしたことを奏聞し、どうすべきかを訴えた。後白河は「行家を思い止まらせるように」と言うだけだった。
同年10月13日、義経は再び後白河に対して、行家を思い止まらせることはできないので、自身も行家に与同して、頼朝と戦うことを告げた。その結果、与えられたのが頼朝追討の宣旨なのだ。むろん、後白河は頼朝を討ちたいと思ったのではなく、義経に押し切られたということになろう。
■むすび
しかし、頼朝は朝廷の意向を尊重したが、信用していなかったのかもしれない。同年10月17日、頼朝の命を受けた土佐房昌俊が京都に忍び込み、義経の邸宅を襲撃したが、これは失敗に終わった。義経は危うく難を逃れたが、もはや両者の対決は避けられなくなっていたのだ。