「どうする家康」大御所時代の徳川家を支えた家臣団とは
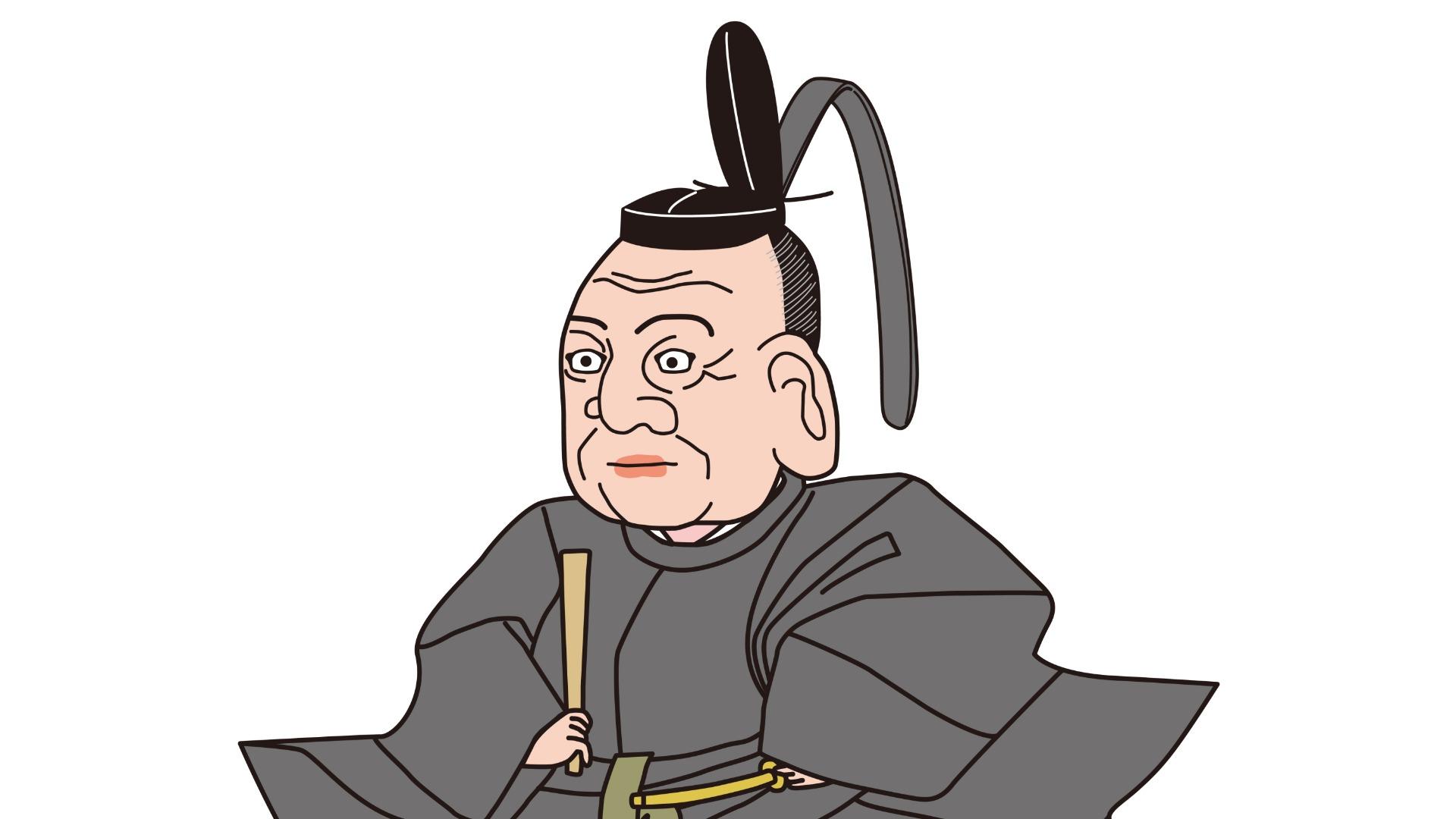
大河ドラマ「どうする家康」の主人公・徳川家康は大御所政治を行ったが、その体制を支えた家臣団について、詳しく考えてみよう。
慶長12年(1605)、家康は駿府城(静岡市葵区)に移り住み、江戸城の秀忠とともに国内支配に当たった。この政治体制を大御所政治といい、配下の有能な家臣団が2人を支えた。
江戸城で秀忠を支えた家臣は、大久保忠隣以下、酒井忠世、土井利勝、安藤重信ら三河時代以来の譜代の家臣だった。彼らは秀忠の配下にあって、江戸幕府の土台作りに携わった。
彼らは将軍政治に関わり、年寄(のちの老中)として重用された。その下には、留守居を酒井忠利が、老中(のちの若年寄)を水野忠元、井上正就が、町奉行を米津田政、島田利正の2人がそれぞれ担当した。こうして江戸幕府の職制は、少しずつ整備された。
また、青山忠成、本多正信、内藤清成らは、関東総奉行という江戸市中を含む関東領国を管掌する職を担当していた。ただし、正信に関しては、駿府城の家康の命令を受けて、その命を実行に移す役割を任されていたといわれている。
家康配下の家臣団は、4つのグループにカテゴライズされている。まず、第1のグループである。本多正信・正純父子、安藤直次、成瀬正成、竹腰正信は、新参の譜代といえよう。近習出頭人としては、板倉重昌、松平正綱、秋元泰朝らが存在した。
第2グループは、僧侶の南光坊天海、金地院崇伝、儒学者の林羅山らのブレーン集団である。金地院崇伝は、「黒衣の宰相」と恐れられる存在だった。
第3グループは代官頭(伊奈忠次、大久保長安、彦坂元正ら)、豪商(茶屋四郎次郎、後藤正三郎ら)で構成されており、特に豪商らは財政面で江戸幕府を支えた。
最後の第4グループは、イギリス人のウィリアム・アダムス(三浦按針)、オランダ人のヤン・ヨーステンら外国人たちである。
江戸幕府を支える多彩な家臣団は、幕藩体制の整備に邁進した家康、秀忠にとって欠かすことができなかった。こうして江戸幕府の基礎は、この頃に形成されたのである。










