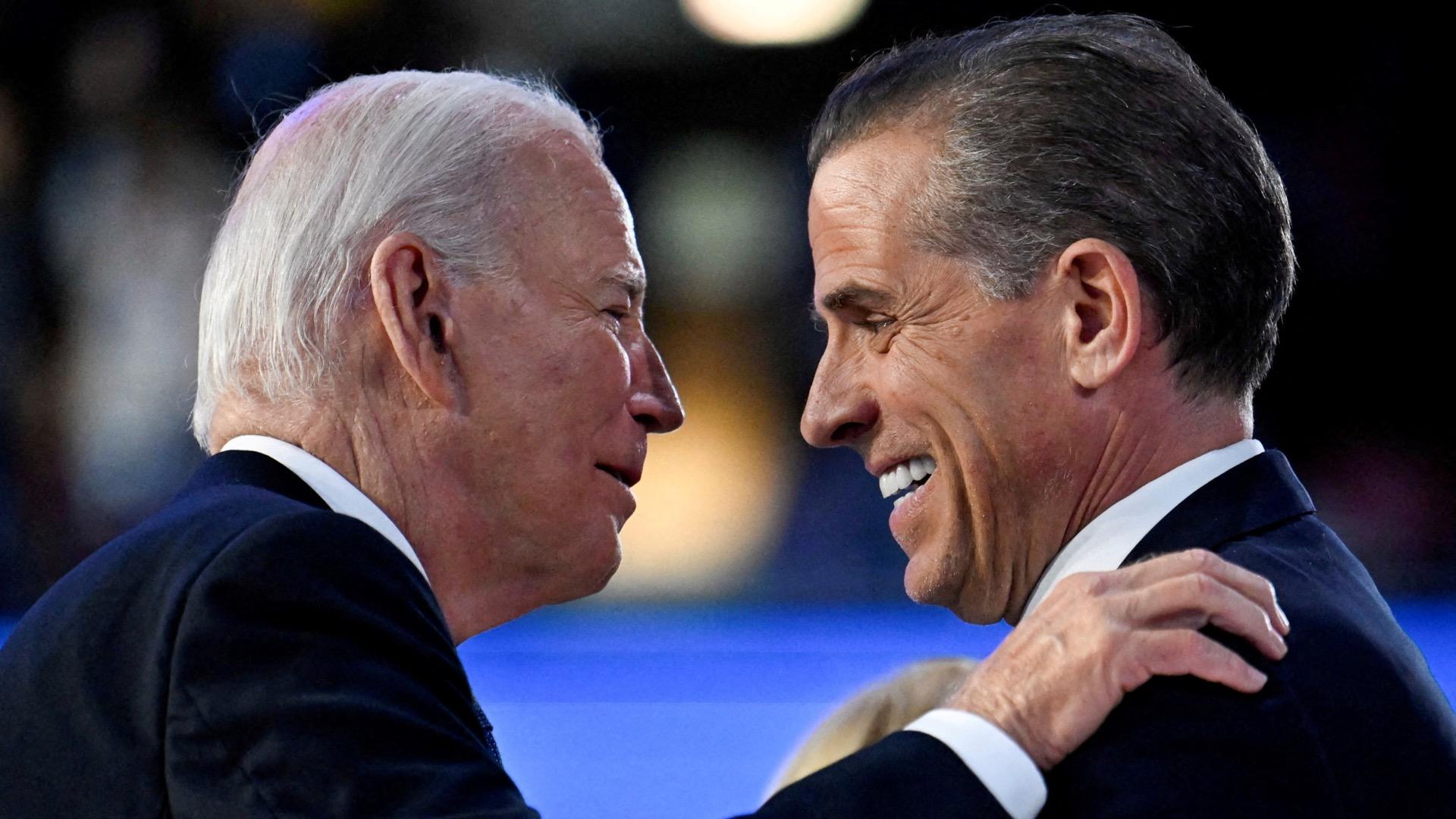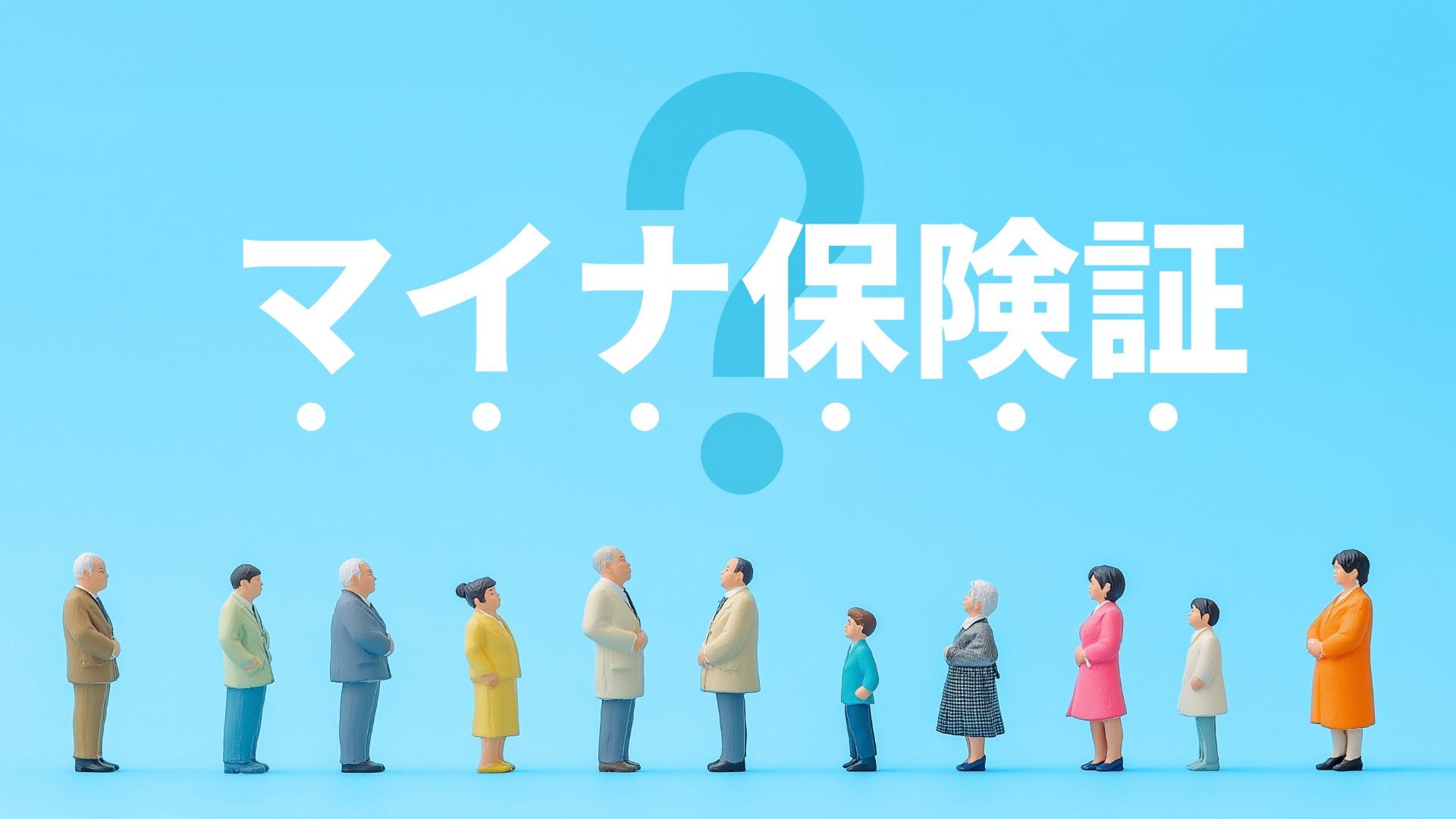子どもが嘘をついたときどう対応する?成長のチャンスに変わる親の対応を幼児教育講師が教えます!

幼児教育講師のTERUです。
日々の子育て本当にお疲れ様です!
今日は『嘘をつく子どもへのオススメの対応』というテーマでお話しします。
【嘘をつくのは本当に悪いことか?】
まずは私が最も重要だと考えているこの話からさせてください。
おそらく多くの方は、嘘というと良くないマイナスのイメージを持たれているのではないかと思います。
ですが、嘘は子どもの成長過程でとても大切なことの1つであり、脳が高度に成長してきた証拠です。
嘘というのは相手の考えを読んで、それを論理性を持って説明できないとつけないものです。
そしてその嘘の精度は年齢によって変化していきます。
有名な実験で、子どもに箱の中身を見ないようにと伝え、その後1人になったときにこっそり見てしまった子どもがどういった反応をするのかというものがあります。
「箱の中身を見ていないよね?」と子どもに聞くと、ほとんどの子が「見ていない」と嘘をつくのですが「箱の中は何が入ってた?」と聞くと、3歳くらいまでの子は「〇〇が入ってた」と素直に言ってしまうそうです。
この実験の結果からも、3歳くらいまでにすでに嘘をつく意識は持っているものの、それをつじつまが合うように答える力を持っていないということが分かります。
なので、そのくらいの子どもたちはすぐにバレるようなかわいい嘘をついてしまうわけです。
これが4〜5歳になると、徐々に上手な嘘のつき方をするようになっていき、それは紛れもなく脳が健やかに成長している証拠なんですね。
実は、人は生まれながら嘘をつくように脳がプログラムされているといわれています。
様々な動物の研究から、自分の生命を守るために相手を騙すような行動は必要な能力として見られますし、人間も同じなのだそうです。
もちろん良くない嘘はちゃんと教えていってあげる必要はありますが、嘘=完全な悪!その子に何か問題がある!ではなく、
- 『成長の証』
- 『嘘をついてしまうのはしょうがないこと』
このように考え、まずは温かく見守ってあげたいですね。
では、ここからは実際嘘をつかれたときにどう対応したら良いのかをお話ししていきます。
【嘘への対応をするときの目的は何?】

私は、子どもの嘘への対応をするときに大切なのは『目的を明確にする』ということだと思っています。
子どもが嘘をついてしまったとき、親として最終的にどうなることを思い描きますでしょうか?
- 嘘をついたことを白状させること
- ちゃんと謝らせること
- もう嘘をつかないと約束させること
色々あると思うのですが、私は
『子どもの精神的な成長に繋がるきっかけづくりをする』
ということが重要だと考えています。
この目的を達成できれば、最終的に子どもがちゃんと自分が嘘をついたことを認めるか認めないかはどっちでも良いですし、最悪謝れなくても良いと思っています。
大切なのは、その嘘の経験を通じて成長できるきっかけを与えてあげることです。
それが達成できれば、その他の結果は重要ではありません。
では、子どもが成長していくためには何をすれば良いでしょうか?
私は親ができることは2つあると思っています。
1.子どもに「信じているよ」というメッセージを伝える
子どもだけでなく、人は『誰からも信じてもらえない』という経験ほど悲しいことはありません。
反対に『人に信じてもらえた』という経験ほど勇気の出ることはありません。
そういう意味で考えると
『嘘をついた自分でも親は信じてくれた』
嘘をついてしまった経験を通じてこのように感じることができれば、子どもは強い安心感を得ることと同時に「こんなパパママを悲しませちゃいけない」と心の底で思うのです。
人は、日頃から信じてくれる人の言葉はまっすぐ受け止められるものですから、そんな親からの信頼を感じることで、徐々に嘘をつかない自分になっていけるんだと私は思っています。
「信じている」と伝えるには
では、具体的に何をすれば良いでしょうか?それは
『子どもの言い分を最後まで聞き、子どもの想いを聴くことを意識すること』
これだけです。
メッセージといっても、何かを伝えるというより姿勢で信じていることを伝えるというイメージですね。
子どもの嘘は様々ですが、どんな嘘でも共通して大切なのは最後まで子どもの言い分を聞くことです。
子どもの言い分を最後まで聞くと、子どもなりの『想い』や『事情』が見えてきます。
例えば、テストの答案用紙を隠してしまった子どもにいきなり「何でそんなことをしたの!」と叱るのではなく
「どうして答案を隠してしまったのかな?」
と尋ね、最後まで子どもの言い分を聞いてあげると
「お父さんに怒られるのが嫌だったんだ」
「お母さんに悲しい想いをさせると思ったから」
などといった子どもの想いが見えてきます。
「怒られるのが嫌」という想いが見えてきたら
「テストの点数が悪かったくらいで怒らないから安心して。それよりも、嘘をつかれてしまう方がお父さん悲しいな!」
と伝えれば良いでしょうし、
「お母さんを悲しませたくない」という想いが見えてきたのであれば
「そっか、お母さんのことを気遣ってくれたのね。ありがとう。そんな〇〇ちゃんの優しいところお母さん好きだよ。でもお母さんは、〇〇ちゃんのテストの点数が低いことより、嘘をつかれる方が悲しいな!」
などと伝えると良いかと思います。
想いを聞く前に頭ごなしに叱ってしまっては、子どもは信じてもらえていると感じませんし、心を閉ざしてしまう可能性もあります。
幼児期や小学校低学年の嘘は半分以上、悪気がある嘘ではなく、人を喜ばせようと思ってつく嘘だったり、悲しませたくないと思ってついてしまう嘘だったりします。
その想いを聞いて、そこに人への思いやりを感じたら感謝を伝え、正してあげる必要があると思えば、それは良くないと教えてあげれば良いんです。
子どもも想いをちゃんと聞いてくれた上での対応であれば納得ができますし、自分のことを信じてくれているとちゃんと感じることができますよね。
1つだけ注意が必要なのが、子どもを信じるということは、子どもの言っていることを全部肯定して、「〇〇ちゃんの言っていることは全部正しいよ」と伝えることではありません。
明らかに間違っていることはちゃんと言わなくてはいけません。
親から最終的に「〇〇ちゃんの言っていることは正しくないよ」と伝えられても、そこまでにちゃんと話を聞いてくれて、想いに耳を傾けてくれていれば、ちゃんと『信じているよというメッセージ』は伝わっているものです。
2.視野を高く広くしてあげるメッセージを伝えること

嘘をついた子どもへかける言葉としてよくあるのが『嘘をつかれた側の気持ち』だと思います。
お母さんについた嘘であれば
「お母さん嘘を言われると悲しい気持ちになるよ、でも正直に話してくれて嬉しかったよ」
お友達に嘘をついてしまったときは、
「自分が〇〇ちゃんだったらどんな気持ちになる?」
このように相手の立場になって考えさせることはもちろん大事です。
ただ5歳くらいまでは脳の仕組みの関係で相手の立場に立って考えることが難しかったりするので使い方は少し考えた方が良いかもしれませんが、それに加えて、もう1つお子さんの成長のために伝えてほしいことがあります。
それが『誠実であることの素晴らしさ』です。
よく嘘に対して「嘘は悪いことだからダメだよ」といったメッセージを子どもに送ることがありますが、それよりも「誠実で正直あることは素晴らしい!」ということを子どもに伝えていく方が、効果的なメッセージなのではないかと私は考えています。
なぜかというと「嘘は悪いことだ」というメッセージはマイナスの表現で、「誠実であることは素晴らしいことだ」というメッセージはプラスの表現だからです。
マイナスな言葉で動機づけをされるよりも、プラスでポジティブな言葉で動機づけされる方が、人は頑張れるものです。
もちろん嘘は悪いことというのは間違ってはいないので、伝えてはいけないことではありませんが、それに加えて「誠実で正直あることは素晴らしい!」というプラスのメッセージも伝えられると、きっとお子さんの中に嘘をつかないで正直でいることに対する良い動機づけになっていくと思います。
「誠実で正直あることは素晴らしい!」と伝えるには
具体的には、子どもの嘘への対応の最後に
「正直であることは、人してとても大切なことなんだよ。正直な人は周りのお友達からも好かれて、良い人間関係を作れるし、周りの人と仲良くできれば楽しいことも増えていくよね。だからいつも誠実で正直でいようね!」
と伝えていきましょう。
「嘘は悪いことだからダメ」というメッセージだけでは「嘘をつかない人間になろう」という非常に視野の狭い考えしか学ぶことはできません。
ですが「誠実で正直あることは素晴らしい」という、もっと広く高い視野で考えることで、大きく精神的な成長につながっていきます。
【子どもが嘘をつかない6つの環境の点検】

ここまで嘘への対応方法をお話ししてきましたが、最も大切なのは嘘をついたときの対応ではなく、子どもが嘘をつかないような環境づくりです。
多くの場合、子どもが嘘をついてしまう原因は環境にあったりします。
なので、子どもが頻繁に嘘をついてしまう場合は、子どもが置かれている環境を点検してみるのが良いかもしれません。
1.親が小さい嘘をついていないか点検
やはり親が頻繁に嘘をついているような環境である場合、子どもはその姿を吸収して、嘘をつくようになります。
忙しい子育てでは、無意識のうちに「子どもだから」と大人都合の嘘をついてしまっていることもあるので、ぜひちょっとだけ点検してみてほしいなと思います。
2.結果主義になりすぎていないか点検
例えば、子どもがテストの結果について嘘をつくことが多いような場合は、親が結果を求めすぎているのかもしれません。
100点取るのが当たり前とか、点数が低いことを過度に叱ったりしている場合、子どもは自分を守ろうと嘘をつきやすいものです。
結果だけではなく、過程を褒めたり、結果が悪いことを叱りすぎていないか点検してみましょう。
3.完璧主義になっていないか点検
親が完璧主義すぎて、身の回りの物の位置やルールなどを細かく日頃から子どもに指示したり、こだわっていると、子どもは自分がそうできなかったときに自分を守ろうと嘘をつきます。
キチッとするのは良いことですが、行き過ぎると子どもの嘘を引き出してしまうこともあるんですね。
4.正直に言って怒られる環境になっていないか点検
今まで正直に言って叱られた経験が多いと子どもは自分を守ろうと嘘をついてしまうものです。
当然ですが、叱られるのに本当のことは言いたくありません。
子どもが正直に話してくれたら認めて受け入れてあげられると良いですね。
5.最近コミュニケーション不足になっていないか点検
子どもが頻繁にちっちゃな嘘をつく場合、親の気を引きたいということが原因かもしれません。
「どうしても忙しくてなかなか子どもとの時間が取れていない」という状況があるのはしょうがないことだとは思いますが、その可能性があると感じるようであれば、皆さんのできる限りできる範囲で良いので、次の方法を試してみてください。
- 子どもの話をちゃんと聞いたり、会話する時間を増やす
- 抱っこや抱きしめるなど体が触れ合うスキンシップを増やす
- 子どもの目を見て話をする
- 一緒にお風呂に入る機会を多くする
- 褒める機会を多くする
- 挨拶をしっかりしたり、子どもの名前を多く呼んであげる
- 「大好きだよ」と伝えていく
6.嘘が良くないことだと認識できる環境の点検
稀ではありますが、嘘というものが良くないことだと認識できていない場合もあります。
そんなときの私のオススメは『しつけ絵本』です。
もちろん親が直接伝えても良いのですが、親が「嘘は悪いこと」と伝えるよりも、絵本の世界に入り込んで嘘が悪いことだと感じていく方が何十倍も効果があったりします。
ちなみに私のオススメはローラ・ランキンさんの『あたし、うそついちゃった』です。良かったら読んでみてくださいね。
いかがでしたでしょうか?
お子さんが嘘をついたときにどうしたら良いのか。
ご対応の少しの参考になれば幸いです。
皆さんの子育てを応援しています!
オススメの関連記事はこちら
動画でより深く学びたい方はこちら