【「麒麟がくる」コラム】三木城主・別所長治はなぜ織田信長を裏切ったのか。完全スルーの三木合戦を考える
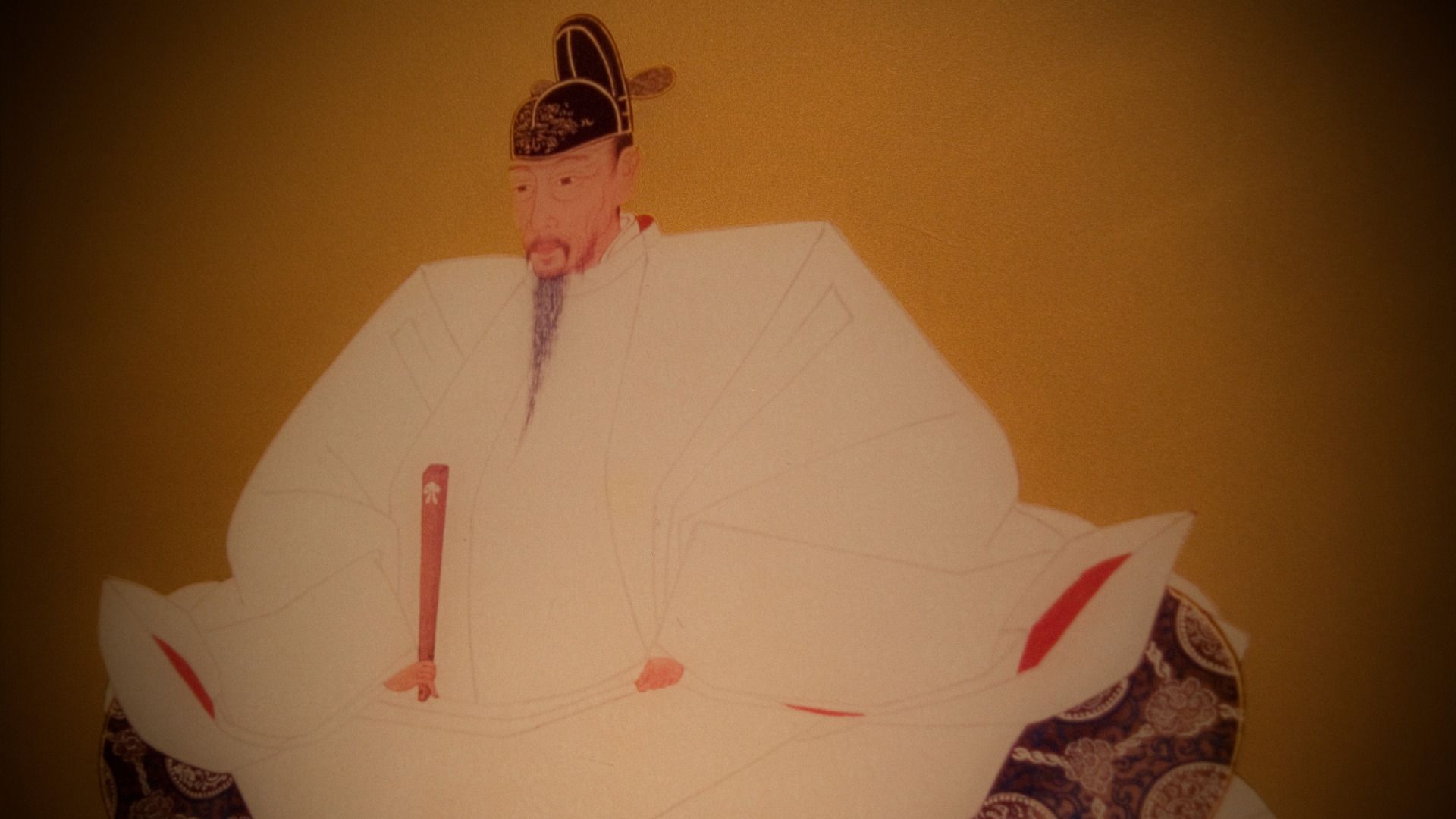
■明智光秀も出陣した三木合戦
NHK大河ドラマ「麒麟がくる」のなかで、明智光秀も出陣した三木城の攻防が完全スルーだった。今回は織田信長も羽柴(豊臣)秀吉も別所長治の裏切りに驚倒したという、三木合戦を取り上げておこう。
■三木合戦とは
天正6年(1578)3月からはじまった三木合戦は「三木の干殺し」と称され、長期間にわたる兵粮攻めで知られる。同時に、三木城(兵庫県三木市)周辺に数多くの付城を築いた合戦としても、大変著名な合戦だ。
織田信長から中国計略を命じられた羽柴(豊臣)秀吉は、三木城主の別所長治をもっとも頼りにしていたが、事態は思わぬ方向に展開する。同年3月、突如として長治は秀吉に叛旗を翻し、毛利方に背いた(『信長公記』など)。では、別所氏はどのような理由があって、信長に叛旗を翻したのだろうか。
別所氏が信長を裏切った理由は、古くから多くの説が提示されてきた。そのほとんどは、『別所長治記』などの軍記物語に拠るものが多い。
『別所長治記』によると、同年3月7日に秀吉が播磨国糟屋館(兵庫県加古川市)を本陣とし、別所氏家臣の別所吉親と三宅治忠と軍議を催した。その際、延々と三宅治忠は自分の作戦を開陳した。
しかし、秀吉はその説明を聞いたあと、治忠の言葉を遮るように「毛利氏の大軍に対して、わが軍は小勢であることから、何度も奇襲戦法を仕掛けるのが肝要である」と説いた。
この作戦に対して、治忠は反論を行ったものの、秀吉からは完全に無視された。この軍議の結果、別所氏サイドには強い不満だけが残ったのだ。あまりに横柄な秀吉の態度に、別所方は怒りを禁じえなかった。交渉役を務めた吉親と治忠は、別所家内部で評定を催し、事後処理を検討した。
秀吉の態度を子細に分析した別所方では、自分たちの意見が無視されるのは、信長の謀計であるとの結論に至った。さらに、先鋒として別所氏が西国征伐を完遂したのちには、秀吉に播磨が与えられると予想した。
そして、信長の謀計に乗ることは思慮が浅いとの意見に集約され、別所方は最終的に信長への謀反を決意し、これまでに例を見ない長い籠城戦を迎える。
■『播州御征伐之事』などの記述
ところで、ほかの後世になった書物では、どのような理由が示されているのであろうか。
『播州御征伐之事』によると、長治の伯父・吉親は佞人(口先が上手で、心のよこしまな人。邪曲で奸智にたけた人)として描かれており、長治に対して「秀吉が播磨で自由な働きをすると、ついには長治に災いをもたらす」と讒言したという。
この話を信用した長治は、信長に叛旗を翻し、三木城に籠城することを決意。このとき、もう一人の伯父・重棟は、秀吉に味方することを決めた。
ほかにも『三木合戦軍図縁起』によると、「名門の別所氏が出自すら判然としない秀吉には従えなかった」という説があるが、実際に別所氏がそう思っていたのかは不明である。
以上の理由については、俗説として退けるべきであり、改めて一次史料から検討を進める必要がある。改めて、別所氏が謀反を起こした理由を考えてみたい。
■別所氏が裏切った真の理由
天正5年(1577)12月、秀吉は別所重棟(長治の伯父)の娘と黒田官兵衛の子・長政との縁談を勧めた(「黒田文書」)。のちに重棟は長治のもとを去り、秀吉方に味方した。つまり、この段階において秀吉は、別所氏内部での家中の混乱を見抜き、重棟を味方に引き入れた可能性が高いといえよう。
天正初年段階の別所氏は、青年だった長治を伯父の吉親と重棟が支える体制を取っており、意思決定に際しては重臣層の意見も重視された。その中で別所家では意思統一が出来ず、家中を去る者が出ても不思議ではない。ましてや重棟は秀吉配下の黒田氏と姻戚関係を結んでおり、別所氏には隙が生じていた。
翌天正6年(1578)3月、本願寺は別所氏以下、高砂の梶原氏、明石の明石氏など播磨国内の有力な国衆が信長のもとから離反したことを把握した(「鷺森別院文書」)。単に、別所氏は単独の判断ではなく、周辺の有力な領主とも十分に情報交換を行い、信長に叛旗を翻すという重要な決断を行ったのだ。
むろん別所氏が期待していたのは本願寺だけではなく、足利義昭による積極的な調略があった。同年3月、義昭は自らの離反工作が成功し、別所氏らが味方になったことを喜んだ(「吉川家文書」)。こうして長治は、毛利氏・足利氏に与し、信長と戦うことになった。
当時、秀吉が有利に戦いを展開させていたが、毛利、足利、本願寺の諸勢力は激しく抵抗し、まったく予断を許さない状況にあった。別所氏は絶えず毛利氏らの動向に注意を払いながら、情勢を探っていた。決して別所氏が一時的な感情で謀反を起していないことは、明白だ。
別所氏の信長への謀反については、二次史料の記述に拠っていたが、一次史料をもとに考えるとそうでないことがわかった。別所氏が信長に反旗を翻した理由は、(1)別所氏が当時の情勢を冷静に判断した結果であること、(2)義昭による熱心な離反工作があったこと、の2点に集約されよう。










