6年前に自らの提案で国会で決めた区割りの見直しを迫る衆院「10増10減」反対論のおかしさ
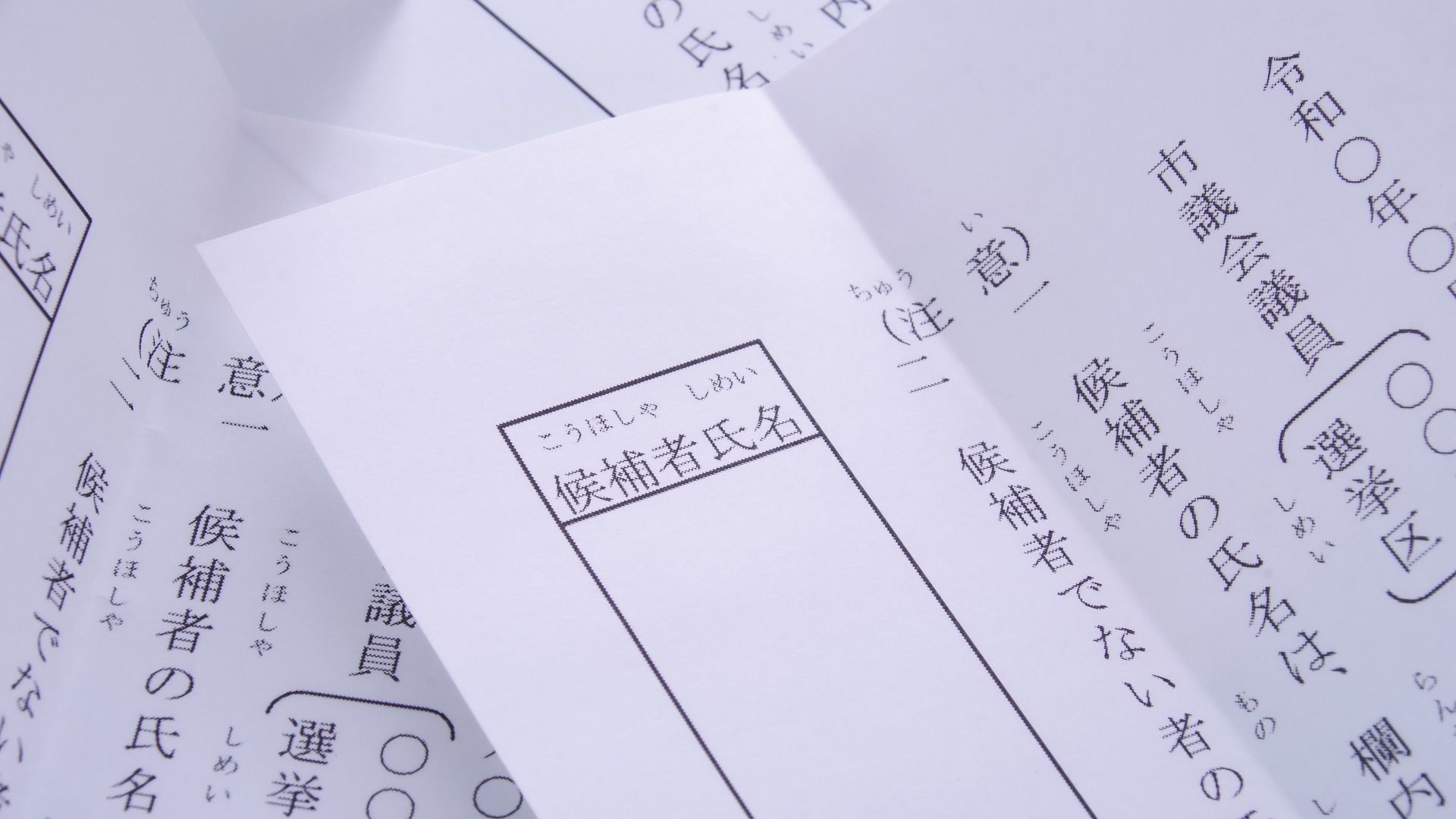
「1票の格差」を是正する新方式「アダムズ方式」がいよいよスタート。2016年に国会で可決成立した改正法に基づき衆議院議員は「10増10減」が必要と計算されています。既定路線にもかかわらず、このところ法案を出した側の自民党の一部議員から反発の声が出てきました。さすがに無理筋とはいえ相当規模に広がりつつあり政局になる兆しもうかがえるから穏やかではありません。何がどうおかしいのかを考察してみます。
16年に自民案で決まった新方式
物語の始まりは2015年の最高裁判決。14年に行われた総選挙で衆議院小選挙区における「1票の格差」(2.13倍)を「違憲状態」と判断しました。これで3選挙連続です。「違憲状態」を「合憲」か「違憲」かにカテゴライズするとしたら「合憲」。この問題で違憲とされるのは
①著しい不平等がある
②不平等を是正するための合理的期間を過ぎている
を共に満たした場合。「違憲状態」は主に①のみを認定しています。ゆえに「②まで満たしたら違憲だよ」とのメッセージでもあるのです。
分立している3権の「司法」トップが「立法」府のあり方を「是正しないと違憲だ」と指摘する以上、放置したら大変。そこで16年、与党(自民・公明)が示した「アダムズ方式」に基づく区割り導入を含む改正法案が賛成多数で成立しました。
この時点で決まったのは新方式の採用は20年の国勢調査を待って区割りを配分する、でした。実現は22年以降。すでに「著しい不平等がある」状態をある程度経過し、さらに6年後に新方式を実施では衆議院議員の任期満了4年を踏まえても遠すぎるため、当面は新方式を準用した「0増6減」と改めます。これで17年総選挙(格差1.98倍)に臨みました。
当時からわかっていた「10増10減」程度の変更
この選挙を最高裁は18年、「合憲」と判断しました。「0増6減」もさることながら国会がアダムズ方式での格差是正を決めたのも評価したのです。
時が過ぎるのは早いもの。「20年の国勢調査の結果、22年頃から新方式にする」と決めた16年の時点では「まだまだ先の話」とたかをくくっていた(?)ところ、21年11月には国勢調査の確定値が発表され、合憲を得る目安である格差2倍未満とするには「10増10減」が必要だとわかりました。
これぐらいになるのは16年段階でわかっていたレベル。その時点での国勢調査(15年調査)でアダムズ方式を当てはめたら「9増15減」が必要で、そこから「0増6減」したから「9増9減」は避けられません。年月を経た分だけ選挙区の有権者数差が若干広がったというだけでしょう。
後は根拠法を持つ衆議院議員選挙区画定審議会(区割り審)が粛々と検討して今年6月までに岸田文雄首相へ新たな区割り案を勧告。その元で恐らくは次の総選挙(解散があり得るため断言はできない)から実施という段取りで何の問題も起きないはずです。16年も今も改正法案を出した与党は同じ自公。阻む理由などありません。
期限がやってきただけ
念のため時系列にここまでの経緯を示すと以下の通り。
・15年の最高裁判決が先の総選挙における「1票の格差」を3連続で「違憲状態」と認定
・16年の法改正で自公の提出した新方式を含む改正法案が可決成立。20年の国勢調査の結果を待って実施するという内容。その時点で「9増9減」ぐらいになるのは分かりきっていた。
・この努力を多として最高裁は18年、17年総選挙の結果を「合憲」と判断
・21年に20年国勢調査の確定値が出て「10増10減」が必要だとわかった
ゆえに「10増10減」は自公が16年にずいぶん先の改正として提案し、最高裁も評価し、ついにその期限がやってきただけ。行わない理由などないのです。
反対する勢力の言い分がおかしい7つの理由
ところが昨年末から細田博之衆議院議長が「地方の声が届かなくなる」、二階俊博元自民党幹事長が「政府の方針は間違いがある」などと重鎮が否定的な発言を始め、相当数の自民党議員も国会内で会合を開いて似たような主張をしています。こうした動きは二重三重にもおかしい。以下に列挙します。
①憲法で国会議員は「全国民を代表する」と定めている。どこの選挙区出身であろうとも。定数が減る地方の声が届かくなるのが現実としたら現国会議員が「全国民を代表」していないと自白するに等しい。
②「1票の格差」問題は憲法が国民に保障している「法の下の平等」に反する恐れがあるから。選挙で面積や森や湖の代表を選んでいるわけではない。
③「政府の方針」でもない。なるほど国会で審議される法案の8割は内閣(=政府)が出していて立法府の判断を仰ぐという形式を取る。しかし国会議員の身分に関する法改正は主務官庁がないので議員立法だ。すなわち16年の改正は立法府の構成員(=国会議員)のみの発案と決定で政府はその通り実施して当然である。
④「地方の声が……」といった異論に理があったとしても、それは16年の段階でわかっていた。にもかかわらずアダムズ方式採用を決定した。
⑥司法トップの最高裁も新方式導入を決めたからこそ選挙結果を合憲とした。根底を覆したら司法府に虚偽の印象を与えたに等しい。
⑦16年に可決した法案を出したのも、その実行を今、一部で反対しているのも自民党である。
そもそも新方式自体が地方に有利なのに
今のところ連立与党の公明でさえ自民のこうした動きに否定的で、自民党内でも「今さら変更はあり得ない」とする者も多数。岸田文雄首相も「現行の法律をしっかり履行し」(=法律は守る)という当たり前すぎる発言で新方式を進めようとしています。
そもそも現在の小選挙区比例代表並立制の導入時に格差2倍以内にするとし、区割り審を設置したのも自民党政治改革推進本部の案に基づいています。中選挙区制度からの移行時、激変緩和措置として都道府県にまず1人を割り振った上で残りの定数を比例配分する(=人口の少ない県が多めとなる)「1人別枠方式」についても2011年の最高裁判決が「廃止を求める」と改革を促してなくなりました。
アダムズ方式自体、小数点以下を切り上げるものだから人口の少ない県に有利ともみなせます。たった1人しか有権者がいなくても1議席は確保できるので。厳しくいえば改良型の1人別枠方式とも。要するに地方が若干多めの定数が得られる仕組みなのです。それですらダメとはどの口でいうのかとあきれるしかありません。
全然違うアメリカの選挙制度の歴史
アメリカの上院は人口の数にかかわらず州に2人としている。これを見習えという声もあります。主に参議院の改革案として出てくるのですが、国の成り立ちがまったく異なるのを無視したトンデモ論に近い発想でしょう。
アメリカは連邦を構成する際に当時の独立13州から代表をいかにして選ぶかでもめました。州と連邦のどちらを重視すべきかと。結果的に上院は「州(=「国」の感覚に近い)の代表」を送るのだから同数。下院は連邦の代表だから人口比例となったのです。日本の都道府県数47に決まったのは19世紀末。知事をすべて内務大臣が任命する中央集権の上下関係にありました。歴史が全然違うのです。










