国の好調な税収増など「インフレタックス」が生じているが、どのように対応すべきか
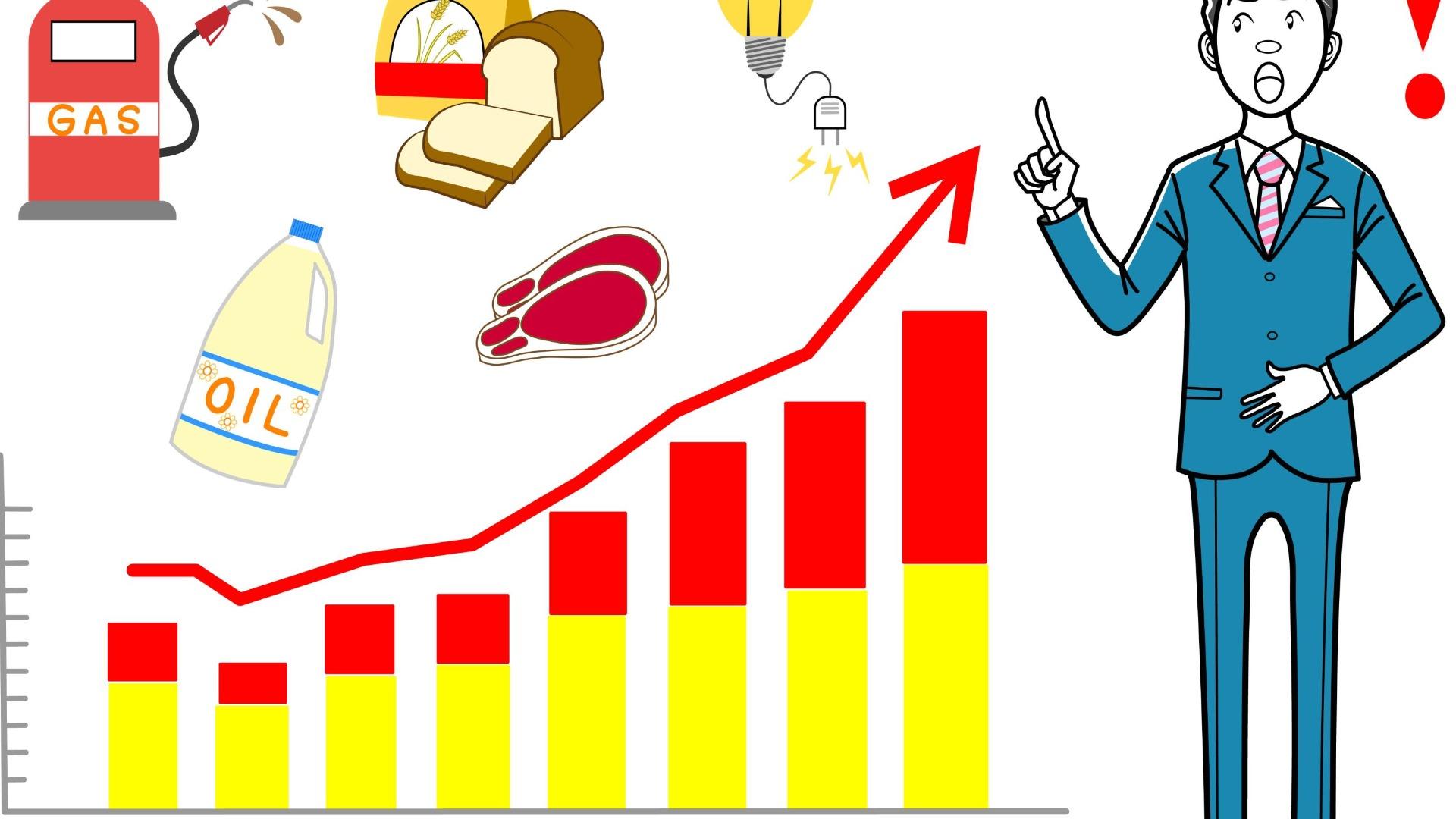
わが国の税収が好調だ。ここ3年間の一般会計税収を見ると、2020年度が60.8兆円、21年度が67兆円、22年度が71.1兆円(決算額)と、この2年間で10.3兆円伸びている。増収の内訳は、所得税が3.3兆円、法人税が3.7兆円、消費税が2.1兆円、相続税が0.7兆円とバランスよく伸びている。23年度も70兆円を超える税収が予想されている。
背景にあるのは、消費者物価や国内企業物価の上昇、つまりインフレだ。インフレは、政府債務にも影響を与える。
政府は1000兆円を超えるの国債残高を保有しているが、低利で新規国債の発行ができたので、普通国債の加重平均利率は0.8%程度となっている。一方家計は、1100兆円余りの預貯金(2023年度末)を保有しているが、金融緩和策の下で金利はほぼゼロである。
インフレ率3%の下では、家計は貨幣価値の低下により年間33兆円の所得が失われている計算になる。一方国の借金は利払いが少なくて済むうえ、残高もインフレにより目減りしていく。つまり、民間から政府へ所得が移転しているのである。
エコノミストは、このようなフローベース、ストックベース所得の民間から政府への移転を「インフレタックス」と呼ぶ。一見膨大な借金を抱える政府にとってメリットが多そうだが、そうとは言えない。
第1に、このような状況は長続きしないということだ。現在のように、金融政策により国債の金利(r)を低く抑え、名目成長率(g)が金利を上回る状況では、「インフレタックス」により債務残高GDP比は一定値に収束し、財政の持続可能性が維持できる。
しかし r が g を大きく上回る状況が生じれば、プライマリーバランス(基礎的財政収支)が黒字化しても、それを上回る利払費が生じるので、債務残高GDP比は悪化する。わが国のように債務残高のGDP比が2倍を超える状況下でrがgを上回る状況が恒常化すれば大きな財政リスクが生じる。世界的、歴史的に見て、rとgの関係は極めて不安定である。
第2に、資産の目減りを恐れる預金者が、金利の高い外貨建て金融資産にシフトさせれば、円建て資産から外貨建て資産への資本逃避が更なる円安を招き、それがインフレを生じさせ、国民生活は混乱する。
最後に、インフレタックスによる増収分を、補正予算などで景気対策として使おうという政治のインセンティブが高まることだ。すでに岸田総理は6月21日、「酷暑乗り切り緊急支援」(電気・ガス料金補助)と低所得者世帯への給付金などの追加の経済対策を行うことを表明した。インフレタックスによる増収分が、効果のはっきりしないバラマキに使われることは、さらなるインフレを招く恐れがある。目の前に迫りつつある金利が正常化する世界に備えた財政政策をとることこそ政治の役割だ。










