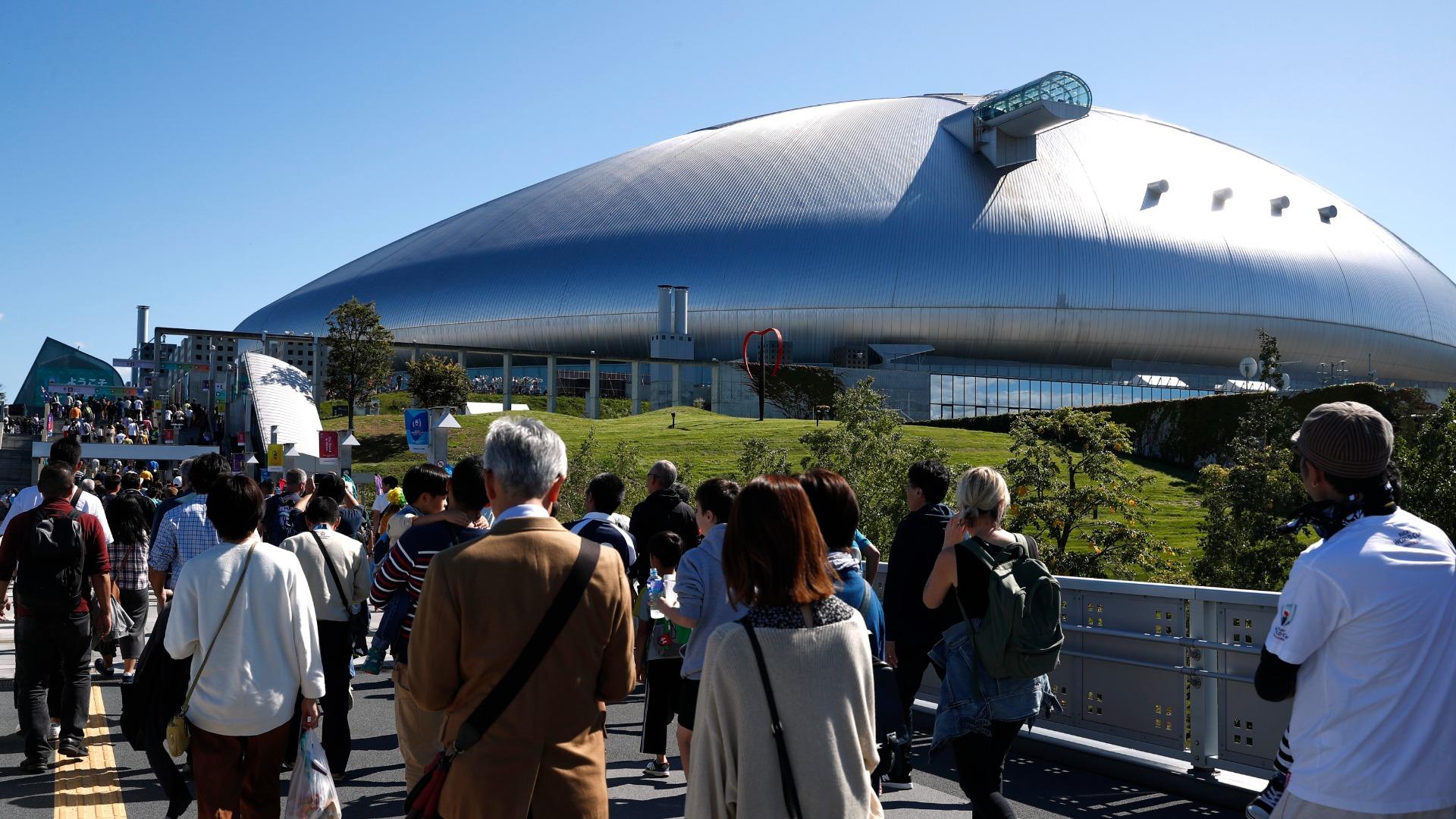【戦国こぼれ話】応仁の乱で活躍した足軽は、戦争の変化によって誕生した画期的な存在だった

テレビの歴史番組を見ていると、足軽を取り扱っていた。足軽といえば、軽装で戦場を駆け抜けたことで知られているが、それは戦争の変化によって必然的に誕生したものであった。その経緯を確認することにしよう。
■平安から鎌倉時代の甲冑
平安時代以後、武将が主に着用した甲冑は、騎射戦に適した大鎧である。その構造は、短冊形に裁断した鉄の薄金板や革の小札(細長い小板で鉄または革製)を革または組糸で威して製作した。
威すとは、「つづり合わせる」という意味である。威し色目は色が豊富で、要所に打った据文金物などの装飾性が高く、武門の趣致を示すために赤糸威、黒革威などと称された。通常、大鎧には星兜を具足していた。
平安時代から鎌倉時代の初期にかけては騎射戦が多く、丈夫な大鎧は適した防具だった。ところが、鎌倉時代中期以後、騎射戦の衰退とともに大鎧は形式化し、室町中期頃には用いられなくなった。
■戦術の変化
大鎧は、実用に向かなくなったのだ。騎射戦の代わりに増えたのが徒歩戦である。以降、戦争の変化とともに防具は進化を遂げる。
平安時代の戦争は、さほど将兵は動員されず、数百人程度の小規模な戦闘が多かった。戦国時代になると、数千から数万の大軍同士が戦うことも増え、武器も槍や鉄砲などの新兵器が用いられるようになる。
戦闘員が増えるということは、防具を短期間に製作する必要が生じる。さらに、機能性や素材の軽量化・簡略化、あるいは新しい素材の採用などで、これまでの大鎧にこだわる必要がなくなった。
鎌倉時代後期から南北朝時代に掛けて騎射戦が減り、代わりに徒歩戦が増えた。そのような事情から、重たい大鎧は機動性に欠けるという欠点があったので、軽い胴丸・腹巻にとって代わられたのである。
■新しい時代の防具
南北朝時代以降に徒歩戦が増えたので、軽量な胴丸が着用されるようになった。胴丸は、古代に用いられた挂甲という鎧に似ており、平安・鎌倉時代には徒武者が着用していた。
胴丸の形態は、胴回りがひと続きで右脇に引合せ、裾の草摺(甲冑の胴の裾に垂れ、下半身を防御する部分)は八間に分かれて歩きやすくなっている。また、主に筋兜と大袖を着用するようになった。
腹巻は胴の前と左右脇から背面両側が続いて背中で引合せ、その隙間に背板をつけた。裾の草摺は七間五段下がりとなっており、胴丸よりも簡便な防具で、鎧の下や衣の下にも着込むことがあった。
■足軽の登場
こうした軽装で出陣したのが足軽だ。足軽は「足軽く駆け回る者」という意味で、その存在は鎌倉時代から確認できる。騎射戦や個人戦が多かった時代から、歩戦による集団戦闘が主流になる鎌倉時代末期以降、その姿が顕著に見られるようになった。
足軽は武士身分だけでなく、さまざまな階層によって構成されていた。なかには、農村で食いつぶしてしまい、足軽に転身する農民すら存在した。
もっとも足軽が活躍したのは、応仁元年(1467)からはじまった応仁の乱である。彼らは放火略奪をも辞さず、目的は己の懐を潤すことにあったという。戦国時代になると、足軽は弓足軽、鉄砲足軽などに進化を遂げた。
■その後の展開
戦いの変化とともにあらわれたのが、「当世具足」である。当世には「今の」という意味があり、戦国時代における最新の具足だった。旧来の具足に対し、あえて当世具足と称したが、のちには単に具足と呼ぶようになった。
当世具足は従来の胴丸を鉄板製とし、槍や飛び道具から身を守る機能を備えた。また、全身を覆うため、籠手・脛当て・佩楯(草摺と臑当との間の大腿部の防御具)・面具などの小具足を新たに付け加えたのである。