かなり近い位置で巨大な恒星ブラックホールを新発見!
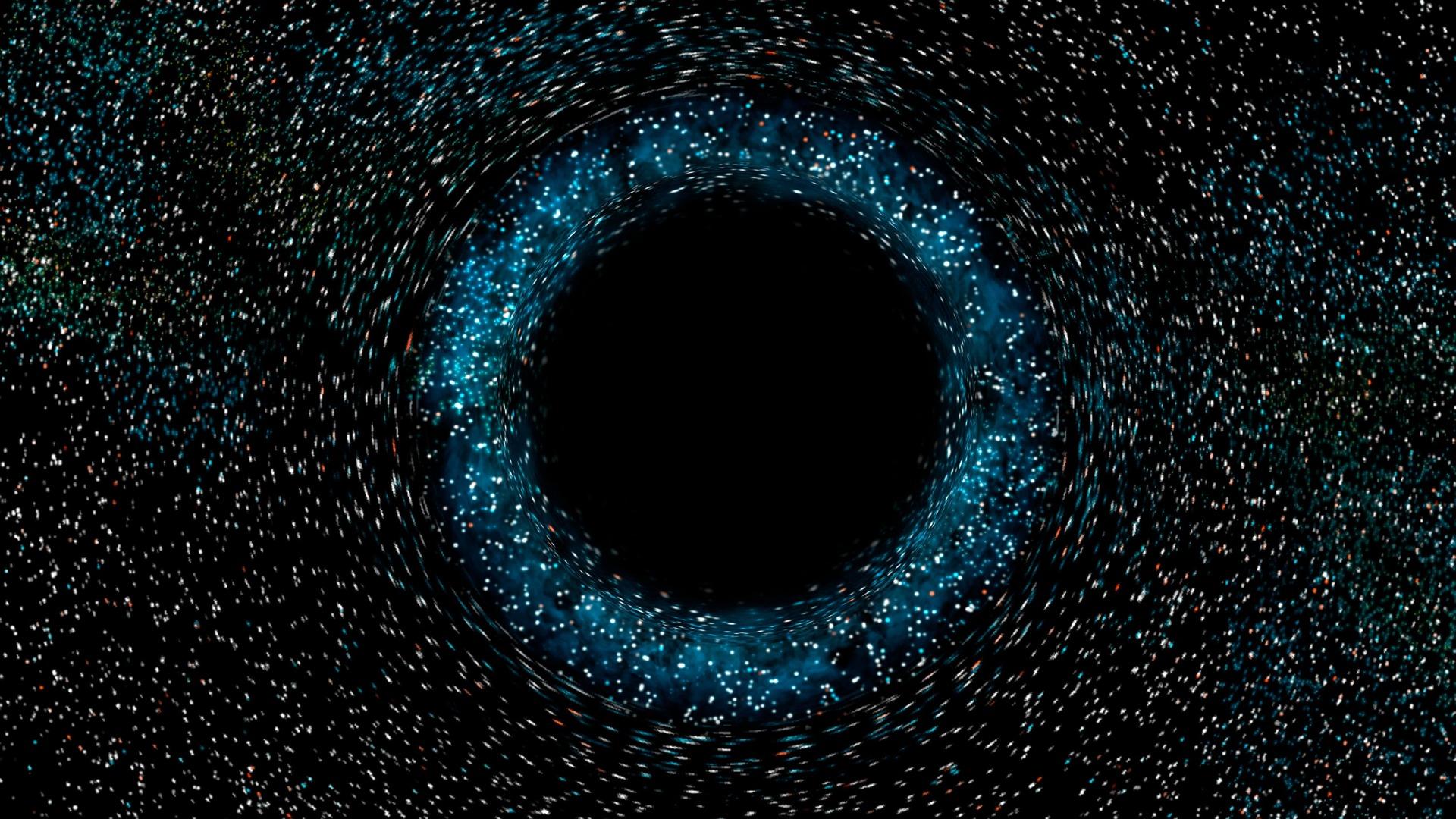
どうも!宇宙ヤバイch中の人のキャベチです。
今回は「非常に近くで、巨大なブラックホールを新発見」というテーマで記事をお送りします。
天の川銀河内に存在する億単位の恒星それぞれの位置や運動などのデータを集めている宇宙望遠鏡「ガイア」は、恒星を振り回す休眠中のブラックホールを新たに発見しました。
本動画ではそんな天の川銀河内に眠るブラックホールと、新発見のブラックホールについて解説します。
●最も奇妙な天体「ブラックホール」

ブラックホールは、宇宙で最も奇妙な天体と言っても過言ではないほど、私たちの常識とはかけ離れた天体です。

ブラックホールは一般的に太陽の30倍より重い超大質量の恒星が一生を終える際、星の核が自身の重力によって中心の1点に向かって際限なく押しつぶされる事で形成されると考えられています。

ブラックホールの内部にあり、ブラックホールの全質量がそこに集中していると考えられている体積0の点は、特異点と呼ばれています。
そんな特異点の周りでは重力が極めて強く、そこから脱出するために必要な速度(脱出速度)が光速を超えています。
ですが特異点から離れるほど重力が弱まり、脱出速度が光速と等しくなる境界面が、事象の地平面と呼ばれています。

ブラックホールの事象の地平面の内部領域や、特異点で何が起こっているのかは本当に気になるところですが、残念ながら現在の枠組みでは、それらを知ることは永遠にできそうもありません。

なぜならこの宇宙で物質が出せる速度には光速という上限があるためです。
これは観測から得られた明確な事実であり、アインシュタインの相対性理論もこの光速度が誰から見ても不変であるという事実をもとに成り立つ理論となります。

物質が移動できる速度の上限が光速である以上、脱出速度が光速度を上回るほど重力が強くなっている事象の地平面の内部に一度でも入ると、そこからはあらゆる物質も光も情報も出てくることはありません。
なのでブラックホールの内部は完全に一方通行の世界であり、その外に住む私たちは中身を知ることが理論的に不可能です。
そのため先ほどの内部構造の説明は、あくまで理論的な予想の一つに過ぎません。
これまでの様々な観測から、ブラックホールが実在する天体であることは間違いなさそうですが、その性質はこのように、奇妙というほかありません。
●ガイアの休眠ブラックホール探索

私たちの太陽系が属する天の川銀河の中には、実に1億個ものブラックホールが存在していると推定されています。
ですがそのうち私たちが発見できたのは、未確定の候補天体を含めてもたったの数十件しかなく、そのほとんどが強力なX線などの電磁波を放つ「活動的な」ブラックホールです。

ブラックホール自体は余りに重力が強く、そこから光すらも出て来れない天体なので、ブラックホールの本体から放たれた光を直接観測し、ブラックホールを発見することは不可能です。

ですが例えば非常に近い距離に伴星が存在するブラックホールの場合、伴星の恒星からガスを奪い、奪った物質がブラックホールの周囲を超高速で公転し、超高温で輝く降着円盤を形成します。
このように何らかの理由で周囲に降着円盤のような明るい構造を持つ「活動的な」ブラックホールの場合、周囲の構造から放たれた強力なX線などを観測することで、ブラックホールを発見することができます。

現状「活動的な」ブラックホールばかりが発見されている一方で、天の川銀河内に存在するほとんどのブラックホールは、地球から観測可能なほど明るい構造をまとっていない「休眠中の」ブラックホールであると考えられています。
強烈なX線などの光を放たないため観測が困難な「休眠中の」ブラックホールですが、手掛かりがないわけではありません。
例えば休眠中のブラックホールから十分距離が離れた位置で公転する伴星が存在し、その伴星が「光を放たないけど非常に重い天体を公転している」などとわかれば、間接的にブラックホールの存在を明らかにできます。
欧州宇宙機関(ESA)の手がける「ガイア」は、無数の天体を継続的に観測し続けることで、その天体の運動や地球からの距離など様々なパラメータを調べています。
よってガイアのデータから、見えない天体からの重力でふらついている恒星が発見されれば、その恒星系から「休眠中の」ブラックホールが発見される可能性があります。
●付近で巨大な恒星ブラックホールを新発見

ガイアは、恒星を振り回す休眠中のブラックホールを新たに発見し、「ガイアBH3」と命名しました。
研究成果は2024年4月に発表されています。
ガイアBH3はいくつもの特筆すべき性質を持っており、発見されてから世界的に話題となっています。
まず地球からわずか1926光年しか離れていません。これは存在が確かめられているブラックホールの中で最も地球から近い、1560光年彼方にある「ガイアBH1」に次いで二番目に近い記録となります。

またさらに驚くべきことに、質量が太陽の33倍もあります。
「恒星ブラックホール」に分類されるものとしては、天の川銀河内で最大記録となります。
天の川銀河内の恒星ブラックホールの平均が「10太陽質量」で、かつての最大記録ははくちょう座X-1の「21太陽質量」であることを考えると、並外れて巨大なことがわかります。
以上の性質から、「非常に近い位置で、非常に巨大なブラックホールが発見された」と言えます。

ブラックホールを公転する恒星の質量は太陽の0.76倍しかありませんが、寿命が近付くにつれて膨張しつつあり、その直径は太陽の約5倍で、太陽の15倍明るいそうです。
ブラックホールと恒星は、この恒星系の重心を11.6年周期で公転しており、お互いの距離は4.5~29天文単位で変動しています。
また、ガイアBH3の伴星には、水素とヘリウム以外の重元素が乏しいという特徴があります。
ガイアBH3を形成した元の大質量星と伴星は同時期に誕生し、同じ重元素量を持っていたと考えられるため、ガイアBH3を形成した元の大質量星にも重元素が欠けていたことを示唆しています。
天文学者たちは、天の川銀河外でも同様の質量を持つブラックホールを発見していますが、これらのブラックホールは重元素が乏しい大質量星の崩壊によって形成されるのではないかと理論化しています。
なぜなら重元素が乏しい星は、一生の間に失う質量が少なく、最期に大質量のブラックホールを生成するための物質が多く残されると考えられるためです。
しかしこれまでは、重元素が乏しい星と大質量ブラックホールを直接結びつける証拠に欠けていました。
まさにガイアBH3とその伴星は、その架け橋となる存在になり得ます。
https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/forth/aa49763-24.pdf
https://www.eso.org/public/news/eso2408/
https://academic.oup.com/mnras/article/524/2/1965/7210551?login=false
https://web.ub.edu/en/web/actualitat/w/study-hints-at-the-existence-of-the-closest-black-holes-to-earth-in-the-hyades-star-cluster
https://www.space.com/astronomers-may-have-discovered-closest-black-holes-earth
https://wired.jp/article/three-black-holes-in-the-hyades-star-cluster/
https://www.astronomy.com/science/closest-black-holes-to-earth-may-lurk-in-the-hyades-cluster/
https://www.mpg.de/19443006/new-method-finds-black-hole-closest-to-earth
https://en.wikipedia.org/wiki/A0620-00
https://www.eso.org/public/news/eso2204/
https://news.osu.edu/black-hole-is-closest-to-earth-among-the-smallest-ever-discovered/
https://arxiv.org/abs/2203.06348
サムネイルCredit: ESA/Hubble, Digitized Sky Survey, Nick Risinger, N. Bartmann










