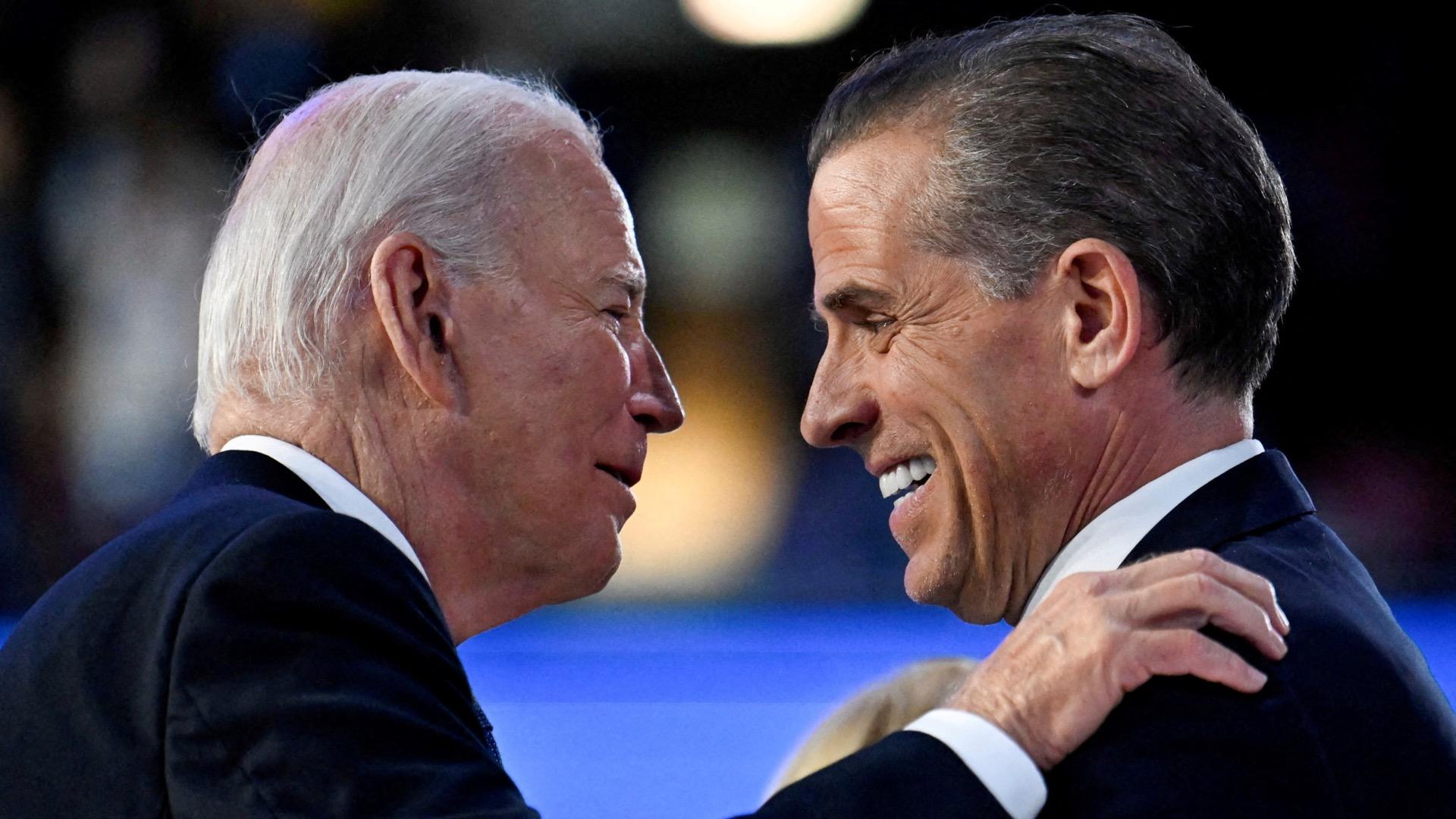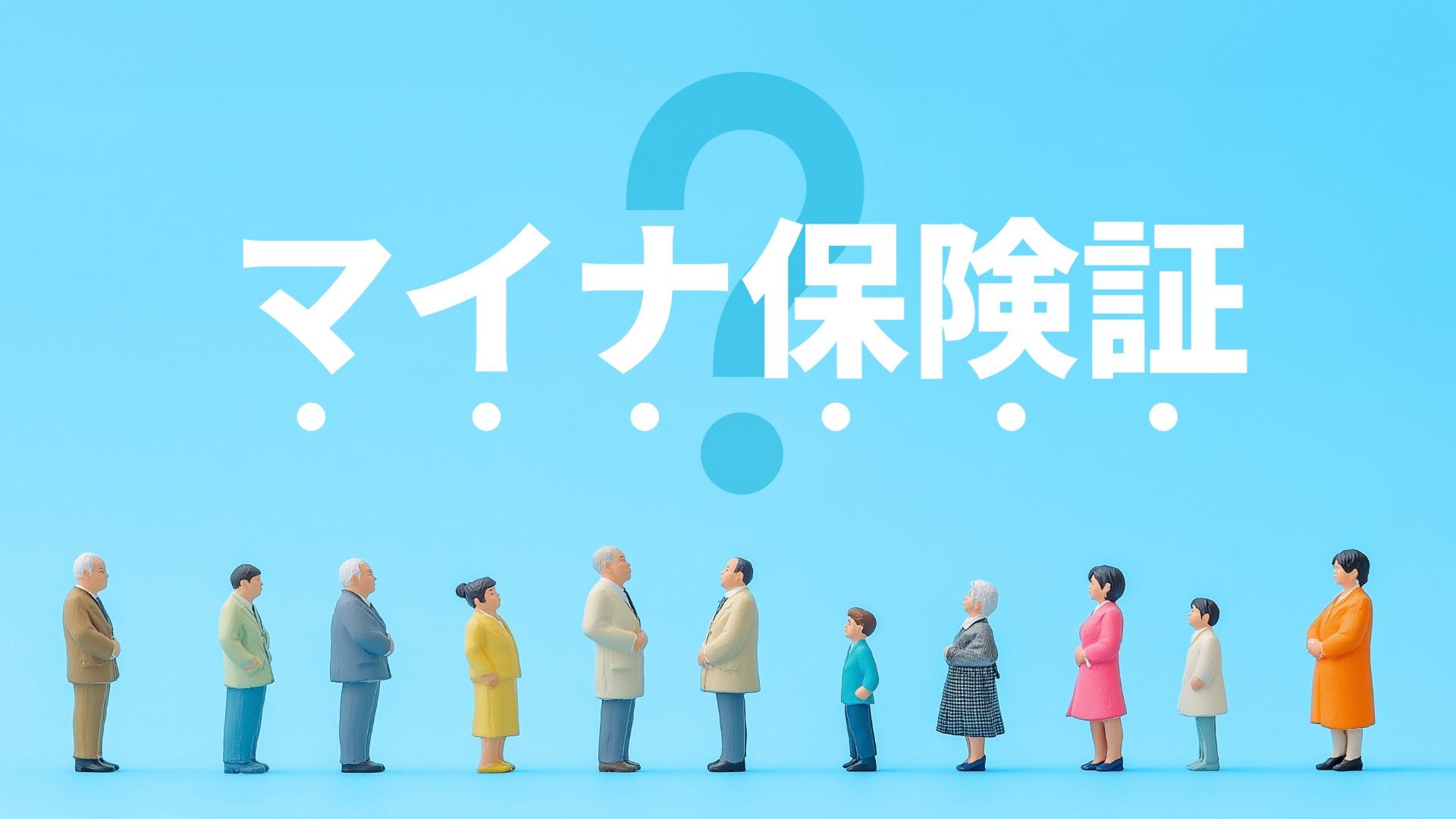子どもが習い事にやる気を出すには習い事を始める前が大事だった!習い事の始め方を幼児教育講師が解説!

こんにちは!幼児教育講師のTERUです!
今回は『子どもの習い事の始め方』をテーマにお話しさせていただきます。
前回までに『子どもの習い事の選び方』を紹介していますので、良ければそちらと併せてご覧ください。
習い事について考えていく上での参考にしていただけたら幸いです。
【習い事の始めるときの4つのポイント】

まずは、習い事を検討し始めてから通室するまでのポイントをご紹介していきます。
①子どもの好きを見極めながら好きの種を撒く
習い事を始める前にすべきことは、子どもの好きなものを探すということです。
前回の記事で、習い事は子どもの好き・得意・興味を伸ばすために使うべきだとでお話ししました。
まずはご家庭のできる範囲で色んなことを経験していき、お子さんの好きを探してから習い事を始めるようにしましょう。
どうしても親の意向でやらせたい習い事がある場合は、それが好きになる種まきをしてみてください。
例えば、野球をやらせたいのであればプロ野球の試合をテレビで見たり、実際に球場に足を運んだり、一緒にキャッチボールをしたりすることで、子どもが徐々に野球に興味を示すようにするということです。
種まきはできるだけ本物でレベルの高いものが良いです。
草野球を見せるのではなく最高峰であるプロ野球を見せ、テレビよりも生で本物を見せた方が質の高い種まきになりやすいです。
②子どもからやりたいと言うまで待つ
習い事を始めるのは子どもがやりたいと言ってからにしましょう。
種まきをし続けても子どもに一向に興味が出ない場合もあります。その場合も、根気強く待ちましょう。
それでも興味が生まれないのであれば、その習い事はやらせるべきではないと私は考えています。
もちろん子どもがまだ2〜3歳頃に選ぶ習い事であれば、子どものはっきりした意思を確認することは難しかったりしますから親の意向でも大丈夫です。
そして気質的に新たなことを始めるのに抵抗があるような子であれば、家では楽しく取り組んでいるけれど習い事となると「嫌だ!」と言うこともありますから、そこは親の判断でまず体験に行ってみるというのはありかなと思います。
③子どもがやりたいと言ったら理由の確認とお金のことも伝える

子どもがやりたいといったら、まずは理由が納得できるものか確認しましょう。
その理由が親として納得できるものであればやらせてあげて良いと思いますが、「友達がやりたいって言っているから」などという本質から少しずれていると感じたものであれば「もう一度考えてごらん」と理由を考え直させることも大切です。
実際、「友達がいるから習い事が楽しい!」という子は多いのではないでしょうか。
ですが、最初の段階からそれが理由では良くないと思っています。
なぜその習い事なのかをきちんと考えて、理由を1つでも説明できるようになってから始めることで、通い始めてからのモチベーションにもつながっていきます。
そして理由が正当なものだと感じたら、その習い事にどれだけお金がかかるのかもお子さんにしっかり伝えていくことが大切だと私は思っています。
「この習い事は1ヶ月に〇〇円かかるよ。そのお金はお父さんとお母さんが一生懸命働いたお金から〇〇ちゃんのために使うからね。だから〇〇ちゃんも楽しく一生懸命がんばってね!」
というように、お金のことと親の想いも伝えましょう。
これをちゃんと伝えるだけで、実際に習い事が始まってからの意識に良い影響があります。
そして、子どもが「やりたい!」と言った習い事が、これまで全く経験したこともないことで、親が種を撒いてきたことでもない、ただ興味だけで言い出した習い事である場合は、可能な範囲で家でそのものについて取り組んでみましょう。
例えば、テレビでバスケを見て突発的に「バスケがやりたい!」と言ったら、まずは家におもちゃのゴールを買ってあげたり、体育館で親と一緒にバスケをやってみるなどして、子どもが本当にその種目を楽しく感じるかを試してみると良いと思います。
その後、本当にやりたいかもう一度確認して、意思が固ければ許可してあげてください。
ちなみに以前ご紹介させていただいたお金の教育の面から考えると、小学生以降は習い事の予算をお子さんに任せても良いのではないかと考えています。
>>詳しくはこちらの記事をご覧ください。
決まった予算の中で自分で習い事を選んでいくことで責任感が生まれ、そして親としても習い事のお金で家計がパンクすることも回避することができます。
④通室する教室を見極める
幼児期から小学生の習い事選びは、何を習うかだけでなく誰に習うかがかなり大切になってくると思っています。
- その教室で実際に子どもを見てくれる先生が信頼できるかどうか
- 子どもに対してどのように接してくれる先生なのか
前回、親の希望で通室を開始することや子どもの苦手を克服するためといった理由での通室はあまりおすすめできないとお話しましたが、先生が人格者で子どもを上手く導き、あっという間に苦手克服&好きを引き出してくれることだってあります。
先生選びは習い事選びの大事な要素の1つです。
大体の習い事は体験のようなものがありますから、まずは体験の際に先生についても良く観察するようにしましょう。
そして体験が終わった後、そのまま帰るのではなく先生の話を聞くことをおすすめします。
体験の先生と実際にクラスを持ってくれる先生が違う場合もありますから、実際にお子様を見てくれる先生と話し、どういった考え方で進め、先生はどんな想いでこの教室で働いているのか、子どもにどのように接してくれるのかなどをしっかりと確認しましょう。
私が考える理想の先生像は、幼児のお子さんの先生あれば『良い表情』で『良い言葉』を使う先生。小学生であれば、子どもたちに考えさせることを積極的にする先生です。
あとは、教室の雰囲気も大切です。
教室全体の空気が重く暗い場合は、何か問題を抱えている教室である可能性があります。
これは一概に正しいとは言えませんし感覚の話になってしまいますが、私は子どもを伸ばす教室はパワーがないと本当に子どもを成長させることはできないと考えています。
その教室に行ったときに、教室のスタッフが笑顔で「お待ちしていました!」「こんにちは!」と元気に迎えてくれるのかそうでないのかは教室の力を測るポイントの1つです。
いかがでしたでしょうか?
皆さんの子育てを応援しています!
オススメの関連記事はこちら
動画でより深く学びたい方はこちら