斉藤守彦さんを偲ぶ──日本屈指の映画ジャーナリストが遺した仕事、未来を生きるわれわれに残された課題

日本屈指の映画ジャーナリスト
去る2月26日、昨年9月に急逝した映画ジャーナリスト・斉藤守彦さんを偲ぶ会が開かれた。
主催は、生前の斉藤さんが仕事をしていた洋泉社、キネマ旬報社、博報堂ケトル、シネマズby松竹の4社、幹事は斉藤さんと親交のあった筆者を含む9名である。会には出版、放送、映画会社、興行会社など多くの関係者が集まり、故人を偲んだ。
斉藤さんは、実力的には間違いなく日本の映画ジャーナリストではトップの存在だった。その特徴は、徹底した取材と細かなデータに裏打ちされた論証だ。作品内容のみに注目して映画を捉えるのではなく、製作や制作、配給、宣伝、そして興行と、川上から川下まで目配せをして映画という存在に向き合っていた。
映画とはなにか?──その問いに実直に向き合ってきた存在だ。
以下、斉藤さんが遺した仕事を振り返りながら、その功績を讃えたいと思う。
斉藤守彦の遺した仕事
以下は、「斉藤守彦さんを偲ぶ会」にて配布された8ページの小冊子に書き下ろした、筆者による全10冊の著書の紹介と仕事の解説である。
プロフィール:斉藤守彦(映画ジャーナリスト/アナリスト)
1961年3月6日、静岡県浜松市生まれ。実家は大工。中学時代に学校新聞の取材・編集を体験、高校時代には自主上映活動「浜松映画サークル協議会」に参加する。79年に上京し、専門学校・日本プリンティングアカデミー(JPA)に入学。卒業後はプリントショップ店長やビデオ会社アルバイトを経て、87年に映画業界紙「東京通信」記者となる。「東京通信」で編集長を務めた後、96年にフリーとなり映画興行の実際からアニメーション、特撮まで幅広く執筆活動を展開。寄稿した雑誌は『キネマ旬報』『宇宙船』『Invitation』『アニメ!アニメ!』『フィナンシャル・ジャパン』『別冊映画秘宝』『ザ・テレビジョン』『日経エンタテインメント!』『スターログ日本販』など多数。さらに映画パンフレット、WEBメディアに活動の場を広げ、幅広く記事・批評を提供する。著書多数(別欄参照)。2017年、東京テアトル『この世界の片隅に』興行記録特集のため、日本全国の上映劇場を取材、これを社内報にまとめる。2017年9月14日頃、虚血性心不全により急逝。享年56。ヒッチコック作品から『トランスフォーマー』まで、ジャンルにとらわれず幅広く映画を愛した。
■ゴジラ・モスラ・キングギドラ 大怪獣総攻撃【共著】

金子修介監督による同年公開作のメイキングムック。緻密な現場レポートをはじめ、多くのスタッフやキャストへのインタビュー、さらに斉藤自身の撮影による現場写真と、半年を費やしほぼ全ページを構成した力作。後記では「ガマの油のような本になった」と自評している。
■図解でわかるコンテンツビジネス〈最新2版〉【共著】

放送や音楽など4業界を解説したビジネス書で、映画業界を担当。基礎的な解説が中心だが、「『製』作者と『制』作者のちがい」といった業界用語の背景を説明して理解を深める工夫も。映画業界の入門書として最適かつ隠れた名著。
■日本映画、崩壊

初の単著。4ページほどの短いコラムが続く構成だが、制作・製作・配給・宣伝・興行と、映画界の構造が網羅されている。加えて、ひさしぶりの邦洋シェアの逆転で活況に湧いていた当時の映画界に対し、「一瞬のバブルに浮かれるな!」(帯文)と、多くの叱咤も。映画ジャーナリストとしての所信表明をした一冊。
■宮崎アニメは、なぜ当たる

副題は「スピルバーグを超えた理由」。88年『となりのトトロ』以降の宮崎駿作品と、同年に公開されたスピルバーグ作品を、興行を中心に比較・分析した企画性の強い新書。両者の作品の宣伝やマーケティング手法が具体的に解説されている。一般読者にも届くように、わかりやすく書かれているのが特徴。
■映画館の入場料金は、なぜ1800円なのか?
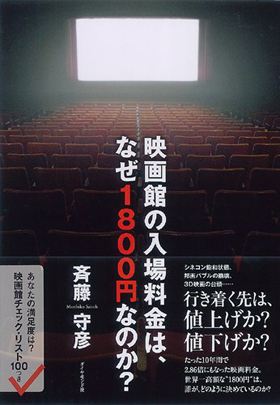
入場料金を切り口に、映画業界の構造的問題を炙り出した一冊。白眉は、業界の斜陽が止まらなかった60〜90年代の入場料金を一年ずつ確認していく3〜5章。需要と供給のバランスが激変していった歴史を入念に追っている。斉藤の問題意識が強くうかがえる野心作。
■「踊る大捜査線」は日本映画の何を変えたのか【共著】

制作者や評論家など10人の論者が『踊る〜』を肯定的にも否定的にも語った新書。斉藤は『ヤマト』にも通ずるファンのオタク的受容を語るなど、観客への言及が多い。最後は、映画参入したテレビ局の功罪を冷静に指摘。ジャーナリストとしての公正性(フェアネス)が強く感じられる。
■アニメ映画 ヒットの法則

04〜11年にかけて執筆したアニメ映画の記事をまとめた一冊。本人のまえがき曰く「ヒット・アニメの実例集」。『ハウル』や『時かけ』、『ポニョ』などのヒット分析が収められている。また、制作者へのインタビューや対談が4本収録されているのも特徴。晩年の『この世界の片隅に』に繋がる仕事だ。
■80年代 映画館物語

80年代の映画館のみに絞って論じた一冊。関係者への入念な取材によって、特定の映画館の存在性をかなり掘り下げている。例えばシネマスクエアとうきゅう開館時のエピソードなどは、非常にマニアックなものだ。また、支配人やアルバイトから聞いた映画館の抱腹エピソードも多数収められている。
■映画を知るための教科書 1912〜1979
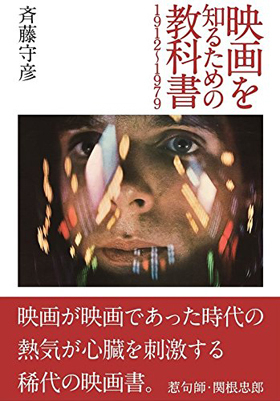
産業とメディア性に主題を置き、黎明期から70年代までの日本の映画史を整理・分析した意欲作。本人も認めるように、田中純一郎の名著『日本映画発達史』の影響が色濃く見える。生前は続編の構想があるとしばしば話していた。斉藤の代表作であり実質的な遺作。
■映画宣伝ミラクルワールド 特別篇

2013年に出た同書の増補版。70〜90年代のヒット作を切り口に、映画宣伝を論じた一冊。多様なケースがわかるように全38章の構成。当時の関係者に取材し、新聞広告などもかなり引用されている。成功例ばかりでなく、失敗例への取材や言及があるのも斉藤らしい。
【註:書誌情報が残されている『日本映画、飛躍と困惑の過去・現在・未来』(11年・アゴラ出版局)は、出版が確認できないので省いている】
(以上、冊子「斉藤守彦さんを偲んで」より)
解説:斉藤守彦の仕事
上の著作以外にも、斉藤は雑誌やネット記事をはじめ、劇場用パンフレットやDVD&ブルーレイの解説など、多くの仕事を遺している。
03年まで続いていた本人のHPによると、書籍でもっとも古い仕事は91年の『こだわり映画館』(滝隆一名義)への寄稿だ。劇場用パンフレットでは、93年公開『高校教師』に関わったのが最古である。
業界紙記者となった87年から映画ジャーナリストとなるが、初の単著を上梓するのは、それから20年後の46歳のときだ。
その仕事内容は、徐々にだが変化している。当初は製作や配給など映画の送り手を主題としていたが、晩年は受け手(観客)との接点となる興行や映画館を扱う傾向が強まっていた。こうした変遷を踏まえれば、将来的には映画観客やファン(受け手)を題材にする可能性が十分にあった。
また、ジャーナリズムと学術的なメディア研究を架橋する極めて稀有な存在でもあった。マンガや文学などの近接分野に比べると両者の隔たりが大きい映画において、映画マスコミと研究者双方から強い尊敬を抱かれていた。
(以上、冊子「斉藤守彦さんを偲んで」より)
斉藤さんのひとがら
以上のように、冊子では限られた紙幅のなか駆け足で斉藤さんの足跡を辿った。ここからは、ごく個人的な斉藤さんの思い出と、今後の映画ジャーナリズムについて触れておこうと思う。
筆者が斉藤さんのことを知ったのは、2006年頃のことだ。たしか雑誌『Invitation』における映画記事だったと記憶する。非常に詳細な映画業界の解説に舌を巻いたのだ。それから間もなく、『日本映画、崩壊』が上梓された。2007年当時、筆者は雑誌『創』において「映画界の研究」という特集を企画から手掛けた。そのために必死に勉強したのだが、もっとも参考となったのは斉藤さんの一連の仕事だった。
なかでも『図解でわかるコンテンツビジネス〈最新2版〉』(日本能率協会マネジメントセンター)は、非常に勉強になった。映画業界への就職を考えている学生から相談を受けたときも、まずはこの本で基礎的な勉強をすることを薦めたほどだ。
すると2008年、日本能率協会マネジメントセンターから私にその新板(『最新コンテンツビジネスのすべてがわかる本』)の執筆依頼があった。斉藤さんが断り、私にお鉢が回ってきたようなのだ。そのとき私が担当編集者に言ったのは、「がんばりますが、斉藤さんほどの水準の仕事ができるかどうかはわかりません」ということだ。自分に自信がないのではない。斉藤さんのレベルが高すぎるのだ。
以降も、斉藤さんの仕事は常に注目していた。Twitterでコミュニケーションを取るようになったのは、2011年の2月くらいからだ。実際に面識を得たのは、その1年後くらいだっただろうか。日劇におけるなにかの映画(失念)のマスコミ試写の際、階段に並んでいる知人のたまたま前にいたのが斉藤さんだった。こちらから思い切って声をかけたのである。
その後、マスコミ試写などで偶然に会う場合は、私のほうから積極的に声をかけていた。昨年だと、亡くなる約1カ月前の8月8日にも、『打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?』の完成披露試写会でお会いしている。そうした際、私はいつも子どものように映画業界について質問攻めにしていた。斉藤さんでなければ答えられないような疑問を常に抱えていたからだ。そのとき斉藤さんは、私が同業者であるにもかかわらず嫌な顔ひとつせず、むしろ嬉しそうに逐一丁寧に説明してくれた。私にとっては、映画ジャーナリズムの信頼のおける先輩だった。

プライベートで飲みに行くなどした機会は多くなかったが、2014年には映画専門チャンネル・ムービープラスの開局25周年記念番組にも声をかけてもらった。1989年の映画について、私が司会役を務めて斉藤さんが語りまくる内容のこの番組は、いまもYouTubeに残されている。
斉藤さんと最後に会ったのは、亡くなる17日前に下北沢の本屋・B&Bで行われたトークイベント・「柴尾英令×小川真司×斉藤守彦『われわれはなぜシネコンにいるのか ~映画最前線物語2017』:『シネコン映画至上主義 「メルマ旬報」の映画評555』(太田出版)刊行記念」だ。『シネコン映画至上主義』を上梓した柴尾さんも、『ジョゼと虎と魚たち』や『リバーズ・エッジ』のプロデューサーである小川さんも以前から知己があり、打ち上げで席を囲んだのが最後となった。タクシーから途中で降りて自宅に向かう斉藤さんの後ろ姿は、いまでも覚えている。
斉藤さんは、非常にひと懐っこいひとではあった。もっというと子どもみたいな印象だ。いつもニコニコしながら楽しそうに映画について話し、急に真面目な顔をして業界動向について意見を述べる──そんなひとだった。
4年前には、私の映画研究のために斉藤さんからある“ネタ”を教えてもらったことがあった。ある学会への投稿論文のための“ネタ”だったのだが、準備はしてあるもののまだその論文は書けていない。個人的には生前に書き上げて、それに「松谷君、これは違うよー」などとツッコミを入れてほしかった。せっかく教えてもらったのに、本当に申し訳ない限りだ。
今後の映画ジャーナリズム
斉藤さんの仕事内容は、軽妙なものもあるが、その多くは客観的かつ論理的で筆致もきわめて冷静だ。さらに、問題点があれば丁寧に検証し、はっきりと批判もする。そのため、業界内には敵も多かったと耳にする。
ただ、そうした姿勢こそが映画ジャーナリストとして信頼の置けるところだった。映画に限らず、音楽やテレビ、ゲームなどコンテンツ業界は、太鼓持ちの記事ばかりになる傾向がある。批判をすると、各社の広報が取材に規制をかけたり、サンプルや画像を提供しなかったりと、ジャーナリズムが機能しない事態に追い込まれるからだ。ゲームなど新しい業界になればなるほどその傾向が強い。
各業界にはそれぞれ優れたジャーナリストはいるが、多くのマスコミ人は各会社の顔色をうかがいながらやりくりしているにとどまる。フリーで仕事を続けてきた斉藤さんは、そうした存在に比べれば格段に硬派だった。
ただ、映画業界と出版業界はどちらかと言えばジャーナリズムに理解があるほうだ。おそらく歴史の長さがそうしているのだろう。斉藤さんを偲ぶ会にも東宝と松竹の取締役をはじめ、多くの映画会社の方がいらっしゃった。映画業界にはそうした懐の深さを感じることが多い。ジャーナリズムやマスコミの存在価値を理解されているからだ。
ただ、私が危惧するのは今後の映画ジャーナリズムだ。斉藤さんの抜けた穴はとても大きい。現状、その穴を埋めることができる能力のあるひとは確認できない。すでに私には、本来なら斉藤さんがしていたはずの仕事が回ってきているが、映画以外の仕事が圧倒的に多い私にとって斉藤さんの仕事をカバーすることなど到底できない。いまの50倍の時間を映画に注力すればある程度はカバーできるかもしれないが、斉藤さんが経験で培ってきた能力に追いつくためにはまだまだ相当の時間が必要だ。
筆者がここで斉藤さんの著作を紹介したのは、そうした未来の映画ジャーナリズムのためだ。斉藤守彦という大きな損失をどうにかしてカバーしていかないことには、現在は好調な日本の映画業界の未来も明るいものにはならない。業界を叱咤し、分析し、改善を提案する──どの産業にも常にそうした存在が必要だ。
斉藤守彦さんの仕事を未来につなげていくこと──これが、残されたわれわれにとっての大きな課題だ。










