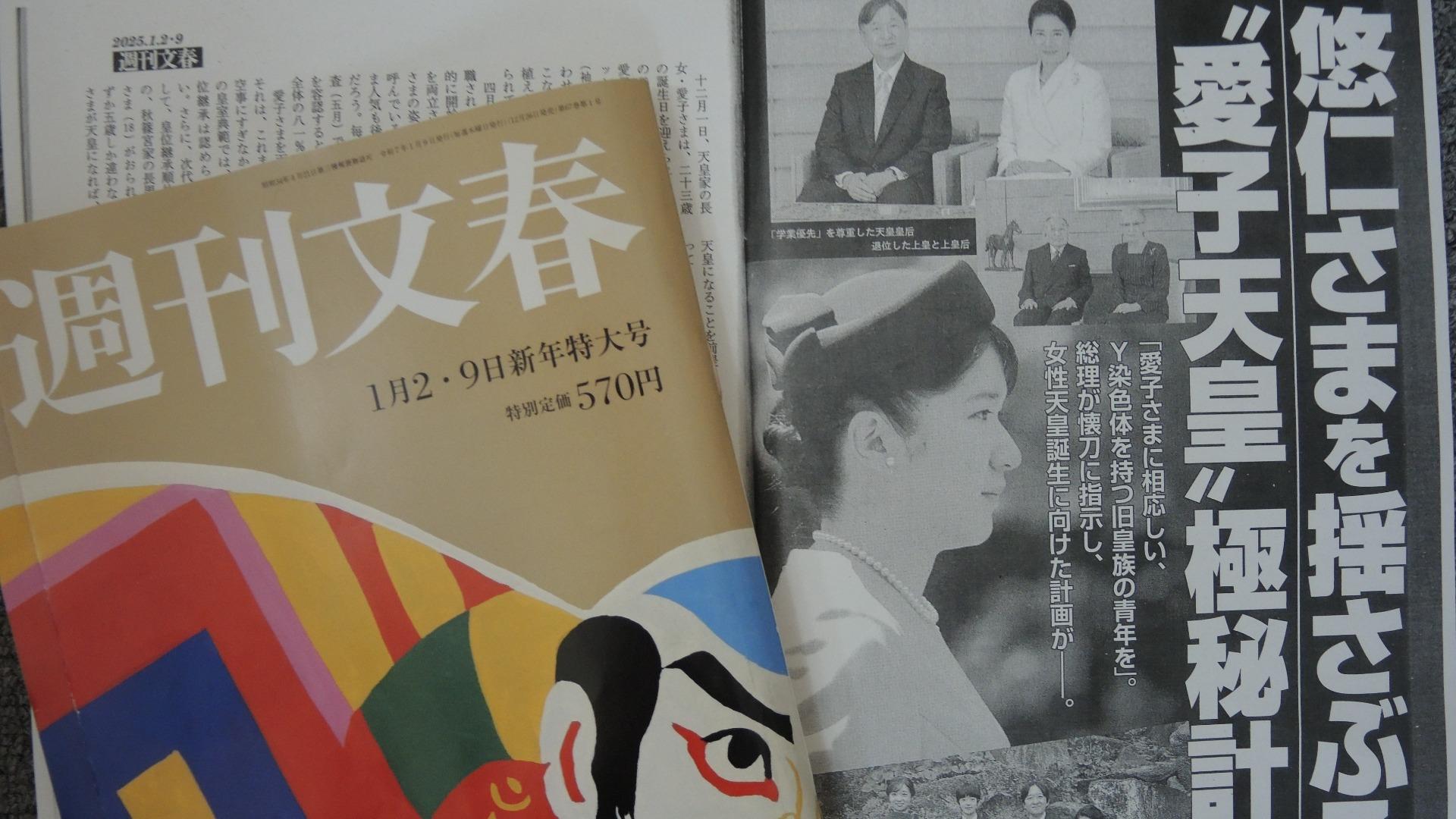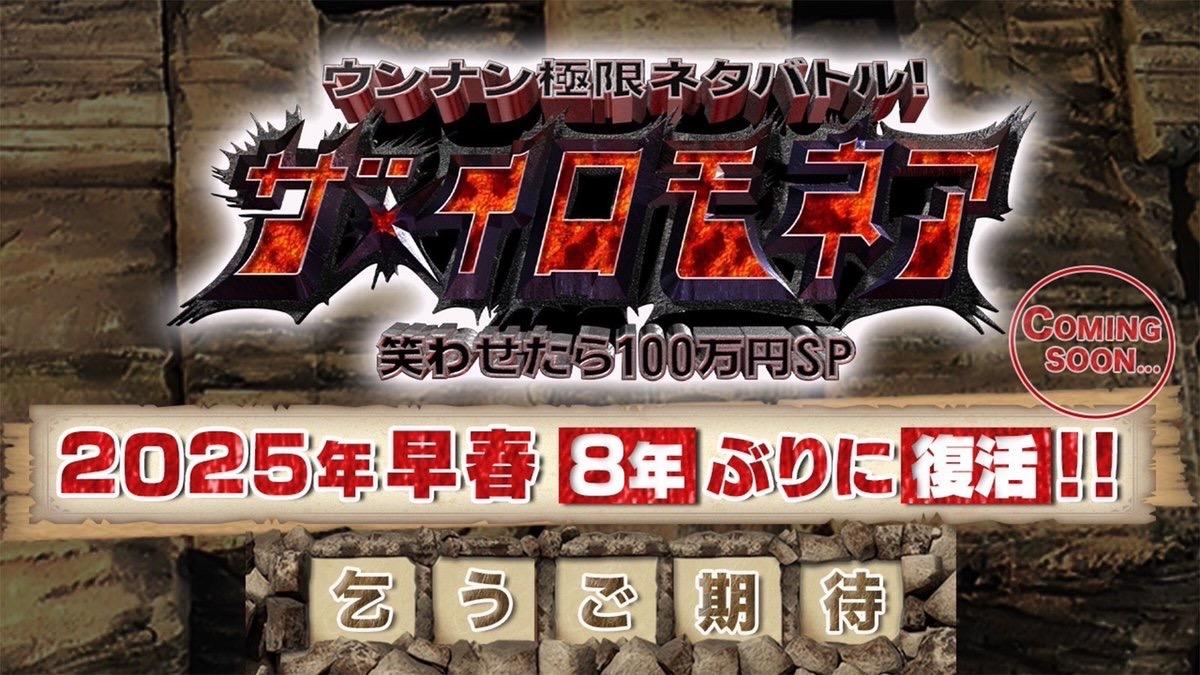「国葬」3日前にアイデアが降りてきた。その結果「後世に残す日本人のサンプル」を見た大島新監督の戸惑い

突然アイデアがひらめいて、わずか3日後、その1日だけカメラを回し、劇場公開が可能な1本のドキュメンタリー映画に仕立てる。
はたしてそんなことが可能なのか?
『なぜ君は総理大臣になれないのか』『香川1区』を送り出し、今や日本のドキュメンタリーの旗手と言ってもいい大島新監督にとっても、新作『国葬の日』は異例のチャレンジとなった。
「国葬」とは、2022年9月27日に行われた安倍元総理の葬儀。大島監督も当初は、「TVニュースと差別化した映像作品ができるのか。賛成/反対の声を拾い上げ、たとえば統一教会と自民党の関係、(事件の容疑者である)山上の背景を織り込み、国葬会場周辺を撮ったとしても、NHKなどの作る番組を超えられないでしょう」という心境だった。
国葬の日、パチンコ店に並ぶ人、結婚写真を撮る人…
映画監督としてどこか踏み出せない状態が続いていたものの、国葬当日の3日前に、まさに青天の霹靂のごとく、ひとつのアイデアが“降りて”きた。
「数日前までの自分が嘘だったかのように、3日前に『やるぞ!』と決めた瞬間から、めっちゃ盛り上がりました」というそのアイデアは、国葬当日、全国10都市にディレクターやカメラマンを派遣して、その場所の人々にカメラを向けること。3日前にも関わらず、奇跡的にスタッフが揃い、撮影が敢行された。
「撮影を1日に限定したことで、ある種のスケッチにならざるをえません。私自身も含め、自分の思想や信条に関係なく、いろいろな声を拾ってもらうことにしました。インタビューはもちろん、その場の日常も取り込み、たとえば浅草で観光してる人、朝の10時にパチンコ屋に並んでる人、北海道では結婚式を挙げてる人、沖縄では基地問題で座り込み運動をしてる人などにカメラを向け、そこから見えてくる日本社会……というのが狙いでした」
音楽やナレーション、そしてニュースなどのアーカイブ映像も使わず、監督いわく「撮ったものをゴロッと出した感じ」という作品から見えてきたのは、現代日本社会の縮図。しかし大島監督は、そこで困惑に陥ることになる。
「国葬に強い賛成、強い反対をもつ人、故・安倍晋三さんという人に何か思いを抱く人もいたのですが、実際に撮影した素材をすべて見て『何も意見を持っていない人がこれだけたくさんいるんだ』という印象でした。賛成/反対への曖昧な態度はもちろん、そもそも国葬に関心がない。僕らがふだん作品で訴える政治的問題も、届かない人にはまったく届かないという思いに改めて困惑した次第で、その困惑を含め、あの日の日本人のイメージが作品に投影されたと思います」

「届かない人にはまったく届かない」というのは、たしかにそのとおり。大島監督のこれまでの作品に触れた人は、彼の政治に対するスタンスも理解しているだろう。一方で大島監督の作品ということで、「あぁ、あの人の作品か」と思想的なレッテルが貼られ、避けられるリスクが増えたのも事実。ゆえに「届かない」人は、そのままの状態となる。実際に国葬への賛成/反対を聞くと、大島監督は「反対でした」と答える。そういう人が撮った映画が『国葬の日』だと思い込まれるのも、これまた現実だ。
「僕自身はいわゆる左派とは思いません。真ん中より“やや左”という立ち位置の感覚で、時の政権のおかしい部分に対してはしっかり意見を言おうと思っているだけです。その言葉が意外なほど届かないという忸怩たる思い。つまり真っ当に政権を批判する人の声が届かない……という感じを、この映画で伝えたかったというのはあるでしょう。なぜ届かないのか。それをみんなで一緒に考えませんか、と伝えたいのです」
反対デモをやっても、もう遅いでしょう
こうした大島監督の話を聞いていると、この日本という国は、10年後、20年後もまったく何も変わらないという“現実”を突きつけられるようで、ちょっと背筋が寒くなる。『国葬の日』には、そうした日本の未来への暗澹たる予感が断片的に刻み込まれている。
「どちらかと言えば国葬に賛成ながら、特に強い意思を持っているわけでもなさそうなタクシーの運転手さんが、『デモをしても遅いでしょう。国が決めたことだから』と語ります。その言葉が代弁するように、日本人には民主主義を否定、とまでは言わないにしても、行使しようとしない雰囲気が充満しています。国が決めるのではなく、われわれが決めるのが民主主義で、そのための行動のひとつがデモであり、もっと強力なものが選挙なのです。日本には制度としての民主主義が存在していますが、意識の中で民主主義が機能していない。そんな事実を今回、僕らのチームが撮影してきた素材から改めて実感してしまいました」

2022年9月の国葬から約1年を経て『国葬の日』は劇場公開される。冷静に考えれば、あの国葬にまつわる騒動は、人々の記憶から薄れつつある。だからこそ、いま観る意味があるのだと大島監督は断言する。
「日本人は、ある種の“忘れやすさ”みたいな気質もあると思います。ですからある程度時間を置いて『じつはこんな日だった』と伝えたい。その意味で1年後に公開というタイミングを考えました。あの国葬の日、静岡の清水では豪雨災害があり、今回映画を観た人がその事実を思い出したりしてくれて、つまり10年後、20年後に『あの日の日本人はこうだった』というサンプルになったとは思っています」
突発的アイデアだったから現実を収められたのか
ドキュメンタリー作家は「何をどうカメラに収めるか」周到な準備を積んで、対象に向かうケースも多いだろう。その場合、作り手のメッセージが色濃くなり、“計算どおり”の作品に結実することもあるに違いない。今回、突発的アイデアで発進したことで大島監督も「もっと前から準備をしていたら、国葬の賛成/反対のはっきりした意見に偏る可能性もあったかも」と吐露する。
日本10都市の点景が一見、淡々と編まれているようなこの『国葬の日』は、大島監督の近作『なぜ君は総理大臣になれないのか』や『香川1区』のような、鑑賞しながらのカタルシスは少ないかもしれない。しかし観終わった後、または観て時間が経ってから、いろいろと思い巡らせることが多い作品ではないか。
無力感に襲われるのか。あるいは何かの意識にめざめるのか。それは、あなた次第である。

『国葬の日』
9月16日(土)より[東京]ポレポレ東中野、9月23日(土)より[大阪]第七
藝術劇場、[愛知]名古屋シネマスコーレほか全国順次
(c)「国葬の日」製作委員会