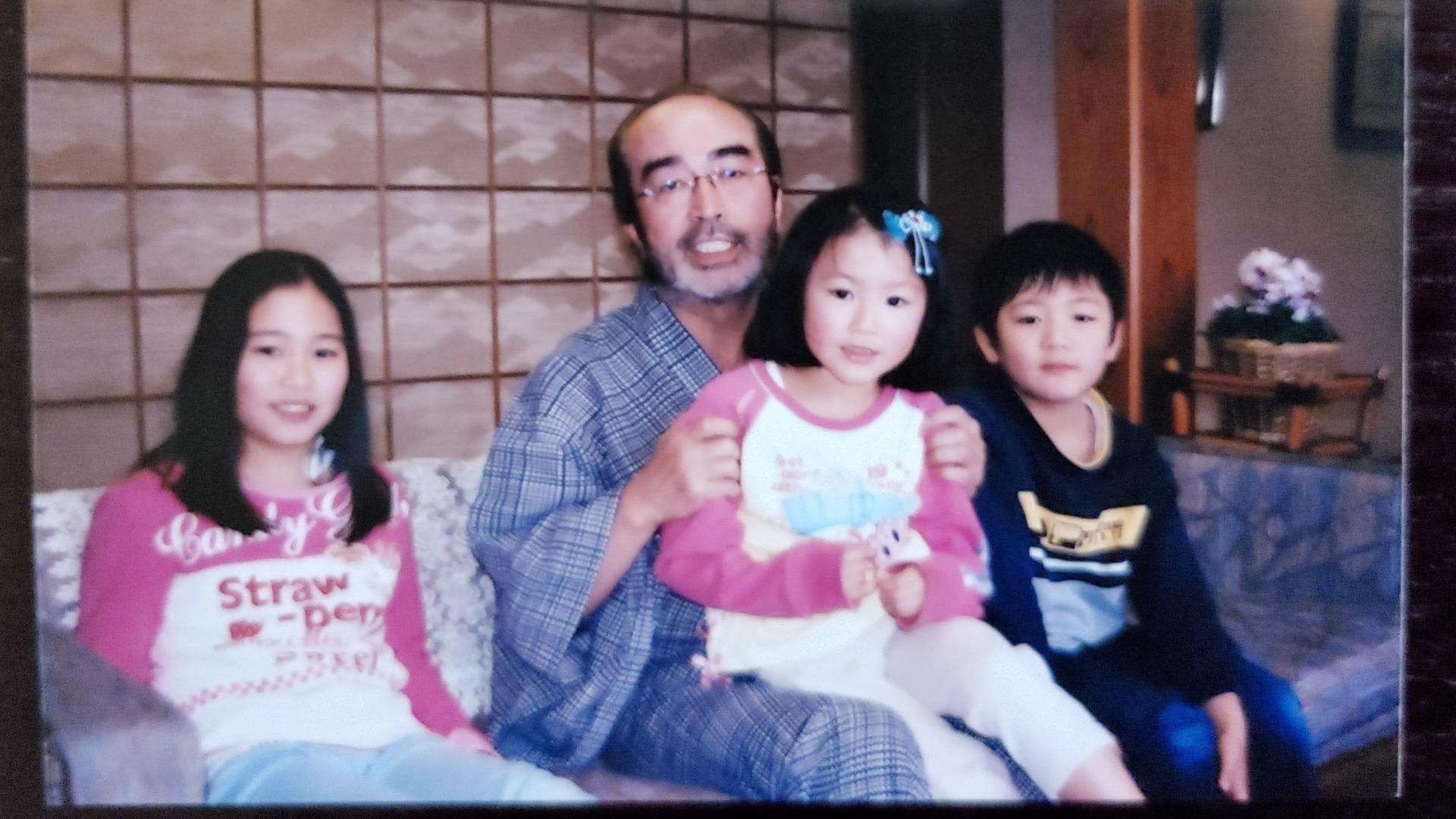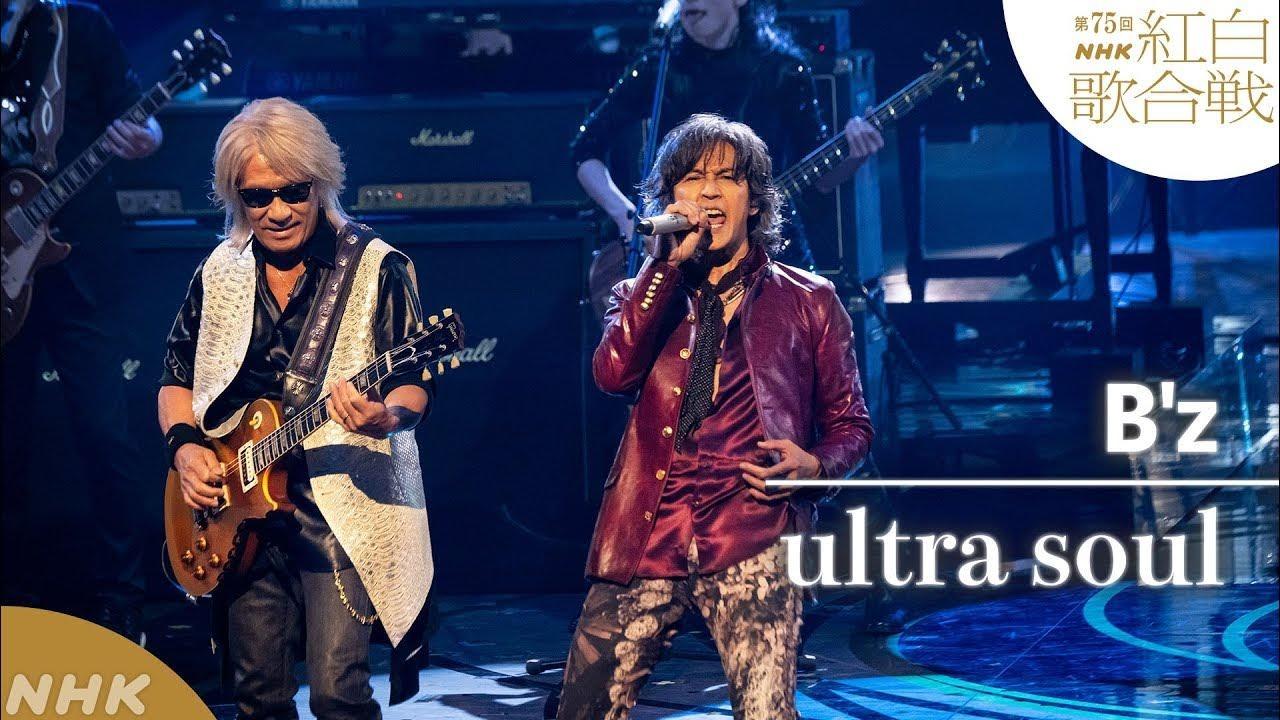【滋賀/竹生島】琵琶湖の小さな島に豊臣秀吉による「幻の大坂城の遺構」が残されてるってホント?

はらぺこライターの旅人間です。今回は古くより”神様が住む島”として信仰を集めている琵琶湖の北部に浮かぶ小さな島、竹生島に残る”幻の大坂城の遺構”として注目されている国宝「宝厳寺唐門」を紹介しましょう。
歴史好きな方は必見です!

竹生島は「(神を)斎く(いつく)島」に由来し、「いつくしま」が「つくぶすま」と変じたとされる。この滋賀県の琵琶湖に浮かぶ小さな島の中には、日本三大弁才天の一つ「宝厳寺」、そして国宝の「唐門」や「都久夫須麻神社」など歴史的に価値の高い建造物がギュッと集まっている。
島に近づけば、まるで神域を守っているかのように切り立った崖が島全体を囲んでいるのが見えてくる。この島は花崗岩の一枚岩からなっているのだとか。
日本三大弁才天の一つ「宝厳寺」へ

島に入り少し歩くと、目の前には165段がある。息を切らしながら進んで行くと鳥居の奥に朱色の建物が見えて来たら宝厳寺に到着する。
宝厳寺の本尊は「弁才天」。江ノ島・宮島と並ぶ「日本三弁才天」の一つで、その中で最も古くに建立されたことから「大弁才天」と称されている。
国宝「宝厳寺唐門」

さて、石段の途中にある小道を進めば…
すぐに唐破風の檜皮屋根が見え始める。これが!秀吉が建てた”幻の大坂城の遺構”として注目されている国宝「宝厳寺唐門」だ。

醍醐寺座主三宝院義演による日記『義演准后日記』や豊国廟社僧の梵舜の『舜旧記』 には、大坂城の極楽橋が豊国神社に寄進された旨の記述がある。
また、2006年、オーストリアの世界遺産・エッゲンベルク城で確認された『豊臣期大坂図屏風』でも極楽橋の正面の姿が竹生島・宝厳寺にある唐破風(からはふ)様式の唐門と酷似することが確認されているのだとか…。
現在の大坂城の極楽橋はどこに?
この極楽橋とは1596年(慶長元年)に秀吉が架けた、大阪城北の丸と二の丸を繋ぐ橋のこと。

ここですね!

ちなみに、唐門・観音堂・舟廊下は、6か年にわたる修理保存事業を終え、2020年の春に美しく蘇っている。
この竹生島は豪華絢爛と言われた桃山様式の「唐門」の代表的な遺構が当時の姿で見られるのだ。これが本当にスゴイ!

桧皮葺、建物全体を総黒漆塗りとした上に金メッキの飾金具が散りばめられ、木鼻の獅子、虹梁中央の蟇股(かえるまた)の周囲には鳳凰や松・兎・牡丹の彫刻がみられる。

二枚の大きな開き戸の桟唐戸(さんからど)や壁には牡丹唐草の彫刻を極彩色塗りなど、その一つ一つが圧巻である。

唐門の建築は1596年、その当時は豊臣秀吉が生存しているので、秀吉がこの門を通り抜けた際に目にしていた光景と同じなのかも!?
そんなこと思えば歴史的なロマンを感じずにはいられない。
尚、この唐門は秀吉死後、京都の豊国廟(秀吉の墓所)に移築され、現在の場所(竹生島)に移築されたものと考えられているそうだ。

そして、この「宝厳寺唐門」を通り過ぎると…
全長30mの「舟廊下」がある。これは朝鮮出兵のおりに豊臣秀吉のご座船として作られた日本丸の船櫓を利用して建てられたもの。国の重要文化財だ。
更に、その先には、国宝「都久夫須麻神社」があり、素焼きの土器に願いを書き、湖面に突き出た宮崎鳥居へと投げ、鳥居の間をくぐれば、願い事が成就するという願掛けの一種「かわらけ」の有名なスポットに続く。
竹生島が魅力的でたまらない!
宝厳寺唐門
住所:滋賀県長浜市早崎町1666
※入島には竹生島への乗船料(往復)とは別に入島料が必要となります。
拝観・納経時間9:30~16:30(観光船就航時間に基づく)
公式ホームページ(外部リンク)
地図(外部リンク)