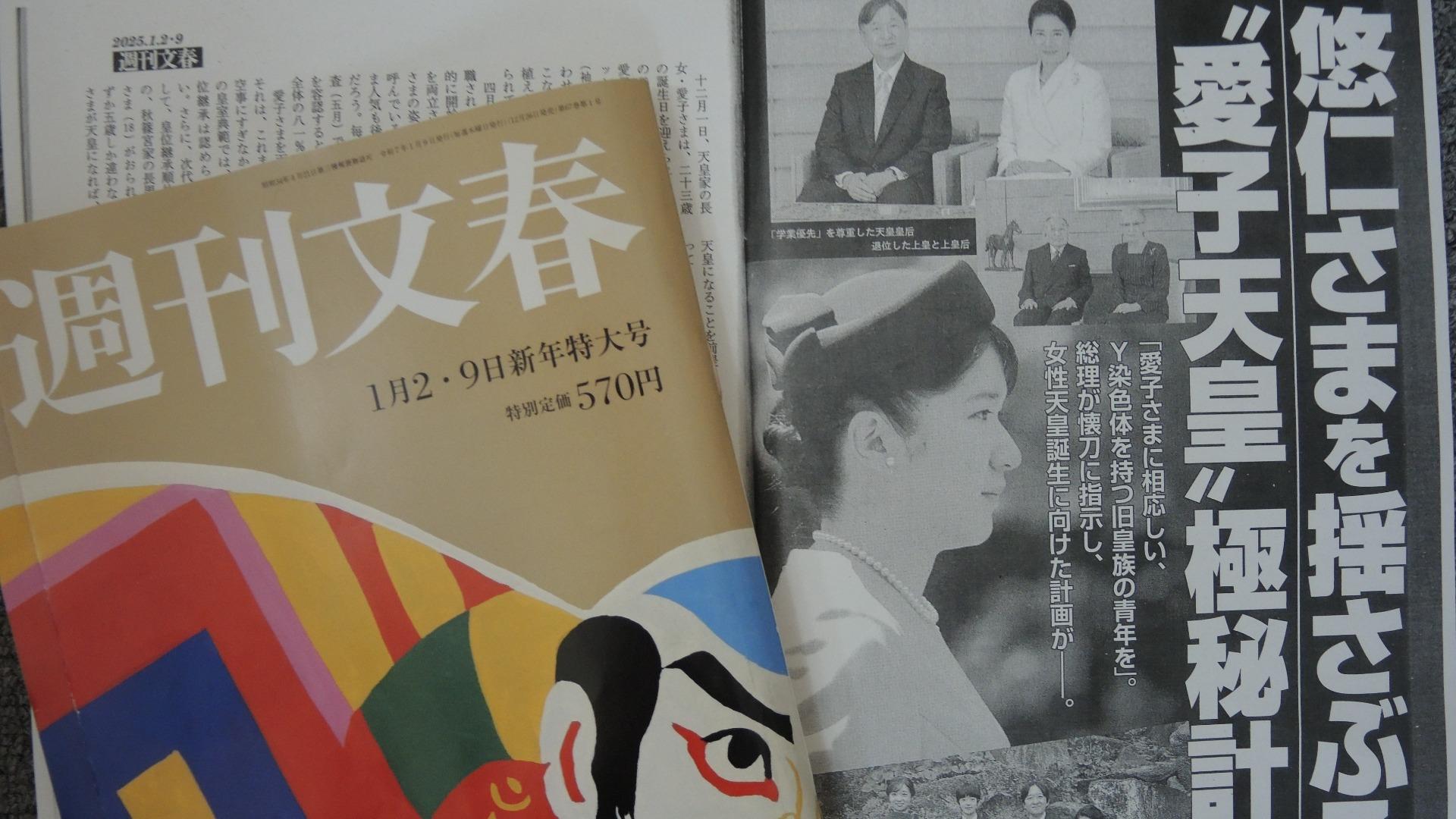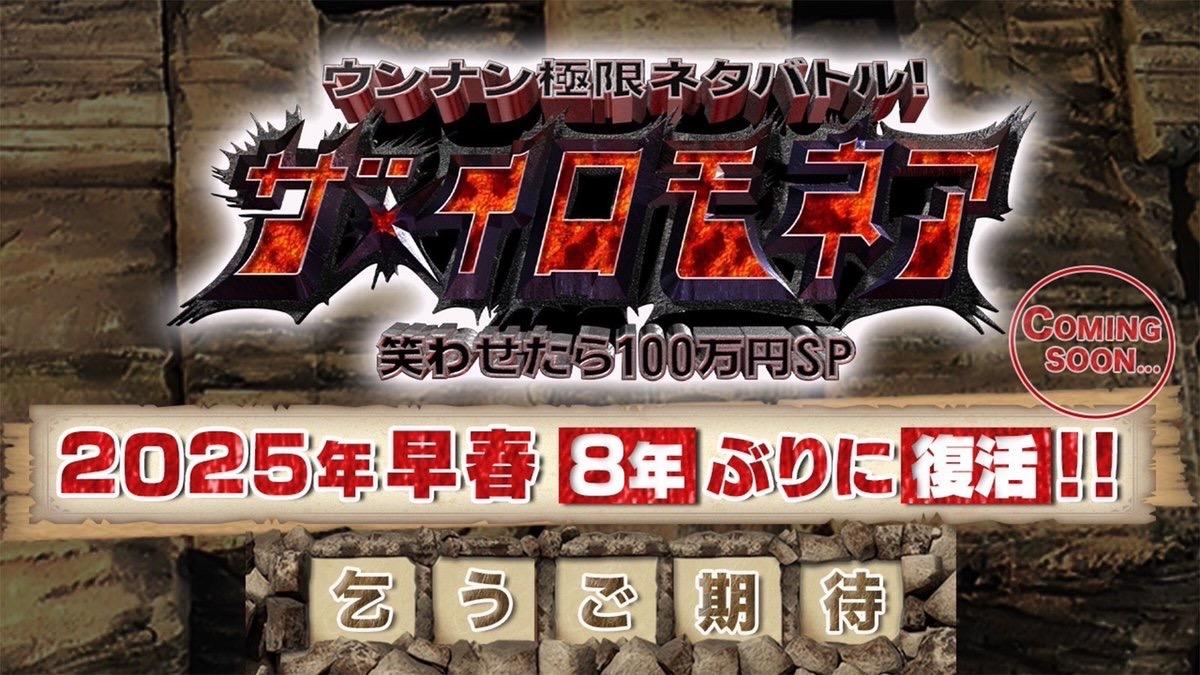駆け付けぬ選択肢はなかった 東京のイスラム教徒、炊き出しなど100回超 東日本大震災 #あれから私は

東日本大震災から11日で10年、東京都豊島区にあるマスジド大塚(マスジドはイスラム教の礼拝所を意味する「モスク」と同義)は発生直後から被災地に食料や生活品を届けるといった支援に取り組んできた。現地の人々に寄り添い、被災の状況に応じて内容を変えながら2年、3年と長く続けた。その活動は計100回を超える。
困っている人を支えよと説く教えを信奉し、さまざまな支援を行ってきたイスラム教徒ら。新型コロナウイルスによって追い詰められる失業者や留学生の支援が活動の中心となっている今も、被災した人々の役に立てそうなことがあればすぐに駆け付けたいとの思いは変わっていない。
毎週金曜に行うはずの集団礼拝は現在コロナ禍のためできないが、震災10年を迎える今週、一人ひとりがその重みを胸に祈りを捧げる。

震災翌日に被災地へ
大地震が襲った2011年3月11日、この日はイスラム教徒が集団礼拝を行う金曜日で、マスジド大塚には大勢の大人や子どもが集まっていた。激しい揺れ、繰り返す余震にも動じず、信者らの行動は素早かった。被災地にあるモスクと連絡を取り、翌12日には物資を満載した車で、津波が押し寄せた仙台市へ急いだ。厳しい寒さに見舞われる避難所へ、飲料水やカップ麺、そして550個の手作りおにぎりを届けた。
「困っている人が目の前にいる時、宗教が何かとかは関係ないですからね」。
そう話すのはマスジド大塚の事務局長のクレイシ・ハールーンさん(54)。震災直後に宮城県南三陸町や気仙沼市などライフラインが寸断された各地の避難所を訪れ、食料品などを配って回った。

4月以降は福島県での支援活動が増え、避難所でカレーを振る舞ったり、布団を寄付したりした。訪問した場所や配った品、足りない物資をマスジド大塚のウェブサイトなどで幅広く発信してきた。呼応してトルコやパキスタン、アラブ首長国連邦といった世界中のイスラムコミュニティにも支援の輪が広がった。

避難所が閉鎖された後も、東京電力福島第一原発が立地する福島県双葉町から住民らが避難してきた埼玉県で2012年、13年と炊き出しなどの支援を続けてきた。
増えていったおにぎり
イスラム教徒の行動原理は、経典「コーラン」に依拠するところが大きい。コーランの4章(婦人章)は、父母に懇切を尽くすとともに、近親者や孤児、貧者、隣人、旅行者など幅広く周囲に親切であれと説いている。
ハールーンさんは「隣人が空腹で苦しんでいる時に自分だけ腹一杯食べるような人は信者ではない。そういう教えがあるんですね」と話し、支援活動を当然視する。
マスジド大塚は1999年の創設以来、近隣との関係を大事にし、地域コミュニティに積極的に関わってきた。2001年9月に米国で起きた同時多発テロ後はイスラム教徒に対する差別や偏見が相次ぎ、ハールーンさんらモスクに集まる信者がいわれのない中傷を受けることもあった。しかしその際も地域の祭りで手作りカレーを振る舞うなど近隣住民との交流を重ねた。
まずはできるところ、手の届く範囲から右40軒、左40軒、前後それぞれ40軒、マスジド大塚は近隣の住宅や商店を対象に、困りごとや要望がないか聞いて回った。地道な活動を続け、徐々に地域社会へと溶け込んでいった。
実直に築いてきた信頼関係が被災地支援の拡大につながった。自分たちだけで用意して届けるおにぎりだけでは足りないと感じ、地元・南大塚の商店街に協力を仰ぐと、快諾してくれた。店主らは復興の願いを込めておにぎりを握り、ハールーンさんたちに託した。送り届けては戻り、また満載して被災地へ急行する、それを繰り返す。
次回は3月22日(火)に、被災地へ運ぶおにぎり作りをする予定です。
ご協力いただける方はご連絡ください。
ぜひみなさまのご協力をお願いいたします。
(2011年3月当時のマスジド大塚のウェブサイトより引用、一部加筆)
などと呼び掛けもした。
回数を重ねるたび一度に送り届けるおにぎりの数は500個、1000個、2000個と増えていった。

地元に根差しつつ東奔西走
マスジド大塚の信者らによる東日本大震災被災者への出張支援は計100回を超えた。震災10年を経ようとする今、発生当初のような物的な支援は行っていないが、「できることがあればいつでも力になりたい」(ハールーンさん)。
困っている人の一助になろうという精神は、マスジド大塚に脈々と息づいている。2018年に岡山、広島両県を中心に大きな被害をもたらした西日本豪雨の際も、マスジド大塚の初動は早く、現地に人手と物資を急送して復興に力を尽くした。東日本大震災の経験を踏まえ、被災した地域で不足しがちな物資や求められる支援を予見しながら、ハールーンさんもすぐに現地入りした。
西日本豪雨の復旧支援では現地のモスクに加え、お寺とも手を携えるなど宗教の枠を超えて協働した。
そしてこの1年は、新型コロナウイルス感染拡大のあおりを受けて困窮する人たちへの支援に力を注いできた。ハールーンさんたちは以前から池袋にある公園でホームレスの人たちに炊き出しなどの支援を行ってきたが、コロナ禍に伴う雇用情勢の悪化で生活困窮者が増えていると肌で感じている。
感染拡大防止の観点から大々的な支援活動や出張支援ができない一方、ハールーンさんに直接、間接に寄せられる相談は多いという。アルバイトができなくなって学費や生活費に困る留学生に対しては、コメや缶詰といった食料提供や金銭サポートをするなどマスジド大塚として幅広く応じている。
昨年の暮れごろ、ハールーンさんに一本の電話が入った。相手は新型コロナウイルスの影響で仕事を失い、食べ物に困っているという見ず知らずの男性。失職したばかりでスマートフォンはまだ持っていたが、早晩料金を払えなくなるほど窮乏している。男性は東京・練馬の公園にいて、ハールーンさんは離れているためすぐには行けなかった。何とかしたいと公園の近くに住む友人に連絡を取ると、ちょうど夕飯の支度をしていたところで、多めに作って公園にいる男性へ届けたという。
相手がイスラム教徒であるか否かを問わず、相談があれば親身に乗ってきた。この先もずっとそうした姿勢で寄り添っていく。
* * * * * * * *
「震災は、本当に起きてほしくなかったですね」
最後、言葉少なに語ったハールーンさん。できることを地道に続けていくとの決意を新たに、震災10年を迎える。