猛暑の甲子園・高校野球大会始まる 24年前には38.8度で試合
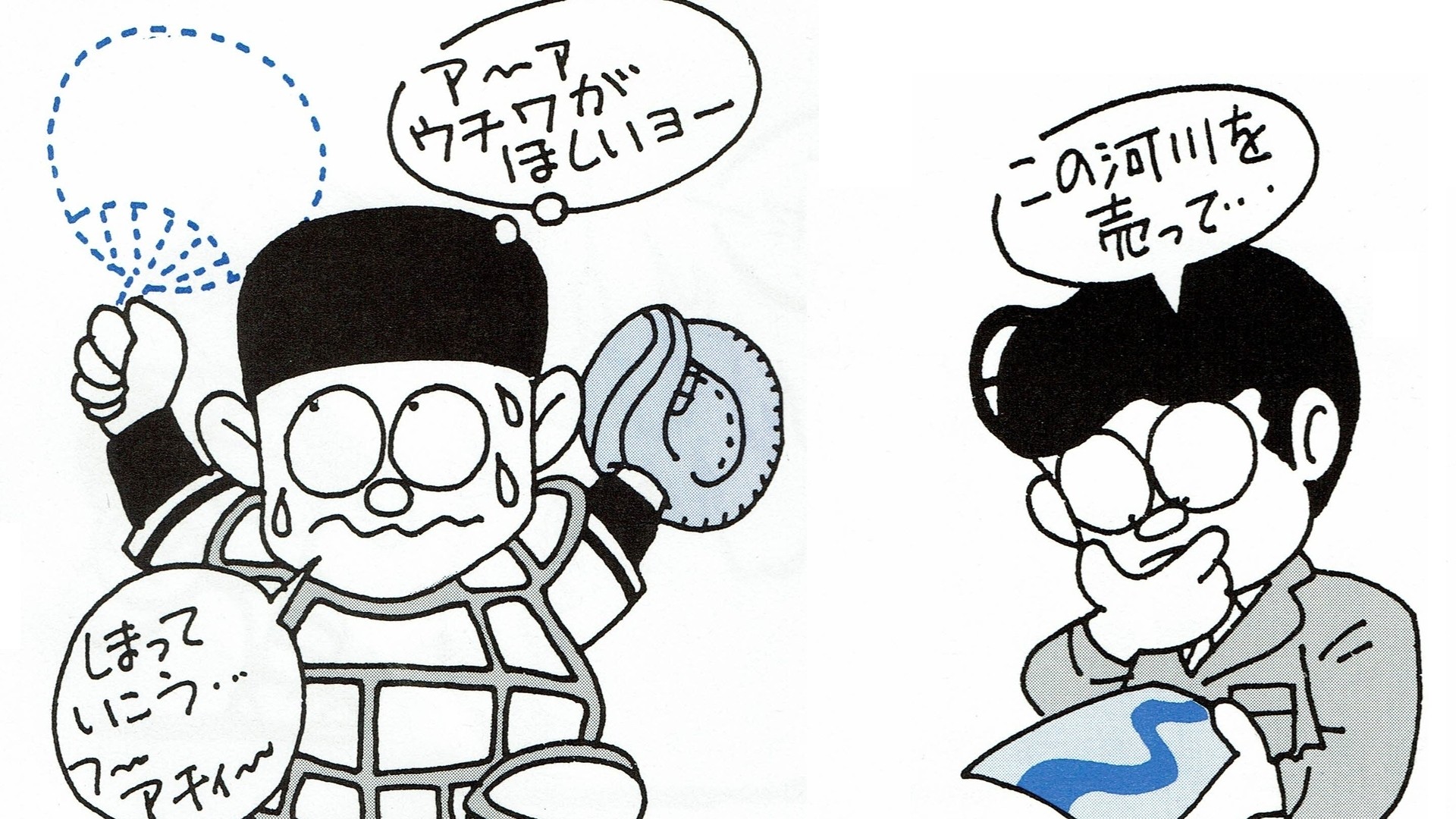
甲子園での野球大会
全国高校野球選手権が8月5日から始まります。
会場の兵庫県西宮市の甲子園球場は、大正13年(1924年)に作られました。
どの年も甲(きのえ)、乙(きのと)、丙(ひのえ)……の十干と、子(ね)、丑(うし)、寅(とら)…の十二支が順繰りにつけられていますが、大正13年は、十干の最初の甲(きのえ)と十二支の最初の子(ね)が組み今わされた60年に一度のめでたい「甲子」の年であったことから、甲子園球場という命名です。
この甲子園球場の建設は、大阪と神戸の間を流れる武庫川の、明治29年(1896年)と明治30年(1897年)の2年連続で台風により大洪水が発生したことがきっかけとなっています。
武庫川の明治29年と30年の大洪水
明治29年は、7月から雨が多かったのに加えて、勢力の強い台風が8月30日タ方に紀伊半島に上陸し、22時頃に大阪付近を通過しています。このため、阪神間は30日夜から31日にかけて風と雨が強まり、多くの河川で堤防が決壊しています。武庫川は31日4時頃堤防が決壊し、瓦木村(現西宮市)は全村木没して砂原化しています。
また、明治30年は、勢力は強くなかったものの、激しい雨を伴った台風が9月29日から30日にかけて九州から瀬戸内海を通って大阪に上陸したため、阪神間では多くの堤防が結界師、武庫川も支流の枝川(えだがわ)の堤防が決壊しています(図1)。
しかし、このときは、根本的に河川を改修する費用がなかったために、堤防の不備を緊急に補修しただけでした。

大正時代の武庫川大改修
大正時代になり、阪神地区の開発が進み、武庫川下流の土地にも価値が出てきました。
そこで、武庫川の支流である枝川と申川(さるがわ)を廃川とし、その土地を売って、その代金で武庫川の河川改修を行い、余った金で阪神国道(国道2号線)を整備する計画が建てられました(図2)。阪神国道を整備するといっても、武庫川付近では、旧阪神国道の北側を通る新しい道路(新国道)の建設です。

廃川敷地は81万平方メートルあり、兵庫県は、道路および水路を除く74万平方メートルを売却面積とし、武庫川の改修工事費の見積もり310万円と、阪神国道の改修費の1割の100万円を加えた410万円で、阪神電気鉄道株式会社(阪神電鉄)に売却しています。阪神電気鉄道は、住宅地経営とレクリエーションセンター設置などを考えていました。
甲子園球場の建設
大正4年(1915年)に大阪の豊中球場で始まった「全国中等学校野球大会(現在の全国高校野球選手権)」は、第3回から兵庫県の鳴尾球場に会場を移していますが、多くの観客がつめかけ、大混乱となっています。そして、大きな野球場の建設が強く要望されるようになり、阪神電鉄は、獲得した廃川敷地のうち、400平方メートルを使って、ニューヨークのヤンキースタジアムに匹敵する東洋一の大野球場をつくっています。
これが、4か月余の突貫エ事でつくられた甲子園球場で、阪神電鉄は、甲子園駅を新たにつくりました(図3)。
甲子園球場というと、暑さのなかにひとときの涼しさを運んでくる浜風が有名ですが、これは、夏の高気圧の勢力範囲に入ったときの日中に発生する海風で、甲子園球場から見ると、ライトスタンドからレフトスタンドに向かって吹いている風です。

猛暑の大会
甲子園球場に一番近い気温観測所は神戸市にある神戸海洋気象台(現在は神戸地方気象台)です。
年によって差がありますが、昔筆者が調査したところ、大会期間中(開幕日から閉幕日まで)の神戸市の最高気温の平均は31.7度でした(図4)。大会期間中の最高気温の平均が30度を下回った年は全体の15%くらいですので、ほとんどの年は真夏の日差しの中での試合が行われます。

平成6年(1994年)の夏の大会の開会日である8月8日は、太平洋高気圧に覆われ、各地で猛暑の記録が続出しました。
神戸市で観測した38.8度は、今でも神戸市の最高気温の記録です(表)。そして、体温よりも高い気温のもとで試合や応援が行われたのはこれが初めてです。

平成6年(1994年)の大会期間中の日最高気温の平均は、34.2度もありました。
翌、平成7年(1995年)は、一番暑かった日が35.6度と前年には及ばなかったものの、大会後半に最高気温が35度以上の猛暑日が連続して、日最高気温の平均は34.3度と、前年を上回っています。
この2年連続で記録的な猛暑となったとき、筆者は神戸海洋気象台の予報課長でした。甲子園で高校野球が始まると、気象台に問い合わせの電話が殺到しました。中には、暑ければ「暑さをなんとかしろ」、雨が降れば「何で雨を降らせるのだ」など、無茶なクレームもありました。
今のように、ネットで気象情報が手軽に入手できる時代ではなく、電話をかけて聞くというのが情報入手の大きな手段でした。
週間天気予報によると、神戸の最高気温の平均は33.4度ですが、予報の上限では35.1度になる予報です(図5)。

平成6年(1994年)、平成7年(1995年)の記録的な猛暑以上の猛暑が予想される今年の大会です。
猛暑の中、無事に熱戦が行われるよう、全ての関係者に特別の配慮をお願いしたいと思います。
タイトル画像、図1、図2、図3の出典:饒村曜(平成11年)、イラストでわかる天気のしくみ、新星出版社。
図4の出典:「饒村曜(平成11年)、イラストでわかる天気のしくみ、新星出版社」に著者加筆。
図5の出典:気象庁ホームページ。
表の出典:気象庁資料をもとに著者作成。










